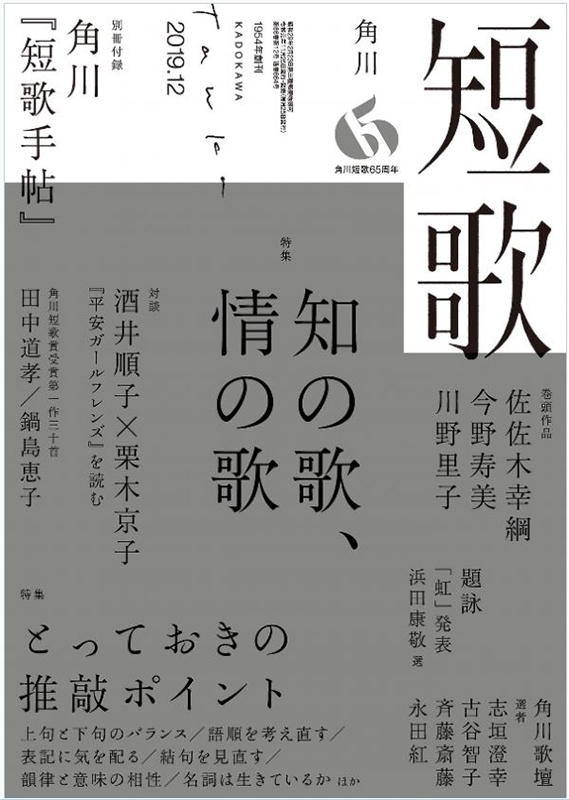
たまねぎを火は甘くする 晩年の兆す速度を僕は知らない
彼方なる星座の人もけだものもおやすみ。撃ち落としてあげるよ
ぼくの夢は夢を言いよどまないこと窓いっぱいにマニキュアを塗る
美樹さやかに僕はなりたい鱗めく銀の自転車曳くゆうまぐれ
笠木拓第一歌集『はるかなるカーテンコールまで』より
手を離したらいまにも消えてしまいそうに繊細な感情を、笠木は和歌にも通底する高い技巧で歌に結晶させる。『はるかなるカーテンコールまで』に描かれる主体はあやふやで不安定な〈ぼく〉だ。〈ぼく〉はその不安定さゆえに傷つくこともあるが、その不安定さゆえに、〈ぼく〉は何にだってなれる。ジェンダーをひらひらと行き来していくような感覚や、古典和歌やスピッツ、志村貴子『放蕩息子』など二次創作的な本歌取りの多さは、〈ぼく〉という無数の可能性として、また壊れやすいアイデンティティのやわらかな拠り所として、ただそこにあった。それがとても好ましく思われた。
睦月都 歌壇時評「「君」という虚構」
今月号の歌壇時評で睦月都さんが笠木拓さんの第一歌集『はるかなるカーテンコールまで』を取り上げておられます。睦月さんの論旨はもちろん「「君」という虚構」を明らかにすることです。その例として笠木さんの歌集を取り上げたわけです。
角川短歌後半に掲載される歌壇時評は比較的若手の歌人が担当することが多いようです。ヒエラルキーがあると言うと失礼かもしれませんが作品はともかく角川短歌の特集などに執筆なさる歌人は中堅・大家が多いと思います。それと比較すると歌壇時評は今の歌壇のメインストリームとはかなり論調が違います。
もちろんそれが悪いとか歌壇の大問題だと言っているわけではありません。ただ歌壇時評を読んでいると中堅・大家歌人の短歌観と若手の短歌観にかなりの違いがあることがわかります。ニューウエーブ以降の若手歌人たちはすでに彼ら独自の論壇のようなものを持っておりそれを一種の〝常識〟として評論を書いている気配があります。
どの文学ジャンルでも若手が次世代を担うわけです。だから若手歌人たちがいわば常識としている短歌観が次の世代の短歌の常識となるのかどうかについていたく興味を惹かれるわけです。
本題に戻りますと睦月さんは「手を離したらいまにも消えてしまいそうに繊細な感情を、笠木は和歌にも通底する高い技巧で歌に結晶させる」と基本的には絶賛しています。正直なところ笠木さんの短歌に「高い技巧」があるとは額面通りには受け取れない。しかし「いまにも消えてしまいそうに繊細な感情」が表現されているのはよくわかります。このあたりがニューウエーブ以降の若手歌人の正念場になりそうです。またそれが「「君」という虚構」に繋がっています。
だってあなたはわたしの暗喩かもしれず手をとればだれも帰れなくなる 佐々木朔
「君」は詩語である。詩語には言葉を現実から異化し、詩としての浮力を言葉に与える一方で、〈君〉そのものを匿名化してリアルな質感を失わせるという、暴力的な側面もある。そんな効果を逆手にとって(か、どうかはわからないが)、このような秀歌も存在する。
佐々木の歌は短歌における二人称代名詞の特殊性のある一面を見事に言い当てている。「わたし」の言い換えとしての「あなた」、「私」の代弁者としての「だれか」、時にはいささか都合が良すぎると思わないでもないオルターエゴとしての「君」は、注意深く観察していると、短歌には頻繁に登場する。佐々木の一首はそんな匿名化された〈わたし〉や〈あなた〉という存在の悲しみをメタ的な次元へと引き上げ、ひりひりとするような生の実感に昇華させている。
(同)
睦月さんは佐々木朔の短歌を引用して「「君」という虚構」についてよりストレートに論じておられます。日記や短歌に表れる「君」は特定の誰かを念頭に置きながら特定の「君」に読まれることを前提としていないので「詩語である」――「文脈や読み手の解釈によってさまざまに想定され、代入され、投影されうる」と論じておられる。しかしこの論理はちょっと無理がありますね。
言葉は基本的に日常言語をベースに考える必要があります。日常言語とは基本的に現実世界そのもののことです。当たり前ですが「五万円です」と言われて自分にとっては大事でとてもキレイな木の葉五枚でお金を払うことはできません。
日常言語では私とは違う他者のことを「君」と呼びます。なるほど日記や短歌に表れる君をわたしたちは不特定多数の他者に置き換えて理解することがあります。しかし作家はまず特定の他者(君)を前提に日記や短歌を書きます。その他者を読者は作家が念頭に置いた君以外の他者に当てはめたりするわけですが自在ではありません。日記や短歌の君は基本的には私と君(他者)の関係性を描いているのでありそれが本質的な自他関係表現になっていれば読者は作品で描かれた君を自分の知っている誰かにも当てはめることができるのです。
ただし睦月さんの「「君」は詩語である」という断定が間違っているわけではありません。日常言語を使って対人関係を描いた日記や短歌とは最初から違っているだけのことです。詩語とは日常言語の意味伝達性を否定した(あるいは日常的な意味伝達以上の何事かを伝達しようとする)言葉です。佐々木さんが日常言語を離れた詩語として君という言葉を使っているのは確かです。
比喩的に言えば「だってあなたはわたしの暗喩かもしれず手をとればだれも帰れなくなる」という佐々木朔さんの歌を「ひりひりとするような生の実感」として捉えられるかどうかが睦月さんの評論が説得力を持つかどうかの試金石になります。もっと言えば「私」という存在主体が希薄に感じられてしょうがないから「あなたはわたしの暗喩」になる(「かもしれず」)ということになる。笠木さんの歌の批評の「手を離したらいまにも消えてしまいそうに繊細な感情」も同じことを指しています。私の主体が希薄になっていることが「「君」という虚構」という考え方を生み出しています。
情報が無際限の海のように広がって私という唯一無二であるはずの存在が小さな情報の結節点としてしか感じられない現代の高度情報化社会(ポスト・モダン社会)において短歌がいち早く私の無力を感じ取っているのは特筆すべき先進性です。ニューウエーブ以降の歌人たちは「短歌は私の表現である」という常識に鋭く対立していますがそれはポスト・モダン世界で私が感じる肉体感覚ゆえだと思います。そこに短歌の未来――新たな短歌表現の可能性があるのは確です。
ただそれをもっと客体化して見つめる必要があります。どんな表現も〝ではない〟の否定形ではダメなのです。〝である〟の肯定にまで至らなければ真に新たな表現にはなりません。わたしの揺らぎを表現した短歌ははっきり言えば未成熟です。狭いサークル論壇の中で素晴らしいと繰り返し絶賛されてもその多くは深読みであり作品自体にまだ強い力はありません。ただこのラインから優れた歌人が必ず数人は現れてくるでしょうね。
高嶋秋穂
■ 笠木拓さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■




