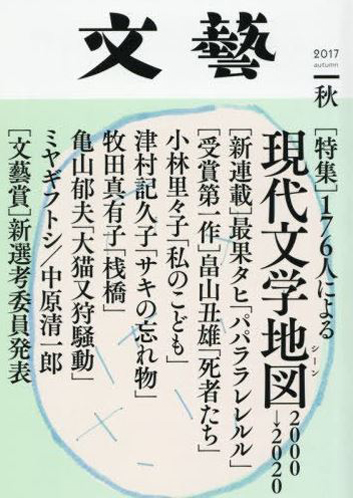
季刊というのはもしかして、日本文化にはあっているのかもしれない。俳句や短歌の雑誌なら必然性はあるし、つまり季節感が出てないと意味がないんじゃないか、と思う。単に毎月出すだけのコストもマンパワーも不足です、ということだと、わりかし義理堅い不定期刊と変わらない。
俳句や短歌ととりあえず関係ない、それでなおかつ日々の暮らしの季節感を押し出すわけにいかない雑誌の場合、季刊ということをどう捉えるかは結構、難題だということになる。けれどもそこを避けて通るのは批判力のなさを露呈しているようなものであって、そんなことで文学が、あるいは別のカルチャーでもいいのだけれど、編集部内で論じられるのか、という疑念がわく。
季節感を扱いづらいと言っても、たとえば数学の雑誌だってできないことはない。学問の世界にもイベントはあるし、そもそも学校行事は季節感満載だ。毎月刊行だとむしろ、のんべんだらりのレポートの集積になりがちでもある。抽象議論だからこそ、ああ、もうそんな季節か、と思わせるような編集がオサレではないか。結局は人間がやっていることだからね、という成熟を匂わせて。
それが文芸誌にできないわけはないのだが。ただ無論、編集部の凝ったコンセプトのための雑誌となり、創作物がまるで見当たらない、というのは論外だ(最近、ときどき見かける)。季刊誌には、季節がめぐってきてやっと出た、という感がほしい。そこには溜まりに溜まった小説作品が吐き出されていなくてはならない。
そうすると確かに、季節感を出しつつというのとはなかなか両立しにくい、というのはわかる。季節にあった作品ばかりを並べるというのも奇妙なものだ。けれども逆に、こんなに季節感のない作品ばかり、いったい小説って何なんだ、と考えさせてのも無意味ではないだろう。
小説は俗世のことを描くものだ。季節感のない俗世もあるかもしれないが、そんなときにも小説は、俳句よりも短歌よりも俗世に結びついていなくてはならない。色でも欲でもいいし、土地の風情といったものでもいい。体温とか匂いとか、すぐれた小説は必ず身にまとっている。香気、というべきものだ。そして小説が抽象性を目指すとき、そこには最後のよりどころとして季節感がある。
だから小説にとって季節感とは後衛でありながら、前衛であろうとするときの支えでもある。文学全般に普遍化すれば、俳句と短歌の季語というものの意味もわかってくる。季刊で小説誌を出すなら月刊誌との違いを季刊の季から考えねばなるまい。年3回刊行の雑誌は…余裕がないだけだろうが。
作品のみならず対談や座談会もてんこ盛りなのだけれど、連載の座談会というのがあるのが変でなかなかよい。座談会とか対談というものは、やってみるとわりと緊張するもので、一期一会感があるものだ。相手との一期一会というより、一種の対決というか勝負の一期一会だ。それが勝負なのだと気がついていないくらいの呑気な相手ならいいのだが。それを連載すると限りなく茶飲み話に近くなる。当たり前だが、季節ごとのそれというのは弛緩の具合がちょうどよい、かもしれない。
谷輪洋一
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
