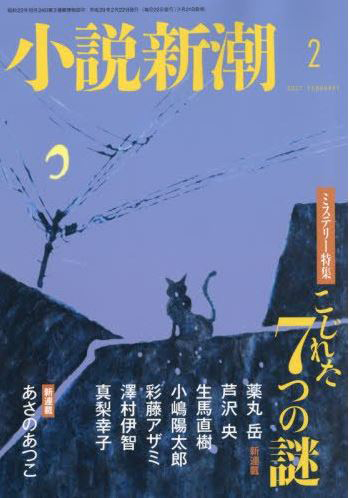
「ミステリー特集 こじれた7つの謎」。読み進むうち、ある変化に気づいた。雑誌や作品が何か変わった、というのでは必ずしもない。読んでいるこちらの状態が変化したようにも思える。が、厳密に言うと、それも少し違うようだ。こういったものを読む、その行為を取り巻く状況、環境が変わった、と言うべきだろうか。普段通りにティーカップを脇に置き、なかば寝そべって読んでいるだけだが。
すなわち物語の中に入り込むことがなくなった。楽しめなくなった、というのとは違う。むしろいっそう楽しくなったかもしれない。物語の中に入り込むというのは、実はそれほど楽しい経験ではない。感情移入で苦しくなるのはよい作品で、貴重な読書体験だが、本当のところそれほど得るところはない。悪い夢を見ているようなもので、目が覚めればそれきりだ。
何をもって得るものとするかは、もちろんそれぞれではある。子供ならば、感情移入そのものが豊かな〝感情教育〟だとも言える。しかし、いい大人が登場人物になり変わったり、ひどく共感したところで、それは最初から読者本人の情緒と共感のキャパシティの範疇に入っている。
つまりは喫茶店での友人とのおしゃべり、その愚痴を聞いてやっているのと変わらない。親交が深まるなら無意味だとは言わないが、新しいものは自分に何も加わらない。それなのに自分の知らないことを追体験しているというだけで、少なくとも見聞を広めている気になるから厄介である。
出版不況、本が売れないとは、端的にこのような自分にとっての無為な時間を割く余裕がなくなってきているから、ということに尽きよう。現に子供向けの本は売れている。子供は本を読むことによって得るものがたくさんあるからである。時間のムダ、と言い放って書物を捨てるなど、世も末感があるが、これだけ毎日、大量の情報を有用・無用で振り分けて暮らしていると、書籍は別、と言えなくなる。
では、有用な情報がのっかっていればいいのか、というと、それも違うだろう。テレビなどでは情報ドラマが以前から盛んに流れているが、それは受け身のメディアに特有の中間的なニーズで、読書という能動的な行為では、情報を取りたければ有用情報のみが詰まったコンテンツに接した方が効率的である。ネットの営業ツールでは動画だと2倍速でしか見られない、テキストの方が効率がいいようだ。
「7つの謎」に順に接しながら気づいた変化は、それをすでに物語でなく、やはり「情報」として摂取している、という事実だ。物語を通して人生を豊かにしたり、成長したりする年齢でも時代でもなくなっている。では小説雑誌から得る「情報」は、我々のなんの糧になるのか。
それがいわゆる実用情報として、我々の実生活に役立つものではないことはわかっている。今回の特集では「こじれる」、「謎」という二つの要素がいずれも言語的な物語、メタフィクション的な結構をもたらしがちであることを示している。すなわち小説自ら「情報」として読まれるべきことを示唆しているのだ。
池田浩
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



