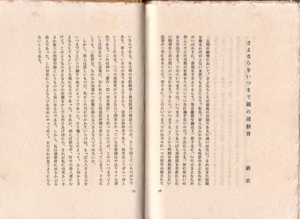
さよならをいつまで露の頭蓋骨 耕衣
『聲前一句』は安井浩司が、所属する同人誌「琴座(りらざ)」に35回に亘って連載した、古今35人の俳人一句を論じた小論だが、その最後で取り上げたのは「琴座」を創刊し主宰した永田耕衣である。安井は23歳で同人となってから、耕衣の死によって終刊するまでの38年に亘って在籍を続けた。同人誌という名目の「琴座」ではあったが、安井にとって耕衣は事実上の「師」であり、耕衣の弟子であることを公言してはばからなかった。
一方で、安井は高柳重信が創刊した同人誌「俳句評論」にも所属し、重信から俳句形式の思想を吸収したが、耕衣を「耕衣師」と呼んだように「重信師」と呼ぶことはついぞなかった。重信の他にも安井は影響を受けた俳人として、「超俳句」を実践し前衛として若手俳人の導師的存在だった加藤郁乎の名前をしばしば挙げることがあるが、郁乎にしても「師」と呼ぶことはなかった。とりわけ「耕衣師」こそが、安井にとって唯一人の「師」であったことは動かし難い事実なのである。
ところで、いささか私事にかかわるのであるが、私にとって耕衣は、偉大な俳句作家である以上に師である、というおもいで弟子の末席を汚してきたことである。俳句作家以上に師であるということは、考えようによっては非礼な言い草であろうし、それは文学を越えた信仰の域じゃないか、と言われても致し方がないと思っていた。だから、私は、生涯は耕衣の文学については冷酷なクリテックを持てぬだろうし、いや、げんに、私は耕衣に対して餌をねだるほいと(*傍点著者)である以外に、耕衣世界の完全な理解、同行者ではないのであった。私には不可視な、正体のよくみえないこの混沌の世界に深く斬り込んで、わが命を落してはならない。だいたいにおいて、歳月の重さを詩法の一翼に据えているこの老師に対して、この世における生存量の重さが、まるきり違うではないか、と本能的に自己納得を強いてきたのであった。私は、永田耕衣の存在の強さを、本能的に感知し、共鳴し、恐怖し、敬虔するだけだと言えば、成程と判っていただけるむきもあろう。
(『もどき招魂』所収「歳月の方法」より)
「歳月の方法」は耕衣を単独で論じた長篇評論で、安井の最初の評論集『もどき招魂』(1974年端渓社刊)に収められている。その文中に、1973年に刊行された耕衣の全句集『非佛』を、「近年にない迫真力をもった書として、我々の前にその雄姿を現した。最近の俳壇で・・・」とあることから、この耕衣論が書かれたのは『非佛』刊行直後と推測することができよう。であれば、安井が飛騨高山から故郷の秋田に居を移し、と同時に関東の純粋読者による安井浩司ファンクラブともいうべき「唐門会」が発足した頃と重なる。また耕衣の「琴座」においてこの『聲前一句』連載が始まり、さらに重信の「俳句評論」誌上では、「もどき招魂」のような俳句原理論や、最初の重信論「道化の華」といった初期の重要な評論の数々が、続々と掲載され始めた時期にも当たる。
それは安井が、俳句という自らの文学営為に対する思考をひたすら深化させ始めた頃で、引用した一文にしても、耕衣との関係を「師弟」という出来合いの意味に委ねるのではなく、改めて関係の本質から考え直した結果に辿りついた認識であろう。「いささか私事にかかわるのであるが」と、厳格な作品至上主義者ゆえ、テクストを離れた日常人事を評論に持ち込まない安井にしては珍しい前置きではあるが、「師」としての耕衣が自身の俳句に対しどのような存在であるのかを確認することが、当時安井が耕衣論を書くうえで、避けては通れないと考えていたのは間違いない。そのうえで「俳句作家以上に師である」という断言からは、安井にとって耕衣が「師弟」という言葉以上に重い存在であることを看取できよう。それは俳句の「師」を越えて、あるいは文学の「師」を越えて、安井の「人生」における「師」であると言っているに等しい。
「人生における師」といえば、それは俳句や文学の領域とは異なる、経験主義的な人生論として捉えられがちであろう。とかく現代文学に関わっているかぎり、「人生」という言葉は「文学」という「知」にとって常に外部として立ち現れる。しかし安井が「俳句」を、「文学」という「知」の内部に閉じ込めておくべきではないと考えていることは、次のような安井自身の発言からも明らかである。5年前に刊行された『安井浩司選句集』(2008年邑書林刊)の巻末インタビューにおいて、“ずばり安井さんにとって「俳句」とは何ですか。あるいは俳句にとって「安井浩司」とは何なのでしょうか”という質問に対し、安井は次のように答えている。
余剰の言い回しを止めて明確に答えましょう。私にとって俳句とは「安井浩司」そのものです。それ以外の何物でもありません。(中略)俳句にとって「安井浩司」とは俳句自身のことなのです。それ以外の何物でもないのです。これが詭弁に聴こえたら、その人は未だ俳句に身を置く苦しみを味わっていないことになります。
ここでいう「安井浩司」を「安井浩司という人生」と言い換えれば、また「俳句自身」を「俳句という人生」と言い換えれば、安井の「俳句に身を置く苦しみ」の意味が浮かび上がってこよう。たとえば、安井が重信論で言及している重信の初期俳句論「敗北の詩」を思い浮かべてみる。そこでは「俳句形式」=「敗北」の形式という前提のもとに、「敗北」を乗り越えるための「俳句」が、俳人たるべき「人生」に不可欠な行為として立ち上がってくる。逆に考えれば、「敗北」という苦しみを自ら引き受けることこそが、俳句形式に身を置くことの本質的な目的であり、その一点にのみ、「なぜ俳句なのか」という普遍的な問い掛けの答えが見出せると言うことである。
しかし、ここまでは依然として「俳句形式」の範疇に過ぎない。それを学ぶためには重信という稀有なる「俳句形式」の体現者が一人いれば済むことである。問題の本質はあくまでも「俳句」という「人生」にある。安井がついに(*下線部に傍点)、「俳句とは安井浩司であり、安井浩司とは俳句自身のことだ」という認識=思想を獲得するためには、「俳句」を越え出たところの「人生」の「師」が必要だった。安井が耕衣を、「俳句作家以上に師である」と語るのは、そうした意味合いにおいてである。誤解を恐れずに言えば、確かに「それは文学を越えた信仰の域」に違いない。だが、そうした批判がもしあるとすれば、それは不可知なものを認めない有識者の自己保身ゆえであり、文学という知の体系を逸脱する事象を無視しようとする学者諸氏の傲慢にほかならないだろう。
「必要だった」とは言ったが、もちろん安井はそうした思想への到達を目論んだ上で、耕衣を「師」に選んだわけではないだろう。耕衣という「師」とたまたま出会い、その後で重信という先達とたまたま出会い、それぞれの作品を繰り返し読むことを通して、また二人との言葉を介した交流を通して、俳句に対する思索を深めていったのだろう。そうした時間が積もり積もった結果、先のインタビュー発言に到達したはずだ。それは「学問」だけでは掴み得ない、また「宗教」よりもはるかに地に足の着いた、それこそ「人生」としか言いようのない思想なのである。
とは言え、そうした思想を「人生」という一言で理解したつもりになったとしたら、それは安寧と引き換えに「敗北」を売り渡すに等しい行為ではないだろうか。「永田耕衣の存在の強さを、本能的に感知し、共鳴し、恐怖し、敬虔するだけだと言えば、成程と判っていただけるむきもあろう」と、物分りのいい読者に問題を委ねるような流儀は、安井浩司という俳人の人生に昔も今も存在しない。ゆえに「歳月の重さを詩法の一翼に据えているこの老師」の、「人生」の原理に至るまで追い詰めなければならないと考えたはずだ。それは、安井にとっての「地獄降り」と言ってもいい経験だったに違いない。
『聲前一句』に話を戻すと、安井が取り上げている〈さよならをいつまで露の頭蓋骨〉は、耕衣円熟期の句集『闌位(らんい)』(1970年俳句評論社刊)に収められた作品で、「戯作・偽一休自伝抄」と銘打たれた巻頭連作17句のうち一句である。句集タイトルの『闌位』とは世阿弥の能楽論の用語で、修行を重ねて至高の境地に達し、さらにそれを越えた奔放自在な芸境を意味する。自身の句集の命名として、耕衣ならではのふてぶてしいまでの自信と、自己愛の極点ともいうべき諧謔に満ちた見事な題名と言えよう。
人間の叙情において、さよならこそが最高の形態であるに違いはない。それはまた相聞を飾るかけがえない本質でもあるだろう。
(『聲前一句』より)
この連載最後の回で安井は、耕衣師の「さよなら」に注目する。もちろんそれは最後を洒落のめしたわけでもなければ、また最終回に当たっての演出でもない。この日常的な挨拶の言葉を前にして安井は、自ら俳句の前衛として作品に向き合おうとはしていない。叙情の最高形態にしろ相聞の本質にしろ、むしろそれは俳句の伝統的な価値にほかならない。ここでの伝統とは、状況論的な前衛の対立項ではなく、本質論的な俳句原理を意味する。そうした俳句原理を前にすれば、前衛俳句の掲げるアンチテーゼなど微々たるものにしか思えなくなってくるのだろう。安井は、当時の自身を含めた前衛俳人コミュニティーを見渡して、「要するに、一片のさよならが欲しくてこの言葉の世界をうろついているに過ぎないのだ」と自虐を込めて言い放っている。
それにしても、妙に味わいのある作品である。この〈いつまで〉は、いつまで?というもっぱら待時間を半折にしたい願望をこめた問いが一方にあり、そこへ、いつまでも!という時間を無限延長したい返事が一方にあることだ。要するに、この〈いつまで〉には巧みに一つの問答が隠されているのである。
(『聲前一句』より)
この評釈の肝所ともいえる部分を引用したが、安井が「ある種の有限願望と無限願望の対話」と指摘しているように、俳句というわずか17文字で「願望」の両極端をほのめかし、それによって「願望」の「根源」を描き切っているところなどは、かつて「根源俳句」として俳句史に認知された耕衣の真骨頂と言えよう。安井は、この対話の当事者を「戯作・偽一休自伝抄」という章題から、問い掛けている有限願望の主が女である森侍者で、答えている無限願望の主が男である一休と解釈している。
二つの頭蓋骨が〈さよなら〉問答をやっている空想図はやはりオツな景色である。(中略)それにしても、二点間を、なかなか高邁かつ妖艶に揺れる〈さよなら〉ではないか。
(『聲前一句』より)
反骨の破戒僧とも呼ばれた一休が、盲目の美人旅芸人だった森侍者を見初めたのは76歳のときで、その年の差は50を数えたと伝えられている。そうしたアンバランスな二人の関係において、若年特有の有限願望と老年特有の無限願望との混交は、たしかに「オツな景色」としか言いようのない「人生」の一風景に違いない。そして、こうしたアンバランスな願望が、死後もなお続いているということを考えるに、願望の有限と無限の交感を成立させている「人生」とは、一体何によってもたらされるというのだろうか。つまり、生死の境を越えてなお、人としての最高の叙情であり、人と人との相聞という本質を成す「さよなら」を交し合う欲望とは、何に由来するのか。
単刀直入に言ってしまえば、それは「尊敬」である。最初に引用した「歳月の方法」の文中にある「本能的に感知し、共鳴し、恐怖し、敬虔するだけ」とは、「尊敬」という行為に他ならない。頭蓋骨となった一休と森侍者という「二点間」の、前者を「高邁」といい後者を「妖艶」というとき、それぞれが男に対する、あるいは女に対する、最高の「尊敬」とは言えないだろうか。繰り返しになるが、「歳月の重さを詩法の一翼に据えているこの老師」の、「人生」の原理とは「尊敬」であり、安井はその「尊敬」を俳句の土台となるべき人生の思想へと昇華し得たのである。
それが、例えば俳句や、昨今の俳人達に向けて、このような〈さよなら〉の形態を少しでも作り上げ得たら、それが私に出来るいささか最上の相聞形態というものかと思い走るのである。
(『聲前一句』より)
安井が言うところの「〈さよなら〉の形態」とは「尊敬」という行為を意味するが、それは「全ての人を敬い師を敬い友を敬う」というような人生訓の類でないのはもちろんである。安井が「尊敬」の対象とするのは、批評の対象となるべき俳人であると言ってもよかろう。それは耕衣師をはじめとして、重信や郁乎、そして赤黄男や三鬼といったすでに鬼籍に入っている先達の俳人たち、そして大岡頌司や河原枇杷男のような同世代の俳人たち、更には摂津幸彦といった後続世代にまで及んでいる。さらに、「昨今の俳人達に向けて」と言っているように、芭蕉、其角、蕪村、子規といった古典も当然含まれる。それは、安井の俳句思想を形成するに欠くべからざる俳人達を指している。
そうやって眺めてみると、この『聲前一句』に登場する35人は、一人残らず「尊敬」の対象であると言えよう。そしてそこに読み取るべき安井の審美眼とは、じつは安井自身の対象に対する「尊敬」の眼差しによって保障されていることが分かる。さらに、それはまず何を措いても、「俳句」そのものに対する「尊敬」が土台にあることだろう。それが終には「詩」への、いや「文学」への「尊敬」に至るのは、安井にとって当然の成り行きである。
だが、ここで手打ちにしては性急の誹りを免れまい。いまいちど先の引用文に戻って、「私に出来るいささか最上の相聞形態」の「相聞形態」に着目したい。そもそも安井はこの冒頭において〈さよなら〉を、「相聞を飾るかけがえない本質」と捉えているが、それは「さようなら」という挨拶そのものに、相手に対する「尊敬」を見出していると考えられる。が、かといって「尊敬」を意味的に理解するだけで、その本質に辿り着けるとは考えてはいまい。「尊敬」の本質とはその行為に他ならず、その行為の本質は「相聞」にある。つまり、互いに尊敬し合って初めて、「尊敬」という行為が本質的に成立するということだ。
安井が、自らを耕衣師に「餌をねだるほいと(=乞食)」と蔑み、耕衣師を「本能的に感知し、共鳴し、恐怖し、敬虔するだけ」の存在と無条件に崇める裏には、眼前の俳句の問題を無視し得なかった現実があった。もちろんそれは俳句だけにとどまらず、文学が抱える問題として、常に安井の眼前にぶら下がっていた。
『聲前一句』刊行から4年後の1981年、安井は俳句総合誌「俳句研究」5月号に、「傘寿の永田耕衣――その強靭な詩的運命」と題した長篇の耕衣論を書いている。本稿の冒頭で引用した「歳月の方法」が耕衣俳句の本質論であるとするなら、これは傘寿を迎えた耕衣の句歴を、その評価という観点から辿り直した随想風の批評文だが、安井は耕衣俳句の評価を辿るのに、近代詩の巨人とも言える西脇順三郎を持ち出している。
耕衣の遅々として推進してきた世界は、西脇詩のごとくに、むしろ観念主義としてうとまれる傾向にあり、耕衣言語のユニークな節回しに、多くの人はまだ耕衣の“読者”たりえていなかった。
(「傘寿の永田耕衣」より)
かねてから西脇順三郎と永田耕衣は、詩と俳句というジャンルの隔たりはあるにしろ、「諧謔」という、とりわけ崇高な文学に相応しくないと考えられていた卑俗な創作原理を共有していたことで、奇妙な同心円を描く存在として捉えられてきた。しかし、それは時として読者の理解の範疇に収まりきれず、崇高な観念の覆いに卑俗な細部の面白さが遮られ、読者の「尊敬」には至らなかった。付言すれば、読者にとって「尊敬」こそが、テクストを読み解くための欲望というエネルギーとなるのだ。言うまでもなくそれは読者の問題であって、西脇や耕衣の責任ではない。
詩人とは、がんらい不安なものである。孤独というより不安的存在と言った方が当を得ている。自分では、只今、自分が何者なのか、一体どうなっているのか分からないのが当然であろう。幾体にも変わりうる幻影のごときにすぎない。それを誰かが(つまり「読者」が)指摘しなければならない。そして、作者はその空(くう)なる中核を指摘される権利があるわけだが、逆に言えば、読者はその作者の空(くう)なる中核に存在できる権利があるだろう。
(「傘寿の永田耕衣」より)
ここでは「尊敬」という人生論的観念が、作者対読者という文学的行為に変換されて語られている。文学という行為には、この作者と読者という関係が不可欠なのは言うまでもない。ならば、作者の「空(くう)なる中核を指摘される権利」とは、作者に対する「読者の尊敬」であり、読者が「その作者の空(くう)なる中核に存在できる権利」とは、読者に対する「作者の尊敬」である。つまり文学における「尊敬」とは、作者と読者それぞれに固有の権利としてある。しかし、そこには権利としての優先順位があるのもまた確かだ。安井は、作者の「空なる中核を指摘される権利」、つまり読者から作者への尊敬が優先されるべきであると主張する。それは文学における批評の「掟」と言ってもよいだろう。
さて、西脇順三郎の例でもそうだし、耕衣の場合も等しく、優れて状況を越えたものは、なかなかその場で直射日光に浴しないものである、と言ってしまえばミもフタもない結論だが、要するに偉大なものにつねに私共の非力が断罪されているのだ、ということだけは知らねばならないのである。それさえ知らずに、現代俳句の批評において、おそろしく尊敬の心を失した批評の現実主義ばかりが目立つ昨今、上物がたちどころにクズにバラされぬとも限らぬ有様なのだ。
(「傘寿の永田耕衣」より)
安井が言っていることは決して難しいことではない。むしろ誰でも読めば分ることに違いない。「掟」には必ずと言っていいほど「裏」がある。読者が優先権を握っている「尊敬」ではあるが、それはつまり、作者は常に読者にとって偉大な存在として立ちはだかることを意味する。逆に言えば、作者の前で読者は常に、非力な存在として断罪される運命にある。非力は断罪されてもなお、偉大なるものを尊敬し続けなければならない。非力が断罪から逃れ、尊敬にそっぽを向こうものなら最後、非力から永遠に逃れることができなくなる。偉大なものの中に存在することはおろか、ひれ伏すことすら許されなくなる。「尊敬」とは他でもない、非力なるものが非力から脱する最後の手段なのだ。
そして、自らの非力を認識することこそ、短詩型文学に課せられた宿命なのだ。繰り返しになるが、重信の「敗北の詩」で言うところの、俳句形式の根底にある「敗北」を、自らの非力を認識することと捉えれば、「敗北」主義をとおして、「俳句」と「尊敬」が結ばれる。たとえば、本稿の発端でもあった俳句ならではの「師弟制度」とは、「弟子」として「師」を尊敬することがその土台であり、また、「尊敬」という行為として、「師」の俳句を引き継いでいくことは、「弟子」の最重要課題である。それは俳句の世界では半ば習慣化されていることだが、だからこそ「頭」で習って覚えればできるほど簡単ではない。
しかし、私は頭蓋骨に皮をかぶる俗人であった。この世界に〈さよなら〉を求めにやって来て、未だそれが思うようにならないことである。
(『聲前一句』より)
安井が困難に感じているのは、〈さよなら〉が象徴する「俳句という人生」そのものであり、それは俗人である以上当たり前であろう。しかし安井浩司とは、俳句のためとあらばどんな困難も厭わない俳人だ。安井の俳句人生を振り返るに、寺山修司から「牧羊神」を馘首されたこと、若手前衛俳人としての活動の拠点だった東京を離れ飛騨高山に隠棲したこと、散文による批評行為を自ら放棄したこと、そして俳壇と袂を分かち秋田でひとり作品を書き続けていることなど、それらは総じて俳壇からみれば「敗北」と映るのは間違いない。もちろんそうした人生の「敗北」の悉くを、安井自らが望んだとは言えるはずもないだろうが、「俳句」のために進んで受け入れたと言ったら言い過ぎだろうか。
「尊敬」を意味として理解することはできても、人生として行為することは極めて難しい。が、人生において行為し得なければ、それが文学に寄与することも有り得ないだろう。さらに言えば、近い将来、文学における批評理論のほとんどが形骸化してもなお、文学に「尊敬」が思想として生き残ることは間違いあるまい。繰り返すが、安井はこの『聲前一句』において、35人の俳人とその35句に対し、極めて厳しい審美眼をもって切り込んでいるが、そうした35の眼差し全てが、自らの非力の認識と引き換えに手に入れた「尊敬」によって裏打ちされている。それを読むことこそが、『聲前一句』を読む価値である。そして、『聲前一句』を読むとは、安井浩司という「敗北」に対する、真摯な「尊敬」である。
*追記
「文学金魚」では、昨年10月に開かれた「安井浩司『俳句と書』展」のキャンペーンとして、開催前より告知を兼ねた「安井浩司論特集」を行ってきたが、会期終了後も断続的にではあるが、引き続き数名の執筆者による「安井浩司論」を掲出してきた。その中のコンテンツの一つとしてこの「声前の眼」を10回に亘って連載してきたが、そもそも書き始めるにあたって目論んだ企図は、『聲前一句』で取り上げられている数多くの「前衛俳句作家」の方法論を作品に即して辿り、「前衛俳句」とは何だったのかを、信頼し得る「前衛俳句作家」のひとり安井浩司の審美眼を通して「総括」することにあった。文学のなかでも、旧態依然としたジャンルとして「アウト・オブ・ガンチュウ(眼中)」だったと言ってもいい「俳句」に「前衛」が存在したこと自体が、門外漢ゆえのロマンチックな欲望を刺激したのは事実であるが、おおかたの「前衛俳句論」が、「前衛俳句」内部の相互慰撫的な視線で書かれていることに失望するなか、テクスト至上主義による辛口な『聲前一句』こそが、「前衛俳句」に対する「正確な」眼を持っていると確信したからに他ならなかった。そしてその確信は半ば的中したように思えた。確かに、安井浩司という審美眼は、「正確」だった。しかし、そこに書かれていたことは、審美眼をはるかに越えた、「思想」だったのだ。はっきり言って「前衛俳句」に焦点を絞っていた自分に、「思想」は手に余るものだった。ゆえに「総括」の目論みはもろくも崩れ去った。しかし、なによりも「尊敬」に辿り着けたのは不幸中の幸いだった。もちろん安井浩司に対する新たなる尊敬だ。そしてこの尊敬は恐らく次の段階を欲望するはずだ。それは安井浩司を「師」として尊敬することである。
田沼泰彦
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

