もうずいぶん長い間、言葉の世界で生きている。僕にとって世界は煎じ詰めれば言葉である。もちろん人間だから、現実世界に満ちている音や匂いや味や手触りは知っている。しかし本当の意味で僕が僕でいられるのは言葉の世界になってしまった。いわゆる〝書き文字の世界〟だけが自分の生を証(あかし)してくれる場になったのである。確かに書き文字の世界にも音やリズムといった、言葉の意味を超えた心地よい生の波動のようなものはある。しかしそれはほとんど意識して来なかった。むしろ意識的に言葉から音を排除してきたのである。
中学から高校にかけて、多くの少年がそうだったように、僕も音楽に夢中だった。同級生とロックバンドを組んでいた。反抗期とないまぜになった幼稚な遊びだったが、僕の夢はソングライターになることだった。キャロルが解散してツイストやゴダイゴ、サザンオールスターズがデビューした頃の世代だから、日本のロックは今ほど盛んではなかった。ご多分に漏れず、僕らも英語の歌をコピーした。まだロックの本場は英米という時代だったから、憧れもあったが、日本語の歌詞ではどうしても満足できなかったのである。
当時、ガロというフォークグループの『学生街の喫茶店』がヒットしていて、サビの『片隅で聴いていたボブ・ディラン』を耳にした時に、これは絶望的だなと思ったのを覚えている。英語なら〝I don’t believe in Elvis/I don’t believe in Zimmerman/I don’t believe in Beatles〟(ジョン・レノン〝The dream is over〟)と沢山の言葉を畳み掛けられるのにと思ったのである。ソングライターに憧れていたが、僕の興味は言葉に向けられていた。英語の試験で苦労しているくせに、アルバムに挟み込まれた英語の歌詞カードとにらめっこしていた。どうやったら英語と同等の文字数を日本語の歌詞に詰め込めるんだろうと茫漠と考えていたのである。
僕らの時代までは不文律としてあった、日本の歌の一音一語原則を初めて大きく破ったのはサザンオールスターズの桑田佳祐だと思うが、最初、僕は彼らを一種のコミックバンドとしてしか見ていなかった。しかし桑田さんの一音に複数の言葉を乗せる方法は、またたく間に広まって驚くほどの洗練を見せていった。英語のイントネーションで日本語を歌う彼の方法はB’zあたりで完全に確立されたと思うが、今ではごく当たり前の歌唱法になっている。音楽的才能に溢れた人が友達にいたら、もしかして、と思わないことはない。しかしやはり僕はソングライターになれなかったし、ならなかっただろうと思う。
大学に進学して詩に触れた時に、僕の中からすっぽりと音楽への興味が抜け落ちた。僕は言葉で自己を表現したかったのである。僕が魅了されたのは戦後詩や現代詩といった自由詩の潮流(エコール)だった。それは究極を言えば意味から構成される理知的な詩だった。根が極端な試みを好む性格もあって、僕はあれほど好きだった音楽を自分のまわりから排除し始めた。できるだけ夾雑物を省いて文字の世界に集中したかったのである。詩人が詩を朗読することにも批判的になった。ほとんどの詩は黙読を前提に書かれている。音楽性という面で書き文字の詩が歌にかなうわけがない。中途半端な音への色気は詩の本質を見失うことに繋がりかねないと思ったのである。
ただ極端を好む性格は、ある地点にまで達するともう一方の極に振り戻ってしまうようである。DiVaというバンドが存在していることは知っていたが、CDは金魚屋の企画で谷川俊太郎、谷川賢作さん親子にインタビューすることを依頼されてから初めて本格的に聴いた。多くの詩人がそう感じているだろうが、歌の歌詞は時に激しく神経を逆なでする。詩に比べて歌詞が劣っているとは思わないが、詩人の倫理・矜持として、言葉の表現という意味でこれではいけないと感じることが多いのだ。
だから仕事中は絶対と言っていいほど日本語の歌を流さない。ただ時間的制約もあり、しばらく仕事中もDiVaを聴き続けた。DiVaの歌は心地よかった。DiVaの楽曲と一般的なJ-POPは何かが決定的に違っていた。歌になってしまえば歌詞とメロディを区分することができないのはDiVaもJ-POPも同じである。楽器の使い方やアレンジ、高瀬麻里子さんのボーカルも歌と渾然一体になっている。しかし詩とメロディという、歌を構成する二大要素のうち、詩の質を明確な意志をもって変えればメロディの質も必然的に変化する。DiVaはこの相関的な質の変化を初めて意識的に楽曲化したバンドだと思う。
いわゆる言文一致というが、話し言葉と書き言葉はイコールではない。表現である以上、歌詞では当然、意味やイメージが絞り込まれている。メロディがあるから話しかけられているような親しみを感じるが、歌詞は本質的に書き言葉なのである。話し言葉はたいていの場合、もごもごと曖昧に始まり、ある地点まで来て唐突に一つの意味やイメージに結晶する。単純化して言えばそれが歌詞の醍醐味だと言える。歌詞は話し言葉の意識で書かれた書き言葉である。しかし詩人の書く詩は、たとえ平明な抒情詩であろうと書き言葉の意識を大きく逸脱することがない。最初からある意味、イメージが、表現の核として露わになっている。
ぼくもういかなきゃなんない
すぐいかなきゃなんない
どこへいくのかわからないけど
さくらなみきのしたをとおって
(谷川俊太郎『さようなら』)
『さようなら』は全十八行の詩だが、最初の数行で全ての主題が表現されている。平仮名で書かれていることからわかるように、『ぼく』はまだ幼い男の子である。彼は『どこへいくのかわからない』まま激しい出発の衝動に駆られている。『さくらなみきのしたをとおって』とあるように、少年にとってそれが死と再生の通過儀礼であることが暗示されている。この詩は最初の一行から詩人の強い思想・感覚で貫かれているのである。なぜ『もういかなきゃなんない』のかが説明されていない以上、物語に展開することもない。親離れや死といった様々な解釈を包含しながら、ただひたすら少年の孤独で純粋な意志が表現されているのである。DiVaの『さようなら』はこの詩の本質を楽曲化している。DiVaの音楽は僕を苛立たせることがないのである。
土曜日の朝のベッド
いつまでも寝ていたい
もし明日が永遠に来ないとしても
それでいいそう思うのも夢
人は本当はいつもひとり
でも嘘ついて生きている
こわいから
(谷川俊太郎『土曜日の朝のベッド』)
谷川俊太郎は初期から一貫してリフレインを多用する詩人である。この作品では『土曜日の朝のベッド』が繰り返される。明示されていないがベッドでまどろむ女性が主人公である。この詩で表現されているのは人間の本源的な孤独だ。寂しさに耐えきれずに『明日が永遠に来ないとしても』と死を考えても、それは一瞬の夢として通り過ぎていく。『人は本当はいつもひとり』なんだと呟いても同じことだ。一人っきりで生きていくことなどできはしない。俊太郎詩のリフレインはアプリオリに存在する作品主題を純化・深化させるために使用されている。リフレインの繰り返しに乗って言葉を書き連ねるうちに、自らが発した言葉の嘘が暴かれ、本当に表現したい痛々しくも純粋な主題が剥き出しになるのである。
ばかだからすきよ
ばかみたいはきらい
あなたはばかだからすきよ
あなたのばかみたいはきらいよ
(高瀬”makoring”麻里子『ばか』)
『ばか』はDiVaの歌姫・高瀬”makoring”麻里子さんの作詞である。冒頭の『ばかだからすきよ/ばかみたいはきらい』の二行でこの詩の主題は表現されている。『ばか』と『ばかみたい』は違うのである。『ばか』は理知や社会性をまとわない人間の本源的真姿のことである。作家は恋人の裸の自我を愛しているのであり、また自らの裸の自我を愛されたいと願っている。それをユーモラスに表現している。この詩は普通の歌詞の書き方で書かれていない。言葉は一直線に本質へと向かっている。DiVaの三人が作詞した作品は決して多くないが、彼らは俊太郎詩から感受した詩の本質を正確に作品化している。
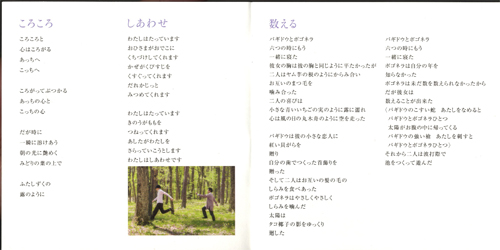
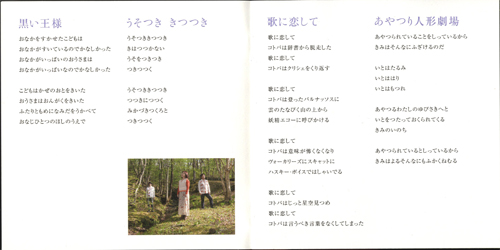
DiVa新譜『うたがうまれる』同梱のブックレット。16ページ構成の小冊子になっている
たいていの場合、話し言葉の意識で書かれる書き言葉の歌詞は、適度に物語を援用しながらそれを詩的な観念やイメージに収斂させる疑似物語(小説)詩である。例えば『あの日笑顔で駆け寄ってきた君は』、『照りつける日射しのもとでひとりバスを待ちながら』といった描写で時間の流れと人の心変わりを表現し、サビの部分でそれを『愛してる』あるいは『空は抜けるように青かった』と一つの詩的観念やイメージに定着させるのである。素晴らしいメロディに乗れば、僕らは大きなカタルシスを得ることができる。しかし詩人が書いた優れた詩は最初から一つの断言である。稲妻が閃いた後に音が聞こえてくるように、色も光も音もない闇を詩人の言葉が切り裂く。まず直観的断言があり、その後に言葉が響くのだ。そしてすべては再び闇の沈黙に戻っていく。DiVaのいきなり言葉が溢れ出し、ふっと虚空に消えてゆくような繊細な楽曲は、そのような詩の特性から生み出されている。
僕は戦後詩や現代詩といった二十世紀の詩の遺産を、正面から受け継ごうとしている二十一世紀の詩人だ。僕の興味は基本的に理知的な思想詩にあり、抒情詩に対して継続的な興味を抱いてこなかった。しかしインタビュアーの一人として、谷川俊太郎の詩を初期から近作まで通読して心から驚いた。比較的丹念に俊太郎詩を読んでいた一九八〇年代、誤解を恐れずに言えば、谷川俊太郎は戦後詩や現代詩といった詩のメインストリームから外れた抒情詩を代表する作家だった。だがこの三十年ほどで俊太郎は驚くべき大家に変貌していた。
大家というのはもう追いつけないという意味である。俊太郎ほど様々な詩の書き方(詩法)を駆使して自在に書ける詩人はいない。ほかの詩人が彼の後を追っても、もう手遅れだと思う。それは戦後詩や現代詩といった、狭い詩の世界のさらに狭いカテゴリーの問題ではない。詩人たちが生涯をかけて取り組む自由詩の〝自由〟の本質に関わっている。俊太郎は形のない自由に形を与えながら、絶えず変貌していく詩人のあるべき姿を体現している。
しかし紙に印刷された詩を読んでいただけでは、僕は俊太郎詩の大きな変化を的確に感受できなかったと思う。俊太郎詩の可能性は一九七〇年代末から八〇年代初頭にかけてほぼ出揃い、八〇年代から九〇年代にかけて確信的に先鋭化されていく。それはDiVaの活動の歩みとほぼ同期している。俊太郎があまりにも高名であるため、一部では谷川賢作が、父であり、DiVaのメイン作詞者である俊太郎から一方的な影響を受け、恩恵をこうむっていると思われているようだがそれは誤りである。この二人の芸術家の間にあるのは対等で良好な相互影響関係である。
DiVaの歌によって自らの詩が内包していた音楽性を引き出され、音楽の一部として相対化されなければ、俊太郎は『ことばあそびうた』や『よしなしうた』といった平明な平仮名系の作品を、ああも確信をもって書き続けることはできなかっただろう。また谷川賢作は決して能弁な音楽家ではないが、彼が肉体的に理解している詩の本質を前提としなければDiVaの歌は生み出せない。詩を素材にした歌は過去にもたくさんある。しかし詩を本当の意味で歌にし続けているのはDiVaだけである。俊太郎も賢作も恐ろしく勘のいい芸術家である。
僕は言葉の意味(思想)を中心に据えることで、そこから音や無意味など無限の表現可能性を引き出せると考えていた。しかし俊太郎詩を通読し、DiVaの曲を聴き続けるうちに、別の方法があることに気づいた。できるだけ言葉が持つ音や意味、イメージを鮮明にして客体化し、それをモノとして組み合わせることで輻輳化した意味(思想)を表現できるはずだ思ったのである。今の僕は抒情詩はもちろん、詩の朗読に対しても肯定的である。話し言葉の意識で書かれる歌詞があり、書き言葉に徹する歌詞があるように、詩にも様々な書き方がある。むしろ自由詩の詩人であるならば、当然のように抒情詩や朗読用の詩を書ける力を持つべきだろうと考えている。自由詩であることが、戦後詩や現代詩、抒情詩といったすべての詩のカテゴリーに先行する。
詩を歌詞にするDiVaの音楽には特殊な面があると思う。もしかすると普通のポップスとしては受け入れられないかもしれない。しかし今までにない独自の音楽である。また詩人の美意識に貫かれた、沈黙と紙一重の詩を素材にするDiVaの曲は、言葉に対して繊細な感覚を持つ詩人たちに愛されるだろう。詩人は自由であるべきだ。だが詩を読んでいるだけでは思想や感性の幅を拡げることはできない。谷川俊太郎とDiVaがそうしたように、触れ合い衝突しながら、自らの営為を相対化してくれる他ジャンルの芸術家との交流が必要だ。
まだささやかな試みを始めたばかりだが、僕は少年の日に捨てた音楽が自分の詩の中に戻りつつあると感じている。詩を暗記せよと言われたら、多くの人が抵抗を感じるだろう。しかし今日も誰かがDiVaの歌を口ずさんでいる。詩を歌っている。音のある詩は素晴らしい。誰もが心の中に詩を、その表現の本質を所有することができる。ポップスの作詞法に妥協しなくても詩は音楽になり得る。詩は音楽を内包することができる。DiVaがそれを教えてくれたのである。
鶴山裕司
■ DiVa 『ばか』 詩・高瀬”makoring”麻里子 曲・谷川賢作 ■ (アルバム『うたっていいですか』収録)
■谷川賢作オフィシャルサイト■
■DiVa取り扱いネットショップ fuku no tane■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


