『砂』はガリ版刷りA5版(No.11のみ活版印刷)で、安井浩司、高橋彦一郎、前田希代志、高桑廣緒、柴田三木男氏(以下敬称略)によって創刊された。昭和37年(1962年)から40年(65年)にかけて通巻14号が刊行されている。編集・発行人は一貫して柴田である。今回と次回の2回に分けて『砂』を紹介するが、今回取り上げるのはNo.1からNo.7までで、安井の処女句集『青年経』特集が組まれた前半部である。以下に『砂』の簡単な刊行データをまとめておく。
・No.1 昭和37年(1962年)6月5日発行 10ページ
・No.2 昭和37年(1962年)8月5日発行 12ページ
・No.3 昭和37年(1962年)10月5日発行 16ページ
・No.4 昭和37年(1962年)12月5日発行 12ページ
・No.5 昭和38年(1963年)2月5日発行 12ページ
・No.6 昭和38年(1963年)4月5日発行 10ページ
・No.7(青年經特集号) 昭和38年(1963年)7月10日発行 20ページ
・No.8 昭和38年(1963年)9月5日発行 12ページ
・No.9 昭和38年(1963年)11月5日発行 10ページ
・No.10 昭和39年(1964年)1月5日発行 14ページ
・No.11 昭和39年(1964年)3月5日発行 14ページ
・No.12 昭和40年(1965年)3月15日発行 10ページ
・No.13 昭和40年(1965年)6月10日発行 12ページ
・No.14 昭和40年(1965年)9月20日発行 12ページ
『砂』創刊号の表紙には『創刊の記』が掲げられている。『黄昏の波が静止する所から、渚の〈砂〉が始まる。それは風雪に耐えた思考の岸や、砂丘となり、実在の陸となる。――この混濁の〈砂〉。私たちは願い、ねがう詩を現実と永遠の接点に宝石のようにちりばめようと試み、幾たび〈砂〉へ埋もれさせてしまったことだろう。そして明日もまた埋れさせていくだろう。――ただありふれたこの新鮮な〈砂〉の誕生をひそかに祝いたいと思う』とある。謙虚な〝創刊の辞〟だが、『砂』同人は前衛的創作姿勢を共有していた。
温む胸像鳥葬陣型回診来る 高橋彦一郎
父の棺おく筵があなたの略奪地 安井浩司
内部意識の煮つまる夜の黒い雨 高桑廣緒
世界線のつつと佛陀の尻へ回る蛇 前田希代志
櫂の重さで男女航く暗い海峡 柴田三木男
(『砂』No.1 昭和37年[1962年]6月より)
『黒』同人の『傷だらけの闇だ ぼくらだ 生きている』(安藤三佐夫)、『工煙くさい逢曳の眸を陽の運河に』(朝生火路獅)、『少年の帽子横向き鉄材切る』(川島一夫)といった社会性俳句の影響を受けた句と比較すれば、『砂』同人の芸術至上主義的指向は明らかだろう。柴田三木男はNo.7で上京当時を回想して、『「群蜂」の前田希代志、松井牧歌、「黒」の安藤三佐、朝生火路獅らと知ったのもこの頃であったか。僕ら二人(柴田と安井のこと)に取って、これら同世代の俳人はやはり異質の人間でしかなかった』と書いている。安井は『黒』に同人参加したが、いずれ『砂』のような前衛誌を求めたかもしれない。
処女句集『青年経』の刊行(昭和38年[1963年])を間近に控えていたこともあり、安井は旺盛に作品を発表している。N0.01からNo.06(No.7発表の1句は第二句集『赤内楽』に収録)までに52句を発表し、内27句が『青年経』に採られている。岡野隆さんの安井浩司未刊句集の調査を読むと、約50パーセントという句集収録率はかなり多いようだ。また評論も積極的に書いている。No.02には『青年俳句の発生的要素をめぐる感想』を発表しているが、これは安井なりの『砂』創刊目的の説明だと読める。
かような風潮(社会性俳句の隆盛を指す)に対し私達の賛同と批判の二ツの均衡は極めてアンバランスだったと思う。なぜなら賛同するものはそれで良かったが、その他のものは批判に一貫性を欠きこの問題を身近におきながら当時なによりも未成熟であったからである。(中略)それは社会性俳句が今ひとつ未熟であった罪と、戦後という不信の世界の中で自分を自らの手で飼育せねばならなかった独裁性が悪しき意味での個人主義的な気概を持たせたという罪であろう。
(安井浩司『青年俳句の発生的要素をめぐる感想』 『砂』No.2 昭和37年[1962年]8月)
安井は『安井浩司『俳句と書』展』所収インタビューで、昭和30年代から40年代にかけて、前衛俳句にとって社会性俳句が巨大な〝仮想敵〟であったという意味のことを述べている。それほどまでに社会性俳句は隆盛を極めたのである。安井は『青年俳句の発生的要素をめぐる感想』で社会性俳句に対する〝異和感〟について論じているのだが、同世代の多くの若者が社会性俳句に異和を感じながらそれに対して有効な批判をできないでいるとも書いている。社会性俳句を提唱した世代が、曖昧なものであれ〝戦争体験〟に立脚していたのに対し、戦後の青年たちはなんの拠り所もなく、『自分を自らの手で飼育せねばならなかった』のである。
戦中派はそれ自身人間的体験から動し難い内容と独自の抵抗感覚を持っているのだ。これらの青年(戦中派のこと)は私達のいわゆる戦後派的知性とは被害体験から発し脅かされ続けていると云いたいのだろうか。しからば眞の被害とは何かということを自らの状況の中で追及すべきであろう。戦後派的知性を発生論から全面的に被害されたものとしてのみ意識し意識そのものゝ変質を求めることなくひたすら俳句美の完成を急ぐとしたらそれは世で好んでいう亜流であり妄想に近い状況設定となる、ということを恐れていいと思うし、いま与えられた新しい課題は社会性俳句を意識の上で克服することだろうとも思う。
(同)
戦後社会の出発点が戦争体験にあるとすれば、従軍体験のない戦後世代もまた戦争の『被害体験から発し脅かされ続けている』ということになる。しかし戦後の青年たちがそれを我がものとして引き受けても、それは社会性俳句第一世代の『亜流であり妄想に近い状況設定となる』可能性がある。ならば戦争体験という絶対的な共通項を持たない戦後の青年たちは、なにによって『社会性俳句を意識の上で克服』できるのか。安井の論はそこへと絞り込まれていく。
これらの俳句(社会性俳句に異和感を覚える青年たちの俳句)を横に読み楽しんでいくとき一見はじめから完成した思想で出発したかの如く見える。戦後を全き〈零〉の点と見て発想している作品の多くを拾うことも出来る。(中略)これらの人達は被害者意識を一寸たりとも脱皮出来ない青年俳句に比べて、戦後から何が始まり何が鮮血を新しく流出させているかを敏感にさとる人達であり仕事の意義は重いと思う。いまこれらが各個において一つの実像を結ぶとすれば、まだ被害されないものがいつか犯されるのではないか、また犯されつゝあるのではないか、その流血とはどんな物でどのように私たちの肉と魂をながれるかという新鮮な不安を超えて闘う新しい人間像であろう。
(同)
社会性俳句に対峙し超克し得る思想を明示できているわけではないが、安井がその焦点を『まだ被害されないものがいつか犯されるのではないか、また犯されつゝあるのではないか』と予感しているのは重要である。その後の安井の評論は、俳句の原理を問う高度に抽象的なものへと向かっていくが、その原点にあったのは社会性俳句への異和感である。現実体験と状況を詠むだけでは、決して俳句文学の本質には届かないだろうという予感である。安井のアポリアは人間の実存的体験(戦争による被害者意識)を超えた傷を探ることであり、まだ誰も明らかにしたことのない俳句本来の傷の探究へと向けられていく。
少し余計なことを書き添えておけば、社会性俳句の認知度は俳句界と自由詩の世界で大きく異なる。現代詩人で社会性俳句に熱い視線を注ぐ者はほぼ皆無だと言ってよい。社会性俳句を飛び越して新興俳句と前衛俳句に興味を持つのが常だ。自由詩は大正期のプロレタリア詩の時代から戦後詩に至るまで社会詩の流れを持っており、その限界を知り尽くしている。確かに戦後の『荒地』派は一種の社会詩だが、彼らはあくまで個の自我意識に留まる芸術至上派であり、プロレタリア詩が突入していった無防備な社会参加・変革姿勢を周到に避けていた。社会性俳句は自由詩では新日本文学系の詩ということになるだろうが、それらが戦後の詩の主流になることはなかった。
また詩人たちにとっても戦争体験は特権的と認識されたが、その限界は昭和29年(1954年)刊の谷川雁『大地の商人』や昭和39年(1964年)刊の堀川正美『太平洋』などで露わになっていた。『太平洋』刊行直後の書評で、政治的にはノンポリを貫いた渋沢孝輔は、鋭敏だと世評高かった堀川の感受性を『感受性の消耗に過ぎない』と切り捨てている。堀川の世代で『荒地』派的な詩の可能性は尽きる。従軍体験を持たない戦後の詩人が戦争体験に基づく思想・観念を受け継ぐことなどできないのである。
いずれにせよ社会事象を題材に詩を作ることが驚きをもって迎えられるという事態は自由詩の世界では起こらなかった。詩人たちは金子兜太の『無神の旅あかつき岬をマッチで燃し』を好意をもって読むだろうが、『広場一面火を焚き牙むく空を殺す』『原爆許すまじ蟹かつかつと瓦礫あゆむ』といった社会性俳句にはなんの興味も示さないだろう。それは散文的な思想・感慨吐露であり詩である必然性を持たない。特に最短形式である俳句では救いがない。詩であるためには根本的に表現手法を変えなければならない。自由詩人から見れば、『戦争が廊下の奥に立つてゐた』(渡辺白泉)や『戛々とゆき戛々と征くばかり』(富澤赤黄男)の方が優れた社会批判俳句なのである。
自由詩の世界では戦後詩と現代詩がほぼ同時に成立している。戦後詩は従軍体験を主題にせざるを得なかった詩人たちの試みであり、現代詩はなんの感覚的・思想的拠り所も持たない戦後の青年詩人たちが始めた試行である。現代詩は入沢康夫・岩成達也の同人誌『アモフル』に所属した詩人たちによって完成形に近づいたが、彼らはできる限り言葉の意味伝達性を遮断し、戦後世界に拮抗し得るような抽象的言語構造完体としての作品を目指した。それは詩人による自由詩の自己規定である。意味もイメージも自由詩の決定的存在理由にならない。社会の変化に呼応して自由に変わりつづける詩の構造が、何一つ表現の制約のない自由詩の存在基盤なのである。
俳句界で何の体験的・思想的拠り所も持たない戦後の青年独自の試みを探れば、その筆頭は安井の文学だろうと思う。社会性俳句が俳壇の主流として認知されていることからもわかるように、それは俳句伝統にのっとった主題の変奏に終始した。しかし安井文学は古くて新しい。それは俳句原理に食い込んで、今まで誰も見たことのない傷を抉って『流血』しているのである。
鶴山裕司
■『砂』No.1 昭和37年(1962年)6月5日発行■
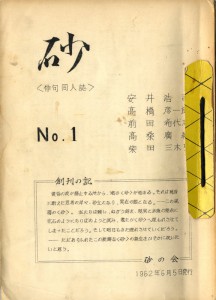
【作品】
青年経 安井浩司
さくら吹雪の域(くに)より手足にだるさ吊り
孤島に曝書すひそかに排卵期の主婦と
夜は遠の冬木の翼で愛降らす
重なり眠むる肉の隙間に寒卵 (①『青年経』)*1
緑蔭の歩みにたえて婚約す
父の棺おく筵があなたの略奪地 (①『青年経』)
牛を叱るビルより翁の首出して
【註】
* 句の後に収録句集名と章を表記してある。数字①、②…は第1句集、第2句集…の略。
*1 定稿では『眠むる』は『眠る』。
【安井浩司関連記事】
・PRコーナー
安井浩司
東京都北区志茂1-14-10 歯科医。26才。ビールには弱いが、洋酒はずい分強い。趣味は推理小説を読むことと、あまり当たらない馬券を買うこと。同人中ずい一の恐(愛)妻家の称あり。
■『砂』No.2 昭和37年(1962年)8月5日発行■
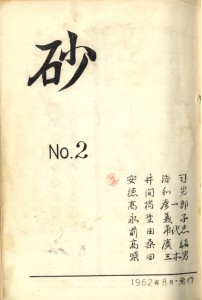
【評論】
青年俳句の発生的要素をめぐる感想 安井浩司
現代俳句の流れが今日ほど枝葉を多彩に岐けて一貫した方向を掴むことが難いといえよう。まして次の時代を担う若い人たちに一貫性をその権威を求めることはより困難になりつゝあるといってよい。むしろ〈一俳人が一俳論を持参すべきだ〉と聡明な一部から言われているように私達もそれに近い形で発展するだろうし又そのように発生してきたことも確かだった。いま既に活躍している新鋭たちにもその一貫性と共通の運動をみることは難く、彼らが戦後派的知性や明日の詩歌のエッセンスを全て代表するものとはいいきれまい。むしろ今日の青年が彼らの混濁の世代に散在していて俳句を通してどんな人間像を求めているかを知ることが重要な課題の一つであろうと思う。このように戦後を新らしく誕生した世代層の人達の俳句の世界を通してみられる思想や文学的主題は全く捉えにくい一貫性のないものなのだろうか。所謂前衛俳句の枝葉を飾る〈亜流〉であろうか。このような懸念に対して青年達自身はどのような考えを準備しているのだろうか。私達はかような事象的な眼と、己れの思想の眼とをきっぱり区別して自らの全てを答えるべきであろうと思う。
いま私達が何かを見、語り俳句の新しい流行を求めていくとき、私達の〈戦後派的知性〉がどのように目醒め続けていたかということを措いては、私達の混沌とした現状と未来を語ることは出来ない。なぜならこれは私達の精神風土の問題だが〈君らはどのように何から出発し又出発しつゝあるか〉という生命根源的な問いに対して、強いて答えようとすればそれは時間的にも空間的にも巨大な戦後から全てが開始されたと云う外なかったのである。実際私達は時間的に戦後を生きた歴史を書きかえようもないし又空間的にこの個我を拡大してきてしまった人間的体験をどうしようもないのだ。それでは私達の個我覚醒の途上にあった私達なりの唯物論的戦後とは一体何であるのだろう。それは写生俳句やかつての社会性俳句とは異質だ。戦後を初めて個我を拡いていった私達が異質的にこれを答えることが私達の課題であったかも知れないのである。この問いかけは青年俳句を探ぐるにきわめて大切でその疑念を明らかにする為私達と今日も現代俳句の根底に流れている社会性俳句との相関関係を措いては語ることが出来ないと思う。これは青年俳句の捉え方に対する一つの提示だが、なぜなら私達と社会性俳句が共に〈戦後体験〉の問題を歴史の上で共通の場におき己れに適した形をまさぐり合っていたからに他ならないからである。戦後体験の問題に共通の場をもちながら社会性俳句にその本質と技術遂行の苦悩をまともに見た私達は、すでにこの運動に対し同調と反発という二つの形で現われようとしたことを見逃してはならない。今日社会性問題の成熟は実作にかけられ方法論にその試金石が持ち込まれて現在に至ったと見てよかろうが、総じてこの作風に〈被害されたもの〉としての発想の類似性を私など感じたが社会性の現代意識を拡げ個から全体をみる眼を得た仕事の新鮮さは意義あるものだった。
かような風潮に対し私達の賛同と批判の二ツの均衡は極めてアンバランスだったと思う。なぜなら賛同するものはそれで良かったが、その他のものは批判に一貫性を欠きこの問題を身近におきながら当時なによりも未成熟であったからである。それは戦後という場におかれた青春性を各自の個我覚醒の途上に散在されたままの状態で賭けられたことは致し方ないとしても戦争体験という巨大な類似性に立つ発想への断層感に敏捷になりその詩的精神風土まで異質のものと感じひどい異物感を覚え始めたのではなかったろうか。それは社会性俳句が今ひとつ未熟であった罪と、戦後という不信の世界の中で自分を自らの手で飼育せねばならなかった独裁性が悪しき意味での個人主義的な気概を持たせたという罪であろう。その意味でこれらが異物感という共通の印象批判を除いては、自らの独裁性に詩精神形成を全てまかせてきた散在者であり文学的技術が未熟であったことと相俟っておよそ現代俳句の表面に出ることなく今日に至っているのである。しかしこの人々が異物感的に社会性俳句に対峙したとしても社会性俳句とは実際何であったろうか。それは事実どんな人達にも不透明な呼び方でしかなかった。社会性俳句とは結局何であったか私達はそこに被害者意識を共にする世代層の祈りと抵抗を感じることに精一杯だったかも知れない。ともあれ今日の俳句へその方法と主体をもち込んだ人々や意識をひっくるめて広く解して文章を進めよう。
以上の大雑把な事柄に従い青年俳句を便宜的に分けると①社会性俳句に同調していったもの②これを異質に受け止めたもの③この中間に育ったもの④全く別の場で俳句を進めたものなどが考えられる。いま①同調と参加したものを今日の新しい俳句の波につらなる一本の軸として取れば、他②③④は前述のような詩精神の形成過程を踏んできてまことに混濁という他はない。①を前者とし②③④を後者として具体的に探ってみよう。前者と呼べる若い人達、社会性意識の中に主体性を考え技術の変革を求めかつ今日の前衛俳句に至る一連の流れをバックアップしこれらと共通の課題のうちに青年像を創る人達だ。かつての〈青年俳句〉というグループとその残兵が印象に残るが〈風〉〈麦〉〈寒笛〉などの若い人達が社会性の濃い詩を磨いており社会性詩論は何よりも荷重な母胎であった。この一貫した詩的現実こそ今日に至りその母体を離れては掴み難い。俳句の抽象化に従い旺盛に方法論の積み重ねを実験しているとしても根底に於て極めて一直線に今日の詩精神を形成していると云ってよい。そのため今日的状況の全てを背負いこむと同時に戦中派世代と最短距離の意識をもつ青年像たちとも云える。これらの仕事は比較的現代俳句の表面にあり人びとに理解され鞭うたれているので多くは述べないが青年どうしという場から今一つ指摘しておくことがある。それはこの人達の意識の類似性と次元の質の問題だがこの仕事に共通して次元の低さに嵌る陥し穴のあることである。意識の高次元化とは何か-さしづめこれらに限っていえる言葉だ。なぜなら高次元化とは意識それ自身の問題なのだから、このような人達の俳句には〈被害されたもの〉というべき意識が極めて受動的に描き出されていることである。それは社会性俳句に同調し被害者意識を無批判に受け入れた側面であるとしたらどうだろう。戦中派はそれ自身人間的体験から動し難い内容と独自の抵抗感覚を持っているのだ。これらの青年は私達のいわゆる戦後派的知性とは被害体験から発し脅かされ続けていると云いたいのだろうか。しからば眞の被害とは何かということを自らの状況の中で追及すべきであろう。戦後派的知性を発生論から全面的に被害されたものとしてのみ意識し意識そのものゝ変質を求めることなくひたすら俳句美の完成を急ぐとしたらそれは世で好んでいう亜流であり妄想に近い状況設定となる、ということを恐れていいと思うし、いま与えられた新しい課題は社会性俳句を意識の上で克服することだろうとも思う。
これらの存在に対して後者②③④とも呼んだまことに混沌とした詩精神の形成を踏んでいる人達に就ても述べておかねばならない。しかしこゝでは②社会性俳句を異質的に懐疑的に受け止めたものに就て述べるに止めたい。それは①社会性論へ同調し今日に至る青年俳句の主役に対抗し一つの性格を現わしており同時に青年俳句が混沌として捉え所のないという要因を持ち合わせているからである。一昔前のことだが〈万緑〉の若い人や〈牧羊神〉という同人誌にその萌芽があったようだが私の周囲では〈青年俳句〉で異才をはなった柴田三木男や大岡頌司の仕事が見られる。しかし努力されている詩精神は各方面に散在しその若い芽を感ずることが出来る。これは戦後派的知性を自己の純粋性を信ずることにより独自の知性を得ようとした人達である。戦後とは犯したもの犯されたものあるいは被爆されたものではなくて、むしろそのような観念(拘束観念と呼び)から自分を開放し戦後とはそれ自身が一つの実在以外の何物でもないという考え方に立つに至っている。私達は戦後という実在的状況に自我覚醒の道をもち個我への執着を余儀なくされ、このような考え方は戦後派的実在感を認識する思想というよりむしろ〈実感〉として詩へ多くの感性が追ってしまったことをどうしようもない。そのため互に自己を純粋に保つ俳壇散在者の相を呈してくる。従ってこれらを横に結ぶ一貫した詩論を求めることの難さがこゝにある。自己の発生母胎に対する認識は各個我の実在的状況においてのみ捉えられるに過ぎず、これらにとって戦後とは無条件降伏にも似た自由の大地だったからである。これらの俳句を横に読み楽しんでいくとき一見はじめから完成した思想で出発したかの如く見える。戦後を全き〈零〉の点と見て発想している作品の多くを拾うことも出来る。荒地に突如置かれた人間がどう生きるかどう嗅覚を磨いていくかという問題を汲みとることも出来る。このような点で社会性俳句を進めた青年達と極めて異質な体質を形成してきたと云えよう。これらは社会性俳句に対する批判というより社会性俳句そのものが一つの明確な理論でない以上かような異質感を持ち合わすことによって、ひたすら傍観して来たと云う方が正しいかも知れない。この人達に今一つ附け加えると戦後という零の地点に自分が先ず存在しているという異常な自信と不安だ。これは無傷のものが裸に晒されているというどうにもならない実在感から始まりそれ故に何よりも敏捷にして独自の感性を育て続けたと信じたい。これらの人達は被害者意識を一寸たりとも脱皮出来ない青年俳句に比べて、戦後から何が始まり何が鮮血を新しく流出させているかを敏感にさとる人達であり仕事の意義は重いと思う。いまこれらが各個において一つの実像を結ぶとすれば、まだ被害されないものがいつか犯されるのではないか、また犯されつゝあるのではないか、その流血とはどんな物でどのように私たちの肉と魂をながれるかという新鮮な不安を超えて闘う新しい人間像であろう。
以上のことがどんな形で現れようとするか、これは今後の課題でもある。今最後に新しい俳句の波の一角の青年俳句に散らばっている素材とその完成の危機について述べ結論としたかったが、もはやスペースがないのでいづれの機会にゆずりたい。
【作品】
青年経Ⅱ 安井浩司
青海へ頭垂れ佛陀と同穴する崖 (①『青年経』)
靴へ肉つまって躍ねたか朝の弔
若い妻が無名の旗振る紅葉の谷
雁よ死ぬ段畑で妹は縄使う (①『青年経』)
喜んで犬死ぬばかり曝書の前 (①『青年経』)
夏野に車輪わが蟹轢き来しと思う
死ぬ直前の脱糞たれかを青麦撫で (①『青年経』)
【安井浩司関連記事】
・PRコーナー
安井浩司(東京都) 昭和11年生。〈牧羊神〉〈青年俳句〉を経て33年〈貌〉創刊。現在〈琴座〉同人。宝井其角を愛し、かたわら実存色の強い作品を書く。
■『砂』No.3 昭和37年(1962年)10月5日発行■
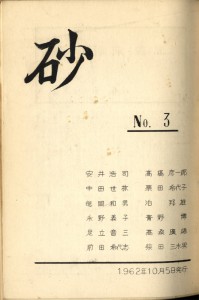
【作品】
青年経Ⅲ 安井浩司
廃墟へ蜜柑の青さで頭うち合うバス
砂嚢のごとく僧を噛み昇降機の着地
色なき車輪組みゆく海辺流れる観音
群衆やもまれて堕ちぬ笑いの能面 (①『青年経』)
首環より落ちている鷹ゴム焚く奥 (①『青年経』)*1
林に鼠垂れこめ朝のミルク散らす (①『青年経』)
轢死者の胸むせかえるパン屑の山
地面の瘤をめぐってかえる燕(つばくろ)や (①『青年経』)
拇指大の友浮く海へ母船刺して
黄ナいろに跫音去り空家の豆袋 (①『青年経』)
黒杭刺すたそがれ菫にとび散る兄弟
鏡の中より威さるゝ日の獅子日陰ゆき (①『青年経』)
死斑のごとき魚眼もつ夜の果樹園の岩
夜空に増える何のかたまり花火あそび
朝(あした)罵倒す 父中心に去る白いマラソン (①『青年経』)
貌よせ牡蛎喰う晩婚すだれを攻める海
【註】
* 句の後に収録句集名と章を表記してある。数字①、②…は第1句集、第2句集…の略。
*1 定稿では『首環』は『鉄環』。
■『砂』No.4 昭和37年(1962年)12月5日発行■
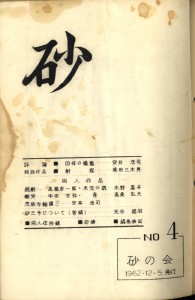
【評論】
回性の嬌態 安井浩司
芭蕉に不易流行という文芸の本質を衝いた言葉がある。この言葉は、俳句の数々の変遷を重ねた歴史のなかを、つねに俳句の生命を支えてきた巨きな石柱のように思える
枯枝に鳥とまりけり秋の暮(*1)
旅に病んで夢は枯野をかけめぐる
私は右の二句にきわめて興味を覚えるのである。枯枝に-の句は、蕉風における〝寂び〟開眼の一句だといわれ、旅に病んで-の句は、諸々の漂泊の果の臨終の句である。いまここで、俳句に描かれた思想に拠って右の二句を対比してみるとき、これらの句の思想の異質さについて、興味ある問題を見出すことができる。
先づ枯枝に-の句だが、私はこれの水も漏らさぬ完遂された思想の姿に驚くのだ。人間が、自然という永遠性に吸い込まれ、一握りの生命体が完全に燃焼し事を終えたと思われる安定感、これ以上にも以下にも何物も存在を許さない俳句的思想の完璧さ。いわゆる蕉風の完全円の〈典型〉を瞠るのである。
だが、このような典型の完成に、開眼し、幾重の流行を積み、ついに臨終の床で詠んだ芭蕉の旅に病んで-の句における思想はどうだったんだろうか。およそ〈俗に還る〉卑俗性の意味は、この際あてはまらないとしても、この句の内奥に、一瞬の〝心の騒ぎ〟とでもいうべき凡俗の味を覚えるのだ。それが、なにか思想の未完成と幼稚さの匂いがしないでもない。
「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」――〈夢〉とは、時間を超越した諸々の相であろうか。だが〈かけめぐる〉とつぶやいた終熄の芭蕉に何か激しい戦慄を感ずるのだ。それは私が思うに、己れの完結的成仏とは全く逆に、終末まぎわに追い込まれながらも〝己れ〟という創造の曲者に執していたのではないだろうか。その己れとは〈枯野〉の不透明さにも似て、〈かけめぐる〉未完の流動体でしかなかったという、何かゞ充ち足りていない響きを覚える。
そして私は、およそ東洋詩にあって無常観の執刀では割り切れない思想、さらばえの前に詩人の面目を回復したようなこの句に、たまらない面白さを感ずるのだ――その未完成も幼稚さも。
かつてさすが永田耕衣は、晩年の芭蕉に〈肉体の濁り〉ありと痛快に云ってのけたが、それは芭蕉における眞の流行ということを看取したことではないだろうか。流行とは、己れ(という流動体)に還ることによって、人間の未知の新しさを見出す喜びを幾たびも重ねていくことだろう。人間の不可知な性(さが)に還る――芭蕉の世界観の中に、激しい回帰の希いがあって、旅に病んで-の句の幼稚ともいえる俳句的思想を描かせたのではなかろうか。
回帰性の文学観は、すでに古された言葉であろう。今日、この文学観の延長に連らなるものとして、〝原始回帰母地〟などさしづめ好餌となってくる。
回帰性の観念は、素朴な意味で自然への回帰性をさしていたが、原始性ということになると、こと自然(アニミズム)で納まらない。恐縮だが、非常に人間臭く且つ現代臭くなってくる。それは人間の素朴さの性(さが)に帰ることによって、未知の性(さが)を現代に拓こうとする俳句の〈流行〉に相関する所以だからである。
人間は所詮、空間的にも時間的にも、一回性の生命でしかない。そして、人間の歴史もまた一回性の個々の積み重ねでしかないといえる。だが、一回性の個の人間へ、一回性のあらゆる人間の性(さが)を還元するところに無数の面白さがある。これが現実風にいって実存主義の包容性とでもいうべきものであろうか。
しかし、この無数の面白さとは、実は一回性の〝己れ〟の面白さなのだ。回帰の道を創造の道におく私たちにとっては、一回性の己れが中心であり、全てゞあり、全世界であろう。他者を分離し排列し総合することは、自分を分離し排列し総合することに他ならない。
こゝで、一回性の半口述半創造者の孤独が中心となって、叙事文芸を口伝してきたという歴史を忘れてはならないと思う。回帰性に支配される一回性ではなく、あくまでその反対が歴史であった、といえないだろうか。
この一回性を基にして、いましばらく原始性の周辺に触れてみたい。
――原始回帰とは、〝古代に還る〟ことだろう。古代に還るといえば、初め自然復帰という観念でしかなかった。だが、その後近代合理主義の進歩にあいまって人間の本能を開放する意味ばかりか、更に人間の原型を求める意味となり、そのうえ原始へ全世界存在の信頼をおく世界観に高揚されている。
このような観念は、私自身大いに面白いと思う。しかし、大いに面白いとは、大いにくだらない面白さも含めてなのだ。私などは、原始が人間の回帰の母地や、帰納の原型という公式へはめ込むよりも、むしろ原始それ自身が一回性の積み重ねでしかない、と見た方が面白い。
秋の暮大魚の骨を海が引く
現代俳句の中にも原始性は語られている。三鬼の晩年の句は、〝己れ〟が原始へ回帰する様を大謄明瞭に描いていて、彼の秀句に教えられ、私も好きな一句である。
しかしその半面私は、この大魚の句に、あまりに回帰母地の〈典型〉とでもいうべきものを感じてしまいそうなのだ。
〈創造〉は、作者自らが混濁の生命保持者であることによって、それ自身テーゼであろう。
〈原始〉は、それ自身いかなるアンチテーゼでもない。だが一回性の己れに、逆に原始を帰し批評精神を加えることによってアンチテーゼとなるのだ。
今こそ逆説を述べよう。
原始性恢復などという思想のようなものがあったら、それは美しい星を拾った考古学者の感傷に似て――佛陀の詞華集を、道徳教典の対象として掘り返すに過ぎないし、又は、自分が〝悟り顔〟でいられる原始という安全弁にはまったようなものだ、と思う。――鏃や天狼、略奪婚の狂い舞い――埋れた素材で、鬼神の翳を描く美しさ、空しさ。この逸物の掘り越しさ、俳句的思想の完璧さと似て、あまりに創造過程における回帰運動への反性ではないか。
私たちは現代をこそ発掘すべきであろう。だが現代とは何なのであろうか。それが実は全くわからない代物なのだ。現代が既にわからぬのに何で原始がわかるのだろう――この結末のない閑話。
たゞに、未知の己れより出発した自分が、また未知の己れへめぐり還り、また漠然と立ち去るという回性の迷路におどろくばかりである。それは、汎自然に定着をめざす己れでありたい、という希いを入れてはじめて細々と俳句の道へつながっている。
芭蕉の〈流行〉は、流行という言葉自身の倫理性はどうであろうと、〝己れ〟の姿を発見して止まないことに尊さがあったと思う。臨終の旅に病んで-の句などは、もはや不易とか流行とかの言葉で追いつけない耕衣流にいう〈濁り〉の塊のようなものではなかったろうか。
尾崎放哉のあの奇テレツだった句を、ある人は俳句と呼び、ある人は俳句と呼びがたいという。しかし放哉にとって、それはどんなでもよかったかも知れない。私はこの人にも芭蕉同様に、不易とか流行という言葉の倫理性を超えた創造の曲者の存在を感じている。自分の性へ帰ることによって、人間というこのはかない神秘性を証する喜び――かような意味を創造の道に失うと、私たちの姿は〝珍花鳥風月リゴリズム〟の前に、あまりに倭少な男神に見えてくるのである。
(完)
【作品】
茂林寺輪講(一) 安井浩司
嬰児わが塔として立つ卵の辺に (①『青年経』)
充血しあおあお瘤垂る競技の丘 (①『青年経』)
絶頂に癌のいろ見す炉辺の一族
山巓へ骨もち去って広場の楽器 (①『青年経』)
花野わが棒ひと振りの鬼割らる (①『青年経』)
馬の脚からしぼられてゆく謝肉祭 (①『青年経』)
蜜柑むやみにむかれる霧の黒人街
■『砂』No.5 昭和38年(1963年)2月5日発行■
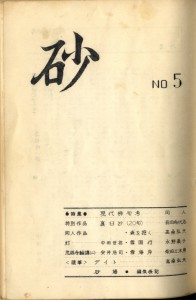
【評論】
形式からの脱皮 安井浩司
今日の文芸における〈形式〉とは、それは文芸の死を意味するといった誰だかの章句があるはずである。この言葉に従うと、さしずめ私たち俳人も死の形式を背負った恰好に違いない。私たちが、俳句を現在のために書くならばまだ問題は少ないが、明日も書くだろうということのために、この俳句という形式に通り一ぺんでなしの考慮を払ってもいいのではなかろうか。私は、今日の俳句は今日の〈言葉〉の上に充分に成り立っているとひそかに自負している。少なくとも俳句が陳旧な手法を克服して、現代俳人の心の動きに耐え得る形式だということを実感を通して把握しつつある。というのが私たちの気持ちではなかろうか。
とすれば俳句は本当に〈形式〉的であるのだろうか。でないのだろうか。あんがい俳句の形式とは、今までの俳句の無駄で余分なものを指していた言葉ではなかったか。
私たちは、死の形式を嘆く前に、俳句を縛りつづけて来た過剰な形式を取り除き、もっと自由な態度を持ち合わせてもいいと思うのである。
【作品】
茂林寺輪講(二) 安井浩司
高背の愛撫切株が電熱器のように
砂に躍ねては短い佛陀遠い昼火事 (①『青年経』)
白い母体へ指刺している牡蛎の村
塩の上ゆく塩見殺しの水飼うや
葡萄園の夜産道すべる斧想う (①『青年経』)
地の股に一電柱の血のこうもり (①『青年経』)
【安井浩司関連記事】
・同人消息
安井浩司
一月七日、長男誕生。二月から埼玉県川越市下新河岸二丁目十三番地(東上線・新河岸駅下車)に新築した新居に移転する。
■『砂』No.6 昭和38年(1963年)4月5日発行■
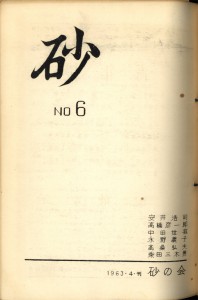
【作品】
茂林寺輪講(三) 安井浩司
遠火事へ耳向きむきに餅の夜 (①『青年経』)
鯛よぎる青葉の扉に渦ひとつ (①『青年経』)
蟹鋳らる形なき器を葬むる朝 (①『青年経』)*1
夜ごと放つ鈍形の鳥を鍛冶の妻 (①『青年経』)
個々に鴉を落とす冬日の中の彼 (①『青年経』)
射撃場に菊より低いパンひと皿 (①『青年経』)
牡蛎むきの村より双手が月落とす
【註】
* 句の後に収録句集名と章を表記してある。数字①、②…は第1句集、第2句集…の略。
*1 定稿では『葬むる』は『葬る』。
【安井浩司関連記事】
・表2広告
安井浩司◆処女句集
青年経
永田耕衣・跋 A5版・フランス装
砂叢書第1集 頒価200円・〒50円
昭和33年以来、5年間の作品約3,000句の中より精選した153句。青春の美しき実存の傾斜の中から、不条理のたくましい意欲をこめて、はじめて世に問う珠玉の作品集。4月中旬刊行。
発行所 砂の会
川崎市萬福寺524〈柴田方〉
・挟み込みチラシ
安井浩司◆処女句集
青年経
永田耕衣・跋 A5版・フランス装
砂叢書第1集 頒価200円・〒50円
登載句153句
4月20日刊行
発行所 砂の会
川崎市万福寺524
拝啓 美しき陽春。いよいよ御清栄のことと御推察申しあげます。
扨て、当〝砂の会〟では同人安井浩司の処女句集〈青年経〉を、このたび砂叢書第一巻として刊行することになりましたので、誠に恐縮ですが、貴誌の誌面に予裕がございましたら、是非右の広告を御掲載いただきたく存じます。なお、予算不足のため、広告料など意にまかせませんので、〝青年経〟送付をもって、これにかえさせて頂きたく存じます。
右よろしくお願い申しあげます。
四月五日
川崎市万福寺五二四
砂の会
柴田三木男
殿
■『砂』No.7 ●青年經特集号● 昭和38年(1963年)7月10日発行■
* 『砂』No.7は安井の処女句集『青年経』の特集で、『砂』同人や著名俳人らのエセーが掲載されている。そのため同人の作品は各1句のみである。『青年経特集』からは、安井を子供の頃からよく知る柴田三木男の『青年経・外伝』を紹介した。
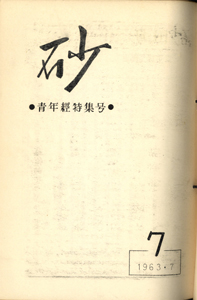
【作品】
死者起(た)ちてこそスカートを裂く土筆 安井浩司 (②『赤内楽』)
【安井浩司関連記事】
・砂場
安井浩司=「琴座」七月号へ「沖の送経」九枚執筆。
・『青年経・外伝』 柴田三木男
安井浩司の処女句集であると共に発行人たる僕の処女句集であったのが「青年経」である。安井に句集を出したいと言い出されたときが、ことし二月末。刷り上がり四月末。僅か二ヵ月のうち、後の一ヵ月は印刷所。したがって一ヵ月の間に、彼は一五三句を選び出し、永田耕衣氏に跋文を、お願し、そして出来上ったものである。表紙の色から用紙まで細かいレイアウト全てを手掛けた僕に取って「青年経」は、数々の不満はあっても、忘れがたい貴重な経験の賜ものであったと言える。
安井浩司は、僕と同郷の秋田県能代市の産であるが、幼いときから行動を共にして来た仲間であり、ライバルである。小学校、中学校、高校と、彼とはつねに机を並べて来た僕らには、兄弟以上の親しさと、無遠慮さがある。大食漢の僕は、小食の安井の弁当を喰うことを第一義としていた高校生時代から、彼は俳句のトリコになっていた。関西への修学旅行で、つねに隣席の彼の食事を平らげたのは僕であったが、こと俳句に関しても彼から得たものは限りなく大きいものがある。
昭和三十三年初夏。僕は秋田から上京したが、このとき二人で「貌」なる不定期刊の同人誌を出した。都合四回ほど刊行したが、青年経第一節は、この時代の収穫であり、永田耕衣という詩人の門を叩いたのもこの時期である。そして大石豪夫、秋地一郎なるペンネームを使っていた時期でもある。当時、僕は榎本冬一郎主宰の「群蜂」に倚っていたが、彼も投稿し、巻頭を得ると共に、それもやめ「琴座」――というよりも永田耕衣に傾注していった。
「群蜂」の前田希代志、松井牧歌、「黒」の安藤三佐、朝生火路獅らと知ったのもこの頃であったか。僕ら二人に取って、これら同世代の俳人はやはり異質の人間でしかなかった。それよりも、高校三年の時に創刊した「光冠」の仲間たち、なかんずく大岡頌司とはその肌合いの上で触れ合うものが大きいようである。
安井浩司は「青年経」以前に五年に亘る句作の実績があるが、いずれ第二句集を編むときに、包含される筈である。それらの句は少年期のリリカルな抒情性に裏打ちされた高い次元の世界を書き尽くしているが、今日の「青年経」の萌芽は、むしろ初期作品の中に多く見ることが出来るようである。また彼は合計三度ほど俳句をやめているが、休止して〝俳句はやめたよ〟といったあとでの作品がガラリとおもむきを変えているのも、一つの特長である。一節「白」と二節「異人伝」の大きな変化はそのせいであるが、根本的には、彼の詩想上の大きい変化はない。
延々十年。あるいはわずか十年。その精華が「青年経」である。よきライバルの仕事に今は満足している最近であるが・・・。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
