一.My Little Lover

まずは皆様にお詫びから。体調を強めに崩してしまいフラフラと呑み歩くことが難しく、今回はこれまで諸事情によりお蔵に突っ込んでいたモノをリサイクルいたします。音楽評についても同様に加筆訂正いたしました。別に新鮮さがウリではありませんが、念のため。
まあ「蔵出し」なんていうと、無闇にハードルを高くしそうですが要は寸足らず。つまり何かが欠落しているのでお蔵入り。例えばコロナ真っ只中で緊急事態宣言下の四年前、京急線沿線某駅にて仕事帰りに訪れた某立ち飲み屋。あの呑む側も呑ませる側も大変だったあの時期、職種的にも罹患は避けたく、意識的に入店は避け段々と家呑み/歩き呑みにシフト中。ただどこかで緊張の糸は切れる。それが偶然あの日だっただけ。店のドアを開けた瞬間「ヤバっ」。まず立ち飲みなのに全員着座、そして年齢層が高いことを確認。無論そこに罪はない。次に気付いたのはマスク着用率の低さ。常連率が高いらしく諸先輩方、よく喋り/よく笑う。飛沫感染の四文字が浮かぶ間もなく、「じゃあ、そこどうぞ」と六人がけのテーブルに放り込まれた。皆様、無視するでも構うでもなく距離感は抜群だが、ノンマスクでベラベラ&ゲラゲラ。私の皿やグラスの上空も例外ではなく……。ちなみに数日経っても体調に変化ナシ。その結果ありきで振り返れば、パンチの効いた話のタネだが、当時のジャッジではお蔵入り。内容云々というより世相とのバランスで決めたような。
書いているうちに取留がなくなって、というのは恥ずかしながらよくある話。アレもコレもと書き連ねるうちピントがぼやけちゃう。デビュー三十周年を迎えボーカル、akkoのソロプロジェクトとして精力的に活動しているMY LITTLE LOVER(当時表記)の「YES ?free flower?」(’96)の時もそのパターン。余白の美しい楽曲として取り上げたのに、書き込むことが増えすぎて……という皮肉な結果に。一聴すればお分かりのように、ぐっと言葉数を抑え、次の言葉が来るまでの余白に淡々とエイトビートが刻まれる音像は、今聴いてもやはり美しい。特にAメロ部分の、単語が一音ずつに切り離され、その意味まで解きほぐされるような感覚たるや。当時の私はシラを切るでしょうが、所謂ヒット曲ということもあり、少々力みすぎたわけです。
【 YES ?free flower? / MY LITTLE LOVER 】
二.ヒューバート・ロウズ
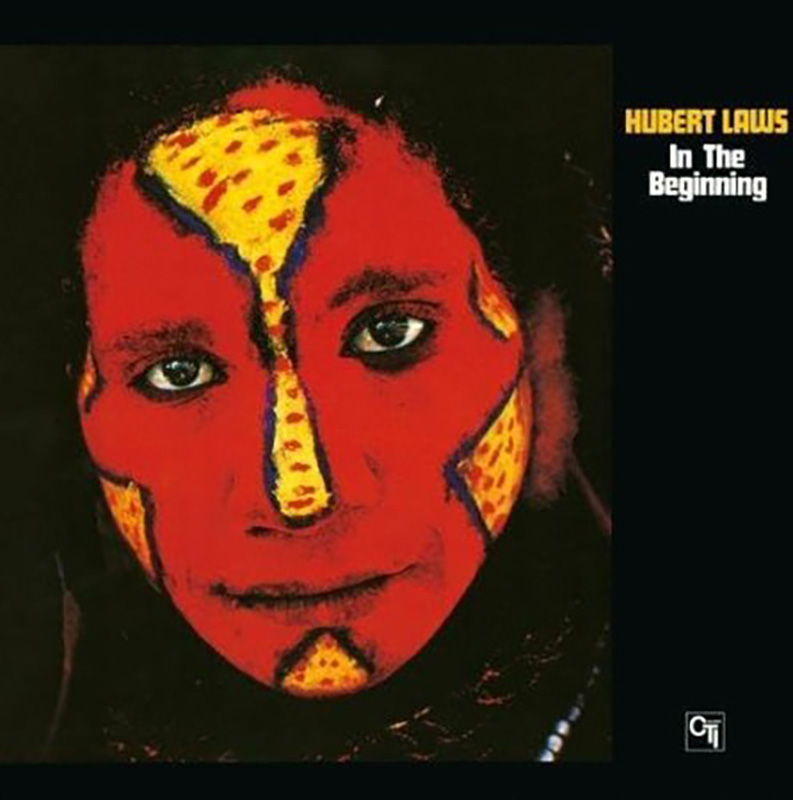
呑み屋においても余白が美しいということはあって、これはこれで言語化するのが厄介な案件。たとえば数年前に閉じたその店は都内某所の割と繁華な場所にあり、それなのに質素すぎる外観から入りづらさ抜群。何なら店舗ではないかのような佇まい。入ったら入ったでデッサンみたいに飾りのない空間で、カタコトらしきオネエサンがテレビを見ながら注文を取る。壁に貼られた短冊メニューは変哲もないモノばかり。味よりもその雰囲気がフィットして、その後も近くに行くたび立ち寄るが、夕方前という時間帯のせいか閉まりがちで、ただまたそれが良い味に。たまに再放送ドラマを見ながら喋りはするけど、改めて記すようなことは何もなく。今回のような御題目があって、ようやく輪郭らしきものが浮かんできた。帰り際の「マタ来テ」という素っ気ない挨拶は覚えているけれど。
あまり文学的でない理由ももちろん沢山あって、端的に言えば準備不足みたいなヤツ。そういう時は大抵アイデアだけが先走っている。思い出すのは「シランクス」(’13)。あの印象派の作曲家、ドビュッシーの無伴奏フルート作品。学生の頃から好きな曲だけど、クラシックは取り上げないつもりなので、何となく別の引き出しに入れていた。そんな折に聴いたのが、ジャズ畑のフルート奏者、ヒューバート・ロウズのヴァージョン。彼のリーダー・アルバムはあまり聴いたことがなく、一番好きなのは『シカゴ・テーマ』(’75)。フュージョン/ファンク味が強い盤だったが、件の曲が収録されているのは『春の祭典』(’71)というクラシックをベースにした盤。ストラヴィンスキーやバッハの作品の中、あの曲は「パンの笛」というタイトルで異彩を放っている。ただやはり「好きな曲を取り上げたい」というだけでは、文章がスッカスカ。余白ではなく不足。書いて間もなくお蔵入りが決まりました。
【 Syrinx / Hubert Laws 】
三.ポリス
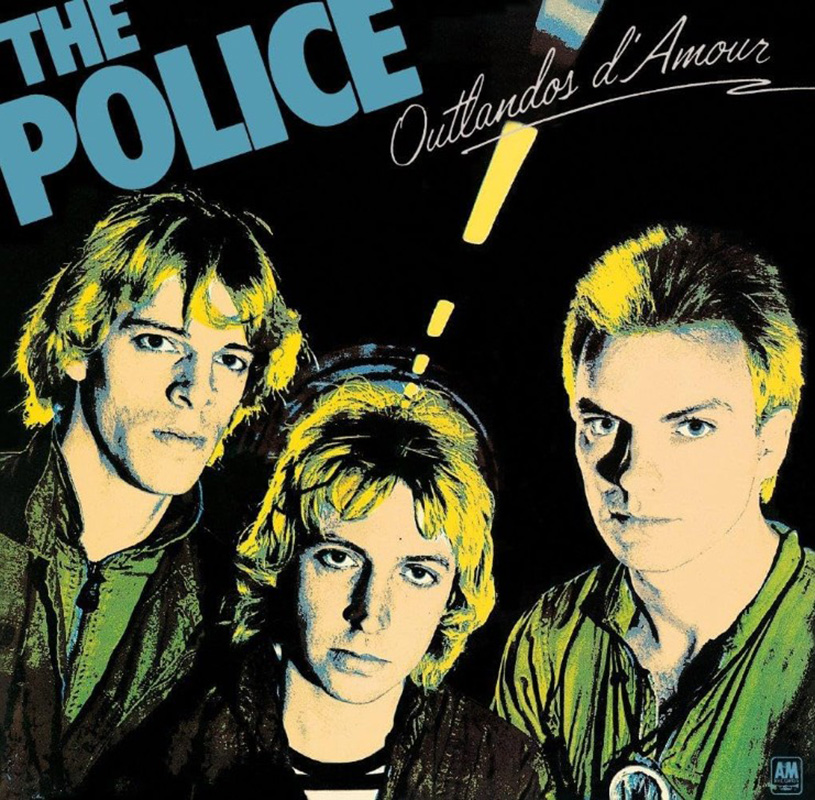
変わったお蔵入りの理由として印象深い店は、現在は都外に移転して居酒屋をやっている酒屋の角打ち。あまりメディアでも紹介されていなく、店の前を通りかかって「もしや」と思い、のパターンで入店。そんな経緯から何となく落ち着かないまま呑み始め、十分ほど経ったところでバイトの青年が御出勤。店主と彼の雑談を肴にゆっくり?んでいると、話が思いがけぬ方向へ。なんとバイトの彼のお爺様が、当時、大畑ゆかり氏と力を合わせて連載をしていた『もうすぐ幕が開く』に出てくる、劇団四季の重要関係者。感慨深いというより、あまりの偶然にテンションが高くなり、危うく声をかけそうに。結局かけなかったのでお蔵入りでしたが、かけていたとしても元々の妙なテンションゆえ、結局仕舞い込んだような気もします。
今回このような形となり、改めて健康の重要性を学ぶと共に、今後再び、という場合に備えて攻撃力だけではなく防御力も鍛えておかなければと猛省。たとえばポリスの名作『白いレガッタ』(’79)と名作『シンクロニシティー』(’83)に挟まれた三枚目と四枚目。昔からあの二枚はちょっと苦手だったけれど、今回もしやと聴いてみたら not bad、悪くない。特に四枚目『ゴースト・イン・ザ・マシーン』(’81)は、次作の存在を念頭に置くと興味深く響く。グレイス・ジョーンズ版の方が馴染みだった「デモリションマン」も良かった。あの二枚について、アイデアという太い幹の不足/減退を、その他の技術でうまくフォローした防御力の賜物、という印象は変わらないが、それってかなり重要だなあと理解。ともかく次回は通常ベースに戻れるようゆっくり養生いたします。
【 Demolition Man / The Police 】
寅間心閑
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


