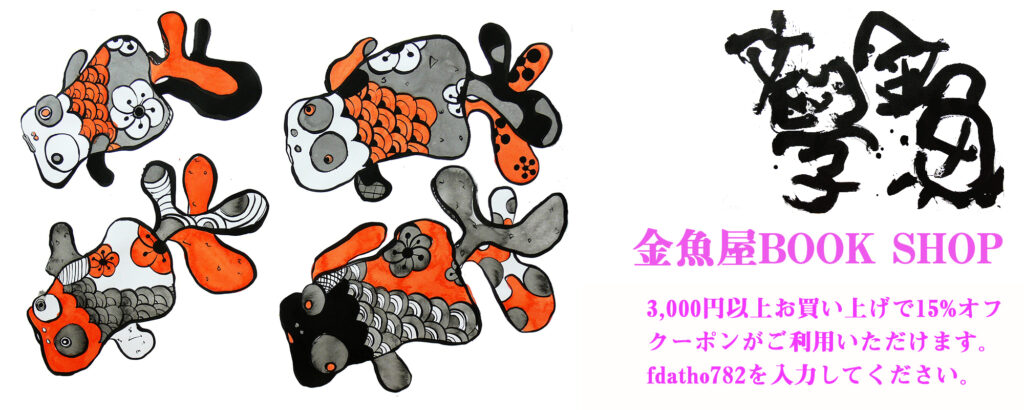日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
by 金魚屋編集部
箒木
この際心置きなく打ち明けてしまいますが、あの女こそまさしく男の心の拠り所というもので。音曲や歌の好し悪しや、身上に係わる由々しき事もよく話しましたし、知恵や情の足らぬ女だなどと思ったためしはなかった。手仕事をさせれば龍田姫*1か七夕*2かという上手で。
「織物が上手だから七夕ねえ、でもそればかりじゃあるまい」と、口を挟んだのは頭中将です、「年じゅう君の無沙汰を忍びたる七夕の君*3か、お目にかかってみたかったものだ。天然の面に差す鮮やかな染め色に優るほど美しいものはないが、湿りの日々が足らないときには、秋づいたころの紅色が浮ついていまひとつ深みが出ない。うきつしずみつがよのさだめ、じゃないが」それだけ言うと、話を続けるように合図するので、左馬頭も応じます。
その折、新たな出会いがございました。優れた女でした。見事に歌を詠み、楽も達者、物言いはなめらかで調子がよく、身のこなしも雅やかなもので。そのひとつひとつが目に留まって舌を巻くような器量好しです、人の噂するのも耳にしました。この女と馴染みになり始めたのがちょうど先の女に倦んできた頃でもあり、喜び勇んで通いましたとも。仲が深まるにつれて離れられなくなりました。
先の女がこの世を去ったと聞いて胸を痛めたのは真なれども、詮方無いものですな、この女の元に頻りに足が向くのです。ところが、よくよく眺めてみますと、はしたない癖の点々とあるのに気がつきました。もとより慎ましい気質ではないし、どこか心を許せぬところがある。こうなるともういけない、いささか気後れし、通いの足も遠のきました。そしてまだ一歩とて穿鑿を進めぬうちに、たまさか女が思いを寄せる間男を突き止めてしまったのです。
涼しい月明かりに誘い出されるような神無月の宵のことです。牛車に揺られて或る大納言の屋敷へと向かう道中、同じ方へ向かう若き殿上人に出会いました。これも縁と伴立って行くことになり、道すがら聞いたことには「女が待ち侘びているだろうが、どうも気が進まない」と。したり。車が止まったのはあの女の屋敷なのです。庭池の水面に弾けた月影が土塀の割れ目越しにきらきら光っておりました。揺らめく水にありったけの輝きを注ぐ青白い月もこの一景に魅入っているかのようでした。これに目もくれず通り過ぎるようでは情が無いも同じ、二人共々車を降りたものの、互いの胸の内など知る由もありません。
この若人が間男なのでしょうが、厚かましくはなかった。門口から伸びる廊下の傍に葦の筵を敷いて座し、空を仰ぎ見て、しばらくの間言葉なく物思いをしておりました。庭の菊は花盛り、その甘い香りにくすぐられると気が鎮まり、赤々とした楓の葉が秋風にそよぐ度にはらはらと落ちてきました。まことあわれな宵でした。
やがて男は懐より笛を取り出してひとくさり吹き鳴らしました。そして「さやきよかげよ」と囁いたのでした。
すると間もなくしてあの女がお返しにと和琴(琴の一種)の甘い調べを爪弾き出したのです。
妙なる柔き音色で流行の節を奏でたるはまこと清き宵にこの上もなく合っておりまして。当然男はうっとりと聴き惚れて、音の出る障子の方へと歩みを進め、足下の落ち葉を一目見ると、恨めしげな声でつぶやくのです、「邪魔者がずかずかと踏みつけちゃいないようだ」そして鼻歌まじりに菊を一輪手折り、
つきいでやわきてことのねならし さやけきにわのこのほとり
おとなうかげこそまことにあらじ きみおもいたつはわれひとり
これだから、とつづけて声を荒げましたが、これは歌の出来栄えに対してのようです。それからまた障子に向かって、「もうひとつやってくれないか。手を止めないでくれ、君の琴を心から聴きたがっている者がこうして傍にあるうちは」そんな調子でご機嫌取りを始めたのでしたが、女は男の囁きへの返歌に、優しくもためらいがちな声で、
あまきふえのねにそえし わがこえなれどあじきなし
おちばをちらすあきかぜに ちるぞあわれとおもいなし
さて、こんな戯合に私が立ち会って黙って業を煮やしていることを女が知るはずもない。今度は箏(これも琴の一種で十三本の弦を持つ)を持ち出して盤渉調(冬の調べ)に柱を合わせ、いっそう見事に爪弾きます。私も楽を好むほうですが、かくも戯けた目に遭わされては恍惚なる旋律とて耳に入るものですか。
こうした一夜の逢瀬を重ねる相手が宮仕えに縛りつけられた処女とか、万一にもお目にかかることの叶わぬような高嶺の花であればまこと甘き仕合せでしょうけれども、それでも一生の伴侶にするかといえば気が進まぬのが吾等というもの。まして我が身にもなってみれば、どうしてそのようなことを考えられましょうか。あの宵の憂き目のおかげで女を見限り、二度と会うことはありませんでした。

【註】
*1 空想上の女人で染物師の守護聖人にあたる。
*2 織女星のこと。恒星のヴェガにあたる。中国の故事伝承に由来し、天にあって朝から晩まで機織りをしている織女に擬人化されている。
*3 右の伝承によれば、天の川のほとりに住まう織女は年に一度だけ七月七日に恋人――彦星または牽牛星と呼ばれる星――と逢瀬を果たす。彦星は天の川の対岸に住まい、二人は一群のカケスが翼と翼を絡めて作った架け橋の上で会う。この伝承に基づき、中国でも日本でも、七月七日は七夕を祝う祭が催される。
(第12回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■