 「モーツァルトとは〈声〉の音楽である」――その声をどう人間の耳は聞き取ってきたのか。その本来的には言語化不能な響きを、人間はどのように言語で、批評で表現して来たのか。日本の現代批評の祖でありモーツアルト批評の嚆矢でもある小林秀雄とモーツアルトを巡る、金魚屋新人賞受賞作家の魂の批評第四弾!
「モーツァルトとは〈声〉の音楽である」――その声をどう人間の耳は聞き取ってきたのか。その本来的には言語化不能な響きを、人間はどのように言語で、批評で表現して来たのか。日本の現代批評の祖でありモーツアルト批評の嚆矢でもある小林秀雄とモーツアルトを巡る、金魚屋新人賞受賞作家の魂の批評第四弾!
by 金魚屋編集部
七.
『モオツァルト』執筆のために、伊東の旅館に籠もっていたときの小林氏の横顔を、大岡昇平氏の小品『再会』は伝えている。その頃は毎夜のように長時間の停電がおこったものだが、暗い蝋燭を囲んで青山二郎、大岡昇平の両氏と酒を飲んでいた小林氏は、いつもの例で青山氏にからまれ出していた。小林氏の批評が「お魚を釣ることではなく、釣る手付を見せるだけ」で、したがって「お前さんには才能がないね」というのである。小林氏は黙ってきいていたが、大岡氏が気がついてみると、
≪驚ろいたことに、暗い蝋燭で照らされたX先生(小林氏)の頬は涙だか洟だか知らないが濡れているようであった≫
この「涙だか洟だか知らないもの」に、どのような感慨が込められていたかを推測するのは愚かなことである。だが、その幾分かはおそらく敗戦の衝撃と哀しみとに由来しているであろう。小林氏は日本の勝利を信じていた国民のひとりだったからである。いや、むしろ敗戦を期待しながら生きるという知識人の姿勢の根本にひそむ虚偽と不誠実を見たのである。戦争がはじまったからには、勝つと思って黙って生きて行く以外にどんな生きかたがあるというのか。この態度が、大勢順応ではなく、氏の生きかたの内奥にかかわっていただけに、衝撃は大きかった。しかし、氏の内面に傷痕がのこったとしても、そこには「戦後」という時代はなかった。敗戦を哀しむのと、それを後悔するのとは別のことである。[中略] 小林氏が、
≪利口な奴はたんと反省するがよい。私は馬鹿だから反省なぞしない≫
という反語を放ったのはその頃のことである。
(江藤淳、新潮文庫『モオツァルト・無常という事』解説)
先日、TVドラマを観ていたら、敗戦直後、八十年前の闇市の風景が映し出されるシーンがあった。
バックには並木路子のうたう「リンゴの唄(作詞・サトウハチロー、作曲・万城目正)」が流れていた。ありていに言えば、TVではもはやありふれた、陳腐と形容するほかない場面だった。にもかかわらず、このとき私はなぜか妙に感動した。このうたはアジアの中ではおそらく日本人にしかない短音階のしらべである。日本人の原像を伝えるような古来の音階と七五調のリズムと、敗戦によってすべてを失った人びととかれらが焼け野原や闇市を徘徊する原風景とが渾然と重なり合ったこのゼロ地点を、この「涙だか洟だか知らないもの」を、小林は「かなし」と表現するしかなかったのだろう。江藤の解析はこの意味で正しい。しかしかれの内奥で鳴っていた音楽はラジオから流れる流行歌ではなかった。モーツァルトのシンフォニーやクインテットだったのである。かれは日本のしらべを、つまり〈歌〉をでなく、まったく異なる文化のまったく異質な音楽をこのゼロ地点に重ねたのである。おそらくそれは偶然ではなかった。小林が天性の〈声〉のひとだったからである。そして、そんな小林の思いを包み込むほどに、モーツァルトという器が大きかったからである。
*
世の中には、ごく少数だが〈声〉のひとがいる。
小林秀雄というひとがその一人であることは、『信じることと知ること』(『考えるヒント3』、文春文庫)というエッセイを読んで以来、確信を抱くようになった。このエッセイを繙いたのには理由がある。のっけからその昔スプーン曲げで世間の話題をさらったユリ・ゲラーの話から入り、友人だった今日出海の父君が心霊学の研究家でクリシュナムルティの会に入っていたときて、ベルクソンの念力にまつわるエピソードに続いたその語り口に、思わず引き込まれたからである。小林のオカルト志向はこれに限らず、若いころから死ぬまで変らなかったと思われるが、それはともかく、こうした「つかみ」はやはり上手い。
じっさいに行われた講演会のテープを原稿に起こして、ですます調のくだけたエッセイに仕立てるという語りの形式は、小林が得意としていた技芸と言うに吝かではないだろう。あたかも講演や対談から原稿に起こしたかのように装ってはじめから創作されたエッセイは、さすがにないだろうと思うが。ともあれ出だしの「つかみ」につい頁を繰らされてしまった私の記憶の片隅には、かつては失望しながらも、あの道頓堀の経験譚の鮮やかな記憶が引っかかっていたのかもしれない。
読み通してみると、エッセイの後半はかれらしい柳田國男論となっている。ベルクソンの超心理学的なエピソードはそのための前フリと思っていい。『故郷八十年』(筑摩版柳田全集第二十一巻)に綴られた、少年時の柳田のふしぎな逸話からそれははじまる。このエッセイを読んではじめて柳田の原著を繙いたひとは私だけではあるまい。
柳田は当時一四歳、利根川べりにある布川の親戚の家に預けられていた時分である。その広い屋敷の庭に、亡くなった老媼を祀った石の祠があった。春の日のことである。いたずら盛りの柳田少年が人目を盗んでこわごわ開けてみると、蝋で拵えた握りこぶしほどのうつくしい珠が置かれてあった。それをそっと覗いたら、何とも妙な気持ちになった。
どうしてそうしたのか今でもわからないが、私はしゃがんだまま、よく晴れた青い空を見上げたのだった。するとお星様が見えるのだ。今も鮮やかに覚えているが、じつに澄み切った青い空で、そこにたしかに数十の星を見たのである。昼間見えないはずだがと思って、子供心にいろいろ考えてみた。そのころ少しばかり天文のことを知っていたので、今ごろ見えるとしたら自分らの知っている星じゃないんだから、別にさがしまわる必要はないという心持を取り戻した。
(同『ある神秘な暗示』)
あやしいこころにとり憑かれていたそのとき、鵯が空の高い処でぴいーっと鳴いた。その拍子にハッとわれに帰った。
あの時に鵯が鳴かなかったら、私はあのまま気が変になっていたんじゃないかと思うのである。
(同)
これを読んだ小林は感動して、
柳田さんという人が分かったという風に感じました。鵯が鳴かなかったら発狂したであろうというような、そういう柳田さんの感受性が、その学問のうちで大きな役割を果たしていることを感じたのです。
(『信じることと知ること』)
このくだりを私は幾度もくり返し読んだ。小林というひとが「分かったという風に感じ」たからだ。柳田國男のエピソードにするどく反応した小林の感受性を、もういっぺん見直さなくてはならないな、と私は思った。このような感受性の核は何もないところからじっくり時間をかけて醸されてきたのではない。もともと次のような下地があった。
潮風に飜って居る庇に下った薄汚い幕から、彼の目は夏の空に移って行った。薄い霧の様なものの彼向で光る為だろう、星が真珠の様な光り方をして、いつに無く大きく近く感ぜられた。
(今日の星は何んだか煩い)――賢吉は空覚えの星座など捜して居る中に、妙な圧迫を感じ初めた。星がグーと近くなって、其の重さが一時に自分の身体に落ちて来た様な感じであった。急に息苦しくなって、彼は自分の心臓の鼓動を感じ乍ら、逃げ場所を捜す様に本能的に四辺を見廻した。今眺めて居た顔の集団が、星の圧力でヅブリと砂の中に首まで圧しこまれて笑って居る。――斯んな幻覚が頭に閃いたと思うと、彼は砂の上にヘタばっていた。何んだか叫び声を立てた様な気がした。――が直ぐ元の気分を取り返した。而して馬鹿馬鹿と口の中で繰り返して居た。恐る恐る見上げる空は、唯、銀砂を撒いた美しい夏の空だった。
(「蛸の自殺」、『小林秀雄全作品1』)
執筆当時二〇歳だった小林と、一四歳のときの経験をふり返る晩年の柳田――二人が幻視したものと、われに帰るまでのこころのうつろいを描くその語り口が似かよっていることにおどろくよりも、やはり二人は一流のモノ書きであるとともに、オカルティスト――いや〈声〉のひとだったと、私は思わずにいられない。
私には柳田が、そしてそれに感応した小林がモーツァルトの話をしているとしか思えなかったのだ。なぜならモーツァルトの音楽を聴くことは、まさしく白昼天に煌く星たちを視、ぴいーっという鳥の声を聴き、「今日の星は何んだか煩い」と独白し、「何んだか叫び声を立てた」まさにそのことだからだ。わたしたちの感受性というものは生来、幸か不幸かこうした音を耳にして自らの皮膜のような意識をそっくり滅却するか、あるいは小林が傾倒したドストエフスキーにならって言えば、わたしたちというこの不完全な容れ物自体をそっくり別の器に換えてしまわねばならない窮地へ追い込まれるほどに、繊細に出来てはいないらしい。
そのドストエフスキーが患っていた自らの癲癇体験を小説の登場人物に一度ならず語らせているのは、愛読者にとっては周知のことだろう。
ある数秒間があるのだ。――それは一度に五秒か、六秒しか続かないが、そのとき忽然として、完全に獲得された永遠調和の存在を、直感するのだ。これはもはや地上のものではない。と言って、何も天上のものだというわけじゃない。つまり、現在のままの人間には、とうていもちきれないという意味なんだ。どうしても生理的に変化するか、それとも死んでしまうか、二つに一つだ。[中略]もし十秒以上続いたら、魂はもう持ち切れなくて、消滅してしまわなくてはならない。
(ドストエフスキー『悪霊』第三篇、米川正夫訳、岩波文庫)
私は柳田や小林の体験が癲癇性のものであると言いたいわけではない。どこまでもひたすら研ぎ澄まされたまれな精神にたまさか訪れる、格別な贈り物であるという点で、三人のいずれにもつうじるものがあると思うだけだ。
柳田と小林のこのエピソードもまたドラマティックな性質のものではない。小林の言うとおり、このように書いてしまえばただの「お話」にしかならないたぐいの経験であって、それは柳田もよくわかっていた。だから「馬鹿々々しいということさえかまわなければいくらでもある」と断ったのだし、小林は小林で「馬鹿馬鹿と口の中で繰り返し」たのである。が、二人とも内心は本気も本気だったので、「馬鹿」と卑下するのは読者へ向けたポーズにすぎなかったのは言うまでもない。
そして、小林はモーツァルトにおける〈声〉にだけは正しく感応したと私が言ったのは、この〈声〉のことである。
*
〈歌〉が文(センテンス)にあたるなら、〈声〉は、さしづめ音節(シラブル)に相当する――そう言いたいところだが、そうではない。〈声〉は〈歌〉の構成要素ではないからである。日本の伝統的な音楽、たとえば人形浄瑠璃などで、三味線が「合いの手を入れる」ときの掛け声、あるいは津軽三味線でいう「たて」をイメージしていただいた方が近いかもしれない。それは〈歌〉にはけっしてなりえず瞬時にして消え、二度とふたたび鳴らされることのない一期一会の音である。要件定義を思い切り広げていうなら、およそ生きとし生けるものが自らの存在を訴えて立てる原初のひびき、それが〈声〉である。そして〈声〉を可能にするのが、呼吸である(〝呼吸〟はモーツァルトの心臓と言っていいが、この点は次回以降に触れる)。
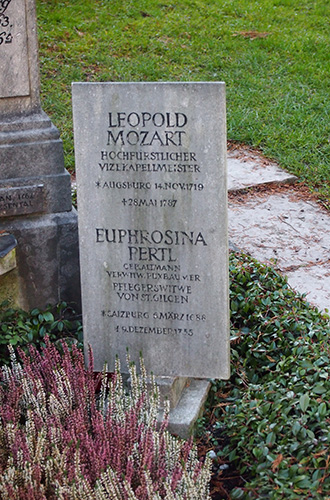
森羅万象、ことごとく何らかの音を発している。
現代物理学の知見によれば、完全静止している物質はこの宇宙に存在しないとされる。ひるがえして言えば、すべての物質は動いている。時空をふるえ動く限りにおいて、いや逆にふるえ動くものの存在する領域を時空と呼ぶなら、時空にあるすべてのものは音として伝わる潜在性を秘めていると考えていけない理由はあるまい。そして音である以上、それを「聴く」こともまた可能でなくてはならない。たとえ象られることのない音なき音であろうとも。それが届くのはただ創造主の耳のみであろうとも。ここに〈声〉のあらゆる潜在性が濃縮スープになった〝原始の海〟がある。
〝海〟から生じたこの世界は、なんとおびただしい〈声〉たちにあふれているだろう。赤ん坊は生まれ落ちるとともに泣き声をあげて母を呼び、その乳房を求めてはまた泣き、恋する者たちは木陰のベンチで語らい、小鳥は森の奥でさえずり、木々は初夏の薫風にざわめき、小川は照り返す光にせせらぎ、波は礁原にさざめき、秋の夜すがら滲みわたる虫たちの音は聴く者のこころを奪い、星空はただ黙してささやきかける。それらは共鳴りそしてみち足りた音である。〈声〉とはとどのつまり「ある」というそのことが、ただ「ある」がゆえに発する音である。
この揺籃の中から、〈声〉は人間を人間たらしめる重要な意味と役割をになうようになる。
それは次の三つである。
①〈声〉とはまず、意味をおびた最初の発声=発生である。人間にとっての世界がそこから立ち上がってくる特異点、それ自らは延長をもたないのに時空を開き、開くとともに自らはたちまち消えゆくもの――それが〈声〉である。
②〈声〉とはつねに他なるものであり、他者の〈声〉である。ひとは自らの発した〈声〉を直接的に、第三者が聴くようにかつ同時に聴くことができない。この一見ありふれた事実は示唆的である。つまりひとは、他者の〈声〉としてはじめて自らの〈声〉を知る。他者への何らかの意思を宿した呼びかけ、異なる者どうしの呼び合いとひびき合い――それこそがコミュニケーションを開き、ハーモニーを生む「場」である。〈声〉とは、そのような「場」を開く力であり、はたらきである。
③〈声〉とはひとに覚醒をうながす〝目覚めよと呼ぶ声〟である。人事不省に陥った垂死の者が、親しき者の呼びかけに応えいっとき眼を開けることがあるように、〈声〉は主体もしくは意識を立ち上げるスイッチである。裏を返せば、自ら〈声〉を発し〈声〉に感応する存在、それこそが主体であり意識である。読者の中には、死別あるいは離別したひとの写真や遺品にありし日の面影をしのぶよりも、CDやカセットテープで録音再生されたそのひとの〈声〉を耳にしてまざまざと姿がよみがえるように感じ、こころを揺さぶられた経験のある方はおられないだろうか。〈声〉とはそのように聴く者じしんを揺るがせ、時をワープさせる波動なのである。
音に意味が宿って〈声〉となった。それはコミュニケーションの「場」を開くとともに多声化し多義化し、やがてことばへと発達をとげた。〈声〉はことばと交わるうちに〈歌〉となり、ことばでは伝えがたいものを伝える乗りものとなった。こうして音楽はことばとともに成った。同時にことばもまた、音楽を必要としたのである(言霊、音韻、詩型)。
※ちなみに日本の伝統音楽である和楽は、弾き物でも吹き物でも打ち物でもいい、何よりも肉声であるが、それらの発するただ一音にいっさいをこめる、おどろくべき表現方法にその神髄がある。〈声〉を〈声〉のままにひびかせるという、とんでもないことをしてのけたのである。音楽の中に亡霊の声たちの気配をひたひたと感じさせるものは、モーツァルトを除けばそれらしか寡聞にして知らない。音楽はことばとともに成った。しかしそれだけではない。音楽の真の目的も正体も別にある。それはわたしたちがことばを手に入れた代償として喪い、忘却のかなたへついえ去った、かけがえのない何ものかを連れ戻すために召喚された巫女なのである(だがこの思いもまた、ことばの掌の上で溶けて消えてしまうだろう)。
モーツァルトの音楽の母は、このような無形の〈声〉たちだ。
もちろんこれは、モーツァルトでなくても言えることである。人間にことばと音楽とが与えられるのはここからであるから。ところがこの音楽に耳を傾けていると、音の波間からほんとうに聴こえて来るのだ。白い積乱雲の湧き上がる音が、小鳥の羽ばたきと浮遊とが、おさな子の笑い声が、亡霊たちのうめき声が――モーツァルトにとって作曲といういとなみは、世界がたえまなく発する形なき〈声〉をすくい取り、呼吸とリズムに乗せ、和声を与え、〈歌〉の中にひそかに差しはさむことだった。モーツァルトの中で、〈歌〉と〈声〉という異質なものは同一化することなく、つねに同居していたのである。この天才はそれを、前半生を費やしての父との旅の日々から、夥しい他者との出会いの中から、おのずと耳と身に滲み込ませたのだった。
小林が「彼は、大自然の広大な雑音のなかから、なんとも言えぬ嫋やかな素速い手付きで、最小の楽音を拾う」と言い、「凡庸な耳には沈黙しかない空間は、彼にはあらゆる自由な和音で満たされるだろう。ほんの僅かな美しい主題が鳴れば足りるのだ。その共鳴は全世界を満たすから。言い代えれば、彼は、或る主題が鳴るところに、それを主題とする全作品を予感する」と語ったのはこのことである。ただし〈声〉の発生源は大自然の中ばかりとは限らない。ところが、こうして生じた〈声〉から象られたはずの〈歌〉の多くに、小林は関心を抱かなかった。それはなぜか。
*
形なき〈声〉は、〈歌〉の中に回収されることなく、そこからこぼれ落ちる。〈歌〉はひとからひとへ歌い継がれる日常のために、げんみつに言えばこの世界でただ一度きりしか出会うことのない〈声〉を、持続する特定の情調や物語の中へ溶け込ませようとするからである。しかしモーツァルトの音楽にあって〈歌〉と〈声〉は溶けあうことなく、むしろその間に生まれる緊張と微細なふるえを表現する。これがモーツァルトのオーケストレーションの生命である。かれの偉大な四大シンフォニーや室内楽はその証しであり、ひびきあう〈声〉たちのとびきりデリケートなあらわれである。そのアンサンブルは、本能に身をまかせつつ湧きあがる魔法の泉のような生成変化を自ら楽しむかにみえるコンチェルトやディヴェルティメント――これこそがモーツァルトの身体と言っていいのだが――と異なり、牢固としたしかもわざとがましさは微塵もない天空の精妙なひびきをいっぱいにたたえ、聴く者には、限りない覚醒の意識を求めてくるのだ。小林がモーツァルトのシンフォニーに引き寄せられた理由は、こうした事情と無縁ではないだろう。
ちなみに筆者は四大シンフォニーと言ったが、ふつうは第三九番、四〇番、四一番『ジュピター』という三つの交響曲を三大シンフォニーと呼んでいる。これにけっして劣らない第三八番『プラハ』を加え四大シンフォニーと呼ぶべきと思ってのことだ。もっとも三大と呼ばれる真の理由は、『プラハ』がその後塵を拝するほどに曲のレベルが突出しているからではなく――『ジュピター』の第四楽章は別格として――完成時期がおなじ一七八八年の夏であるという事情がからんでいる。同時期にこれほどまで趣の異なる、しかも完成度の高い作品を三つも立て続けに書けた事情である。作者がこれを当初から三部作として構想したとまでは断言しない。だが、あたかもまったく異なる三つのそれぞれ独立した図柄を、串刺しに通してみればより巨きな一幅の名画のごとく映じるのはたしかである。ただし、あらわれるのは主題労作を旨とした古典派の高峰の情景――一九世紀の作家で音楽評論家のE・T・A・ホフマンが語ったような――ではさらさらなく、後にも先にも誰も目にしたことのない異景であるが。
ともあれ、大トリである第四一番ハ長調(K五五一)『ジュピター』のわけても終楽章を耳にするにつけ、ド・レ・ファ・ミのいわゆる〝ジュピター音型〟にはじまる四声のからみあい、その果てにすべての動機が渾然一体となるコーダは、いくたび聴いても星辰こぼれる漆黒の空間へひとり放り出された思いになる。この曲がウィーン古典派のひとつの頂点を示すとみなすべき理由はよく言われるポリフォニー(対位法)とホモフォニー(和声)、対位法とソナタ形式の高次元での融合にあるだけではない。作曲家はこの楽章で、セバスチャン・バッハによって極められ、そこから学んだフーガの尖端をも飛び出している。〈歌〉と〈声〉――〈声〉を自らの細胞組織の中に取り込もうとする〈歌〉の運動とそれをはみ出していく力、これら相容れない異質なものどうしをともに自らの懐深くみちびき入れ、化合させたのが終曲のコーダである。これによって、かれは後にも先にも類例のないまったく新しい音を創り出したのだった。
萩野篤人
(第04回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『モーツァルトの〈声〉、裏声で応えた小林秀雄』は24日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


