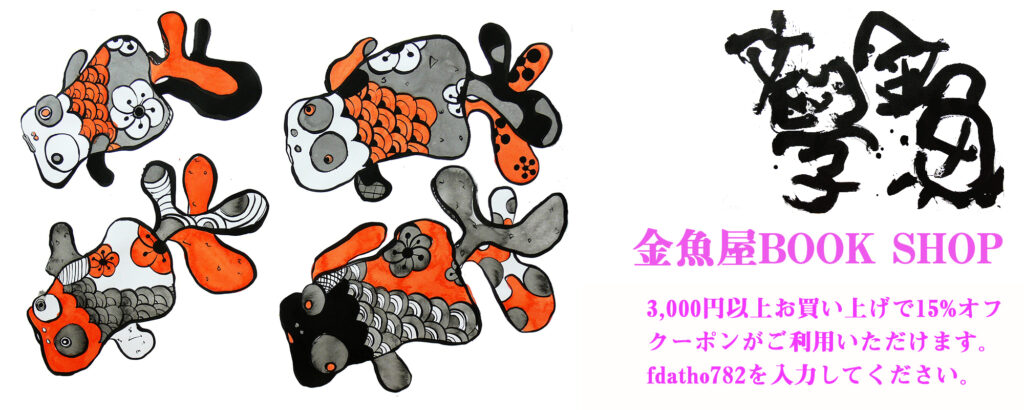日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
by 金魚屋編集部
箒木
ねえ御三方、此身に覚えし二様の女性の一様に申してすげないもので。僻む女も世慣れた女も度を過ぎてしまいますとね。かくして若い折に学んだのです、かような女性に心を寄せるものではないと。今は益々そう思います、とりわけ世慣れた女はいけない。ぬれいろにはゆるはぎのつゆ、ふれるやいなやかげときゆ――ささのはこぼせしたまあられ、てのひらにとけうせしやあわれ――花は遠くから眺めるときほど色めいて唆られるものです。これを心に留め置き、どうぞかような女性をば遠ざけておかれませ。味気無いことを申したものだとお思いかしらん、しかし七歳巡る頃にはきっと心底頷かれましょう、あだめく恋路を行くのはつまり徒らに名を貶めるだけ、と。
左馬頭の忠言に変わらず頷く頭中将。源氏は、もっともなことと舌を巻いておりましたのでしょう、やがて口を開き、「そんな気障な女禍続きじゃ懲りるわけだ」と、仄かに微笑みを浮かべておりました。
次は、と切り出したのは頭中将です、僕の話でもしようか。左馬頭にはよほど女難の相があったと見える、心底惚れ込んでいたやも知れぬ女には手に負えぬほどの悋気が潜み、また別の女の浮気に居合わせて心離れしようとは。しかし僕とて度を過ぎた内気者と巡り合った縁には難儀したのだ。あれもまこと心立てのいい女でね、左馬頭に同じく、終生の契りを結ぼうという積もりはなかったのだけれど、たいそう惚れ込んでいたのは慥かだ。通い足らぬと重ねるうちに離れがたくなっていった。いつも女のことを思ったし、女の側もすっかり心を許していた。すっかり許した心とて怨みに曇ることはありや、意地悪をしたくなるのが人の本性というものだろうが、どんなに意地悪を重ねても怨む気色さへ見せなかった。滅多に寄り付かずにいたときでさえ、怒りも騒ぎもしないどころか、一時たりとも離れてなどいなかったように振る舞って見せる。この物言わぬ辛抱は小言を浴びるよりも堪えた。親も友もない独り者であったから、いっそう義理に迫られる。それでも女のしおらしさにつけこんで、放ってばかりいた。すると、今度は隣向かい誰かが僕らの仲を嗅ぎつけて、何の折にか、仲違いさせようという魂胆の文を送りつけて脅したらしい。それを知ったのは後になってからだったのだけれど、たしかに女は悄気返って困り果てていたと思う。幼い子もいたから、子を案じてさらに心を痛めていたようだった。或る日出し抜けに一束の撫子*1が届いた。あの女からだった。
ここにきて頭中将の顔が曇りました。
「それで」と源氏が訊ねます、「何と書き添えてあった」
なに、歌が添えてあっただけだよ、
わすれがたにしあれどこに もえいずるはなをたおりてみゆる
いつくしめるころのおぼえに ひとすじおつるたおやめのつゆ
詠んですぐに女を訪ねた。相変わらずしおらしくしていたが、心ここにあらずという具合であるのもはっきりしていた。庭草に光る露に目を落とし、秋虫の物憂げに啼くのをじっと聞き入っていた。夢語りの中にいるような心地で歌を返した、
さきみだるるはなぞのに わがめもしばしまどえしが
ひときわだってあやなる とこなつ*2をたれそみそれじ
撫子を愛でるのは後にし、まずは母花を慰めることに心を注いだわけだ。女もかぼそく歌を返した、
つゆにたわみしはなをなで ふくあきかぜのつめたきに
あえかないろもやがてあせ かれるをあわれむひとぞなき
悲しげな声音はそれきり、なにを咎めるのでもない。ひとりでに涙が溢れるのをかえって気に病み、隠そうとさえした。そんな悲しみには慣れているから平気だという風に装っているんだ。僕とて心を痛めたが、まだ女の辛抱を試したかった。またしばらく無沙汰にしていたが、ついに罰が当たった。女は痕ひとつ残さず失せてしまった。もしまだどこかで生きていても酷い有様となっているだろう。
度を過ぎた内気に囚われず、心が無いにも等しいおとなしさにも打ち克っていたなら、言うべきときには不満を託ち、それが温もりにも生気にもなり、行方知れずとなることもなく、僕が心を試そうということもなかった。先にも言ったが、物思う心がない、喜びも悲しみも表に迸り出ないような女は、吾等を有にすることができないんだ。

そんな性質こそ相容れなくても好いた女だもの、今もなお母子の消息を探ってはいるのだが、だめだね。あの子もかわいらしい子だった。今でもつい考えては心苦しくなる、たとえ僕が女のことを忘れられても、女はきっと忘れないだろうし、悲しい思い出が蘇って声を上げずにはおれない夜を重ねていることだろう。
我々の見てきた女達から学ぶことをまとめてみようか。指を噛む女は乱暴ゆえに男心を手放してしまう。不実で世慣れた女はいかに楽や歌の音が甘かろうと苦い咎めを受けてしまう。三つ目の、心を秘しておとなし過ぎる女は冷たく無口だと謗られ、結局は己を苦しめるだけで、人にわかってもらえない。
ではどんな女を選べばいい。数多ある女から選び取ることの難しさに面食らうのは万人の宿命とも言える。それでも吾等は望み通りの女を探すべきものだろうか。血眼になって美の権化、吉祥天女を探し求めるべきか。そんなのは叶うはずもない、迷信さ。
【註】
*1 可愛い幼子を指す語を冠す花――またその薄紅色。
*2 常夏(終わりなき夏の意)は撫子の異称のひとつで、詩歌では意中の女性を含意する。
(第13回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■