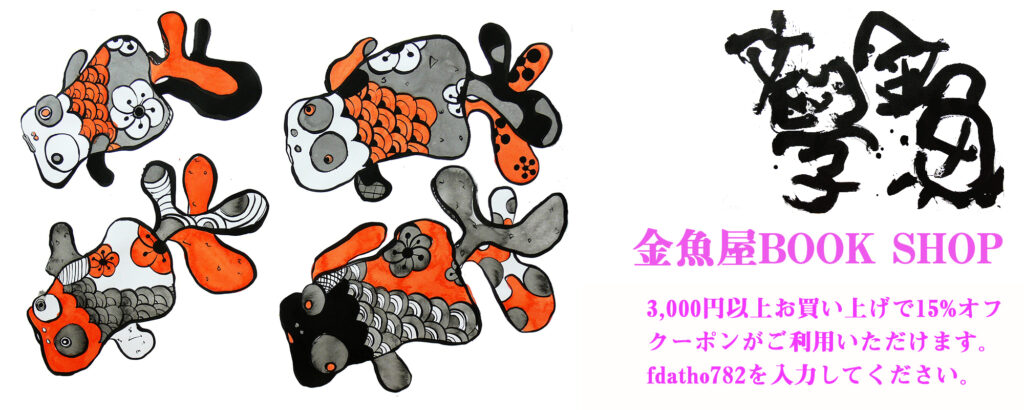日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
by 金魚屋編集部
箒木
この御寛ぎは婿君にあるまじき不覚でございました。
その日の暮れ頃になって人の言うことには天一神(中央を司る方位神)*1の塞にあたる八卦方位の門戸は鎖しているらしい。しかも二条の屋敷(前章で修繕について触れた例の屋敷です)も同じ方位にありました。
「では何方へ行ったものか」と言ったきり、源氏は悩める気色もなく転寝を始めたものですから、動じもせぬとは恐れ入ったと一同は口々に驚きの声を上げました。そのうちに、侍臣の紀伊守の在所が中河(京極川)のほとりにあり、この頃は庭に川の水を引いているので涼やかで良いという話が耳に入りました。
「それはいい、こんなうっとうしい夜にはうってつけだ」と言って源氏は身を起こし、訪問を所望すると、紀伊守は一言仰せの通りにと応じながらもうかぬ顔、ほかの侍臣にしぶしぶ語るに、伊予守*2の在所の都合により、今宵はその妻(紀伊守の継母)が寄宿しており、家が荒れているとか。
源氏もそのことをしかと耳にしておりましたが、心は変わらず、「それこそ吉報。たとい像でも美女なきところになど宿るものか、おもしろくもない」
こうも迫られては他に打つ手もなく、使いを出して部屋の支度をさせました。使いが出てまだ間もないというのに、源氏も紀伊守の屋敷へ向けて出立なさります。そう急かずともと言い宥める紀伊守の言葉は耳に入らぬ様子。
舅に挨拶することもなく、選りすぐりのお供だけを連れて、なるべくひっそりと屋敷を後にしました。
寝殿の東庇の間を開け放し、仮拵えにも源氏を迎える支度が整えられ、まことせっかちなお迎えとなりました。なにをさておき源氏が感心したのは庭の一景です。池の水面の煌めき。それを囲む生垣の神さびた趣。按配のいい前栽の青々とした美しさ。かくも見事な庭に夕風が吹きそよぎ、夏の虫がそこはかとなく歌い、蛍が惑わかすように舞う。

お供は渡り廊下をくぐるせせらぎを臨む間に通され、酒を酌み交わし始めました。主人は源氏に膳を用意するよう急ぎ命じます。
いっぽう源氏はぼんやりと辺りを見回しながら、こんなのが左馬頭の言うところの中の位というものかと考えておりました。この同じ屋根の下にいつか噂に聞いた若き美女がいるかと思うと、一目見たいものだと気が逸ります。
その時、右手の小部屋から漏れ聞こえる衣擦れの音に気がつきました、それに続いてどこか感じのいい若い話し声にくすくすと押し殺した笑い声が混じって聞こえます。その小部屋の格子窓は少し前まで開いていたのですが、それをだらしがないと思ったのか、紀伊守の命でぴしゃりと閉じられ、今は襖障子の紙越しにかろうじて光の漏れるばかり。中を覗けぬものかと部屋の端まで寄ってみても甲斐なし。しかし盗み聞きならと源氏はそこを離れません。どうやら小部屋は女人の居室と隣り続きになっているようです。微かに話し声が聞こえました。源氏は頭をぴったりとつけて聞き入ります、どうも自分の噂をしているらしい。
「あんなに立派な皇子にもう相手が決まっているのが定めなんてかわいそうじゃない」という声。
「でも楽しみ放題できる幸せとすっかり縁切りでもないんでしょ」と別の声。
取るに足らない噂話ではないか、しかし源氏は耳をそば立てながら、たわいなく夢にも見る美しい御方を思わずにはいられないのでした。密か事がこんな形で見つかったり耳に入ったりしたらどうしたものだろう、そう思うと空恐ろしくもなるのでした。
【註】
*1 十二天将にまつわる俗信。この神が天降って巡行する間、その方角への筋上を進むことはおろか、留まることさえ禍いの因と言われていた。
*2 *2 伊予の国司の次官。若妻や家族を京に残して、伊予に赴任しているか。
(第16回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■