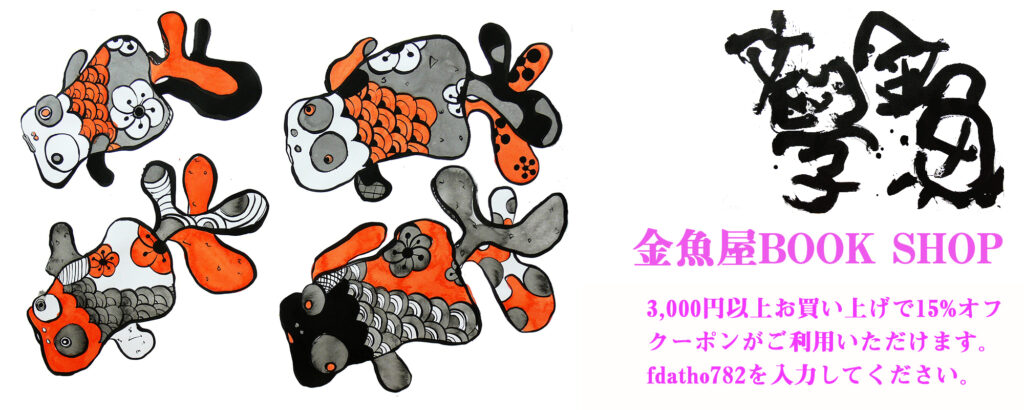日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
by 金魚屋編集部
箒木
その後の談義の始末ときたら。
なべて思慮の足らない者というのは――これには男も女もないけれど――大したことでもないのにひけらかそうとするだろう。それくらい気に食わないものはないな。いかさま、女のどこに三史五経を修める用があります。世間や家内の事情にまんざら無案内なのも困るが、そうしたことは知らず知らずに覚えるのだから、なにも学問をしなくたって、女共の雑談に興を添えるくらい聞きかじった程度のことで事足ります。学に驕れる女など話にならない。真名*1も至言金言も女のためにあるのじゃなし、それをあえて用いたところで世人は閉口するだけ、女は女男に非ずと弁えよ、というわけで。識者ぶっていると謗られるだけでしょう、就中やんごとなき貴女にその例の多いこと。畢竟、からっきし歌が詠めない無風流でもいけないが、歌詠みの俘になったり、濫りに引歌して悦に入る手合いに成り下がってはならない、そんな女は須く、謹む場では厚かましく、身を入れて働くべきときに決まって上の空。その思い違いの甚だしいことときたら、たとえば五月の節会*2です、一同厳かな儀に一心一向という中、女共の心の内ばかりは菖蒲に掛けた歌詠みにかまけて気もそぞろ、九日節会*3ならどうか、御歴々がお題に沿った詩作に没頭する傍で、 勝手に露置く菊花を題にして大それた詩興を巡らし、女だてらに男と競おうと躍起になる。何事にも潮時というものがございます、誰でもそうですが、女なら人一倍場を弁えることを常より心がけておらなければなりません、誰も気に留めていない時に出来た出来たと言い立てるなんてもってのほかです。学のひけらかしと姦しさこそ倹約してほしいものだ、それから得意な話題でも場の求めに応じて無知な振りができればなおありがたいのだが。
源氏はといえば、この女性論に終いまで付き合いながらも、思い当たるのは例の御方のことばかり、余計なところもなければ物足らぬと思うところもない、中庸を往く例のあることを幸いに思うのでした。さしたる結論の出ぬままに、夜は過ぎて往きました。
長雨上がり晴れ渡り、源氏はついに御所を出で、御新室の葵上の住まう舅の屋敷を訪れました。対屋の私室に居るというので、すぐに通してもらいました。奥ゆかしく端座した様子には何一つとて忽にしない丹念の跡が有り有りとしておりました。
左馬頭の言うところの信の置ける女とはこういうのを言うのだろう、という思いが奥へと歩を進める源氏の胸によぎります。と、同時に、その気高い妃然とした感じには束の間の恥じらいを覚えて、照れ隠しに侍女に話しかけずにはいられません。親しげなれど重苦しい室内にいくらか気圧される思いでした。ちょうどそこに舅が通りかかりました。足を止めて戸口に掛かった簾越しに話掛けてきたので、「暑いのにわざわざ」と源氏は声を顰め、「何の用かな」と呟くも、舅を呼び入れようという気にもならず、そのまま行き過ぎてもらいました。これには一同微笑とし、くすくすと忍び笑いが聞こえます。「口の軽い連中だこと」と言って咎めるように見回すと、源氏は脇息(肘掛け)に身を投げ出して静かに安らうのでした。
【註】
*1 固く形式ばった書体。
*2 五月五日の端午の節句は五大節句のひとつ。宮中では厳かな祝典が催された。水辺に生い茂る菖蒲の緑深く伸び盛る季節のため、菖蒲(学名はcalami aromatici)の節句とも呼ばれる。
*3 前注の五大節句のひとつ。九月九日に催された祝宴で、参加者はその場で割り振られた韻字をもとに唐詩を作るのが習わしだった。端午の節句を菖蒲の節句と言い慣わしたのと同じく、菊の季節のため菊花の宴とも呼ばれる。
(第15回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■