 宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
by 金魚屋編集部
12
出入り口を開閉できるリモコンは手に入れた。しかし、岩石砂漠の荒野を逃げなければならないのだ。白衣のポケットに車のキーは入っていなかった。職員用の更衣室があるはずだ。監視カメラをチェックしていたのがあの男なら、交代要員が到着するまで時間を稼げる。ただ、タイムリミットは不明だ。いますぐにでも警報音が鳴り響くかもしれない。
早いほうがいい。
「いつもどおりにしていて。いつカメラが動くかわからないから」
言い残し、美雨は部屋を出た。通路の向こう側に現れた、さっきの女が瞼に浮かぶ。
彼女はどこへ行こうとしていたのか。
美雨は走った。横目に部屋の窓が入りこんでくる。生徒たちの姿も視界を掠めた。隅で蹲ったり、ベッドで身を丸めたり、それぞれに防御の姿勢を取っていた。カメラの稼働ランプが消えたからだろう。今回は自分の番だと怯え、ドアが開かないよう祈っているのだ。
丁字路まで来た。あの女はどちらに消えた。美雨が顔を上げたのは一瞬だった。超がつくほどの近眼だと確認することはできたが、どちらへ向かったのかはわからない。目を伏せ、白衣の裾を睨み、早く去れと念じていたに過ぎない。
裾。どちらへ翻った。足の運びはどうだった。右か、左か。
美雨は、問題ありません、と左手を挙げて応えた。彼女に背を向けようと踵を返し、右に身を捻った。女はどうだった。視界からすぐにいなくなった。彼女の姿は引き千切られるように視界から消えた。美雨から見て左側に向かっていったのだ。
思い出した。曾が現れたのも左側だ。仕事場の方角か。ならば。
美雨は右へ舵を切った。職員とすれ違うかもしれない。身を隠す場所はないかと探したが、どこのドアも施錠されていた。助手から奪ったマスターキーは生徒の待機部屋用か。このままドアが開かなければ通路の奥まで行くしかない。そこに何があろうと、ほかに選択肢はなかった。横歩きになり、部屋という部屋を検めていく。すると純白の壁に切れ目が見えた。五メートルほど先だ。身を隠せるスペースを見つけただけで、ここから脱出したかのような安堵を覚えた。
スペースの先に階段がある。たった三段だけの。いつか両親と行った和食屋を思い出させた。確か、小上がりと教えられた。
スペースに入ろうとして、反射的に通路へと転がり出た。
来る。
足音。声。男。会話。ひとりではない。
どうする。
美雨は壁に背を貼りつかせた。こちらへ折れてこないようにと念じながら。

あの男性助手なら簡単に仕留められた。絶対にこちらを組み伏せることができると油断していたからだ。しかし、相手が複数であれば勝ち目は薄くなる。一人目を一撃で仕留めなければゼロパーセントだ。
先に出てきた男を狙う。
身構え、血の気が引いた。男たちが同時に現れたのだ。並んで歩き、伸びをする。
祈るしかなくなった。
男たちは談笑していた。美雨には気づかないまま、美雨が来た道を辿っていく。疲れた顔で、欠伸を繰り返して。
美雨は両膝に手をついた。一拍遅れて冷や汗を感じた。
当直を終えたのだろうか。ふたりとも私服姿だった。
ここか。美雨は「小上がり」へ入った。二股に分かれ、男女の表示がある。耳を澄ませたが話し声は聞こえない。物音もしなかった。女性用の更衣室を選んだ。施錠し忘れたロッカーがないか。確かめようとして天を仰いだ。自動ロック式。こじ開けられたとしても警報が鳴る。男性助手の高笑いが聞こえた気がした。あのまま体を許したほうが苦しみは軽かったはずだと腹を抱えている。
あの男はどうやってロッカーを開けていたのか。覆い被さろうとする姿が脳裏に蘇った。屈服させることを日常にしてきた、その自信が口元に浮かんでいる。眼球を擦らんばかりに揺れるIDカードの向こうで、注射針を突き立てるタイミングを見計らっていた。
美雨は踵を返した。IDカードだ。
しかし。
視界の端に「赤」が現れた。監視カメラが再稼働したのだ。更衣室から飛び出すタイミングを待っていたかのように警報が鳴った。車のカギはもちろん、護身用具さえないというのに。
部屋が並ぶ通路まで来ると、美雨はマスターキーを使い、つぎつぎに開錠していった。
「早く!」
生徒が溢れ出てきた。夢に中った顔をして。しかし、心の片隅に残されていた微かな望みが、条件反射のように機能しているにすぎない。通路を埋めるしか能がなかった。
唯を部屋から出した。戦果がないことを伝えると、雨雲で洗ったように顔が暗くなった。
「……やっぱり無理なのよ」
「とにかく出るの。あとはそれから」
足は重たいままだ。
「外に行けば、カギをかけていない車が見つかるかも」
岩石砂漠には「工場」以外に何もなかった。盗難される心配はないと考えているのなら、キーをつけたまま降りた運転手がいるかもしれない。
「見つからなかったときは、これで」
唯が取り出したのは銀色の何かだ。それを指に滑らせると血の跡ができた。バターナイフを研いだものだという。

医務室で首吊り自殺を目撃し、言葉を失った。あんな姿を曝すのは嫌だと思い、必要なときのために準備していたらしい。
「怖くてできなかった」唯が刃物を預けた。「美雨の手でやって。それなら本望だから」
「バカなこと言わないで。外に出てみなきゃわからないでしょ」
美雨は、刃物を返そうとして、白衣に押しこんだ。悶着している時間はない。受け取ることで唯が納得するならそれでいい。何より武器になる。
怒声に振り返った。制服が見えた。警備の担当者に違いない。こんな事態は想定していなかったのだろう。向かってくるのは三人だけだ。お世辞にも屈強とは形容できない男たちだが、足をふらつかせた生徒には充分すぎるほど脅威だった。騒動の源がどこにあるのか、彼らは完全に把握していた。
生徒たちは壁にはなり得なかった。時間の問題だ。警備員は体力や腕力で勝負しない。青白い閃光を炸裂させていた。スタンガンだ。
美雨の視線は彼らの腰元に注がれた。ベルトループにカギの束をぶら下げてある。美雨が隠れようとして失敗した部屋のものだろうか。そのなかに、種類の異なるカギが含まれていた。金属ではないし、形状も違った。出入り口のリモコンよりさらに小型だ。車のスマートキーかもしれない。
美雨は、先陣を切って向かってくる警備員の動きを観察した。あの男に切りかかれば威嚇になる。こちらが武装しているとは思っていないだろうから、きっと焦る。先手を打てば陣形は崩れるはずだ。しかし二人目をどうする。唯の戦闘力はないに等しいのだ。二人目と三人目が同時に攻撃を仕掛けてくれば太刀打ちできない。どちらかを殺傷できたとしても無意味だ。この戦いでは、一矢報いるということになんの価値もないのだから。
男たちがドミノ倒しを楽しむように向かってくる。追いつかれる。美雨は刃物を握った。どれだけ慌てさせられるか。それにかかっていると言っていい。あとのふたりを同時に倒すことは不可能だ。ならば威嚇しながら後退する。エレベーターに達するまで。
タイミングよく乗ることができれば勝算はある。良くも悪くも、出入口へ辿り着ける道は一本だけだ。
「先に行って」美雨は唯の背中を押した。「エレベーターを待機させて」
彼女の足は動かない。スタンガンの進撃に凍りついている。
「わたしも必ず行く。それまでなんとかして!」
一人目が、表情を確認できるほど近づいてきた。血走った目があった。怒りより笑みに見えた。男性助手と同じだ。いや、彼らは組んでいたのだろう。白衣組が監視カメラの操作を独占できるとは考えにくい。警備組がオフにし、助手に襲わせた。彼らは交代で部屋に侵入していたのではないか。
唯の戦闘力には期待していなかった。しかし、エレベーターを任せることさえできない。希望が消えかけたときだ。陽炎のように漂う生徒のひとりが、先頭の警備員にしがみついた。表情に気概と呼べるほどの色はない。それでも体が勝手に動いたように見えた。薙ぎ倒された生徒も立ち上がり、二人目、三人目の肩に掴みかかる。A・B班の非力な生徒ばかりだが、数が砦になった。警備組の突進は勢いを失い、生徒の群れに揉みくちゃにされた。
数か威力か。電光の餌食になった生徒は壁に凭れかかり、群れから零れ落ちていく。警備組の勢いが回復した。三人目の男が生徒を抱え、床に叩き落とそうとした。そのときだった。切り裂くような叫び声が聞こえた。曾だ。失神している生徒のそばに駆け寄り、状態を確かめている。彼女たちは商品であり、警備員の給与をかき集めても払えない額で取り引きされているに違いない。男たちがコンセントを抜かれたように足を止めた。
曾を追い抜いてきたのは、べつの制服を着た男たちだ。女性の姿もある。胸にプリントされたマークは、トレーラーの荷台にあったものと同じだった。業者だろう。そのなかのひとりが警備員に掴みかかった。
「制圧の仕方も知らんのか!」
美雨は、直立している一人目の警備員に近づき、腰からスマートキーを引き千切った。彼は美雨の背中を追いかけようとしたが、業者の男に恫喝された。
生徒の群れが息を吹き返し、スタンガンを奪い取ろうとしている。

業者は、みるみる数を増やし、生徒たちの爪先にゴム弾を撃ちこんでいた。矯正に支障のない場所を攻撃しているのだ。一列に、しかも交互に向きを変えた陣形で突き進む。
美雨は刃物を突き出し、空を切りながら叫んだ。「行って、早く!」
唯がなんとか足を動かした。そのあいだも敵は発砲してくる。いったい何発用意してあるのか。腰袋から弾を補給する数秒間だけが、美雨たちに与えられたかすかな自由だった。タイミングを計り、エレベーターとの距離を詰めようとした。しかし。
「ここがゴールなんだよ」
業者の男が最前列の警備員を押し退けた。刃物を思わせる目で睨んでいる。
「落第者だけに与えられる、有難い使命さ」
足を止めざるを得なかった。対峙させられた。一歩でも動けば踝から下が使いものにならなくなる。悶絶している生徒がその証左だ。
「投降すれば傷つけない。『出番』が来るまで穏やかに過ごせばいい」
美雨は刃物を突き出したまま静止した。エレベーターの到着音を待っていた。唯は乗り場に着いている。
曾も大股で近づいてくる。
この距離で撃ち損じることはないだろう。美雨ができるとすれば、どちらの足に狙いをつけているのかを予測することだ。それが可能なら、一発目だけはかわせる。距離を詰められる。格闘に持ちこめるかもしれない。二発目を狙うとしても、敵は再び足を撃たなければならない。的は小さい。緊張を伴う大仕事になる。
五分と五分。つまり唯と逃げることは叶わない。エンディングは美雨の人柱で成り立つ。
美雨は片手を挙げ、白衣を脱ぎはじめた。
投降の意思だと受け取ったのだろう。敵が銃口を床に向けた。
「行って!」
白衣をうしろに投げた。口を開けているエレベーターのなかへと滑りこんでいった。必要なキーはポケットに忍ばせてある。
唯は乗りこもうとしなかった。こちらへ歩み寄ってくる。諸手を挙げて。
「――どうして」
「わたしだけ行っても意味ないから」
あなたと会って、わかったことがあるのよ。唯は種明かしを披露するかのよう言った。
「誰かのために何かをする。それで救われる生き方もあるってこと。わたしは美雨のことが大好きだから、憧れていたからできる。心からそうしたいと思う」
この局面で微笑みを浮かべていた。分身のそれと重なった。美雨がどんなに愛想のない態度で接しても、彼女は笑みを絶やすことはなかった。大好きな人と会っていて楽しくないはずがないでしょうと言わんばかりに。美雨は溜息を吐いた。それが隙になった。唯に刃物を奪われた。
「結局、何が言いたいのかっていうとね」唯が頸動脈に刃を立てた。「あなたは誰かの希望になれる人なのよ」
鮮血が宙を舞い、曾が飛びこんできた。水漏れした箇所を見つけたように押さえている。が、血の勢いは止まらない。指のあいだから噴き上がる。
美雨が近づこうとすると、唯は胸を突いて押し返した。手のひらをプリントしたように赤黒い跡がついた。刹那、背中を引っ張られた気がした。細く、しかし、強靭な糸で縫いつけられているような感覚だった。振り返ると分身がエレベーターのなかにいた。こっちへ、と誘っている。
見捨てるわけにはいかない。胸で唱えると、引っ張られる強さが増した。
誘っているのではなかった。ここから退散することこそが使命なのだと叫んでいる。
唯の命が萎んでいく。彼女を囲む全員が血塗れだった。
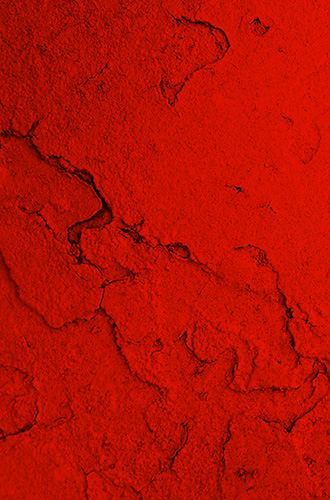
彼女は死ぬ。分身と同じように、この世から消えてなくなる。
美雨は今度こそ振り返っていた。糸を手繰る思いで分身を見詰めた。彼女が殺害されたあと、美雨は断末魔を望んだ。自殺の真似事をして、彼女の声を聞こうとした。しかし何も語ってくれなかった。
ようやくわかった。彼女は気づいてほしかったのだ。彼女が何を望んでいたのかを。
彼女が憧れた宋美雨は、臆さず、振り返らず、毅然と戦ってきた。彼女は、美雨が負けることを誰よりも望んでいなかった。
高速エレベーターがデジタル表示をフル回転させている。息を整える間もなく到着した。音も気配もないフロアに転がり出ると、頬を射す照明が笑っていた。この先に待ち受けている障害が確実に気持ちを削ぐはずだと。
階段は天に繋がっているのではないかと思うほど高く、長い。階下の格闘で気力の残量が尽きかけていた。すぐに太腿が悲鳴を上げた。手をつき、蜘蛛の姿勢になっていた。
追っ手の気配が空耳だと気づいたとき、目のまえにある鈍い銀色と向かい合っていた。ドアだ。リモコンを操作したが、外の空気は入ってこなかった。赤い突起を押し続けても、ドアはにこりともしない。認証が変更されているのだ。曾が執拗に追いかけてこなかったのはそのせいだったのか。
美雨はドアをたたいた。開くはずがないとわかっていても、全力でたたかなければならなかった。何もしなければ唯は無駄死になるという思いがあった。彼女がしてくれたことを思えば、背後から曾の手が伸びてくるその瞬間までたたくべきだと。
余力が尽きるまで時間はかからなかった。ドアに額を押し当てたときだ。電子音が耳に届いた。轟音を混じらせ、それは間違いなく接近していた。
ドアから離れた刹那、外から凄まじい衝撃が伝わってきた。銀色が内側に凹み、僅かだが隙間が生まれた。指をこじ入れようとして、しかし、美雨は後じさりした。また電子音が聞えたからだ。ほぼ同時にもっと強い衝撃が襲いかかった。
轟音の正体に気づいた。エンジンだ。三度目の衝撃でドアが折れ曲がった。美雨は、車が前進したタイミングで外に転がり出た。
雨は止んでいた。昇りはじめた太陽を見上げると、視界に入りこんだ影があった。金色の虎。尚真だった。
運転してきたバンが乗り捨ててある。それではドアを壊せないと思い、トレーラーを品定めしたのだろう。やはり不用心な停め方をしたドライバーがいたのだ。
尚真は、手首を千切らんばかりの力で引っ張り上げた。胸元についている血の跡を撫で、様々なことを一纏めに理解したような顔をしていた。
「ワケあって、骨のあるやつが要る」
それだけ告げると、美雨を助手席まで抱えていった。

*
食材を届け、空いた容器などを回収する。生徒の健康管理に関わる資料は、学園の事務局から細かく送られてくるが、それだけでは足りない。実際に足を運び、センターで給食する職員から生の声を聞くことも重要だった。彼らは数値化できないような生徒の反応を直に見ている。栄養の過不足を微調整するといったレベルとは違い、食事をどう楽しんでいるのかという点にも気を配ってきたのだ。真に健康な飲食とは何か。それは完全にストレスから解放された状態で摂れるかどうかだ。会話が弾むような場を提供し、食味を引き立てる香りや盛りつけのベストバランスに拘りながら、明晰な頭脳と健全な心身を向上できるメニューを開発し続けなければならない。
食材を運ぶドライバーの使命は重要なのだ。担当者から見聞きした内容を自分の経験と照らし合わせ、取捨選択し、最善策も含めて報告する責務を負う。
「副部長」
部下が怪訝な声を出した。外を指している。
「ずいぶん、時間がかかりましたね」
そのとおりだった。届けに向かえば一時間はもどってこない。すべての義務を消化するまでは最低でもそれくらいはかかるからだ。彼がハンドルを握っていたときはもっと慎重に情報を集めた。上司に突っつかれたことはない。いいネタを仕入れてくれば、上司はいつも機嫌がよかった。その上にいる上司にはもっと受けがよかったからだ。そうやって信頼を一枚ずつ重ねた結果、部のナンバー2に就くことができた。親会社の重役室で最重要な使命も与えられた。
今日は倍以上の時間がかかっていた。慎重に、という彼の口癖を思い出してのことだろうか。それならば喜ばしい変化だったが。
彼は、ドライバーの表情を見やり、眉間を寄せた。いつもなら駐車場に停めた直後に連絡が来る。エンジンを切るか切らないかというタイミングで。しかしインターフォンは鳴らなかった。車を降りると真っ直ぐ棟に入った。ここへ向かっているのだ。
何かが起こり、それを校内で目撃した。通話連絡できないほどの何かとはなんだ。万にひとつでも傍受されては困る何か、ということになる。
いつもよりずっと遅く帰ってきた。そこに注目したところまではいい。しかし、何が起こっているのか、という点に拘ることはなかった。この愚かな部下は、今日もせっせと横流しの物品をかき集めている。党員の子息、イコール、バカ息子だ。出世することに疑いを持たず、邪険にされるとは夢にも思っていない。
「外してくれないか」
彼は物品のひとつを拾い上げて言った。茎が曲がっている程度の「異状」だが、この野菜をつくるためにどれだけの労力と予算が注ぎこまれているか。補佐役を拝命していながら、こいつは手間暇という言葉を学ばないまま搬送部の住民になった。重要なことを何ひとつ身につけることもなく、明日も明後日も損得勘定ばかりを気にして生きていく。その腐った眼に向けて、彼はハッキリ「出ていけ」と命じた。毒気に触れた経験がないのだろう。部下は目を瞬くだけだった。
「聞こえたろ」
彼は手にした野菜で頬を打った。部下は鼻血が滴り落ちる現実を信じられずにいる。目元も切れ、赤い涙を流していた。
「……あ、あんた、自分で何をしたか」
かろうじて、という声だ。
「ぼんくらを躾けた。どこが悪い」
何かが自分に与えられ、誰かが自分に従う。その構図には慣れ切っているだろう。しかし、逆はなかったはずだ。あんた、という言葉も借り物である。
「おまえはいま、誰と話しているのかわかっていない」
「誰と、って。それは」
「わたしは崇高な使命を与えられた番人だ。そのことを、まるでわかっていないのだ」

ドライバーが息を切らせて入ってきた。人払いしたことを告げられ、玉の汗を拭った。
「ご報告が」
起こってはならないことが現実になった。盗聴されるおそれのない専用回線を使う必要がある。発動すべきときが来たのだ。
「わたしだ」彼は一本道の先を睨みつけた。「王さんを。研究主任を頼む」
(第12回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『クローンスクール』は毎月15日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


