 宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
by 金魚屋編集部
11
地の底へ繋がっているような階段だ。ライトは点灯しているものの、階下の様子を確認できない。連れてこられた生徒たちは異状に気づいたはずだ。一階部分にあれだけ広い一角を設けながら、どうしてこんな階段を降りなければならないのかと。工場が稼働している音も聞こえてこなかったのだから。
側面には無数の傷がついていた。クリーム色の塗装が剥げ、コンクリートが顔を出している。手錠を擦らせた跡か。作業助手は怯える者たちを強引に連れこんだのだ。
作業助手の力は強く、美雨は踵を浮かせた状態で歩かされた。彼らの体臭は鼻が曲がるほどきつかったが、鮮度のいい空気を吸える術はない。
爪先が痺れてきたころ、ようやくフロアに着いた。天井の角にあるライトが斜めに放射され、この空間に何もないことを知らせている。機械音が底から響くだけだ。それが徐々に近づき、やがて鈍い到着音とともに静まった。フロアの先にエレベーターが見えた。
ドアが開いた。エレベーターは、貨物専用ではないかと思うほど背が低く、狭かった。生徒たちは、人格を無視された「モノ」として扱われているのだ。
作業助手は何も語らず、力を緩めることもなかった。手に余るときは容赦しないと伝えつつ、諦めさせるには最適な方法だった。それでも生徒たちは訊いただろう。どこへ連れていくのか。何をされるのかと。
美雨は違った。「64はどこ」
意表を突かれたのだろう。反射的に、という口調でひとりが答えた。
「各自に部屋が与えられている」
「トレーラーは業者のものでしょう」
口を滑らせた作業助手に食ってかかった。もうひとりに制圧されるおそれはあったが、気づいていると伝えるにはそれしか方法がなかった。
「わたしたちの頭をいじって、矯正して、売る。そうよね」
無言が返ってきた。87の見立ては的を射ていたようだ。
「いつなの」
「順番はない」
買い手からの要望に合致すれば、すぐにでも出番があるという。
「仕上がりには個人差がある。それも条件のひとつだが、おまえたちの性格も然りだ」
性格?
「それが仕上がりを決定づけると信じられている。なんの根拠もない話だが」
矯正された状態がどれだけ長持ちするか。そうした市場価値を決める判断材料のひとつに性格の良し悪しがあるという。

「業界の都市伝説みたいなものだな。特にこの国の消費者からは強い要望がある」
値段に反映するからこそ選別には慎重になるというわけだ。
「64は」
「まだ出番ではないようだ」
そのうちに、という重い響きがある。
階下に着いた。強い光が四方から浴びせられ、影さえできない眩さだった。人工的な真昼が広がっている。
地上の建物部分は、どこかから移されてきたのではないか。あまりに粗末なつくりに思える。広いだけで、近代性も科学性も感じられなかった。ここは違う。
彼らが手を離した。逃走の心配はないという確信だろう。事実、抗う気力が萎えそうだ。心の襞に隠してある思いさえ覗かれそうな、完璧な黄金色のなかを歩かされていく。
やがて広大なスペースが消え、それが映像だったことに気づかされた。目くらましの先にあったのは通路だ。すれ違うにはどちらかが体勢を変えなければならないほど狭く、しかし、奥の景色を確認できないほどの長さを誇っていた。
通路の片側には透明な窓が並んでいる。部屋だ。それぞれにナンバーが打ってある。
3―11 3―20 3―39
1と2からはじまる部屋がない。第三世代用なのだ。しかし、ここから下の階はなかったはずだ。第一世代と第二世代は処理されてしまったということか。
「64に会わせて」
「ダメだ」
「五分だけ」
「なんになる。おまえたちの『使命』に変わりはない」
3―64の表示が見えた。手錠をつけたまま、美雨は体ごとドアにぶつかった。
「唯!」
窓に顔を預け、声を限りに叫んだ。
「わたしよ。美雨よ!」
窓に額を打ちつける。割ることができるならそうしたいと思った。しかし、ガラス製ではなかった。目のまえに火花が散るだけで、窓は憮然としている。部屋の様子を検めようとしたが、視界は斑に霞んだ。64がどこにいるのか、こちらに気づいたのかさえわからなかった。足もふらついた。作業助手が警棒を振り上げている。まともに食らう。失神し、運ばれる。64に会えることはない。叶わない。
「やかましい!」
刺さるような甲高い声だった。
「何をやっている」
女性だ。白衣を着ていた。医者か研究者か。
その顔に焦点が合ったとき、美雨はタイムスリップしたのではないかと思った。あまりにも面影が濃かったからだ。オリジナルなのだ。第三世代は彼女の細胞から生まれた。
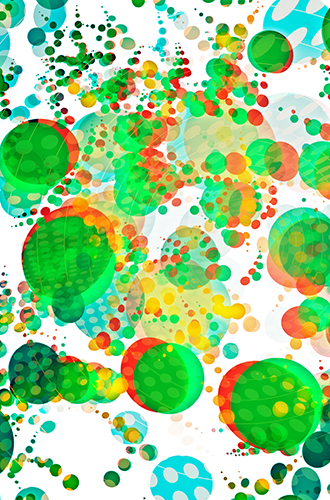
作業助手たちが最敬礼している。
「どうして鎮静剤を打たない」
「ずっと大人しかったものですから」
「ここへ送られてきたからって、彼女たちは無能ではないのよ」
女史が美雨の頬を包んだ。湧き水で研いできたかのような冷たい指先だった。
「ごめんなさいね。すぐお部屋に案内するわ」
首から下げたIDカードに指名が記されている。曾薇(ツォンウェイ)。彼女こそが生みの親であり、失敗作の処分にも関わってきたのか。
「お願い。64に会わせて」
「どうして」
「伝えたいことがあるの」
「どんな」
「会って言います」
「伝わらないわ」
自分たちの脳をいじくる姿は想像できなかった。慈愛だけが瞳の奥に見える。
「64のことはよく憶えている。無抵抗だったという意味でね。部屋に入ってからも同じ」
覚悟を決めたのよ。曾はそう言って、同伴する男性助手に目配せした。作業助手より年嵩で、曾と同年代に見えた。短く返事を切る姿は忠犬そのものだったが。
「生徒を傷つければ、直々に校長と掛け合う。いいわね!」
またしても怒鳴られ、作業助手は膝に額がつくほど頭を下げた。
美雨のことを思う言葉に聞こえるところが厄介だ。毅然さと勇ましさに打たれそうになる。商品を傷つけることは絶対に許さない、という意味でしかないのに。
部屋まで来た。64の居場所から二十メートルほど離れている。
男性助手がマスターキーを翳すと、ドアがスライドした。なかは寮の部屋と同じ広さだ。しかし、調度はない。簡易ベッドとトイレが対極の位置に置かれているだけだった。天井の中央部分にはカメラが設置されている。
「明日の朝一番で精密検査をおこないます。気分が悪くなったら、あのボタンを」
枕元に緑色のスイッチがある。
「64は性格がよさそうだから、出番が早まるかもしれないわね」
曾は、自宅へ招くかのように美雨を部屋に入れた。
「騒げば鎮静剤を打ちます。半日は動けなくなると思って」
脅し文句さえ優しい響きのままだった。
ドアがスライドすると室内は無音になった。通路が静かだということはエレベーターを降りてわかったことだが、それ以上に防音機能が優れていることは疑いようもない。美雨が部屋に入ったあと、ドアの向こうでは、曾が作業助手たちと話していた。口の動きだけで内容がわかるほどの剣幕だった。そんな彼女が窓に近づいても音は漏れない。64がどんな状態だったにせよ、美雨が窓をたたいたところで気がつかないはずだ。
64は性格がいいから高値がつく。買い手との交渉がまとまれば、矯正作業が開始されるという。どうすれば彼女の部屋に行けるだろう。手錠なら外せる。87からカギを受け取り、忍ばせていた。しかし、不審な動きを見せれば職員が飛びこんでくる。ここもカメラで監視されているのだ。パニックを装えばどうか。鎮静剤を打ちにきた職員を制圧し、ルームキーを奪う。応援が到着するまでに64の部屋へ行き、話す。要件は五分で済むのだ。あるいはコールボタンを押して不調を訴える。入ってきた人物をどうにかするという意味では変わりない。問題は制圧できる保障がないということだ。相手は武具を用意しているかもしれない。五分五分の戦いになれば長引く。しかし、ほかに選択肢はなかった。
暴れるか、ボタンを押すか。暴れれば複数の職員が押しかけてくるはずだ。有無を言わせずに注射針を突き立てられる。ならばボタンだ。気分が悪いフリをしていればいい。こっちは手錠をはめている。相手の警戒心が薄いことは間違いない。
後ろ手にカギを抜き出した。カメラからは死角になっている。いつでも挿しこめるよう、手のひらのなかに移動させ、ベッドに倒れこんだ。少しだけ呻き声を発してみる。あとは、もぞもぞと首を動かし、額でボタンを押せばいい。
やってみるとなかなか難しかった。目で追って確認しても、いざ押そうとするとボタンの位置がわからなくなるのだ。ようやく突起を探し当てたときだった。窓の外に人影が見えた。ドアがスライドした。音もなく白衣が入ってくる。曾が連れていた男性助手だ。

暴れていたわけではない。コールしたわけでもない。にもかかわらず現れた。カメラの稼働ランプが消えている。切ってきたのだ。逆光だが、表情の変わりようは隠せなかった。理性も消えていた。曾には事後報告するつもりか。通路を歩いていたら苦しがっているのが見えた。入ると暴れたので鎮静剤を打ったと。
「通過儀礼みたいなものだから」
覆い被さってきた。美雨の両肩を掴み、仰向けにする。足をこじ開けるのかと思いきや、腹に座ろうとした。
どうすれば効率的に無力化できるか、この男は知り抜いている。いや慣れている。何度もやったのだ。ほかの生徒たちに。おそらく64にも。
首から下げているIDカードが、美雨の眼球を擦るように振幅する。顔をずらそうとしたときだった。部屋がさっきより暗くなった気がした。助手が肘鉄を落としていた。視界が捻じ曲がった。
丸めた布を口に押しこんでくる。どんなに叫んでも外には聞こえないというのに。そのほうが興奮するということか。
しかし、相手が動いてくれて助かった。みぞおちを圧迫していた男の尻が離れたからだ。その隙を見逃さず、美雨は体を横向きにした。膝で腹を包むような体勢をとると、手錠にカギを挿しこんだ。
「無駄だって」
引き攣ったような笑い声だった。
もうひとつ幸運がある。この男が鎮静剤に頼ると予測できたことだ。できるだけ商品を傷つけずに楽しめる。しかも効果覿面だ。絶対に使う。
注射器を取り出した瞬間を狙った。美雨は、男の手首を掴むと、自分の胸元へ引っ張りこんだ。相手がバランスを崩し、倒れこんできた瞬間が勝負の分かれ目だった。男の首に足を回し、もう片方の足で挟みこむ。両脚を使い、相手の首と片腕を同時に極める。頭を押さえると頸動脈が締まり、確実に落とせる。
C班の生徒も扱ってきたというのに、こんなオーソドックスな締め技への対処さえ知らないらしい。頭を押さえるまでもなく、男の手から注射器が零れ落ちた。美雨の頬を掠め、ベッドに突き刺さった。上半身がゴムに変わったかと思うと、男は白目を剥いた。太腿に力を入れただけで気絶してしまったのだ。
白衣のポケットを探るとマスターキーと黒く小さな立方体が入っていた。赤い突起がついている。作業助手たちも持っていた。外のドアを開閉するリモコンだ。
白衣を剥ぎ取り、袖を通す。代わりに手錠をプレゼントして。
通路に誰もいないことを確認し、美雨は部屋を出た。
カメラはもちろんあった。点灯していないが、ほかの職員とすれ違うかもしれない。そのときは、できるだけ相手に近づかせ、急所を打ち、鎮静剤を使う。部屋に引き摺りこみ、あの男と一緒に眠ってもらう。
鉢合わせにならないことを祈った途端に人影が見えた。白衣だ。通路の向こう側にいて、足を止めている。64の部屋まで数メートル。

顔を上げられず、足元しか確認できない。しかし曾ではない。彼女は低いヒールを履いていた。向こうの人物はスニーカーだ。しかもノーブランドの安物である。作業用に使い古されたもの。職位は低い。
「変わりはない?」
尋ねる声に馴れ馴れしさがある。同じ助手か。それならば、こちらがニセモノだと気づいてもよさそうなものだが。
美雨は上目で確かめた。女性だ。牛乳瓶の底を切り取ったような眼鏡をかけている。目を細めても、こちらの白衣姿を確認できているにすぎないのだ。
「問題ありません」
美雨は咳払いしながら左手を挙げた。
「どうだか」
皮肉るのが習慣なのだろう。警戒した口ぶりではなかった。
潜りこむようにして部屋に入った。唯は一瞬だけこちらを見たが、ベッドから起き上がろうとしない。右腕をだらりと垂らし、目を閉じる。いつでも。そんな心の声が聞こえてくるようだった。捲られた袖を直してやると、少しだけ瞳に生気がもどった。
「――美雨」唯はシャッターチャンスを見つけたように目を瞬いている。「どうやって」
経緯を伝えると、呆れたような、驚愕したような、あらためて認め直したような表情が返ってきた。「ダメよ。連れもどされるわ。きっとひどいことをされる」
「それでも来たかった。伝えたいことがあった」美雨は唯を抱き締めた。「ごめんなさい」
緊張しているのがわかった。強張らせた体で訊いていた。わざわざそんなことを告げに来たのかと。
「あなた、ご両親と何を話したの」
美雨が電話したとき、唯の母親は怒りと不快感を隠さなかった。揉めたのだろう。
「売り言葉に買い言葉ってあるじゃない。誤解し合うこともね。だから会って伝えようとしたんでしょう?」
ここに忍びこみ、詫びるつもりでいた。それは叶った。しかし彼女を置いていけば確実に「操作」される。見捨てることになる。何かが起こるはずだと気づいていて、口も手も出さない。それこそが分身にしてきたことだ。
「一緒に行きましょう。きっとわかってくれるわよ」
しかし。
「必要ない。望んでもいないし」
「望んでない?」
「わたしを育ててくれた感謝を伝えたの。そしたら、あの人たち、なんて言ったと思う」
ふたり、が、あの人たち、に変わった。
「感謝しているのは自分たちのほうだって。十八年間やり抜けば、都市民になれるんだそうよ。戸籍欲しさにわたしを育てたってこと。子供のために尽くす親のフリをして」
唯が額に筋をつくった。この顔で怒鳴ったのだろう。
「売り言葉に買い言葉でもなければ、誤解でもない。わたしは自分の意思でここに来たの」
両親に責任を負わせようと、敢えて逃亡したのか。
「だからって手術されるのを待つの」
「ほかに行くところなんてないわ。信じられる人もいない」
「わたしを信じてるんでしょ」
「それとこれとは話が違う。行き場所の話をしているのよ」
「同じよ。わたしと一緒にいればいい」
美雨は分身のことを伝えた。
「熱狂的なファンだった。どんなに敵が増えても彼女だけは離れなかった。励みになったわ。なのに、わたしは彼女の心を利用した」
自尊心のなんたるかについて両親から教わってきたはずなのに、得意になり、戒めを忘れた。結果、彼女を死に神に明け渡すことになった。
「わたしには、そんな恐ろしい心が宿ってるの」
「だから誰とも接しないようにしてきた」
「あなたを不幸にすると思ったから」
「でも来てくれた。その子への罪滅ぼしかもしれないけど」
「謝りに来たのは、わたしを慕ってくれて嬉しかったから」
唯の目が潤んだ。

「ここから脱出できたとしても、きっと捕まるわ」
「C班の手が届かない場所へ行く」
「そんなところない」
「日本よ。わたしは留学する準備をしていたの」
叶えることはできなかったけど。日本語でそう伝えると、唯が口を押えた。
「どこに行けたとしても、きっと日陰で暮らすことを強いられる。ただ、そのために必要なものがこの国では揃う」
美雨の実家は都市圏と地下経済の境目にあった。そこを利用する者がいかに多いか、どれだけ根づいた慣習なのかを幼い頃から間近に見てきた。高級なスーツ姿の男女が屋台の金貸しを訪ねる。党のバッヂをつけた人間が臆面もなく物品を換金する。ゴージャスな外車で乗りつけ、垢に塗れた男たちと商談する。目撃するのは日常茶飯事だった。
「おカネさえあればなんとかなる」
その気になれば、自分を犠牲にすれば稼げる。唯はすぐに理解したようだった。あの助手にされたことを思えば乗り越えられると。未来のためだと唱えれば、辱めの意味は変わる。苦痛にも意義が裏書されるのだと。
訓示がはじまる時間だ。起立して出迎えるのが常で、胡が遅れることは一度もなかった。権威への拘りが強く、完全無欠を見せつけることが日常だった。1―30や19が逃走した事件への対応もその方針に基づいている。爪先までメンツで塗り固めた男が、しかし、この朝は姿を見せなかった。
彼が校長室で待機中だということはみな知っていた。出勤時、在室灯を確認するのが習慣になっているからだ。いつもの朝を疑う者は誰もいなかった。それでも現れない。何かあったのだ。みな目だけで会話しはじめた。しかし、確認しに行ったほうがいいという眼差しは少なかった。遅刻したことを認めさせるような行動は厳に慎むべきだと譲らない。
三十分が経過し、校内アナウンスの開始を告げる電子音が響いた。アナウンスできる場所は限定的だ。職員室の機材に触れている者はいない。あとは医務控室か校長室だけだ。
胡の掠れ声が聞こえた。職員への訓示を放り出し、何を伝えようとしているのか。

『校長という身分でありながら、わたくしは』
搾り出すように語りはじめたのは、胡が犯したスキャンダルの一部始終だった。生徒をたぶらかし、特別に部屋を与え、愛人として囲っていたという。
「そんなバカなこと、信じられるか」
「脅されているのよ、きっと」
「こうしちゃいられない」
黄を中心とした体制派の教師たちが、防弾仕様のケースを開錠した。警棒などが格納されている。培養組との顔合わせのさい、逃げた生徒を鎮圧した武器もここから取り出した。
張も廊下に出た。声はさらに高く響いた。職員より生徒に聞かせようとしているのだ。
校長室は施錠されていなかった。胡がマイクに向かっていた。後ろ手に縛られ、顎を突き出し、膝を震わせている。1―41に支えられていないと顔を窓に突っこんでしまいそうだ。その彼女は銃を密着させていた。あれでは狙いを外しようがない。教師たちは立ち尽くした。まかり間違えてトリガーが引かれれば、誰かがその責任を負わされる。
彼女は張と目を合わせたが、なんの感情も向けなかった。教師のひとりとしか見ていない。彼女を再び校内に呼び寄せたのは張だというのに。
特別な捜査を依頼するため、一本釣りした。その彼女が、胡の愛人だったというのか。
胡は、かつての逃亡事件を揉み消すために他言無用を命じ、19が失踪した事件もなかったことにしろと指示した。ふたつがリンクしているという証拠が見つかれば、失踪事件は逃亡事件へと成り代わる。胡はふたつの逃亡事件を学園史から消そうとしたことになるのだ。しかも今回は校長として命令した。前回とは意味合いが違う。
張から特命を受けた1―41がスキャンダルの相手でもあった。こんな偶然があるのか。彼女は、前校長、王の方針に賛同する張を認めていた。胡を追い詰めるために呼ばれたことも理解していた。それなのに捜査協力を受けた。依頼内容を胡にバラすこともなく。愛人なのに。
「わたしに何を望んできたか、みなさんに説明してあげなさい」
股間の銃をさらに押しこむ。ナイフで抉るように突き上げる。
胡は剥製のように動けない。ただの脅しではないと実感している。しかし、目は虚ろで、卒倒の兆しが見て取れた。
「早く!」
1―41は、あの一件でメンツを潰された。それでもへこたれず、見事に卒業資格を手にした才女だ。彼女にしか知り得ない葛藤があったはずだ。物静かで理知的な雰囲気は、当時の試練を経て得られたものだろう。それがいまはどうだ。まるで別人ではないか。
威厳の塊がすすり泣いている。手段を選ばず、というやり口に怯え切っている。
別人。
依頼したのは確かに1―41だった。しかし、いま目にしているのが彼女ではないとしたら。捜査の過程で1―30と入れ替わったのか。組ませた22も騙されてしまった。だからこそ難なく校内に侵入できた。すべては胡に復讐するためだった。
(張先生)
林が袖を引っ張った。隣にいる梁もこちらを見ていた。ただならぬ表情だった。
(願ってもないタイミングだわ)
いましかない、という。しかし生徒の協力が不可欠だ。アプローチした者は僅かだった。
林が袖を離さない。張の懸念は充分に理解しているという顔だ。
(トップ5と培養組以外の生徒は、きっと理解してくれます)
反体制側に賛同するなら脱落予備軍だ。数では圧倒している。
時期尚早だと窘めてきた。みずからにも言い聞かせてきた。22からの捜査報告が上がり、証拠が出揃うまではと。
(張先生!)
梁がうしろを指した。校長室のドアは開けたままだ。その向こうに生徒が群れていたのだ。外組ばかりだが、AもBもCもなかった。胡を出せ、と目が沸騰していた。
(第11回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『クローンスクール』は毎月15日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


