 宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
by 金魚屋編集部
7
入校して初めての事態だった。C班の授業がすべて休講になり、教室内で自習するよう言い渡された。教師たちが緊急会議をおこなうためだという。
空席がふたつあった。昨日、初仕事を命じられた生徒が揃って休んでいる。
87のことだ。ものの見事にターゲットを捕らえ、外組トップの座を死守するのは間違いないと思っていた。が、彼女は担架で運ばれてきた。医務室に直行し、治療を受ける羽目になった。暴漢に襲われ、負傷したのだ。田が駆けつけたときにはゴム弾を使い果たし、警棒一本で応戦していた。何より悔やまれるのは、時間内に捕縛できなかったことだろう。
同伴した19は行方不明のままだ。状況から判断すれば、裏通りで襲撃され、すでに殺害されている可能性が高かった。場所が場所である。遺体が出てくることはまずない。
仕事上のトラブルは少なくないようだが、生徒が拉致され、行方知れずになったことはないと黄は話していた。カリキュラムの進め方にも大きく影響するのではないか。
聞けば聞くほど、いつ起こっても不思議ではない内容だ。C班の仕事に付いて回る特有の問題だろう。ターゲットの逃亡先は誰にも予想できない。シグナルを追えば密林に迷いこんだような状況に陥ることもある。狩人のほうが命を落とすかもしれない。
自習を続けている最中、教室中央から歓声が上がった。95だ。教壇に置かれている電光掲示板の表示が更新したのだ。外組のトップがついに入れ替わった。87の牙城が崩れた瞬間だった。遺体が見つかっていないため「19」はまだ表示されている。87と同様に減点されたため、三位から四位に落ちていた。
95の興奮は収まらなかった。自習が手につかず、独り言を繰り返していた。これまでの努力を呟き、目を潤ませている。それができるのも87の姿がないからだ。しばらくは95の自画自賛を聞くことになるだろう。
87は医務室組を見下していた。とうの本人が同じ立場になるとは思ってもみなかったはずだ。今頃は純白のカーテンに見下ろされ、きりきりとした思いで横たわっているのではないか。少しは自殺した生徒の気持ちに寄り添えるだろうか。美雨は頭を振った。そんなことを思うより先に、自殺しか選べない心を蔑むに違いない。
一日中、机に噛りついた。監視カメラがあるせいで気は抜けないものの、それでも格闘技や射撃の恐怖から離れた日常は静穏だった。もちろん自薦している立場だ。仕事が入れば87のように傷めつけられるかもしれない。

ベルが鳴り、一日の終わりを告げた。会議の行方しだいでは明日も自習だという。今日はやけに配給部が賑わった。いままで忘れていた何かを取りもどすかのように、昼時だけではなく、放課後も騒がしくなったのは久しぶりだ。美雨は、いつにも増して誰かと交わることがなかった。授業が終われば、真っ直ぐ寮へもどるつもりでいた。95の独り言に煩わされ、頭がおかしくなりそうだった。校舎裏にある渡り廊下を進み、出入り口でIDカードを翳したときだ。背後から声をかけられた。
連れていかれたのは職員室ではなかった。射撃用の器具を置いてある倉庫だ。開かずの暗幕が下ろされている場所で、オイルと火薬のにおいが沈殿していた。
「相変わらずだな」と張が口元だけ歪めた。「おまえは誰とも群れない」
「後々、面倒ですから」
「だからこそ、こうして呼び出せたわけだが」
「なんの用ですか。早く部屋で休みたいんですけど」
「そう焦るな。おまえを見込んで、という話だ」
「だいたい、こんなことをしている暇があるんですか。会議はどうなりました」
会議は終わっていないし、進行具合にも納得していないという。泥縄の対処法が話し合われたのだろう。
「カリキュラムが変わるのですか」
「付け加える内容はあるかもしれないが、基本路線に変更はない」
授業内容に瑕疵はなかったという判断だった。ならば、どうして不満足なのか。
「87は」
「運ばれたのは脳震盪を起こしていたからだ。大事をとった」
安静にしなければならないが、打撲と傷の程度は軽いという。
「あいつらしいよ。七人を相手に格闘したらしいからな。体力が切れて最後のひとりには手こずっていたようだが、あとの六人は半殺し状態だったそうだ」
捕縛したターゲットが逃げないよう、見張りながらの立ち回りだったはず。それでも打撲で済んだのは87の底知れない力が働いていたからではないか。美雨はもちろん、彼女と訓練した生徒なら誰でもそう感じるはずだ。培養組に締め落とされそうになっても参ったと意思表示したことがない。関節を極められても同じだ。負けを認めるくらいなら死を選ぶ生徒だ。その彼女が現場で死闘を演じた。男たちは本物の獣を目の当たりにしたのだ。
「19は」
「まだ見つかっていない」
C班の生徒には発信機が装着されていない。が、手渡されたモニターがその役目を果たしている。監視役の田は生徒の現在位置を画面上で検められる。彼女たちがどんな計画を立て、実行に移すのか。これまでの経験から、生徒の動きを見れば推測できるという。
「挟み撃ちにするプランだったらしい。19は裏道から背後に回ろうとした」
ターゲットが隠れている建物のそばまで歩み寄った。順調だった。ややあって、87が表通りから接近してきた。その直後、19からのシグナルが消えてしまった。田は急行したが19の姿はなかった。87を襲ったような男たちはどこにでもいて、何が起こっても不思議ではない。しかし、シグナルが消えた現場付近には、事件直後の物々しさや生々しさがなかったという。19は、いつでもターゲットを捕らえられる絶好のポジションにいた。87が捕縛に動けば、挟み撃ちは完了するはずだった。順調に事が運んでいたというのにシグナルは途絶した。しかも失踪現場に事件の痕跡はなかった。類推できることはひとつだと張が目を尖らせた。
「意図的にモニターの電源を切ったのかもしれない」
だとすれば。
「逃げた可能性が高い」

培養組が逃亡したというのか。C班の生徒は逃亡できる環境に置かれている。だからこそ予防措置がとられてきた。しかし、事実上、培養組には適用されないものだった。彼らには責任を代理させる「両親」が存在しないからだ。教化による信頼がすべての担保であり、その大前提が崩れる最悪の事態だった。
「あってはならないことだが、以前にも同じ事件が起きている」
「え」
「過去に一度だけ」
第一世代の培養組だったという。
「五年前のことだ。C班としての初仕事に臨み、隙を見て逃亡した」
「襲われたのでは」
「今回ならそれも考えられるが、当時はもっと荒っぽかった」
87たちは挟み撃ちにする計画で臨んだ。それぞれの追跡ルートを担当し、互いの動きを確認できる状態にはなかった。だからこそ87はパートナーの「失踪」に気づかないまま捕縛を決行するしかなくなったのだ。前回は、パートナーである外組をうしろから殴り、昏倒させたうえで逃亡したという。
「しかし、うやむやにされてしまった」
当時の校長は王盛。胡はC班の担任、黄と張は副担だったらしい。格闘技の授業を受け持つ周は、胡が校長に就いてから着任していた。
「失踪事件が起き、C班では密かに緊急会議が開かれた。胡は王校長に正確な情報を上げず、襲撃事件として内々に処理した」
今回も胡が関わっているという。現場にいた田から報告を受け、担任の黄は五年前の事件と関連づけられることを恐れた。迷わず胡校長に伝えたのだ。
「前回と今回では手口が違う。しかし、胡はまたしても同じように決着させた。遺体は未確認だが、暴漢に襲われて命を落としたと断定するのが妥当である。そう党に報告した。現場は市街地の外れに広がる下層エリアだ。見つかりにくい環境を逆手に取った」
会議の内容に不服だったのはそのせいか。しかし、臭いものに蓋をするなら日常茶飯事だ。不都合なことは黙殺する。隠す。なかったことにする。そんな結末が最優先されることは誰でも経験してきた。何を今更、という感が強い。
「おまえの生い立ちを読ませてもらった。民主派の親に育てられたそうだな」
張は決意表明のように声を低めた。
「わかる気がするよ。おまえは誰にも媚びない」
「両親には疑問を持っています。わたしを騙していたのですから」
「だから教わったことをすべて否定するというのか」
心の拠り所であり、松明そのものだった。ジレンマが美雨を苦しませている。
「おまえの感性も、理性も、思考様式も、すべて両親から受け継がれたものなんだよ」
一挙手一投足が観察されてきた。美雨が否定しようとしても、第三者から見れば明白なのだ。多勢と体制に逆らうことは条件反射だった。張が検分するように瞳を覗きこんだ。
「おまえだから頼みたい」
頼む? 教師からそんな言葉を聞いたことがなかった。
「出てきていいぞ」
張が倉庫に声を向けた。ガタっと音がして、鉄扉が開いた。現れたのは若い女性だった。
「第一世代の卒業生だ」
西口付近には監視カメラがあり、侵入させるのは骨だったと張が苦笑いした。職員室と校長室でモニタリングできるからだ。会議が終了し、教師たちがカフェテリアに集まった隙を突いたという。

美雨は顔を突き出して見詰めた。クローンはみな同じ顔をしているものだと思っていた。世代間で変化があるとしても、マイナーチェンジされる程度だろうと。
「驚くのも無理はない。世代毎にオリジナルは違うからな」
クローンは、研究者がみずから提供した細胞でつくられたという。第一世代を担当していた女史はかなりのクールビューティらしい。第三世代は深い栗毛だが、彼女は光を映す黒髪だ。うしろで束ね、いわゆる「お団子」にしている。象牙色のピンが壁のように白い肌も引き立てていた。顔立ちは細面。大陸系特有の釣り目が印象的だ。全体的に華奢だが、女性らしさを引き立てる部分は豊かだった。青さが抜け落ちた色香を感じる。
「いい手本になる大先輩だよ。おまえと同じ外組出身者だからね」
ナンバーは41。第一世代のため正式名称は1―41となる。美雨は3―22だ。
外組でありながら卒業資格を得た。培養組を蹴散らせるほど優れていたということだ。雰囲気も秀でている。こうして向かい合っていても、遠くに掲げられた絵画を見ているように息遣いを感じなかった。
「逃亡したのは1―30。彼女を殴って行方をくらませた」
パートナーとして組まされていた培養組だ。今回と同じ構図だった。
「当時、張先生は、いつか似た事件が起きるってほかの先生たちを説得したようだけど」
1―41が話を引き取った。
「でも無視された。教化プログラムに欠陥があると認めたくなかったのよ。どんな精巧な製品でも、必ず不良品は見つかるのに」
「培養組も同じだと」
「各世代にひとりくらい存在しても不思議ではないでしょう。でもプログラムを変更するほどの事態ではないと判断された。リコールするには代償が大きすぎるということ」
「19が逃亡した可能性が高いと考えられるのは、過去に1―30の件があったからだ」
張が「しかしながら」と苦い顔で続けた。
「もっと問題なのは、ふたつの事件が関わり合っている可能性だよ。1―30が手を貸したのかもしれない。逃げることができたのは1―30だけだからな」
「培養組の先輩として連絡を取り合っていたということですか?」
「そうなる」
「生徒には送受信できる手段がありませんよ」
「培養組が予行練習する場所は当時と同じだ。後輩と接触する機会を窺っていたのかもな」
「19は、突然現れた先輩に説得され、逃げることに決めたと?」
教化された生徒だ。考えにくい話ではないか。
「培養組は外の世界を知らない。自由を味わったことがない」
先輩の背中に翼を見つけたとしたら、単なる刺激では済まないだろうという。張は確信しているのだ。外組と違う環境で育てられてきた事実が災いしたと。
「1―30の居場所が掴めれば、19を探し出せるかもしれない」
「匿っている可能性がある、と」
張が頷いた。
「胡は党に報告せず、事実を握り潰した。それを証明するための決定的な情報が欲しい」

張は、内ポケットを手探りすると、細かく折られたペーパーを差し出した。走り書き程度の内容がプリントアウトされたものだ。
「ひと月ほどまえになる。C班の事務局宛にメールが入った」
ペーパーには住所とアパート名が記されている。
「1―30の隠れ家だというタレコミだ」
「事務局のアドレスを知っているってことは学園関係者ですよね。元職員とか」
「胡から指示を受けた我々以外に、1―30が逃亡したことを知る者はいない」
「わたしを覗いてね」1―41が自嘲した。
マイナスポイントは教師の匙加減でどうにでもなる。口外すれば簡単にベスト5から零れ落ちてしまう。同じような事件が起こるまでは、こうして張に呼び出されるまでは、存在しない記憶として扱ってきたという。
「送信元を追ってみたが、足跡は残っていない。もっとも、そんな初歩的なミスを犯すとは思えないがね」
「どうやって1―30の居場所を特定できたのでしょう」
「送り主に訊いてみる以外にないな。もっとも、具体性のある情報を、秘匿性の高い事務局のアドレスに送ってきたんだ。期待できると思う」
張が「ただ」と首を振った。
「わたしが直接出向くわけにはいかない。目立ちすぎる」
彼は体制派の教師からマークされている。フリーハンドで動くには無理があるだろう。
「だから君たちを呼んだ。なんとしても探ってもらいたい」
話の流れから予想はできた。しかし、疑念が根を張って動かない。
「1―30が逃げたとき、あなたは、どうして王校長に報告しなかったのです」
胡の言いなりになったのだ。それなら張自身にも責任がある。
「事件があきらかになればC班の権威が地に落ちる。胡の主張は、当時のわたしにはまともなものに聞こえた。ようやくここに赴任できたという自負があったし、別格の扱いを受けるC班に配属された。メンツが判断を狂わせたとしか言えない。いまはそれを恥じている。だからこそ同じ事件が起こったら解明してみせると誓ったんだ」
自分は手を汚さない。それが何より引っかかった。
「胡校長や取り巻きのことが気に入らないからでしょう? あの人たちを追い落として、自分にとっていい環境をつくりたいだけじゃないですか?」
「確かにわたしは、初代校長である王氏を恩師と崇めている。それは、かつてのような伸び伸びと学べる場所にもどしたいからだ。胡のやり方は間違っている。減点を重視した方式に特化し、規律をより厳格にした。学園創立当初は、両親への連絡が可能だったというのにね。不安定な生徒の心を和らげる効果があったし、両親への疑念も時間をかけて話し合うことで解消された。すべてが完璧だったとは言えないが、いまよりはマシだった」
方針が変更されてから、生徒は、より強いストレスに悩まされるようになった。王時代に立ち返らなければならない。そのための捜査だと張は強調する。
「外組にとっても悪い話じゃないないだろう?」
19が、培養組の一角が、じつは逃亡していたおそれがあると伝えられた。しかも過去にも酷似した事件が起こっていた。胡の指示により、C班ぐるみで隠ぺいした。C班の事務局宛に送られたタレコミは、張のように王氏を崇拝する者からもたらされたのか。
どうやって1―30の居場所を発見できたのかは不明だ。しかし、今回の事件が起こるまえから情報が送られていたという点は注目に値する。本ネタの可能性が高い。
ただ、飲み下せと言われたところで、すぐ頷けるはずがない。体制か反体制か。その二極的な争いに引き摺りこまれる。自動的に色がつく。依頼を受けた時点で、美雨は張の手足となって動かなければならなくなるのだ。1―41と話し合い、明日の朝までに答えを出せ。張はそう言って用具室をあとにした。王氏の時代がいかに恵まれていたのか。彼女を通じてひとつでも多く実話を聞き、意思決定の判断材料にしろという。
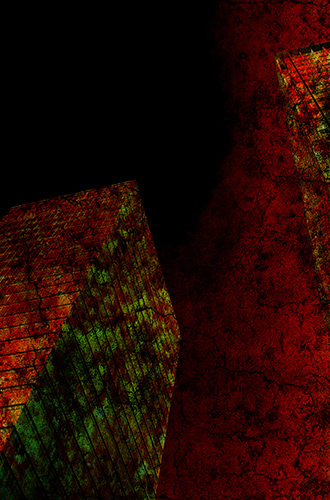
体制か反体制か。選ぶべきは反体制だと心が命じた。そもそも体制側につくという選択肢は存在していなかった。張が指摘していたように、美雨の魂には「反」に与すべきという信念が染みついている。階下に降りた。配給部の灯りは消えていて、昼間の喧騒が嘘のようだった。このまま寮の部屋へ行き、1―41から話を聞くつもりでいた。彼女は寝泊まりできる準備も整えてきたという。それほど張に入れこんでいる。いや、張の言い分に魅せられている。自分を卒業させてくれたかつての方針に郷愁を感じているのだ。
体制か反体制か。寮へ繋がる渡り廊下の手前で、美雨は足を止めた。西口の奥。配給部と対極の場所に医務室がある。自室へもどれる気力が残っていない者たちは、夜を待ち、寮が寝静まるのを待って医務室から出るらしい。
体制か反体制か。これまでも、それが問われる場面をいくつも経験してきた。高校二年の夏。美雨は、都市部の生徒も参加する競技ディベートに出場した。外資系企業がスポンサーになっていることもあって、参加者の半数以上がこの国で働く外国人の子供だった。ディベートに与えられたテーマは「史実への責務」である。
美雨は、政治利用されている「史実」を列挙し、欧米や日本の史学研究者がどう主張しているのかを提示した。この国で語られてきた歴史を史実だと疑わない生徒たちにとって、美雨の主張は売国奴の証明そのものだった。しかし、美雨を論破できる者はいなかった。決勝トーナメントで戦った論客でさえ、最後の最後には同じセリフで美雨を罵った。「被害者感情をなんだと思っている」。競技ディベートは、判明している事実と実証済みのデータのみを武器に、そこから積み上げられる主義主張で雌雄を決するという科学的な戦いである。感情云々を持ち出すのはルール違反であり、何よりナンセンスだった。
ひと口に外資系といっても、この国の政府に阿る企業ばかりではない。近年では通商問題で圧力をかけるために進出する企業が増える傾向にあった。そのうちの数社が共同主催者となり、未来志向で開明的な大会を開いた。ディベートの性格は結果に現れる。金色のトロフィーを手にしたのは美雨だった。
普通ならば反逆的だと断罪されても不思議ではない。しかし、美雨の身には何も起こらなかった。両親もいつもと同じように仕事ができた。といっても美雨は十七歳だった。この国で教わる歴史と違った解釈を論じても、それを公の場で披露しても、政治的な影響力はまだないと見なされた。あるいは、子供の大会に口を出して大人気ないと批判されればメンツが立たないと考えたのだろう。美雨は勝手にそう思っていた。いまなら無傷で済んだ理由もわかる。クローン計画が遂行中だったからだ。何があっても美雨を処罰するわけにはいかなかったのである。
ずっと日本かぶれだとバカにされてきた。何か主張すれば「あいつは、そうだから」と笑われた。一方で、美雨に味方する者も現れるようになった。似たようなディベートは何度か開かれ、美雨はいつも優秀な成績を収めた。そのたびに注目を集めた。やがて美雨を応援するグループと非難するグループが会場を二分するようになった。そんなファンのひとりに美雨のクラスメイトがいた。彼女は美雨をバカにする生徒から唾を吐きかけられた。それでも一番のファンを自称し、一歩も譲らなかったのだ。

美雨は徹底的に嫌われたが、イジメの対象ではなかった。退かなかったからだ。多勢であればあるほど理路整然とした攻撃に徹した。売国奴は見下されるが、信念を貫く者は畏れられる。美雨は敵視され、一目置かれた。
美雨を陥落できないクラスメイトは、ほかにイジメの対象を求めた。無理矢理にでも探さなければならなかった。首都を一望できるエリアに住んでいながら、都市民と同じ待遇を受けられない階級の生徒ばかりだ。嫌でも押しつけられる格差意識が生んだのは、誰かをイジメ抜くことで「階級」を一段でも上げるという歪な差別システムである。
対象になったのは複数名の生徒だった。彼らがへこたれないよう、日替わりでイジメるためだ。自殺者が出てもマスコミが注目することはなかった。いくら遺族が騒いだところで、口に札束を突っこめば事足りたからだ。
イジメられていた生徒にとって、美雨はヒロインに違いなかった。学校で負けなかっただけではない。党や政府でさえ彼女の口を塞げなかったのだから。一番のファンを自称したのは、イジメにあっていた女子生徒のひとりだ。言動だけでなく、歩き方や背格好まで似始めた。毒味をする従者のように、いつも目の届く場所にいた。美雨が攻撃されそうなときは、決まって歩み出た。美雨が戦うまえに相手にダメージを負わせるためだ。
みな、彼女のことを単なるファンだとは思わなくなった。分身として扱った。
そんなある日、事件が起きた。横殴りの雨が降った。やけに蒸し暑かった。美雨は夏風邪をこじらせ、学校を休むことにした。いつもなら美雨に合わせ、分身も休んだ。この日は違った。美雨のためにノートをとろうと出席したのだ。彼女の威を借りられず、イジメのターゲットにされることがわかっていながら。
案の定、苛烈なイジメを受けた。それでも晴れやかな気分で放課後を迎えた。美雨のためにノートをとれるのは自分だけ。ミッションを完全にやり終えたからだ。彼女の心情は、周りの目撃情報から窺える。分身は帰りしなに髪の毛を梳かし、服装の乱れを正し、颯爽と玄関へ向かったという。どうせ大雨に打たれるのに、と笑われても相手にしない。その三十分後に襲われた。滝のように雨が流れ落ちる土手の下で犯された。
美雨本人と間違われたのは確実だ。しかし、いくら格好を似せたとしても、犯人が気づかないとは思えない。それでも分身を凌辱し続けた。考えられるのは、気づいたからこそ手を緩めなかったのではないかということだ。美雨本人が相手なら、脅かすだけで意味がある。あそこまでやったのは、間違ったと思われてはメンツが立たないと考えたからだ。つまり目的を変更した。見せしめにしようと。
分身を襲い、しかも、本人を襲うよりも高い効果を上げるにはどうすればいいか。徹底的にやることだ。二度と真似ができないくらい執拗に。だからこそ辱められるだけでは終わらなかった。気を失っても許されなかった。
殺人犯は捕まっていない。おそらく捜査もおこなわれていない。公安としては、暴漢に勲章でも用意したい気分だったはずだ。美雨は体制に邪魔なサラブレッドであり、エースの卵だったのだから。何より、クローン計画が遂行中で手を出せない存在だった。

自分を真似れば敵を増やす。いつか報いが来ると伝えていた。しかし、彼女のことを本気で心配していたのなら怒鳴ったはずではないか。憧れを砕くような言葉を浴びせたはずだった。美雨はどちらも選ばなかった。
いつも敵に囲まれていた。自分はもちろん、両親までターゲットにされた。心を奮い立たせることで、彼らを論破することで、畏れを抱かせることで乗り越えた。しかし、いくら勝率を伸ばしても、一寸の理解も得られなかった。勝つほどに周りは自分を遠ざけ、忌み嫌った。そんなとき分身が現れた。煩わしさを覚える一方で、心地好さも味わった。自分に熱狂する者がいるという事実に酔った。彼女は自身を捨て、宋美雨になろうとしていた。それほどまでに入れこんだ。惚れこんだ。
登校時、分身は美雨の自宅付近で待つようになった。あの朝もそうだった。美雨が家から出てこなかったため、不審に思い、分身は宋家の呼び鈴を鳴らした。
美雨はリビングで横になっていて、彼女が来たことに気づいていた。が、顔を合わせようとしなかった。何も告げなかった。彼女が尽くすことを通じて、自分への想いが色褪せないことを実感できるからだった。
分身が美雨に憧れたのはほかでもない、多勢に屈せず、媚びず、貫いたからだ。その端緒を忘れ、美雨はいつしか誇れることを誇りにしていた。分身を利用したのだ。誇れるという甘美さを貪るために。
単独で行動したらイジメられる。美雨がいなければ滅多打ちにされかねない。やめたほうがいいと告げればよかった。教祖が命じれば、信者は飲み下したはずだ。ひとりで帰宅することもなければ、待ち伏せしていた暴漢に想像の限りを尽くされることもなかった。
彼女の悲運は、美雨がその気になればなんとかできた。
おかしくなったのは、あの事件があってからだ。美雨は自殺の真似事をしはじめた。重ねるごとに深刻化した。薬の量は増え、切り傷は深くなり、両親が見つけなければ窒息していた。それでも止めなかった。
自分が辱められることで、美雨の貞操と命を守ることができた。本望だった。そう言い切る分身の声を聴き取るためだった。あの世との境に行こうとした。分身が死んでからも、一途だった心を貪ろうとしていた。しかし、望んだ声は聞こえなかった。いくら黄泉の国に迫ってみても、囁きさえ聞こえてこなかった。
分身の死によって、美雨の責任を問う声が校内に広がった。こればかりは両親から学んだ持論も役に立たなかった。自室から出られなくなるまで時間はかからなかった。日に日に沈みこむ娘を案じ、両親は日本行きを提案した。自分を生かせる場所で、という言い訳は驚くほどの妙薬になった。この国の言葉から逃れ、父から教わってきた日本語を浴びて過ごす。想像するだけで気持ちが和らいだ。美雨は勉強を再開し、父親が舌を巻くほど日本語を上達させた。党の抵抗が懸念されたものの、渡航許可を含め、あからさまな妨害はなかった。次代のホープを海外に追い出せるからだと思っていたが違ったのだ。どのみち十八歳になれば「指定校」へ送られる。ならばいまのうちに夢を見させておこうとした。そのすべてが、外組の持ち帰る貴重な体験になるからだ。
目のまえで1―41が熱っぽく話していた。
小門から出入りしなければならないため、張のキーカードをコピーしたものを使うという。問題は、日が替われば認証が書き換えられてしまうことだ。捜査から帰るタイミングには特に気をつけるべきだと念を押す。捜査は夜間限定になり、体力的には厳しい。しかし、今回の事件で教師たちがパニックになっている。会議は長引く。
「しばらくは自習が続くでしょう。居眠りでもしない限り、減点にはならないわ」
そう告げると、王が校長だった頃の話を繰り返した。もう三度目だ。当時は両親と連絡を取ることが許された。それがどれだけ大きな意味を持っていたのかが強調された。最初の話で美雨が鋭く反応したのを見逃さなかったのだろう。
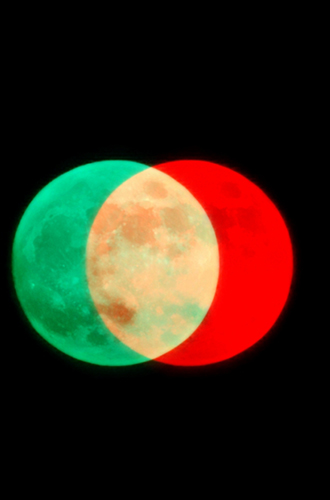
そう。王氏の時代なら64はどうだったか。美雨は唇を噛んだ。64が現れたとき、もっと早く気づかなければならなかったのだ。彼女も分身と同じだったのだと。現に自分は彼女をなんとかできた。街へ出るなと指摘できた。自分だけが運命を変えられた。それなのに何もしなかった。またしてもやり過ごした。
分身を救えなかったという思いがあった。だからこそ、自分には関わるな、と告げた。それで解決できると思った。しかし、過去から逃げていただけだった。張からの依頼は願ってもないことだ。分身が、あの世から与えてくれた機会だと思いたくなるほどの。
王氏の時代にリセットできるなら64を救えるかもしれない。
過去を清算したぶんだけ未来は変わる。そう信じたかった。
ライトを消したRV車とミニバン、スポーツワゴン車が並んで停められた。一本道の様子を確認できる空き地だが、雑木林に取り囲まれている。民家もなければ街灯もなく、鬱蒼とした枝葉が月明かりを遮っていた。身を隠すには絶好の場所だ。
教師の住まいは、学園から十キロほど北上した丘陵地の麓にある。この空き地はいわば中間地点で、いま住んでいるマンションの候補地として選ばれた場所のひとつだった。一部だけ林が切り拓かれているのは、そのときの調査の名残である。同僚の車が通り過ぎるのを待ち、ようやく三台のドアが開けられた。
「22が腹を決めた」
張は足元にある小枝を折らないよう気を配った。物音はひとつでも減らすのが鳩首凝議の決まり事だ。
「調査にはどれくらいかかりそうです」
語尾が昂ぶっている。A班教師の梁。三人のなかで一番若く、熱血漢である。
「自習が続いているあいだは負担も軽いだろうが、それ以上はね」
「会議しだいということですか」
「長引かせるつもりでいるが、こればかりはなんとも」
浮かない顔だったのはB班教師の林だ。いつもは黄以上に感情を表に出さないが、それが生徒用にカモフラージュされたものだということは張たちしか知らない。彼女の主張は強硬策路線から外れることがなかった。
「見通しが立たない捜査に期待するより、勝負に出たほうがいいんじゃない」
張は首を振った。「まだ早い」
「これだけ証拠があるのに」
林がポケットからメモリースティックを取り出した。映像、音声、写真。かき集めたテータのすべてが入っている。同じものを張と梁も保管してある。
「待つんだ」
それなりにデータは揃った。しかし、張には、彼らを仲間に引き入れた頭目としての責任がある。やるとすればC班内の「不正」を押さえてからだと思った。
「充分だと思うけど」
林も譲らない。
「第一世代の頃からやってる。自浄作用なんてあるわけないしさ」
B班の仕事は、党の要人たちに施す性接待だ。彼らはクローン計画の賛同者であり、重要なサポーターだ。少女たちの生育具合と教化の効果を直に味わってきた。B班の授業は彼らをどうもてなすかという点に特化され、入校まで性体験のなかった生徒は男性教諭が手合わせすることになる。
「一番深刻なのはウチですよ」梁が匙を投げるように言う。A班の仕事には毒物が欠かせない。パーティや会合にコンパニオンとして潜りこませ、ターゲットの飲食物に混入させる。党にとって目障りな人物はもちろん、指導部の批判勢力も対象だ。
「一度甘い汁を吸ってしまうと、もとにはもどれません」
この特殊な仕事を、能力を、教師たちが利活用してきたのだ。あくまでも個人的な目的で。A班の副担は、別れた夫の交際相手を狙った。以来、気に入らない人物が現れるたびに毒を盛る。B班の担任は自分用に性接待させた。アダルト動画マニアで、恋人に求められないプレイの数々を強要する。体制派の作業助手と事務局員も不正に加わる有様で、被害者はいずれも培養組の生徒だ。彼女たちの純粋さにつけこんだ蛮行である。教化されてきた彼女たちにとって、教壇側に立つ者からの求めや指示は絶対なのだ。
「あの子は信用できるの」林の懸念は、22の成績不振に向けられた。
「民主派の生徒は初めてだが、成績とは無関係に素質は充分だよ」
C班の不正は立証できずにいた。1―30の事件以来、一度もなかったからだ。
「いまの時点でA・B班の教師を告発するのは容易い。しかし、彼らが左遷されて幕引きということも考えられるだろう」
「そうなれば告発者もただでは済みませんよ」梁が身震いした。「胡に反抗的なのは誰でも知っていますから」
「今回は質が違う。揉み消しを指示したのは一介の教師ではない。現校長なのだ」
その胡を告発しようとしている。充分すぎるほどの準備が要る。
「でも、急がないといつ異動させられるかわからないわ」
「取り敢えずは残ったじゃないか。いまの世代を卒業させるまでは安心さ」
「第三世代を指導しているうちに、ってことですね」
「焦らず、報告を待とう」
林にも念を押した。
「成功すれば、王先生が再任する可能性だってある」
王は研究者で、クローン計画の中心人物だった。実績を買われ、学園建設を一任された。国内に散在している学園を統括する大役を担いつつ、ここの校長として計画の完成を目指すことになったのだ。しかし、第一世代の卒業に合わせるように異動させられた。指導部の交代が起こったからだ。
胡が校長に抜擢され、後日、王は政治局入りを果たした。論功行賞ではあるものの、期待された中央委員には選ばれなかった。なぜか解放軍のナンバー3に就かされた。軍人の遺伝子治療にかかわるチームのトップだというが、張たちには期待外れの人事である。王の方針が指導部に嫌われたという意見が大半だ。
胡の方針が不正塗れだと発覚すれば、現指導部の考え方も変わる。胡を選んだというメンツは潰れるが、明日の国の舵取りにかかわるメンツを思えば変えざるを得ない。小さなメンツはより大きなメンツの犠牲になるのがセオリーなのだから。
張は自身に言い聞かせた。潮時を待つのも行動のうちだ。
(第07回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『クローンスクール』は毎月15日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


