 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十八 『三四郎』第八章 二十円(下編)
e:愚弄したのですか?
原口と野々宮は茶を飲むために精養軒に出かけていく。美禰子と三四郎はまだ見ていない絵を見るために残る。原口は深見という画家の水彩画について、『実物を見る気にならないで、深見さんの気韻を見る気になって』見るようにとアドバイスする。
「ここでは、技巧的な油絵と、水墨画のように人の品性そのものを表す水彩画という対比があるんじゃないかな。『地味にかいてある』けど、『筆がちっとも滞っていな』くて『一気呵成に仕上げた趣がある』水彩画には、まさに東洋風の水墨画的な魂が通っているって、漱石は言いたかったように見えるね」
「前に見ていた兄妹の描いた油絵のベニスと、この水彩画のベニスが対比されてるってわけね」
三四郎が、さっき何をささやいたのかと聞くと、美禰子は、
『「野々宮さん。ね、ね」』
という。次いで、
『「わかったでしょう」』
という。
「美禰子は、ちゃんと種明かしをしているわけよね。けれども、無意識でわかっていることを意識で受け止めかねている三四郎は、現実を否認しちゃうのよね。わかることを拒んじゃう」
『「野々宮さんを愚弄したのですか」』
と三四郎は問うが、美禰子は
『「なんで?」』
と無邪気に答える。
「ここで、美禰子は三四郎が理解し損なったということを理解したわけだ。あるいは三四郎が美禰子の本当の気持ちに気づきたくないのだということに気づいたんだね。でまあ、ゲームにつきあうことにする」
「三四郎は、『美禰子が好きなのは、自分ではなく野々宮なのだ』という事実を拒んでるってことね。そこで、『野々宮を愚弄した美禰子はけしからん』と怒りを覚えるという形で逃げちゃうわけのよね」
「やっぱり母親に指摘されたとおり意気地がないんだな、三四郎は。現実に向き合う勇気がもてないんだよね」
f:雨宿りー「借りましょう」「みんな、お使いなさい」―
展示会場を出るときに、互いの肩が触れる。『男は急に汽車で乗り合わした女を思いだした。美禰子の肉に触れたところが、夢にうずくような心持ちが』する。
「また美禰子が汽車の女とつながったわね」
「池のほとりで出会ったときにも、三四郎は同じように汽車の女を思いだしているからね。厳然とそこにあり、自分が勇気をもって進めば手に入るかもしれない存在、肉を持った存在なのだけれど、三四郎にはその勇気がもてない。その誘惑を感じても、『夢にうずく』ようにしか感じられない」
「現実とはまだつながらないわけね」
「踏み出したいのに踏み出せない、第三の世界に入りたいのに入れない自分。実の所だれともまだしっかりつながっていない自分。そういう孤独感がこの後表現されるよね」
「雨宿りの場面ね」
「そう、展覧会を出ると雨が降っている。『「あの木の陰へはいりましょう」』と美禰子が言い、二人は大きな杉の木の下に入る。けれどもそれは、『雨を防ぐにはつごうのよくない木である』。それでも二人はぬれながら立っている。やがて雨が濃くなって、雫の落ちない場所が減り、二人は『だんだん一つ所へかたまって』いき『肩と肩とすれ合うくらいにして立ちすくんで』いることになる」
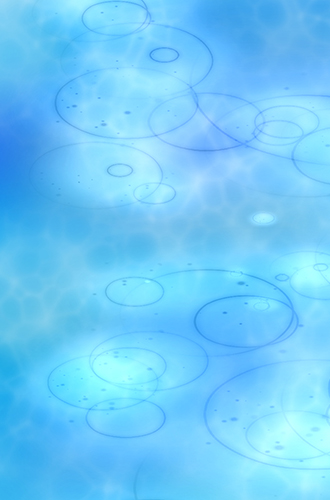
「もしかしたら、美禰子もまた、三四郎と同じく孤独なのかもしれないわね。兄が結婚することで、寄る辺を失うってことだけじゃないわ。技巧で男を引きつけるのももしかしたら、意図的なものじゃないのかもしれない。彼女、『「私、なぜだか、ああしたかったんですもの。野々宮さんに失礼するつもりじゃないんですけれども」』っていうでしょ。ほんとに、本能的にああいう気を引く行動をとってしまう自分がいるんじゃないかしら」
「生まれつき持っているコケットリーみたいなものだってことかな」
「そう。だから、意図せずして男を引きつける行動をとってしまうのだけれど、本当に引きつけたい人はなかなかなびいてくれない。三四郎のような、本命でない者だけがそばにいてくれる。そういう孤独感もあるんじゃないかしら」
「世界に見捨てられたように、激しく降る雨にぬれながら肩を寄せ合う孤独な二人っていうわけだね」
「だから、現実では決して男女としてつながれないことがわかっている美禰子は、せめてお金を介して、三四郎とつながろうとしたんじゃないかしら。『「さっきのお金をお使いなさい」』って三四郎に言うでしょ」
「三四郎は『「借りましょう」』っていうけど、美禰子は重ねて『「みんな、お使いなさい」』っていうものね。三四郎の側は借用のつもりでいるけど、美禰子は贈与のつもりでいるってことだよね」
「美禰子にしてみれば、ここまで引きつけてしまったことへのせめてものお詫びという意味があったのかもしれないわね」
「三四郎には伝わってないけどね、当然」
というわけで、おさらいの時間です。
与次郎が借りたまま返さない金を、美彌子が貸すと言っていると与次郎から三四郎は告げられる。それで、期待して向かった三四郎だが、プライドが邪魔して素直に借りると言えない。結局美彌子の機転で借りる形になる。美彌子に誘われて三四郎は美術展に行くが、そこで野々宮の姿を認めた美彌子は、野々宮の嫉妬を誘うように三四郎との親密さをアピールするふりをする。そのことを、三四郎は野々宮を愚弄したと怒る。会場を出た二人は、雨宿りをする。降りしきる雨の中肩を寄せ合いながら、美彌子は「なぜだか、ああしたかった」のだと言い、貸したお金をすべてお使いなさいと告げる。

「でまあ、ここで気づいたんだけどさ」
高満寺が得意げに言った。
「え、何に?」
「ほら、今回の殺人って、お金がらみじゃないってことよ」
「ああ、恭助を殺しても一文の得にもならないってこと?」
「そうね。だから、動機はきっと他にあるのよね。怨恨とか、嫉妬とか、もっとドロドロした感じの奴よ、たぶん」
「どうだろうな。直接お金を取るとかじゃなくても、資本主義とのつながりはあるような気がするんだけど」
「え、ってことは与次郎?」
「いや、まさか。だって、彼こそ動機がなさすぎるでしょ」
などと議論していたところ、またしても俺が腰に下げている通信機がぴろりろぴろりろ言い始めた。
「おいおい、いい加減にしてほしいなあ」
「いいから、出なさいよ。緊急事態なのよ、間違いないわ」
それはわかっている。わかっているけど、このタイミングでまたしてもか、との思いはぬぐえない。こっちは、社運をかけた大事件と格闘中なのだ。
「はい、今度はなんですか?」
「悪いわね。時間は取らせないわ。ちょっと厄介なことになってるのよ、助けてくれない」
わお、セクシーヴォイス。これは間違いなく「管理局に咲いた仇花」として名高い香本綾嬢に違いない。茶色の制服を着た、生真面目人間の群れの中に、あの美女が、同じく茶色い制服に包まれて埋もれている。いや、きっとこのまま埋もれてしまう。だって、彼女はどうやら、この仕事を愛しているらしいから。
まあ、いずれにせよ、この声いやされるわあ。なんせなあ、とちらりと隣の筋肉(ウー)マンを見やる俺であった。
「何?」
俺の目線を察した高満寺が、ガンを付けてくる不良のような口調で聞いてきた。
「あ、いえ、何でもございません」
「ね、お願いよ。一刻を争うの」
「そりゃあそうでしょうね。こんな連絡が入るんだから」
〝一刻を争うの。いますぐ私に会いに来て!〟だったらいいんだけど、まったくそういう方向ではない。
「いいかしら、今からすぐにワープしてもらうけど」
「今度はどこですか?」
終わったら、デートおねがいしま~す、とも言えないが。
「鴎外の『高瀬舟』よ」
「でも、あれって二人乗りの舟でしょ。俺たちが行っても乗れないんじゃないですか。しかも、俺の相棒は見ての通りの巨漢ですよ。一人だけでもあんな舟沈んじゃいそうなんですけど」
「いいえ、乗らなくていいのよ」
『高瀬舟』といえば、中高生の読書感想文のド定番。安楽死の問題を巡って若者に考えさせる絶好の素材とされている。遠島、つまりは島流しを申し渡された罪人を運ぶ舟の船頭庄兵衛と、弟殺しの咎をしょった喜助との対話が主な内容である。島流しになる罪人は通例みな『目も当てられぬ気の毒な様子』をしているものなのに、喜助は『いかにも楽しそうで(・・・)口笛を吹き始めるとか、鼻歌を歌い出すとかしそうに思われ』るほど、はればれとした表情をしている。

それを不思議に思った庄兵衛が話を聞くうちに、病に苦しむ弟が自殺を図ったのを幇助したという事実が明るみに出るという物語である。ただ、この物語では、安楽死を肯定も否定もせず、読者に判断をゆだねる形を取っている。
「なんです? 喜助がほんとはサイコパスだったとかそういう改変ですか?」
「いや、そうじゃないの」
管理局からの癒しの響きは、さらにセクシーな波長を伴いながら俺の鼓膜を愛撫してきた。
「だって、喜助、いまは高瀬舟に乗ってないんですもの」
「え、乗ってない?」
「そうなの。安楽死が成立しなかったの。行けばわかるわ。すぐ、京都北山にある喜助の掘立て小屋に向かって!」
「わかりました」
「ありがとう。今度きっとお礼はするから」
えっ、ほんと! やるやる、いくいく、なんでもしちゃう! ってな感じのはしたない俺であった。お礼ってなんだろう。デートとか? お茶とかでもいいけど。その辺から始めませんか? ってな感じで一人盛り上がってしまったが、気が付けば掘立て小屋の前に立っていた。
喜助はまだ西陣の織屋で働いている時分と見えた。
「ちょいと失礼しますよ」
俺はそおっと小屋の中に踏み入った。喜助の弟がまだ剃刀を喉に当てていないことを祈りながら。
そして驚愕した。
「ジャック・キヴォーキアン先生考案、タナトロンをお送りします」
そんな垂れ幕が小屋の壁に垂れ下がっていた。
そして、喜助の弟と思しき人物が、腕に点滴装置を付けたまま安らかな顔で横たわっていた。
ジャック・キヴォーキアンは百三十人もの患者を安楽死させ、死の医師と呼ばれたアメリカ人である。彼が発明した自殺装置のひとつがタナトロンで、点滴によって注ぎ込まれたチオペンタールで昏睡状態に陥った後に、塩化カリウムが点滴される仕組みになっており、これによって患者は眠ったまま心臓発作で死を迎えることができるというものである。
「なんてこと」
それでも俺は躊躇せざるをえなかった。小説内の人物とはいえ、いまこの人は安楽に死を迎えようとしている。それを俺が止めていいのか? 不治の病に苦しむこの人には安楽に死ぬ権利があるのではないだろうか? そんな、読書感想文を書いている中高生が取り組んでいる課題そのものが、俺をも直撃した。
「悪いけど」
最終的に俺は職務を優先し、喜助の弟の腕から点滴の針を抜いた。おそらくはチオペンタールで眠ったままの弟を残して、俺は装置と垂れ幕を抱えてその場から逃げるように立ち去った。
「ありがと」
管理局に装置と垂れ幕を持ち帰ったところ、香本綾嬢が駆け寄ってきてくれた。彼女の髪の毛から発散される芳香が鼻を打つ。それでも、俺の心は晴れなかった。
「あ、御厨君落ち込んでる!」
香本綾が、心配そうに俺の顔を覗き込んだ。
「まあ、わかるけどね。あんたも、喜助の気持ちがわかった、ってわけだ」
「っていうよりむしろ、弟君の気持ちを思って切なかった」
ほんと、こういう仕事は疲れるわ、そう思いながら本務に復帰した。それでも、ワープする途中で、俺は気持ちを切り替えた。とりあえずは目の前の仕事に集中だ。と思った矢先、大変なことに気が付いた。しまった。香本綾嬢をデートに誘うの忘れてた。
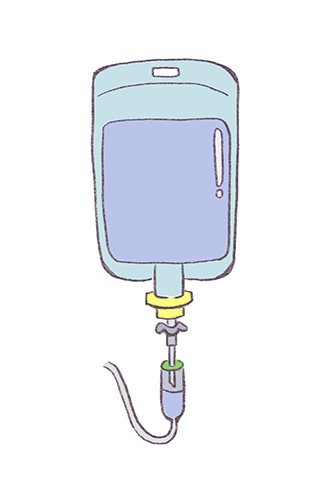
(第30回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月13日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


