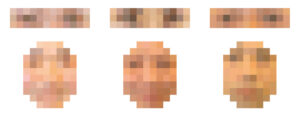 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十九 『三四郎』第九章 「君、あの女を愛しているんだろう」(前編)
a:晩餐会―物理現象と人間現象―
先だって原口が広田先生を誘いに訪れた精養軒の会の日がやってくる。例の、『文芸上有益な談話を交換する晩餐会』のことである。影の仕掛け人である与次郎に勧められて、三四郎も出席する。
「このとき、三四郎はお光さんを身にまとうのよね」
「うん、お光さんのおっかさんが布を織って、お光さんが縫いあげた羽織のことだよね。
つまり、熊本で自分への嫁入りを待望している女の家で作られたものだ」
「ここでも与次郎が、そそのかすのよね」
「確かに。三四郎はあまり気に入ってなかったんだけど、着なければ自分が持って行くと与次郎にいわれて着る。日頃はお光さんをあまり意識しているわけではない。そのくせ、自分の所有物のひとつとしては、というよりむしろ領土の一部としては認識しているって感じなんだろうね。だから与次郎にはやらん、というわけだ。そして『着てみると悪くはない』と感じる。つまり、熊本に帰ってお光さんと結婚するのも悪くはないという無意識の気づきがここであったことになるよね」
「しかも与次郎に『「その羽織はなかなかりっぱだ。よく似合う」』とだめ押しまでされちゃう感じだものね。美彌子より、お光さんとの方がしっくり来るよと、言われているようなものよね」
晩餐会では、声の大きな原口が野々宮に話しかけたことをきっかけとして、話題の中心ができる。最初、話題の中心となるのは光線の圧力である。
野々宮は、『雲母か何かで、十六武蔵ぐらいのおおきさの薄い円盤を作って、水晶の糸で釣るして、真空のうちに置いて、この円盤の面へ弧光燈の光を直角にあてると、この円盤が光に押されて動く』と説明する。(ちなみに十六武蔵というのは、江戸時代から明治時代にかけて流行ったボードゲームのことである。インターネット普及後オンラインゲームのひとつとして復活し、誰でも遊ぶことができるようになった)。
これに対して広田が、物理学者は自然派ではないという話を始める。
「自然を観察するだけでは、光線の圧力は試験できないっていう意味だよね。『人工的に、水晶の糸だの、真空だの、雲母だのという装置をして、その圧力が物理学者の目に見えるように仕掛ける』わけだから、自然派じゃないっていうわけだ」

「『光線と、光線を受けるものとを、普通の自然界においては見出せないような位置関係に置くところがまったく浪漫派じゃないか』というわけで、自然派じゃなくて、浪漫派になっちゃうのよね」
「すると、野々宮が、『いったんそういう位置関係に置いた以上は、光線固有の圧力を観察するだけだから、それからあとは自然派でしょう』と返し、別の人物が『「すると、物理学者は浪漫的自然派ですね」』と、文学でいうイプセンとの類比を持ち出す」
かくして、科学談義が文学談義へと移り変わっていく。
広田が『「ある状況のもとに、ある人間が、どんな所作をしても自然だということになりますね」』と、物理現象と人間行動との違いを指摘する。つまり、『ある状況の下に置かれた人間は、反対の方向に働きうる能力と権力を有している』ということだ。
「要するに、自然現象と違って、人間はきまった法則にしたがっては動かない。ある状況に対して、どんな行動もあり得るから予測はつかないということだね」
「人間現象は、物理現象ではないっていうことね」
b:あの女を愛しているんだろう
帰り道で与次郎が、借金を返さない言い訳をする。その中の一つのエピソードは、こんな内容である。
知人の男が、失恋の結果自殺しようと短銃を購入した。
↓
そこへ友人が金を借りにきた。
↓
金がないので代わりに短銃を貸し、友人はそれを質に入れることで一時をしのぐことができた。
↓
やがて、友人がなんとかなり、短銃を受け出してきたころには、知人はもう死ぬ気がなくなっていた、というものである。

「これに続けて与次郎は、『「おれが金を返さなければこそ、君が美禰子さんからお金を借りることができたんだろう」』と、奇妙な理屈をいう」
「借りておいて、恩に着せてるみたいだけど、一面の真実ではあるわね」
「与次郎のエピソードでは、金と短銃が交換され、その結果として貸し主は救われる。そして今回は、金と美禰子が交換され、その結果として三四郎が幸せを感じる、という類比があるってことかな」
「恩に着せる前振りとしては巧妙よね。それに続けて、与次郎は『「それでたくさんじゃないか。――君、あの女を愛しているんだろう」』というわけだもの」
「もしかしたら、田舎者の三四郎の行動から、三四郎の気持ちは周り中にバレバレなのかもしれないな。気づいているのは与次郎だけじゃないのかもしれない」
「しかも、三四郎はそのお金を実際すでにほぼ使ってしまってる。二十円は家賃、残る十円からその夜の会費を与次郎の分まで払ったために、すでに二、三円しか残っていない」
「さらにその残ったお金で、三四郎は白シャツを買う気でいる」
「この辺が三四郎のぼんぼん気質なんだろうね。借りた金でも頓着なく使ってしまえるわけだから」
「平気でおごられる与次郎も与次郎だけどね。だってその夜の会合に無理矢理三四郎を誘ったのはそもそも与次郎だったわけでしょ」
「都会っ子にうまく利用されているってわけだよね。与次郎にはすべてお見通しっていうわけだ」
「でまあ、借りた三十円を使ってしまって、それを結局は熊本の母に平気で無心してしまうところが、三四郎のどうしようもないぼんぼん性を顕わにしているわよね」
「で、心配したお母さんは、そのお金を監督者としての野々宮に送ったと知らせてくるわけだ」
「当時の三十円といえば大金だからね」
「与次郎は、返す必要なんかないというわよね。むしろいつまでも借りて置いた方が『「向こうでは喜ぶよ」』とまでいう。そして、『「人間はね、自分が困らない程度内で、なるべく人に親切がしてみたいものだ」』からだと説明するのよね」
「選科生で、広田の家に居候しているということは、与次郎の家庭が裕福ではないことを示している。貧しい家の出である与次郎は、資本主義の矛盾を感じている可能性もあるよね。だから、金持ちから金を取るのは当然のことだというアナーキスト的な発想が根底にあるのかもしれない。」
「社会的立場はともかくとして、死んだ親のおかげ、あるいは実業界か政界にいる兄恭助のおかげで、美彌子は経済的にはアッパークラスなわけよね」
「与次郎はよくわかっている。ある意味人が見えているんだね。だから、階級差という意味でも、美禰子よりもむしろ、よし子といっしょになることを三四郎に勧める。『あれならいい、あれならいい、と二度ほど繰り返』すくらいだ。階級差の問題だけじゃなくて、美禰子が三四郎の手に余る存在であること、三四郎にとってほんとうに安心していられるのは、母親と同位相にあるよし子であることが、与次郎にはよくわかっているわけだ」
c:ヘリオトロープ
その日の夕方、三四郎は野々宮のところへ行く途中で、シャツを買いに大きな唐物屋に入る。和装と洋装が共存していた時代だから、二種類の服が必要だったわけだ。制服を着るときは、どうしてもその下にシャツを着る必要があるわけで、制服は洋装の一種だったことになる。
ところがそこで、香水を買いに着た美禰子とよし子に偶然出くわす。結局三四郎は二人に選んでもらったシャツを買う。美禰子に借りた金の残りで買うのである。代わりに、香水の相談を受けて、ヘリオトロープという香水を適当に勧める。二人があっさりそれに決めてしまった為に、三四郎は一種の罪悪感すら感じる。
「香水の文化ってのも、明治から始まるわけだよね。それまでは、ずうっといわゆるお香の文化だったわけだから」

「ヘリオトロープは日本に初めて輸入された香水みたいね。元々は植物からの精製物を使ってたけど、ヘリオトロピンっていう有機化合物が同じ匂いを持つことがわかって、一般に普及したらしいわ」
「ってことは、この香水も合成物だった可能性が高いわけだね」
「つまり、紛い物、偽りのものってことかしら」
「二人の真正の恋にはいたらぬ関係を表すものとしてはもってこいじゃないか」
「香水、つまりかぐわしい匂いといえば・・・」
またまたあ。この大事な時に高満寺が、にやにや思いだし笑いをし始めた。やめてくれよ、それ、思い出しちゃまずいんちゃうの? 恐れ多くも日本文学の中心に位置している漱石文学のただなかで、あの事件を思い出すこと自体が冒涜であるような、そんな気がしつつ、俺もやっぱり思い出して、思わず鼻をつまんでしまうのだった。
「『好色』改変事件か」
「そうね。犯人は「変態仮面」を名乗る侵入者だったわね」
「あれにはまいったな」
「思い出しちゃった? あの匂い」
「おいおい、やめてくれよもう」
芥川龍之介の『好色』は、『今昔物語』の逸話を下敷きにしたもので、かなり際どいテーマを扱っている。間違っても中学の教科書には載らないタイプの小説である。色好みのプレイボーイ平貞文、通称平中が『何だかかう水際立った、震ひつきたいやうな風をしている』侍従を手に入れようとするが、ことごとく彼女の機知によって交わされてしまう。たとえば、『せめては唯見つとばかりの、二文字だに見せ給へ』(せめて、わたしの手紙を見た=読んだという二文字だけでもいいから返事をください)と手紙に書いたところ、彼の手紙を切り取って「見つ」の部分だけ送り返してくるといった有様であった。思いがかなわぬのであれば、彼女を忘れるしかないと思った平中は、『「だがその姿を忘れるには、―たった一つしか手段はない。それは何でもあの女の浅間しい所を見つける事だ』と考える。そして、女の童を襲って、侍従の糞が入った筐を奪う。さらには、その筐を開けて中身を見る。『薄い香色の水がたっぷり半分程はひった中に、これは濃い香色の物が、二つ、三つそこへ沈んでいる』。けれども、それは丁子の匂いを発するかぐわしいものである。不思議に思った平中は、ついには『そっと水を啜って』みさえする。そして、それが丁子を煮出したものであり、濃い香色の物も平中のたくらみを破るために侍従が作らせた香細工の糞であったことに気づき、『「侍従! お前は平中を殺したぞ!』と呻いて死んでしまう、という物語である。
「まあ、元の物語からして、かなりぶっ飛んだ変態色の濃いものなのよね」
「そうだね、中学生なんかが喜びそうなネタだよね」
「でも、「変態仮面」は、その糞をリアルなものに置き換えたわけよね。つまり、完全なるスカトロ物語に変えてしまった。その糞を噛み、それが入っていた汁を呑む平中をスカトロジストに変えて、彼の死を喜悦の死に変えてしまった」
「うへえっ。あの修復に行った時にあたりに漂ってた匂い、また思い出しちゃったよ。もう勘弁、その話は勘弁。どうか丁子でも、ヘリオトロープでもいいから嗅がせてくれ、俺の鼻の嫌な記憶を上書きさせてくれっ」
まあ、この仕事もいろいろあるって、わかってもらえたことと思う。文字体験がリアルな現実体験になるこの装置にも、若干問題点があるとすれば、こういう場合だというわけだ。ああ、あと、リアルな交通事故とか殺人現場の描写もきついけどね。
まあその辺は、「R指定描写回避登録」をしておけば、なんとなくぼやかされて通過することができるからご安心を! そうだね、昔の映像で言えばボカシとかいれる感じ、あるいはモザイクをかける感じになるから、登録した読者は、その部分をリアルに体験せずに通過できるっていう仕組みなのである。もちろん「チャイルドロック」ってのもあって、いまでは子どもがアクセスできる作品はかなり限定されてるのも事実だ。
というわけで、いやな、ほんとに余計な回り道をしてしまった。後悔先に立たずとはまさにこのことだ。次に高満寺が、いたずらな笑みを浮かべても、もう絶対同調したりしないと決めた。うん、いま、決めた! というわけで、さあ、仕事仕事。
(第31回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月13日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


