 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十八 『三四郎』第八章 二十円(中編)
c:貸借関係という絆
美禰子は光る絹を来て、端然と座る。笑みを帯びて自分を見る美禰子に、三四郎は『甘い苦しみ』を感じる。
三四郎が金は借りても借りなくても大丈夫だというと、『美禰子は急に冷淡に』なる。三四郎は借りておけばよかったと後悔するが、『自分から進んで、ひとのきげんをとったことのない男』である三四郎には、取り繕いようがない。美禰子もまた、自分から近づいてきてくれはしない。
「金を貸すということで、優位に立てることが、美禰子に余裕を与えていたってことかな」
「三四郎も、三四郎で、ほんとに融通の利かないぼんぼんよね」
「でも、結果的には美禰子の側が譲歩してくれる形になるんだよね。三四郎は、そういうかたちでしか人との関係を結べないんだな」
美禰子が出かけるといい、三四郎が同行することになる。出がけに、美禰子が『三四郎の耳のそばへ口を持ってきて、「おこってらっしゃるの」とささや』く。
「この辺がなんか、美禰子のツンデレな感じだよね。突き放しておいて、ふいっと近づいてくる感じ。三四郎が翻弄されるわけだ。まあ、出かける美禰子に同行するといったことが、三四郎なりの譲歩だったのかもしれないけどね」
美禰子と歩きながら三四郎は、『だれの許可も経ずに、自分といっしょに、往来を歩く』美禰子について、親がおらず放任主義の兄のもとでわがままに育ったからだろうと推測し、『これがいなかであったらさぞ困ることだろう』と考える。
「つまり、まだまだ女性は男性中心的な家庭の従属物だったっていうことだよね。未婚の身でありながら、自分の意志で、同じく未婚の男性と往来を平気で歩くというのは、当時の価値観からはあり得ないことだった」
「イプセン流って与次郎が評したのはそういうところよね。西洋風の自立した女性を演じてる、あるいはそうでありたいと願っているってことよね」

「万事が西洋風ってことだよね。英語しかり、キリスト教しかり、広田や野々宮と互角に話ができる知性しかり、サンドイッチしかりって感じだよね」
「でも『腹の底の思想まで』イプセン流なのかどうか、三四郎ははかりかねているわね」
「そう。結末を見ればわかるように、やはり心の底にはあきらめがある。明治の日本の世の習いには逆らえないという諦念がある。でも、そのときがくるまでは、せいぜい自分らしく生きたいという切ない感じもあるわけだよね」
「そういう自分を見せる=そういう自分で魅せる相手として三四郎は選ばれたともいえるわね」
「うん、田舎出の純朴でありつつ、エリート意識の虜でもある三四郎は恰好の餌食だよね」
二人はいっしょに歩いているのに、お互い相手がどこへ行こうとしているのか知らない。
『「どこへいらっしゃるの」
「あなたはどこへ行くんです」』
という滑稽な会話が交わされ、美禰子が思わず笑ってしまう。
「美禰子は、三四郎がすっかり自分の虜だってことを確認できたわけよね。だから、余裕が生まれた。三四郎をかわいいと思ったのかもしれない」
「がむしゃらに美禰子についてきてるわけだからね、三四郎ときたら」
「だから、自分の優位を確認できた美禰子はお金を貸すことにするのよね。関係性をより一層明確にするために」
「少なくとも、お金を貸している間は、資本主義社会だから、美禰子が優位に立つわけだからね」
「驚いたことに、この時代に美禰子は自分名義の通帳を持っているのよね。家長の許しなしに、自分の裁量で使えるお金を持っている。それも三十円貸したところで大して痛まないほどの額が入っていると推測できるものを」
「でも、女である自分が卸しに行くことはできない。それが、当時の社会の風潮だったんだろうね。だから、三四郎に代わりに行かせるわけだ。それも貸すためとはいっさい言わない。自分のためにおろしてきてほしいというニュアンスで伝える」
「頭がいいわよね。卸したお金は当然三四郎がもっているわけで、『預かっておいてちょうだい』のひとことで、押しつけがましくなく貸すかたちになってしまうわけだから」
「三四郎の方でも、借りたという意識なく借りることができるからね。彼のプライドの壁なんか、とっくにお見通しってわけだよね」
d:高等モデル
三四郎がお金を卸して戻ってくると、美禰子は丹青会の展覧会の招待券を見せ、一緒にいこうと誘う。原口からもらったのかと聞くと、そうだと答え、絵のモデルをしているのかと問われると、『「ええ、高等モデルなの」』と答える。
「これは、当時話題になっていた高等遊民にかけたものだよね。『三四郎』の中にも出てくるけど、当時は就職難ということもあって、高等教育を受けた後、就職しないで、読書などをして優雅に過ごす若者が多くいたらしい。石川啄木も親の財産で暮らしてて、自分のことを遊民って言っていたからね」
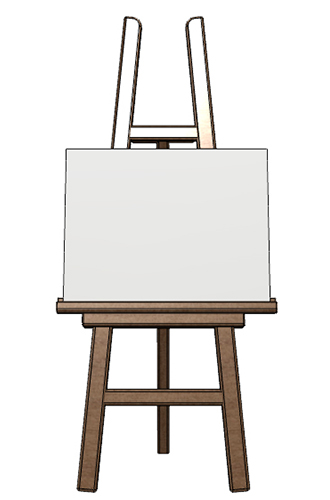
「美禰子も高等教育を受けたけれども、裕福な家庭で特に働くこともなく不自由なく暮らし、気まぐれにモデルなどやっている。その状態をうまく表現した冗句ってわけね」
「さりげなく、高等っていう自負も付け加えるのを忘れてないしね。自分は決して三四郎たち本郷文化圏の人間に劣ってはいないのだということを言わずにはおれないんだよね、美禰子っていう人は」
「あと、黒田清輝の『朝妝』事件の記憶ともつながってるのかもしれないわよね」
「ああ、フランス人女性が裸で鏡の前に立って髪の毛を束ねてる絵だよね。明治二十八年に京都での展覧会に出品された西洋画で初めての裸体画だよね。猥褻論争が巻き起こったやつ」
「つまり、自分は、裸になるようなモデルじゃないっていう意味での高等モデルよっていう意味もあるように思うわ」
「なるほど、洒落た冗句だよね。言葉の使い方がうまい。でも、冗談なんか思いつくセンスのない三四郎は黙ってしまう。美禰子の方では、うまい返しとか、賞賛とかを期待してたんだろうけど、こういうとき、三四郎はすぐ黙っちゃうのよね。その辺が自分からぼろを出せない、自分に自信がない男の典型的な姿なのよね」
「傍目には寡黙な男と映るけど、実際には機転も効かないわ、気は小さい弱い男だわって、形無しなんだよな」
展覧会に向かう途中でも、未婚の若い二人の男女が連れだって歩く様が、学生たちの敵意の視線を浴びる。『学生が多く通る。すれ違う時にきっと二人を見る。なかには遠くから目をつけて来る者もある』とある。いかに、この二人連れが、当時の世相から見て異様であったかがわかる。
「わたし、にらまれる感じを直に感じたわ」
「うん、すごい敵意だよね。道徳とか常識をかさにきた怒りであり、嫉妬であり、憎しみだ。三四郎はそれを感じてるけど、たぶん美禰子は確信犯だから、それを自分への賞賛くらいにとらえてたんじゃないだろうか」
e:展覧会場―「似合うでしょう」―
展覧会場で、三四郎は己の無能力をさらけ出す。『油絵と水彩画の区別が判然と映ずる』程度にしか絵がわからず、『巧拙はまったくわからない』三四郎である。
「ここで、絵を見ている三四郎を、美禰子が離れたところから見る場面があるわよね。『先へ抜けた女は、この時振り返った。三四郎は自分の方を見ていない。女は先へ行く足をぴたりと留めた。向こうから三四郎の横顔を熟視していた』って。これって」
「うん、意味深な視線だよね。これまで熟視するのはいつだって三四郎の側であって、美禰子は見られる側だった。ここで初めて美禰子が三四郎をガン見しているわけだよね」
「それなりに心動かされていたってことかしらね」
「恋愛感情に近いものはあったかもしれない。ただし、ペットに向けられる視線のようなもので、そこにはどうしても主従関係みたいなものが含まれているような気がするけどね」
そこに声がかかって、美禰子を我に返らせる。声をかけたのは原口で、その後ろにいるのは野々宮である。『原口より遠くの野々宮を見』た美彌子は、すかさず、あともどりをして三四郎の近くに行く。
「ここでの行動はさすがだよね」
「野々宮の存在を認めた途端、三四郎は疑似的な恋愛の対象から、野々宮という本命をターゲットとした小道具と化すわけよね」

「そう、三四郎はただただ利用されるだけだ。三四郎に近づいた美禰子は『人に目立たぬくらいに、自分の口を三四郎の耳へ近寄せた。そうして何かささやいた。三四郎には何を言ったのか、少しもわからない』それで、三四郎が聞き直そうとすると、美禰子はもう原口と野々宮の方へ去ってしまっている」
「見事な演出よね、周りにはほとんど目立たぬよう気配りをしつつ、野々宮にはきちんと二人の親密さをアピールし、同時に三四郎には実のところ何も告げてはいないわけだから。野々宮の気を引くためだけのこの演技を、瞬時に行ってしまえる美禰子はやはりすごいと思うな」
「実際、野々宮は刺激されてるよね。三四郎に向かって『「妙な連れときましたね」』と声をかけるのは、『どうしてお前が美禰子と二人きりで来てるんだ?』っていう意味だよね」
「そこへすかさず美禰子が第二弾を打ち込む。『「似合うでしょう」』っていう言葉で。野々宮は言葉を失って、後ろを向いてしまう。効果覿面ってわけね。そういう意味で美禰子は、人心操作の達人でもあるわね。自分の見せ方も心得ているし、なかなか憎い奴だと思うわ」
原口は、ベラスケスの描いた肖像画の模写をさして、ここに美禰子の肖像画を飾る予定だという。畳一枚ほどもある大きな絵のある特等席である。
「その模写のことを原口はできがよくないという。その理由として、『「どうも、原画が技巧の極点に達した人のものだから、うまくいかないね」』と表現する。これって、美禰子のことを言ってるわけだよね」
「技巧の極致に達した女性美禰子を、自分が不出来な模写をしてここに飾る予定だという意味かしら」
「うん、さすがに画家として人を見てきた原口には、美禰子の正体が見えているのかもしれないね」
(第29回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月13日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


