 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十七章 『三四郎』第七章 広田先生
a:田のなかを流れる小川―与次郎―
広田先生は、夕食後、机に向かって筆で紙になにか書いている。与次郎を訪ねてきた三四郎が声をかける。『先生は顔をうしろへねじ向けた。髭の影が不明瞭にもじゃもじゃしている』。
「その気配が『写真版で見ただれかの肖像に似ている』ってことは、まあ、それなりに様になる姿だったってことかな」
「でも、誰とも定まらないのよね」
「誰にも似ていないオリジナリティがあるということだ、ともいえるかもな」
「考えてみると、明治時代って、ようやく電化されたといっても、まだラジオもテレビもなかったのよね。だから、食後もだらだらバラエティとかプロ野球とか見たりせず、すぐに勉強したり読書したりできたのね」
「それしか、する事がなかったともいえるけど」
話題は与次郎のことになる。時々ふらりといなくなるという与次郎を三四郎が気楽でいいというと、広田は『与次郎のは、気楽なのじゃない。気が移る』のだという。それを田のなかを流れる小川に比して、『浅くて狭い。しかし水だけはしじゅう変わっている。だから、する事が、ちっとも締まりがない』という。それを聞いて、三四郎は先日用立ててやった二十円を、与次郎が返してくれるかどうか不安になる。多少弁護するつもりで、彼なりに先生のために尽力していると三四郎は口にするが、それはどんな尽力かと問われて困る。「偉大なる暗闇」関係のことは口止めされているせいである。そこで三四郎は話を逸らす。
b:優美な露悪家
三四郎が広田の元を訪れるのには三つの理由がある。
その一は、広田の普通ではない生活ぶりに関心を持っているからであり、二つ目は、彼といると気が楽になるからである。野々宮には大いなる功名心のために禁欲する気配があり、自分も居住まいを正さねばと言う気になるが、『広田先生は大平』だからである。高校で淡々と語学を教え、著書をものして名をなさんとすることもない。そんな広田の暢気さが、自分を悠揚とした気分にしてくれるのである。
三つ目は、広田が野々宮ともっとも近い人物なので、『先生の所へ来ると、野々宮さんと美禰子との関係が自ずからめいりょうになってくるだろうと思う』からである。

「結局、美彌子のことが知りたいってのが訪問の動機なのよね」
「うん、寝ても覚めても、美彌子、美彌子、美彌子、美彌子って感じだな」
だから、三四郎は探りをいれることにする。野々宮がまた下宿に戻って不便をしているのではないかと問うと、そんなことには無頓着な男だと広田は答える。『「家庭的な人じゃない。その代り学問にかけると非常に神経質だ」』という。結婚する気はないのだろうかと探りを入れると、『「あるかもしれない。いいのを周旋してやりたまえ」』と返されたうえに、『「君はどうです」』と逆に問い返されてしまう。
母には勧められているがその気にならないと答えると、広田が歯を出して笑う。その笑顔に三四郎は急になつかしさにとらわれる。美禰子や野々宮を離れた、『眼前の利害を超絶した』なつかしさである。
「このなつかしさって、なんなのかしら」
「たぶん、広田の、自分に囚われていない感じがもたらすものだろうね。広田は、自分の個人的な幸福も、名声も、富も追い求めていない。自分本位じゃないんだよ。それはたぶん、九州の田舎にあった他(ひと)本意の感覚に近いもので、だから、三四郎は懐かしさを感じたんじゃないかな」
「つまり、九州は基本的に他本意で、東京は自己本意ってことかしら」
「そうだね。そんな東京にあって、広田は自己本位から自由だということだろうね」
そうした状況について、広田は、昔は『「君とか、親とか、国とか、社会とか、みな他本意であった。それを一口にいうと教育を受けるものがことどとく偽善家であった』という。ところが、社会の変化で、自己本意、つまり西洋流の個人主義が輸入されたことに伴って、我意識が強くなり、いまは露悪家ばかりになったという。
「つまり、自分中心を隠さないってことね」
「たとえば、食べていくために教師をやっているのに、学生のためにやっている振りをするのは偽善であり気障である。対するに、与次郎のように自分に正直にやりたいことをやっているのは厭味がないということになる」
「さらに、話が進んで、二〇世紀になってからは利他本位の内容を利己本位でみたすというやり口が流行るというわよね」
「うん、昔の人は偽善であることを隠そうとしたが、今の人は偽善であることを明確に示しながら偽善を行うということだね」
「そういえば、昔、売名行為と言いながら被災地で歌った歌手がいたわね」
「これを、『優美な露悪家』と広田は言うわけだ。露悪が洗練されたものだというわけだね」
「三四郎は、これが美禰子にあてはまることに気づくわよね。この時代にふさわしからぬ彼女の振るまいは、まさに『優美な露悪家』と映るわけね」
「でも、その枠にも収まりきれないところがあるように三四郎には思われて、困惑する。淡々とこうした内容を講じ終えると、広田は何事もなかったかのようにたばこを吸う」
c:画家広田
そこへ与次郎が現れ、画家の原口が来たことを告げる。原口は、『フランス式の髭をはやして、頭を五分刈にした、脂肪の多い男』である。野々宮より二つ、三つ上に見え、広田先生よりいい着物を着ている。
「また与次郎が、露悪行為をしていたわけね」
「あからさまに自分の目的のために動いていたわけだ」
「原口を焚きつけて、文学者や芸術家、大学教授らが集って『文芸上有益な談話を交換する晩餐会』を開くようにしむけたのよね。つまりは、広田先生のことを知識人階級に知らしめようという与次郎の策略なわけよね」

広田が出席の意を示したので、用件は一瞬で片づき、最近広田が稽古しているという一中節の話になる。一中節というのは、三味線を弾きながら浄瑠璃を語るという音楽スタイルのことである。
広田は声が大きすぎるのに対し、美禰子の兄恭助はまったく形無しだという話になる。ここで原口と恭助もつながっていることが明らかになる。
「ここで三回目だね。被害者、つまり美彌子の兄の名が出たのは」
「ほんとにさりげなく、そして遠くにいる感じだね。近くにいるけど、三四郎からはとても遠い。いないに等しい存在だよね」
「でも、彼は三四郎の知人みんなとつながってるのよね」
「そうだね。いないようで、しっかりいるんだよな」
「それが、殺された理由と関係あるのかしら」
「当然あるだろうね。問題は、さりげなく存在感を示す彼にはどういう存在意義があったかってことだよなあ」
やがて、原口は、美禰子が『団扇をかざして木立をうしろに、明るい方を向いているところを等身(ライフサイズ)にうつしてみよう』と思っていることを口にし、三四郎の感動を呼ぶ。
「原口は、西洋の扇は嫌みだけど、日本の団扇は新しくておもしろいっていうけど、両方が共存しているわけで、つまり和様混淆の文化ならではよね。それに、考えてみれば、西洋画家である原口が、純和風の技芸である一中節を稽古しているというのも、いかにも和洋混淆で明治らしいし」
「鼓の音のような絵はかけないって原口は言うよね。西洋画をやっている人間が、いかにして日本的なものをその様式で表現できるかを、彼は追求してるってことじゃないかな」
「それは、西洋文学を学んだ漱石の考え方でもあったんじゃないかしら。西洋的なスタイルで、どうやって日本の文化的特徴を描き出すかっていうことが、彼のテーマだったわけでしょう」
d:蕎麦屋
帰りに蕎麦屋に寄った三四郎は、高等学校の生徒たちが広田の噂をしているのを耳にする。どうやら、彼らは与次郎の書いた「偉大なる暗闇」に感銘を受けている様子である。三四郎は『活版の勢力はやはりたいしたもの』だと気づく。それと同時に、そういうもので人の評判が左右されると知って『筆を執るものの責任が恐ろしく』なりもする。
気分が落ち込んでいるところに母からの手紙が来る。お前は『度胸がなくっていけない』から、度胸のすわる薬を医師にこしらえてもらって飲めと書いてある。三四郎はばかばかしいと思いながらも感謝を感じる。そして返事を書くがその中に『東京はあまりおもしろい所ではない』という一句がある。
「おもしろくないっていうことは、つまり自分の思い通りにはならないって言うことだろうね」
「学問も、女性もなかなかハードルが高くて手に入らないってことね」
「そして、そういう弱音を聞いてくれるのが母親というわけだ。強がらずに、素のままの自分をさらけ出せるのが母親なんだね」
「今のところ、実の母親がいるから、代理のよし子は三四郎のなかであまり必要性が増してこないってわけか」
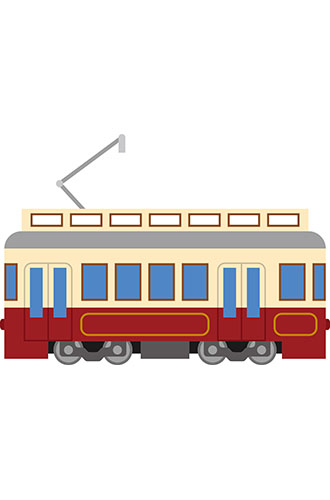
「いずれにせよ、ここで三たび恭助のことが出たね。姿こそ現さないけれど、少しばかり不器用で憎めない感じの人物像が思い浮かぶわね」
「うん、野々宮と同期で、広田の教え子で、原口の知り合いってわけだね」
「そして、美禰子の兄でもある」
「けっこう重要な存在なのに姿を現さないのね」
「うん、三四郎には見えないところにいる人物なんだよね。そしてとうとう物語の終わりまで三四郎が恭助に会うことはない」
「じゃあ、殺されても殺されなくても、あんまり関係ないんじゃないの」
「どうなんだろうね。その辺の見極めがまだつかないな」
だから、読み(=体験し)進めるしかないのだ。俺たちには。
この章の内容は単純だ。広田の元を訪れた三四郎は、広田との対話で、与次郎が「田のなかを流れる小川」であり、美彌子が「優美な露悪家」であることを悟る。そこに画家の原口が来て、有識者の晩餐会に広田を誘う。そして、その原口が団扇を持った美彌子をテーマに絵を描こうとしていることを三四郎は知る。そして同じく原口の話を通して、事件の被害者である美彌子の兄恭助の、憎めない人物像が浮かび上がる。
「そうよね、人に恨みを買うような人物では、どうやらなさそうだわ」
「ということは、彼が殺される理由は人間性以外のところにあったことになるね」
「何かをやらかしたとか?」
「あるいは、何かを象徴しているってことだろうね」
「象徴? なんの?」
「わかんないけど。他の登場人物にはない何かのはずだよ」
「たとえば何?」
「野々宮の科学とか、広田の文学とか、原口の芸術とか、そんな感じ」
「恭助は法学士よね」
「ってことは、法とか政治とか?」
「まだ、わかんないけど」
そう。なんとなく、感じてることはあるのだ。ただ、まだ言葉にならない。もっと読み=体験し薦めれば、形になってくるような予感はある。
「じゃあ三四郎は?」
何を象徴してるのかって?
「卵かな」
「卵?」
「うん、まだ、何にもなれてないけど、これから何かになるかもしれない可能性っていう意味で」
「ああ、そういうものを象徴していると」
なんとなく、高満寺は、俺の意見に賛同しかねるという風だった。
「違うと思うわけ」
「そうね、むしろあれじゃない」
「何」
「悶々とした青春。満たされない欲望。でも、踏み出せない自信のなさ」
「ってことは、ストーンズの『サティスファクション』みたいな感じだよね」
俺の頭の中には、あの呪文のような粘っこく重ったるいリフが鳴り響いた。アイ・キャント・ゲット・ノー・サティスファクション。
(第27回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月13日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


