 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十八 『三四郎』第八章 二十円(上編)
a:二十円と美彌子
与次郎が三四郎から二十円を借りた理由が説明される。
広田が家を借りるにあたって三ヶ月の敷金が必要だったが足りなかった。そこで、野々宮が妹にバイオリンを買ってやるために国元の親父から送ってもらった金を借りた。ところが、これを増やしてやろうと考えた与次郎は、馬券に代えてみなすってしまった。その金がないと、よし子がバイオリンを買ってもらえないままになる。そこで、三四郎が、母から送られてきたばかりの金を貸してやった、という顛末である。
「なんともいい加減な男だよね、与次郎は」
「ほんとうに広田に恩義を感じてるのかしら。ってことは結局敷金も足りてないってことでしょ? 広田に迷惑かけてるわよね」
「さらに、よし子もバイオリンを買ってもらえないままになっている」
「三四郎が貸した二十円は野々宮に返されてよし子のバイオリン代になるんだよね。ってことは広田の敷金は足りないままだってことになる」
「広田だから、許したってことかもしれないわね」
「あるいは、別口で借金してなんとかした可能性もある」
「ああ、その可能性が一番高いね。って、そこでちょっと思ったんだけど、与次郎って、アンチ資本主義社会って感じなのかな」

「どうして?」
「だって、金ってものにまるで重きをおいていない感じじゃないか。っていうより、馬券にしてすってしまうあたり、まるで金に復讐しようとしてるようにすら感じるんだけどね」
「そうね、まるで罪悪感もなさそうだしね」
与次郎のアンチ資本主義というのはなんとなくうなずける気がする。なにしろ、明治になって貨幣が支配する世界がようやく確立しようとしている時期で、貨幣経済っていうのは新しい体制だったわけだ。そして与次郎は、そんな貨幣経済の社会において決して明るい未来を約束されていない。貨幣が支配する世界は、与次郎に冷たいというか、与次郎にとっては敵のようなものなのだ。
そんな読みを裏付けるように、与次郎は金を返さない。返さないまま年末が迫ってきており、三四郎は家賃のことが気になってきている。
そこへ与次郎がやってきて、あちこち工面に回ったがみな月末で都合がつかなかったという。最後に、法学士の里見恭助のところに行ったが留守だった。ところが、妹の美禰子がいて、お前が取りに来れば貸すといっていると告げられる。
「出たわね。美彌子の思わせぶりが」
「うん。とにかく、三四郎を翻弄するよね」
「あとあれね。このくだりからすると、恭助と与次郎は以前から面識があったってことになるわよね」
「そうだね。これで、被害者恭助は、どうやら三四郎を取り巻くすべての人とつながりがあったらしいということが明らかになったね」
「思ってたより、重要な人物ってことなのかもね」
金の話が済むと与次郎は、いま地道に活動を続けて『西洋人ばかりではいけないから、ぜひとも日本人をいれてもらおう』というところまで話を持ってきているという。つまり、枠は作った。後はそこに、広田をはめ込むだけだということだ。ただし、広田先生のための運動だと思われないように、広田先生の名は出さないようにしているという。そして、先日原口が広田を誘いに来た晩餐会に出るようにと三四郎に告げる。
「与次郎って、おかしいわよね。なんだか矛盾してる」
「うん、二十円借りておいて三四郎に蕎麦屋で酒をふるまうし、滅多に人に払わせないというんだからね」
「美禰子に借りれる算段をしてきたときだって、借金は返さないくせに、金はあるからと三四郎を銀座の天麩羅屋に連れて行こうとするじゃない。金は使いきるものだっていう江戸っ子気質ともちょっと違うような」
「やっぱり、反資本主義なんだよ、きっと」
「ええい、憎い金め、こんなものは使っちまうにこしたことはないっ、って感じかしらね」
「三四郎はそんな与次郎について、『長く東京にいるとあんなになるものか』って思うけど、あんなになるってどんなになることだろうね」
「まあ、熱心に根回しをして広田を教授にしようとしたりとか、金を借りて返さなくても平気でいられるとか、そういうことかしらね」
「なんというか、核がないよね。確かにずっと忙しくしているけど、中身がない感じがすごくある。忙しくしていることが、存在している理由になっているような感じだな。結局何も生み出さない。借りた金はなくなってしまうし、広田のことだって」
「そうね。すごく不毛な努力家よね。結局大事な金を競馬でするような活動に終始してる感じがするわよね」
「なるほど、彼は博打が好きなわけだ。やってることは全部博打だもんな」
「逆にいえば、安定とか、確かなことに背を向けてるってことかしら」
「スリルがあることなら、なんでもやるって感じだよね。社会に適合して安定に向かう方向とは逆のベクトルを感じるな」
「公務員には向かないタイプね」
b:鏡のなかの二人
次に三四郎は、美禰子の所へ行くことを考える。『美禰子の所へ行く用事ができたのはうれしい』のだが、『頭を下げて金を借りるのはありがたくない』と妙なプライドが出てきたりもする。
「で、とにかく行ってみてからどうするか考えようと決めて、後は妄想タイムよね」
「うん、美禰子のことをとにかく妄想する。『美禰子の顔や手や、襟や、帯や、着物やらを、想像に任せて乗けたり除ったり』する。あした会うときに、『どんな態度で、どんな事を言うだろうとその光景が十通りにも二十通りにもなって、いろいろに出てくる』」

「さらには、美禰子が与次郎ではなく自分に金を手渡したいといったことが、『自分にははなはだたのもしいこと』ではないかと己惚れるのよね」
「でも、すぐに不確かになる。『「やっぱり愚弄じゃないか」』と考えて赤面しちゃう。でも愚弄だとした場合でも愚弄する理由がわからない」
「なんだか、忙しいね。妄想や空想や推量で一喜一憂してるわけだから」
翌日、昼から授業が休みになったので、三四郎は里見の屋敷にでかける。前を通ったことはあっても、入るのは初めてである。通る度に『里見恭助という人は、どんな男だろう』と思ってはいたが、『まだ会ったことはない』。ベルを押して『「美禰子さんはお宅ですか」』と言ったときに、気恥ずかしさを感じる。
「未婚の女性を、未婚の男性が訪ねるというのは、当時としては異例のことだったんだろうね」
「でも、菊人形の時のことなどを考えると、三四郎も、美禰子も、けっこう平気でそういう禁忌を破っているわよね。よく考えると」
「うん、実はなかなか二人とも〈進んでる〉わけだよね。男女交際に関しては」
「常識を知らないというか、無視してるというか、そういう感じよね」
「さりげなく書いてあるからわかりにくいけど、読書=体験してみるとそのへんのぎこちなさがよく伝わるよね」
三四郎が応接間で待っていると、バイオリンの音が聞こえる。とはいっても、曲の一部を弾いたものではなく、『ただ鳴らしただけ』である。その感じは『不意に天から二、三粒落ちて来た、でたらめの雹のよう』と形容されている。
「これも美禰子の技巧よね、きっと」
「もしかしたら、ちゃんとは弾けないのかもしれない。ただ、自分が発している『妙に西洋のにおいがする』気配を補強するためのもののようにも聞こえる」
「あなたにはそう聞こえたわけね」
「うん、君もだろ。読書=体験は音のイメージも伴うから」
「どうも好きになれないのよね、彼女が出す音すべてが」
「で、まあその音楽に三四郎は『なかば感覚を失った』状態にある。冒頭の、うとうとして目覚めるのと同じ感じだよね。三四郎は、よくこういう自失状態に陥るよね」
「で、気がつくと自分の前にある鏡の中に美禰子が映っているわけよね。『美禰子は鏡の中で三四郎を見た。三四郎は鏡の中の美禰子を見た。美禰子はにこりと笑った』となる」
「不思議な場面よね。現実ではなく、鏡の中で二人が見つめ合うんだから」
「一幅の絵のようにも見えるよね。二次元にその瞬間が切り取られるんだから。しかも、ここでは目に見える以外のものは存在しないという意味でも絵だよね」
「西洋の絵画にはけっこうあるでしょ、鏡がモチーフのやつ」
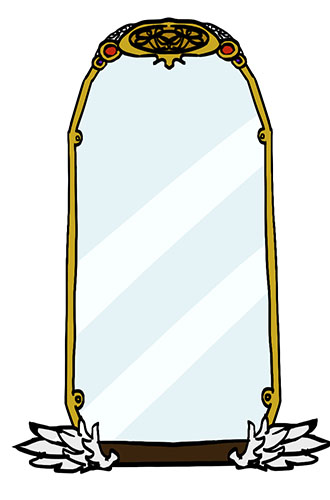
「そうだね、「蘊蓄」によれば、古くはベラスケスの『鏡のヴィーナス』や『ラス・メニーナス』、ファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻』、一九世紀だとバーン・ジョーンズの『ヴィーナスの鏡』とか、とにかくかなりの数がある。漱石が留学中にこういう絵のうちのどれかを見たのは間違いないだろうね」
「でも、不思議なことに鏡の中で男女が見つめ合うっていう構図は」
「ないよね。すごくありそうなのに。ダリの絵で鏡の中でダリとガラが見つめ合うってのがあるけど、それは『三四郎』より後の時代の作品だからね」
「すぐに美禰子が声をかけて、三四郎が振り返り、二人は現実で目線を交わすことになるから、鏡の中での邂逅はほんの一瞬なのよね」
「でも、読書=体験をすると、ここは妙に印象に残るわよね。その短さがまた、写真で切り取ったような感覚を残すっていうか」
「うん、二人が真に一体であった希有な瞬間なのだといえるかもしれないね。それ以前だと、一緒に人魚の絵を見たとき、一緒に雲を見上げたとき、美禰子がぬかるみを越えようとして、バランスを崩して三四郎の手にすがったときなんかに二人の接近があった。でも、この場面ほど、不思議な一体感を残す場面はないよね」
「実際、現実には二人はこのまま結ばれることはないんだものね。美禰子はやがて、原口によって、この場面みたいに二人でじゃなくて、たった一人で平面の中に描き込まれて固定されることになるわけだし」
「そう、そこに三四郎は結局入れないんだよね」
「だけど、鏡がほんの一瞬、三四郎の、そして、もしかしたら美禰子にもあったかもしれない願望を切り取って固定してくれた、っていう感じかしら」
「だから、美禰子に声をかけられた三四郎は『振り向かなければならなかった』って描かれるんじゃないかな。ほんとうは、三四郎はもっとあの鏡の中に二人で固定されていたかったってことじゃないかな」
(第28回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月13日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


