 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十六、『三四郎』第六章 帝国大学運動会(下編)
f:「あれは椎」再演
よし子が、入院していた時に世話になった看護婦に礼を言いに行くといって、唐突に病院に出かけてしまう。この辺りも自分の内的欲求に忠実なよし子らしい行動だといえる。美彌子とは逆で、よし子にとって大切なのは、人がどう思うかではなく、自分がどうしたいかということなのである。
その結果として、三四郎と美禰子は池の傍に二人きりで残される。美禰子は木陰を指して、『「あれを知っていらしって」』と言い、三四郎は『「あれは椎」』と答える。つまり、初めての出会いの時に、美禰子と看護婦が交わした会話を、役柄を変えて再現するわけである。
「こういうことだよね。美禰子の側では、あれが演劇的な、見せるためのやりとりであったことを意識しているし、三四郎の側もその演出にきちんと魅せられていたことを示しているのよね」
「さりげない対話に見えても美禰子の場合はすべてが計算ずくであり、それがまったくないのがよし子だということになる」
「恋愛は演劇的だってことかしらね」
「そうだね、三角関係ってのがその典型例だろうけどね。一人の女性をめぐって互いに演技を披露しあうことで、互いの欲望を刺激しあうわけだから。そして美禰子は、野々宮を刺激するために、三四郎を利用することにしているということかもしれないね」
三四郎は、気になって仕方がないことを問う。つまり、野々宮と何を話していたのかということだ。
「つまり、三四郎の側はこの三角関係の演出にみごとに取り込まれているっていうことだよね。わかりやすすぎるほどに」
「ここで美禰子の口から初めて原口という画工の名前が出る」
「それ以前には、野々宮の口からも一度出ていたね」
「野々宮との会話は、原口が写生をしているから、ポンチにかかれないよう気をつけろと言う忠告だったことがわかって、三四郎は拍子抜けするのよね」
「とにかく、美禰子と野々宮の関係が気になって仕方がないわけだ」
「だから、よし子が昨日から美禰子の所にいる、野々宮は家を引き払って下宿に戻ったと聞いてさらに安堵するわけね」
「そうだね。家を構えるということは結婚準備が整ったという印だったわけだから、下宿に戻ったことは『「自分にとっては、目前の迷惑を少し長距離へ引き移したような好都合にもなる」』と思うわけだ。とりあえず、当分野々宮が美禰子と結婚する心配をしなくてすむわけだからね」
「でも、同時に不安にもなる。よし子が美禰子のところにいるということは、野々宮が頻繁に美禰子の所に出入りするということであり、結果的には二人の距離が縮まる結果になるのではないかというわけだ」

三四郎は、そういう『疑いある未来』のせいで、平静を装うのがつらくなる。そこに看護婦に礼を言いに行っていたよし子が戻ってくる。
下宿生活に戻ったことに関して、美禰子は『大いに野々宮さんをほめだ』す。学問のために俗用を避ける人物はむしろ尊敬に値するという趣旨である。とくに外国にまで聞こえるほどの研究をしている野々宮ならなおさらだという。
「三四郎は、ここで自分を顧みる機会を得るよね。それから、美禰子の正体を見抜く機会も」
「ええそうね。自分が『田舎から出て大学へはいったばかり』であり、『学問という学問もなければ、見識という見識もない』、つまり、美禰子から尊敬を受ける資格がないばかりか、むしろ馬鹿にされている可能性すらあると思い至るのよね」
「自分は愚弄されているのではないかと思うわけだけど、もう一歩踏み出せない」
「そうやっぱり、自分のことも、他人のことも突き詰めることから逃げちゃう」
「なんていうか、三四郎はまだ意識をもって行動していない感じなんだよな。前意識みたいな不確定で曖昧な自我のままで生きているみたいだね」
「三が前意識で、四が意識だとすると、やっぱりその境目あたりをうろついてる。時に四に行くこともあるけど、すぐ三に戻ったり、三と四の間をたゆたったりしている。そんな感じかしらね」
「本当の自分、何者でもない自分と直面するのが怖いから、帝国大学学生という肩書きにすがってる。その肩書きだけで、美禰子の関心を惹くに値すると思いこみたい。でも、内実から言えば、野々宮や広田とは比べものにならないくらい卑小な自分がいる。でもそのことから目をそむけなければ、美禰子と釣り合う自分をイメージできない」
「そして、そんな三四郎の懸命の自己欺瞞を、美禰子はまた利用しているってわけよね」
「美禰子に、自分と釣り合う男として扱われることで、三四郎は気持ちよくなるわけだ。だから、これは恋愛感情に見える、自己愛なのかもしれないな」
ところで、三角関係と聞いて、俺が即座に思い出すのは、あの『トラウマむかしばなし事件』である。
「覚えてる、舌きり雀の話?」
高満寺に軽く振ってみた。
「ああ、あれね。わたしたちがタッグを組んで間もないころの事件よね」
「うん。まだ仕事に慣れてないせいもあって、反響のすごさにびっくりしたよな」
「ええ、あの犯人も反聖文シンパを自称してたんだったわよね」
「そうそう。『ほんとうは恐ろしいんだよ~ん、おじさん』とか名乗ってたよな」
「そのわりには、物語剥奪五年の刑を言い渡されてピーピー泣いてたけどね」
「そこはチュンチュンって泣いてほしかったわよね、雀だけに」
もうお察しはついたことと思われるが、『ほんとうは恐ろしいんだよ~ん、おじさん』は、子供向けの童話を原話に差し替えることで、子供たちに生涯ぬぐえないトラウマを与えたのであった。VRで体験するだけに、その恐怖たるや半端なかったといわれている。
「舌きり雀」の場合は、
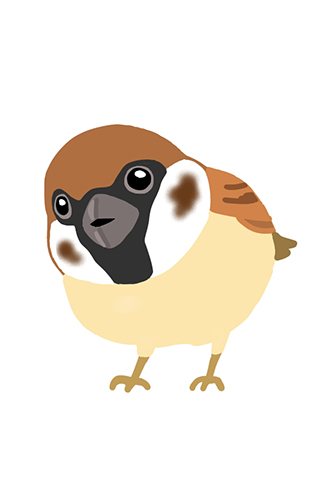
「むかしむかし、あるところにおじいさんが住んでいました。おじいさんは、怪我をしている若い娘を助けてあげたのですが、その娘が好きになってしまいました。少女の名前は雀といいました。おじいさんが、若い娘に夢中になっているのを知って、おばあさんはたいへん怒り、嫉妬しました。そこで、おじいさんのいないときに、娘を襲って舌を切り、娘を追い出しました。娘がいなくなったのを知ったおじいさんは、『雀やあ、雀やあ』と狂ったように娘をさがしまわりました。さんざん苦労して娘を探し当てると、娘は自分を愛してくれたおじいさんに、自分はほんとうはお金持ちだと明かして、おじいさんが自分と離れられくなるようにしました。そして、おじいさんに、おばあさんをだまして連れて来るように言って、おばあさんを殺しました。こうして、おじいさんと雀とは、幸せにくらしました。みなさん、こういうのを、三角関係というのですよ」とまあ、だいたいこういった趣旨の物語に書き換えられていたのだった。
特に舌を切る場面や、雀を探すおじいさんが舐める艱難辛苦、雀がおばあさんを殺す時の残酷描写が、子供たちに深い心の傷を与えたといわれている。逮捕された時本人は、「幼いころから本物に触れる、それが一番大切なことなんですよ~ん」とかうそぶいていたわけだが、物語剥奪の実刑を言い渡された途端、大泣きになって赦しを請うたという情けない顛末となったわけであった。
さて、第六章を振り返ってみよう。内容としては、与次郎が広田を東大教授にするためにレトリック満載だけど中身のない「大論文」を書いたり、懇親会で学生たちを誘導しようとしたり懸命に活動している場面が前半。後半は、帝大の運動会で三四郎が美彌子をガン見し、森のなかでよし子、美彌子と対話する場面となっている。
「いまのところ、なんだか帝国大学構内の森に囲まれた池が物語の中心にあるような印象があるな」
「そうね。物語はほとんど本郷周辺を離れないし。その真ん中にこの森に囲まれた池があるんだものね」
「でも、この森と池は『たいへんな動き方』をしている東京とは対極にあるようだ。なんていうか、現実と遊離した場所っていうイメージがある」
「アジールっていうか」
「ああ、それいいね。アジールの語源はギリシャ語で、侵すことのできない、神聖な場所ってことらしいからね」
「いまのところあれだね、この森に入った登場人物は、三四郎以外には、美彌子と野々宮とよし子だけだね」
「それが、三四郎にとって、東京での人間関係のコアにあるってことかしらね」
「そして、事件の犠牲者は、三四郎にとっての最重要人物である美彌子の兄だ」
「遠いわよね」
「うん、美彌子の兄っていうと近いようだけど、三四郎の目線からするとやっぱり遠い。なんで反聖文は、彼を犠牲者に選んだんだろう」
「三四郎以外の人物の目線で見るべきなのかもね」
「って誰の?」
「さあ、わかんないけど、それが事件の謎を解く鍵かもしれないわよ。その辺を推理するのがあんたの役目でしょうが、探偵さん!」
どんっ!と背中を叩かれた。背骨がひしゃげて肋骨に接触し、間に挟まれていた心臓と肺が破裂の危機に瀕した。
(第26回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月14日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


