 自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。
自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。
by 金魚屋編集部
池上晴之(いけがみ・はるゆき)
一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。元編集者。三十五年以上にわたり医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の編集に携わる。共同体としての「荒地派」の再評価を目下のテーマとして評論活動を展開している。音楽批評『いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう』を文学金魚で連載中。
鶴山裕司(つるやま ゆうじ)
一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。
■鮎川信夫の時評■
池上 鮎川信夫は晩年、一九八三年頃かな、十年間は詩をやめると言いましたよね。
鶴山 同時代の仲間、それこそ「橋上の人よ」と呼びかける人がいなくなったってことでしょうね。さっきの「戦友」が書かれた一九六〇年代でも、もう「荒地」的精神の共同体は怪しかった。
鮎川さんと吉本さんの対談に「戦後の歴史と文学者」があるでしょう。一九八〇年の対談だけど、黒田三郎さんが亡くなったので「現代詩手帖」で北川透さんと追悼対談して、その際、黒田さんが「詩人会議」の運営委員長をやっていたから「詩人会議」を「日共系」と言ったら、「詩人会議」所属の詩人たちだけでなく、共産党の機関誌「赤旗」からもすんごい批判されたというのを吉本さんとの対話の枕にしています。鮎川さんは、世間では「詩人会議」は日共系と言われてるから、なんの気なしにそう言っただけなのに、なんでそんなつまらんことにこだわるんだと首をひねっている。
で、鮎川さんの批判者に関根弘さんがいた。鮎川さんは初期の詩論で関根さんの詩を評価しています。まあかつての仲間の一人だったわけです。関根さんは「『芸術前衛』について」という鮎川批判を書いたわけだけど、これに対する鮎川さんの再批判が身も蓋もない。「『詩人会議』の連中は、黒田三郎を敬い、関根弘を侮る。どこかで、何かが間違ってしまったのである。これは小さな歴史のイロニーである。黒田ではなく、関根が『詩人会議』の運営委員長だったら、私に向ってこうまで醜悪な論争を挑むようなことはなかったろう」とある。
こういう批判はホントにキツイねぇ。関根さんは芸術論を振りかざして鮎川さんを批判したわけだけど、鮎川さんの方はケツをまくっちゃってる。僕が書いた関根さん批判じゃないから言いますが、要は本音は黒田の方が詩人として格上で、差がついちゃったのが気に入らないんだろ、ということです。
鮎川さんが黒田さんが「詩人会議」の運営委員長になったことについて、「困ったもんだ」という意味のことを言っています。でも大病した黒田さんにお見舞いの電話をして話したときに、一生懸命「詩人会議」の運営委員長をやってるんだと言ったのを聞いて、まあ生き甲斐があっていいか、くらいで批判せずに黙っていた。でもそこに現世の利害やルサンチマンが入り混じると手厳しい。
鮎川さんは「列島」系詩人に対しては一貫して好意的で、小野十三郎さんや長谷川龍生さんなんかの詩は高く評価している。変遷はあるにせよ、思想が一貫していて崩れなければ評価する。だけど大きく崩れを見せると、鮎川という人はどこかでピシャッと何か言うわね。
でも戦後ってのはそういうもんだ。現代も同じだけどね。ただ今から振り返ると、戦後社会の変節点は一九八〇年代だった。九〇年代になると高度情報社化会が始まるからね。いわゆる戦後詩を含む戦後文学は一九八〇年代で終わりです。その時期に鮎川さんが詩を書かなくなったのは当然かな。カナリヤみたいだね(笑)。
池上 なるほど……何で詩を書かないなんて言ったのか、その理由を長年疑問に思っていたんですけれど、そう考えれば納得できます。つまり、戦後詩の「終わりの始まり」だったわけですね。なるほどなぁ。いや、これでぼくの中では、すっきりしました。鮎川信夫が戦中に旧作「橋上の人」に手を入れ始め、その行為の意味を『戦中手記』で思想として表現した一九四五年三月が「戦後詩」の始まりで、一九八六年十月の鮎川信夫の死で戦後詩が終わった、ということでいいとぼくは思います。
何だか結論みたいになっちゃいましたけど、せっかくの機会ですから、鮎川信夫という人についても語り合いたいですね。鮎川信夫はどんな感じの人だったんですか。
鶴山 ひとことで言うと人嫌い。対談とかが終わると、「じゃ」と言ってすぐ帰っちゃうんだもの。お見送りに出たら、もう車に乗って走り出してる感じ。雑談とかはあまりなかった。晩年だけかもしれないけどね。だけど吉本さんと一時間とか二時間対談して、吉本さんを車で家まで送っていって、そのまま朝の四時頃まで話し込んだって書いてるけど、それはとっても稀なことだったと思います。よほど気が合ったんでしょうね。もちろん一種独特のカリスマ性はありました。鮎川さん、田村さん、吉本さんは、この人たちはちょっと違うなぁという迫力がありました。
池上 鮎川・吉本対談は側で聴いていてどうでしたか。
鶴山 うーん、よくわからなかった(笑)。こちらは吉本さんと鮎川さんの直近の著作を全部読んでるわけじゃないからね。でも彼らは互いの本をイヤになるくらいキチンと読んでてさ。それで梗概と言いますか、そのおさらいをしないで、二人でいきなり核心的な話を始めちゃう。わかり合ってる同志でしか出来ない対話ですね。最後は決裂してしまうわけだけど。
池上 鶴山さんは、鮎川信夫と実際に仕事をした最後の世代の編集者ってことになるんですよね。
鶴山 そうですね。「現代詩手帖」にいた時にお亡くなりになりましたから。よく知られた話ですが、お亡くなりになるまで、誰も鮎川さんの自宅の住所を知らなかった。お亡くなりになって初めて、喪主がいること、つまり鮎川さんが結婚していて奥さんがいることをみんな知った。北村太郎さんも知らなかったって言ってましたから。人付き合いがいい人とは絶対言えないね。鮎川さんの連絡先は、甥御さんの家の電話番号でした。でも鮎川さんは超大物詩人だったから、お世話になってる出版社は、どこにお中元とかお歳暮、年賀状を送ってたんでしょうね(笑)。
池上 ちょっとお話ししたように、ぼくは大学生の時、一九八三年の秋だったと思うんだけど、「無限アカデミー」の現代詩講座で鮎川信夫と北村太郎の対話を聴いたんです。対話といっても実際には鮎川信夫が友人としての北村太郎に話をしているみたいなリラックスした雰囲気で、北村太郎が鮎川信夫のことを尊敬しているんだなぁという感じがよく伝わってきましたね。
話の内容はうろ覚えなんだけど、第二次世界大戦に向かう中で若い詩人たちが何を考え、どう感じていたのかという話の流れで、一般には知られていない詩人の作品を取り上げて鮎川信夫が朗読したんです。太平洋戦争が始まった一九四一年十二月八日にこういう作品が書かれていたということを皆さんに知っていただきたくて朗読しました、と言っていました。詩の内容は覚えていないんですけれど、「僕は〈バイバイ〉風に手をあげる。」というリフレーンだけが耳に残っています。少し甲高い声で、でも「バイバイ」という言い方が鮎川信夫のイメージとはミスマッチな、何かかわいらしい感じがして、ちょっと意外に思いました。後で調べたら、これは金山利美という詩人の「開放」という詩で、「詩と時代――詩人の姿勢について」というタイトルの過去の講演でも詳しく取り上げていました(『すこぶる愉快な絶望』に収載)。要するに、持ちネタだったわけです(笑)。
当時は中曽根康弘が総理大臣をやっていて、マスコミや世論は「右傾化」とか「戦争を起こすんじゃないか」という論調が多かったんですよね。それに対して鮎川信夫が、「よくマスコミの連中が「中曽根はバカだ」とか言うんだけど、中曽根はバカじゃないですよ。バカだといっている奴より、はるかに頭がいいですよ。戦争になるんじゃないかと言う人がいるけれど、中曽根は絶対に戦争は起こしませんよ。中曽根がやっている限り、絶対に戦争にはならない。どうしてかと言うと、彼は戦争に行っているんです。あの戦争を経験した人間なら、戦争を起こせばどういうことになるかは身に沁みてわかっているはずなんです。むしろ日本が戦争を起こすとしたら、第二次世界大戦を経験していない世代の人がリーダーになった時でしょうね」と言ったことをいまでもよく覚えています。
講座が終わって、会場だった神宮外苑の絵画館の石造りの古い廊下に出たら、シャーロック・ホームズ風の帽子を被って、ベージュ色の暖かそうなオーバーコートに身を包んだ鮎川信夫が大きな背中をちょっと丸めて廊下の隅でたばこを吸っていた。思い切って話し掛けてみようと思って近づいて行ったんだけど、さすがに詩の話をするのは無粋だなと思って、とっさにシャーロック・ホームズの翻訳を話題にしようと決めた。鮎川信夫訳で一つだけ出版されていないシリーズがあったんですよ。で、「『シャーロック・ホームズの事件簿』の翻訳はいつ頃出るんでしょうか」と尋ねたら、鮎川信夫は甲高い声で「あぁ、そうですね。そういえば今日は翻訳の話はしなかったですね」と答えてから、キョロキョロって辺りを見回して、声を潜めて「実はね、下訳を頼んでいたおじいさんが最近死んじゃったんですよね」って言ったんです(笑)。
ぼくはびっくりしちゃって、初めて会った人にそういうこと言うかなぁって(笑)。「あぁ、そうなんですか」とぼくが言うと、鮎川信夫はちょっとうなずいて、「いま文春で連載をしているでしょ。それもあってなかなか時間が取れないんですよね。でもやらなくちゃいけないですね」と少し早口で続けた。ぼくが学生だということは見ればわかったと思うんだけど、ぼくに対してフラットに、対等に話をしてくれた。それがとても印象に残りました。あと、普通だったら「亡くなった」って言うと思うんですけれど、「死んじゃった」って言うところが、何ていうかなぁ、ぼくからすると「さすがは「死んだ男」の作者、鮎川信夫だ」と(笑)。
鶴山 池上さんもご存知だと思いますが、有名詩人や作家の翻訳本は、最終的な手を入れるにせよ、たいてい下訳者がいる一種の名義貸しです。村上春樹さんは自分で訳してるかもしれませんが。田村さんもアガサ・クリスティなんかを翻訳してますが、田村さんに同じ話をしたら、「俺が翻訳なんてメンドーなこと、するわけねーだろ」と言うと思いますよ。芸風が違いますね(笑)。ただ鮎川さんや田村さんは正直でした。後期の詩に「山を想う」があるでしょ。
帰るところはそこしかない
自然の風景の始めであり終りである
ふるさとの山
父がうまれた村は山中にあり
母がうまれた町は山にかこまれていて
峰から昇り尾根に沈む日月
おーいと呼べば
精霊の澄んだ答えが返ってくる
その谺のとどく範囲の明け暮れ
在りのままに生き
東洋哲人風の生活が
現代でも可能であるのかどうか
時には朝早く釣竿を持ち
清流をさかのぼって幽谷に魚影を追い
動かない山懐につつまれて
残りすくない瞑想の命を楽しむ
いつかきみが帰るところは
そこしかない
鮎川さんは、いつもしかつめらしい詩だけ書いてたわけじゃない。ちょっとらしくない詩で、こりゃ「四季」派じゃんと思いますが、ふとホントにそうだなぁと思って書いた詩なんでしょうね。
池上 この詩はどちらかというと述懐というか心境詩という感じがしますけれど、鮎川信夫の詩には、ある種の抒情が流れていますよね。
鶴山 基本は抒情詩人だと思います。モダニズムの洗礼を受けて短歌的抒情から切れ、そこに思想を付加して「荒地」派の戦後詩が始まるわけだけど、中期になると、その時々で思ったこと、感じたことを書きはじめる。「四季」派を頭に思い浮かべていた可能性は低いけど、それを詩が緩くなったと見るか、素直になったと見るのかは微妙なところですね。
鮎川さんが『荒地詩集』の最初の方で、彼が一種の精神的共同体を夢見たのは間違いないと思います。それは個が世界と対峙する精神的共同体だったと思います。どこで書いていたか分からないけども、鮎川さんが戦争から学んだ一番大きな事の一つは、集団は責任を取らないってことなんだね。もちろん極東裁判で東条英機さんらが戦犯として死刑になったわけだけど、日本文学報国会なんかで翼賛詩を書いた詩人たちの責任は、うやむやになってしまった。みんな自分たちは大きな流れの中に巻き込まれて、集団に呑まれたんだっていう言い訳をしたわけです。それを見ていた鮎川さんたちは、集団ではなく、個ですべての責任を取るんだ、そういう美しい精神的共同体を目指すんだという理想を掲げた。「橋上の人」なんかにそれがよく現れています。ただこれは絶対矛盾でしょ。個が責任を取るんだったら集団になりようがない。ただその理想の精神的連帯だけで一種の個の共同体、並列の共同体というのを鮎川さんは目指したんだと思う。『荒地詩集』の最初の方なんかは、鮎川さん中心なのに彼は目立たない形になっています。三好さんがほとんど詩集一冊分ぐらい書いている。俺が俺がの人ではないね。
ただ鮎川さん最大の問題は、比喩的になってしまうけれども、「橋上の人」から一歩も動かなかったことです。鮎川さんには、吉本さんのような原理的著作が一冊もない。初期を除いて全部頼まれ仕事です。その時々に応じて一生懸命なんですが。
池上 すると鮎川信夫が自発的に書いたのは『戦中手記』ぐらいなんでしょうか。
鶴山 それと「『荒地』について」とかの、初期の詩論ですね。もちろん学生時代から戦後すぐの時期は自発的に詩を書いているけど、詩人として名前が有名になってからは、詩も評論・時評もほとんど頼まれ仕事になっていく。
池上 『荒地詩集1951』巻頭の「Xへの献辞」には「僕達各個人が如何に分裂し、模索の方向を異にし、未明の混沌とした内乱状態にあろうとも、なお一つの無名にして共同なる社会に於て、離れ難く結び合っていることも、より一層深く理解してくれるだろう」とありますね。
鶴山 わっかりにくい文章ですよね(笑)。でも「僕達」が「分裂し、模索の方向を異にし」、「混沌とした内乱状態」にあるのは、なにも若い「未明」時代だけじゃない。「無名にして共同なる社会」というのも矛盾した言い方だ。思想や利害で結ばれた社会や団体が「共同」意識を持てば、必ず名前を持つからね。要は俺たちゃてんでバラバラだけど、名付け得ない共同体意識で結び付いている、はずだと言っているわけだ。鮎川さんらしい文章だけど、この方は理想を掲げた瞬間に、その終末を予感しているようなところがある。戦後的な明るい未来には飛びつかない(笑)。
池上 鮎川信夫は、「荒地」のメンバーは、元々それぞれ考え方がまったく異なっていることをよくわかっていたんですね。
鶴山 僕らだって、学生時代に何の利害関係もなく遊んだ友だちなんかは、ケツの穴までわかるでしょ(笑)。何十年か経ってオジサンになっても、コイツ、変わんねぇなって思うもの。鮎川さんは、中桐さんに最後に会ったとき、「もう君とは会わないから」って一種の絶交宣言をして別れたって書いてますよね。中桐さん、メチャクチャな酒の飲み方をして、ヤメロって言っても聞かないから。実際お葬式にも行かなかった。奥さんも「来なくていいです」と言ったみたいだけど、意地悪じゃなくて、鮎川さんと中桐さんの関係をよく理解していたからですよね。古い友だち同士なら、その機微は手に取るように理解できます。
池上 鮎川信夫以外の「荒地」のメンバーは、「Xへの献辞」に書かれた精神の共同体という理念を、どのくらい理解していたと思いますか。
鶴山 鮎川信夫的文脈では、理解してなかったと思います。みんな個々に独立した作家だから、どんどん地金の資質が露わになっていきます。作家に「代表作はなんですか?」と聞けば、ほとんどの作家が「昨日書いた作品」「最新作の本」って答えますよ。「荒地」の作家たち本来の資質は、それぞれの後期から晩年の作品に一番よく表れています。資質がかなり違うわけだけど、鮎川さんが偉かったのは、皆が「Xへの献辞」にあるような美しい精神の共同体を離れ始めても、衿首を引っつかまなかったことですね。ナントカ詩人会の会長にはならなかった。「荒地」のメンバーで言えば、田村さんと吉本さんは鮎川さんと同じような独立不羈の精神を持っていたと思います。でも創作者は悲しいもので、似た面があると、最終的にはあんまり仲良くできなかったりするんだね(笑)。
池上 出発時から、「荒地」のグループとしての解体は織り込み済みだったという感じもするんですけどね。
鶴山 理想のアドバルーンは上げた。文章だから誰でも読めるので、時代が経っても分かる人には分かるってことじゃないですか。
池上 だけど実際には最後の『荒地詩集1958』が出る年には、「新日本文学会」の詩人から「荒地」「櫂」「氾」のメンバーまで集結した「現代詩の会」の初代委員長になっているから、やはり「荒地」の解体は鮎川信夫にとってはひとつの区切りにはなったんでしょう。三木卓は『若き詩人たちの青春』という本で、「鮎川信夫を担ぐ、という構想のお膳立てをしたのは関根弘と長谷川龍生だろうと思う」、「鮎川信夫は、すでに戦後詩における象徴的存在だった。鮎川のキャラクターからして、委員長就任にそれほどの興味を感じたとは思えない」、「だがあえて会の冠として収まったのは、若い詩人たちの仕事のために、それが筋のとおったものなら応援したいという気持があったからだ、と思う」と書いています。
興味深いのはね、三木卓は「これは後年のことだが、鮎川が、堀川正美や山田正弘のような若い詩人たちに、/「自分たちが年刊で出している〈荒地詩集〉という場を、きみたちに利用してもらえるなら、いつでも譲るよ。そういう気持なんだ」/と話していたのを、そばで聞いたことがある」というエピソードを紹介しているんですよ。吉本隆明が、自分が荒地賞をもらった『荒地詩集1954』の時点で、「荒地賞みたいなものを荒地の初期からの詩人たちが設定したときは多分、行き詰っていたといいましょうか、終わりのときだと思います」と講演で語っているんですが(「荒地派について」『ほぼ日刊イトイ新聞』)、グループとしての荒地は数年で事実上解体していたということなんでしょうね。
ぼくは読者としておもしろかったのは『荒地詩集1951』だけで、『1952』以降は内容がマンネリ化しているように感じましたし、後半のものはもう「荒地派」って感じがしなかった。だから共同体としての荒地派は『荒地詩集1951』で始まると同時に終わっていたと考えてもいいようにぼくは思うんですよね。
ちょっと話は変わりますが、鮎川信夫が結果的に最後に書いた詩となった「風景論」という作品がありますよね。この詩をぼくは鮎川信夫の代表作の一つに挙げたいんです。
何を得
何を失うとも
到達したところから
一歩一歩あゆむほかない
視界をさえぎるのは
煙か霧か
眼鏡の疲れをぬぐい
深く息をすることもあったが
偽の革命
愚かな戦争
過ぎてしまえば幻の
半世紀は車窓の景色であった
遠ざかる列車のひびきに
家族あわせの円居が
窓の灯をにじませる夜には
いつもかわらぬ休息がありますように
単調なくり返しのようで
同じ風景は二度と現れない
私一人の人生でも
同じ時は決して戻ってこなかった
いまし朝雲を東によせて
大陸からの寒波はきついが
議事堂のまるい空はきれいに澄み
ときわの首都は世界の影を映している
一九八二年一月三日の「朝日新聞」に掲載された詩ですが、ぼくはリアルタイムで読んだんじゃなくて、一九八七年に出た最後の詩集『難路行』に収載されて初めて読んだんです。それまでは、同じ一九八二年の「現代詩手帖」一月号に掲載された「海の変化」という詩が、最後の作品だと思っていました。この詩は「もはや、わたくし、と特定する必要はない。わたくしには、わたくし以外の/どんな現象も起りようがなく、わたくしの影は、孤独とはいえなくなっているから、」と始まって、「これが罰か、太陽と海を呪ったことの? たった一度の空想の罪にしては、酷すぎる報いではないか!/必死の思いで、前方の真っ暗闇を凝視するが、もう何も見えぬ。叫ぶ、が、声にならない。ぴったり浪に包囲されて、」と「、」で終わっちゃうまさに絶筆という感じの救いのない作品なんです。
ところが、雑誌の一月号っていうのは前年の十二月には編集作業を終えて年内に発売になっちゃうから、実際にいつ書いた詩なのかは別にしても、「風景論」が最後に発表された作品になるわけです。もっとも当時は読んでもピンと来なかったんですよ。新聞に出した詩だから、わかりやすい作品にしたのかな、六十歲くらいになると、こんなふうに思うのかなぁという感じだった。でも自分がこの年齢になると、とてもいい詩だと思うようになりました。「海の変化」の後に「風景論」があったことで、読者としてのいまのぼくは救われた思いがしています。「遠ざかる列車のひびきに/家族あわせの円居が/窓の灯をにじませる夜には/いつもかわらぬ休息がありますように」という詩行に、「橋上の人」であり続けた鮎川信夫のやさしい祈りが込められているような気がするんです。鶴山さんはどう思いますか。
鶴山 鮎川さんは六十六歲の若さでお亡くなりになったから、たまたまこの詩が遺作になっただけだと思います。詩という表現の中心に戦後詩を据えている人は、多分、「偽の革命/愚かな戦争/過ぎてしまえば幻の/半世紀は車窓の景色であった」という詩行にこだわると思います。でも「過ぎてしまえば幻」なんだから、あっさり読み流していいでしょうね。うーん、正直な詩ですが、だいぶ衰弱した詩だと思います。
鮎川信夫という作家を考える場合、詩とか評論、エッセイ、時評などの、文学ジャンル別に考えてはいけないと思います。もちろん詩人なら詩作品が一番大事。それは大前提です。でも鮎川さんの稀であり、奇妙でもあった精神の全体像を把握するためには、詩から時評までの作品をひとまとまりとして捉えた方がいいと思います。
さっき言いましたように、鮎川さんは戦争でたまたま生き残ったという意識がとても強い。ただ多くの従軍作家、戦中作家のように、戦前・戦中の皇国主義日本を、頭っから否定し批判しなかった。戦後に、コミュニズムを含む、新しい思想や理想に飛びつくこともなかった。六〇年安保、七〇年安保に対しても冷ややかだった。その理由は、鮎川さんたちの世代が、戦前に戦争はイヤだなと思いながら、声を上げなかったからです。当時すでに、プロレタリア運動、プロレタリア詩がありました。弾圧され検挙される詩人がいることを、戦前「荒地」のメンバーは知っていた。でも政治思想を表現するのが詩ではないだろうと考えていた。
鮎川さんの『戦中手記』は時代の良心の書だと思いますが、従軍に際して抵抗していませんね。あっさり入隊した。軍隊では丸一年くらい殴られっぱなしだったと書いていますが、鮎川さんはその理由を理解している。当たり前だけど、頭でっかちの文科の学生を召集しても、兵隊として役に立つわけがない。極めて乱暴ですが、日本軍は鮎川さんらのような学生を短期間で兵隊に仕立て上げる方法を知っていた。鮎川さんもそれを理解しています。兵隊になりきって何も考えないことは、楽だという意味のことを書いています。結核にならなければ、命令されるまま敵陣に突っ込んでいって戦死したはず。それは消極的であるにしろ、戦前の抑圧社会に抵抗したモダニズム詩人の自由の放棄であり、精神の死であり、敗北なんですが、鮎川さんは、そんな絶望的な状況の中でも、人間は平気で生きていられるということを学んだ。鮎川さんの人間不信は戦中の自己から生まれている。『戦中手記』は戦争を美化も批判もしていない。どっちかの側に立てば楽なんですが、そんなに単純なものじゃないよ、ということです。発表当時、『戦中手記』が注目を集め、大岡昇平の『野火』のようなベストセラーにはなりませんでしたが、同時代の人たちに強く訴えかけた理由です。
生き残り、死に損ないの鮎川さんは、戦後、ある意味戦前の「橋上の人」を改作することで文学者として出発したわけですが、個として社会に対峙するという孤独な橋の上の人の位相から、生涯一歩も動かなかったと思います。そんな人が、興味を持ち、仕事にできたのは、変わりゆく戦後社会を斜めに切ってゆく時評だけだったんじゃないかな。鮎川さんには悪いんだけど、僕は後期鮎川信夫の代表作は時評でいいと思います。鮎川信夫論を書く人たちは、鮎川さんがプロパーの詩人であり、すべて詩を中心に読み解かなければならないということに、こだわり過ぎていると思います。彼の同時代に対する誠実さは、時評でも表現されていると思います。
池上 ぼくが鮎川信夫の時評で好きなのは、晩年の『時代を読む』じゃなくて、一九六八年に刊行された『一人のオフィス 単独者の思想』なんです。一九六六年度の「週刊読売」の連載をまとめた本ですが、『時代を読む』よりもエッセイ色が濃いので、いま読んでもおもしろい。まず、「一人のオフィス」というのが実に鮎川信夫にぴったりな連載タイトルですよね。「仲間もいなければ、組織もない。大都会のまっただなかにある、たった一人の仕事場。孤独で自由な現代的オフィス。そんなところで、だれにもわずらわされずに、すきなことをすきに書けたら、というのが夢である」というのが、連載を始めるにあたっての抱負です。鮎川信夫は別に晩年になって、詩をやめて急に時評を書き始めたわけじゃないんですよね。
「あとがき」には、「しかし、もちろん、私は、この仕事をいやいや引受けたのではなかった。時とともに変り、季節とともに移っていく生きた現代社会のvintageの世界に思いきりひたってみたいという願いがないわけではなかった。この一年は、この一年の収穫によって、この一年としての意味を持つ。それは二度と経験することのできない一年である。この一年の刻印を、わが身にきざみつけておくのもわるくはないであろう。永久的なもの、不変なものを目ざす詩人なるが故にこそ、vintageの世界は別の興味をひき、これまでの批評とはちがった冒険心をかり立てるものとなるであろう」と書いています。わざわざ「vintage」っていう英語を使うところが、いかにもモダニスト鮎川信夫らしいでしょ(笑)。
余談になっちゃうけど、「あとがき」って西洋の本ではあまり見かけないですよね。「序文」はあるけど。ジャック・デリダが『散種』という本で、「序文」は「書物」に含まれているのか、いないのかというようなおもしろいことを論じていたと思うんだけど、「あとがき」ってなぜか全集に収載される時にはカットされちゃうことが多いんですよね。だから、この「あとがき」はあまり読まれていないと思います。だけど、「あとがき」には案外重要なことが書かれていたりするんですよ。
ぼくは読者が二千人ぐらいの専門誌から数十万人も読者がいる一般向けの雑誌まで、いろいろ編集してきたんですけれど、もしこの「あとがき」が「週刊読売」の本誌に掲載されていたら、編集者は絶対に「vintage」がどういう意味なのか、鮎川信夫に加筆を求めていたと思いますね(笑)。普通の読者が読んでよく意味がわからない言葉は、メジャーな媒体では必ず説明を付けるようにするんです。で、この英語の「vintage」ってどういう意味か鶴山さんわかりますか(笑)。もちろん年代もののワインというイメージがある単語なわけだけど、ぼくはよくわからなくて、大学生の頃に使っていた研究社の『日英語表現辞典』で調べました。
そうしたらね、「vintageはまた同時代(contemporaneous)の産物として人間のことも言う」って書いてあったんです。「この一年の収穫」という意味に、「同時代の産物としての人間」という意味を重ねて使っているんですよ。実はこの『日英語表現辞典』の著者は鮎川信夫の奥さんだった最所フミで、刊行された一九八〇年頃は現代英語の表現が学べる「読む辞典」として結構使われていたと思います。『一人のオフィス』が刊行されたのは一九六八年だから、もちろん鮎川信夫がこの辞典を参照したわけじゃないんですが、こういった英米圏の文化的教養が背景にあったことは間違いないですね。
「風景論」には「単調なくり返しのようで/同じ風景は二度と現れない/私一人の人生でも/同じ時は決して戻ってこなかった」とありますよね。鮎川信夫は、「日本が同じような形で占領されることは、過去にも未来にもないのであり、一回性として考えなければならない」と書いています(「疑似現実の神話はがし」)。「二度と経験することのできない一年」というのが、鮎川信夫の人生観の基底には強くあるのだと思います。
『一人のオフィス』の連載第一回の結びの言葉は「勇気をもって生きていくほかはない。」なんですが、「風景論」は「何を得/何を失うとも/到達したところから/一歩一歩あゆむほかない」と始まります。これが「橋上の人よ、/霧は濃く、影は淡く、/迷いはいかに深いとしても、星のきまっている者はふりむこうとしない。」と一九五一年の「橋上の人」で書いた鮎川信夫が三十年後に到達した場所だったように思えます。
鶴山 戦後詩が一世風靡した理由に、六〇年、七〇年安保世代の疑似戦争体験があると思います。でも鮎川さんみたいに、人間存在のあさましさを底の底まで見て、希望も絶望も安易な逃げ道じゃないかって考えた人はいませんね。
池上 詩人としての鮎川信夫、批評家としての鮎川信夫、時評家としての鮎川信夫、エッセイストとしての鮎川信夫、翻訳家としての鮎川信夫がいると思うんですが、散文家としての鮎川信夫もいますよね。一九七三年に刊行された『厭世』というちょっと不思議な本があるでしょう。随筆なのか短編小説なのか、本の帯には「鮎川信夫短篇集」って書かれていますけど……。
鶴山 私小説、大嫌いだって書いてるくせに、『厭世』は私小説じゃないか(笑)。鮎川さんを、吉本さんのような一貫した思想家として捉えちゃいけないよね。
池上 ふたりとも表現のいちばん深いところでは「詩」になってしまう点は共通していると思いますが、鮎川信夫は原理主義者ではないですね。ぼくが鮎川信夫の文章で好きなのは、小説風の『厭世』よりも、例えば猫好きの鮎川信夫が家の中で猫と隠れんぼした話を書いた「小猫との遊戯」のようなエッセイなんです(現代詩文庫『続・鮎川信夫詩集』に収載)。だけど、『厭世』を読むと鮎川信夫のことがよくわかりますね。
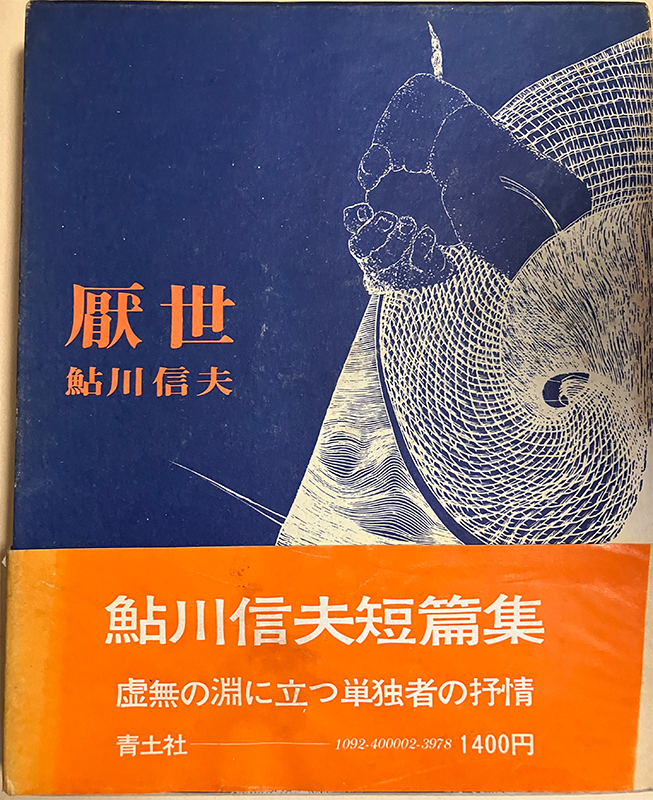
鮎川信夫『厭世』
昭和四八年十一月二十日発行 青土社
鶴山 猫好きで、晩年までずっと何匹か飼ってたみたいですね。で、表題作は、戦前の「荒地」からの仲間で、自殺してしまった竹内幹郎のことを書いています。竹内の自殺の理由はハッキリわからない。『厭世』はまあ、鮎川さんにはとてもよく合っているタイトルですが。ただ鮎川さんは、『厭世』だけじゃなく、意外と自分の来歴なんかをたくさん書き残しています。「父」という詩があるでしょう。
父なる存在そのものが
わたくしには厭わしかったのだろう
ゆっくり食物を咀嚼する口の動き
複式呼吸のいきの音
健康を気づかう父の
そんな瑣細な努力さえ
わたくしにはあさましく映っていて
面をそむけさせたのである
黙々と机に向って仕事をする父の背中に
刺すような視線をあびせて
何度、声にならない叫びを上げたろう
あなたはやがて分ってしまう何かであり
ぼくたちの間にはどんな逆転もありえないのだから
あなたは早く死ねばよい
これ以上、理不尽な感情があるだろうか
自分をこの世に存在させていることで
父を憎む
これは、父にとって
子なるわたくしの存在が心から厭わしかったことの
家族的な反映だったのだろう、と
今ならばわかっている
これ以上、合理的な感情があるだろうか
父とは半生のつきあいだったが
どんな言葉の交換もなかった
わたしくは父の書いたものを理解せず
父はわたくしの詩の一行も理解しなかった
父は黙ってこの世から去っていった
わたくしは病み衰えた父の腕に
カンフルの注射を三、四度射っただけであった
言葉の理解のとどかぬところで
ぼくたちは理解しあっていた
測り知れない深さで
世界を映す鏡に
何も映っていないときには
わたくしの顔が映るのである
子のいない冷たい歓喜に
すこし歪んだわたくしの顔が。
一九七九年発表ですから後期の詩ですが、この詩は圧が高い。珍しく「わたくし」という、正座したようなかしこまった人称を使っています。鮎川さんは小学生の頃から原稿を書いたりして、お父さんが刊行する雑誌を手伝っていた。家庭内暴力みたいな形でお父さんに反抗することはなかった。お父さんが文筆家鮎川信夫を育てたと言ってもいいわけですが、本質的には親子に「どんな言葉の交換もなかった」。
この詩はお父さんがとっくに亡くなった後に書かれたわけですが、「ぼくたちの間にはどんな逆転もありえないのだから/あなたは早く死ねばよい」という二行は、お父さんの存在が鮎川さんにとってとても重く、いつか精神的に抹殺しなくてなならなかったことを示しています。でも思いきって精神的にお父さんを抹殺しようとしたら、「言葉の理解のとどかぬところで/ぼくたちは理解しあっていた/測り知れない深さで/世界を映す鏡に/何も映っていないときには/わたくしの顔が映るのである」となった。
理解できず、嫌ってもいたお父さんを底の底まで見つめれば、〝お前は私じゃないか〟といった認識にならざるを得ない。これは鮎川さんのように、父親に反発して違う道を行った息子たちには切実に響くでしょうね。父親と考え方が違ってしまった息子たちは、ここまで残酷に書かなければ父という存在を理解できないかもしれない。良い詩だと思います。最後の二行はいらないと思いますけど(笑)。
池上 さっき本の「あとがき」には意外に重要なことが書かれていることがあると言ったんですが、『時代を読む』の「あとがき」で鮎川信夫はこんなことを書いているんです。
「放っておけば内向的にしかならない少年の私を、無理にでも時代や社会にむかって眼をひらかせたのは、私の父であった。折しも今年は、その父の三十三回忌に当っている。父は、いぜんとして突張りをやめない不肖の息子の所業を悲しむだろう。」
これは「父」から六年後の一九八五年二月に書かれた文章で、晩年になって、鮎川信夫が時評を書くようになったのはお父さんのおかげだと正直に述べているんです。吉本隆明が鮎川信夫への弔辞で「貴方の死と一緒に、戦後詩の偉大な時代が確かに終りました。それとともに幼年の日のエディプスが偉大でありうる時代が終っていくのだと存じます。いまその場所に立ってお別れの礼を致します」(「別れの挨拶」)と語ったとおり、「幼年の日のエディプス」が鮎川信夫という偉大な戦後詩人を作り出したと言っても過言ではないですし、一九八六年当時日本ではドゥルーズ=ガタリの『アンチ・オイディプス』(市倉宏祐訳)が流行していたことが象徴するように、鮎川信夫の死とともにエディプスが偉大であり得た時代も終わっていったということだと思います。ぼくらも三十七年前に「その場所」に立っていたわけですよね。
ちなみに、ぼくは大学時代に、ドゥルーズ=ガタリの『アンチ・オイディプス』を翻訳した市倉宏祐さんから原書講読の授業を受けたんですが、彼は鮎川信夫よりひとつ年下で、学徒動員で海軍に入って特攻隊の待機要員として終戦を迎えた方でした。市倉先生は上官として何人もの特攻隊員を送り出した体験を、終生自分のテーマにしていました。当時流行していたポスト・モダン系の研究者とはまったく異なる観点で、ヨーロッパの近代と日本について考えた人だと思います。印象的だったのは、「人間は天と地の間に存在する」というのが彼の人間観だったことです。零戦を操縦した体験から、人間存在を、平衡を保って飛び続けなければ生きられない存在、言ってみれば「空中の人」と捉えていたんです(『ハイデガーとサルトルと詩人たち』)。市倉先生は海軍でも飛行機乗りだったから「空中の人」で、鮎川信夫は陸軍の兵士だったから「橋上の人」であり続けたんじゃないかとぼくは考えているんですけどね。
あとね、この『時代を読む』の「あとがき」にはちょっと謎めいた文章があるんです。「週刊文春」での連載が自分の生活のリズムとなり、一種の規律になっていたと述べた後、鮎川信夫はこう書いているんですよ。
「規律は何程か自己改造の役に立つ。十七、八年前、週刊読売で「一人のオフィス」を書いた時がそうだったし、四十五年前、日本軍の真珠湾攻撃の前後に新聞社に勤めていて、軍隊に入り傷痍軍人療養所で「戦中手記」を書くまでの時期が、そうであった。この事件は、いわばその延長線上にあったと自己評価して、とり返しのつかぬ〈時間〉の言訳とするほかはない。」
ぼくは「この事件」っていうところに引っ掛かるものを感じたんです。「週刊文春」の連載が「事件」ってことはないだろうし、「とり返しのつかぬ〈時間〉の言訳」ってどういう意味だろうって。しばらく考えてみて、これはぼくの憶測に過ぎませんけれど、この「事件」は「三浦事件」としかぼくには思えなかったんです。三浦和義の「事件」をめぐって、鮎川信夫と吉本隆明が「全否定の原理と倫理」という対談で決定的に対立したことはよく知られていますよね。この文章が書かれたのは、その対談以前なんですけれど、対談の中で吉本隆明は「もう何でも言ってしまえというところに鮎川さんの表現の位置が入っていったんではないかなと思ったんです」と言っています。一方、鮎川信夫のほうは、こう語っているんです。
「あのねえ、最近一つだけ自分で変わったなと思うことに、間違いってものをやりたくなったってことはありますね。おかしな言い方だけど、とにかくぼく、間違いってことはやってないんですよ。戦争中からずっと続いて一ぺんもやったことがない。もし間違いがあったらどっからでもかかってこいと言えるくらいやっていないわけ。だけどそれには一つの秘密があって、ぼく自身が一種の受動態なんですよ。だから間違うかもしれないってとこには足を出さない。だけどそんなのちっとも感心したことじゃないということに近頃気が付いたんだよ。」
先ほどの「あとがき」には「規律は何程か自己改造の役に立つ」って書いてありますよね。鮎川信夫は「週刊文春」の連載で「三浦事件」だけでなく「戸塚ヨットスクール事件」についても積極的に発言して、批判を浴びたりしていました。鮎川信夫は「週刊文春」の連載をすることで「自己改造」をしたんだと思うんです。「とり返しのつかぬ〈時間〉の言訳」というのは、戦中から戦後ずっと「受動態」つまり「橋上の人」として「足を出さない」できたことへの言い訳という意味じゃないかとぼくは解釈したんです。そして、この自己改造は世の中や父親に対する最後の「突張り」でもあるんですよ。だから「父は、いぜんとして突張りをやめない不肖の息子の所業を悲しむだろう。」と書いたんだとぼくには思えるんです。
■鮎川信夫をどう読むのか■
池上 ところで、ぜんぜん鮎川信夫の詩を読んだことのない人が、何か読んでみようと思った時に、鶴山さんならどの詩を勧めますか?
鶴山 「橋上の人」と「死んだ男」の二篇でしょうね。「死んだ男」には「遺言執行人」が出てくる。
たとえば霧や
あらゆる階段の跫音のなかから、
遺言執行人が、ぼんやりと姿を現す。
――これがすべての始まりである。
遠い昨日……
ぼくらは暗い酒場の椅子のうえで、
ゆがんだ顔をもてあましたり
手紙の封筒を裏返すようなことがあった。
「実際は、影も、形もない?」
――死にそこなってみれば、たしかにそのとおりであった。
Mよ、昨日のひややかな青空が
剃刀の刃にいつまでも残っているね。
だがぼくは、何時何処で
きみを見失ったのか忘れてしまったよ。
短かった黄金時代――
活字の置き換えや神様ごっこ――
「それがぼくたちの古い処方箋だった」と呟いて……
いつも季節は秋だった、昨日も今日も、
「淋しさの中に落葉がふる」
その声は人影へ、そして街へ、
黒い鉛の道を歩みつづけてきたのだった。
埋葬の日は、言葉もなく
立ち会う者もなかった
情激も、悲哀も、不平の柔弱な椅子もなかった。
空にむかって眼をあげ
きみはただ重たい靴のなかに足をつっこんで静かに横たわったのだ。
「さよなら、太陽も海も信ずるに足りない」
Mよ、地下に眠るMよ、
きみの胸の傷口は今でもまだ痛むか。
現代詩がブイブイいわせてた時代は、「この詩がわからないならお前が悪い」でよかったけど、今は「わからん詩を書くお前が悪い」になってますね(笑)。それでいくと、この詩の始まりの、「たとえば霧や/あらゆる階段の跫音のなかから、/遺言執行人が、ぼんやりと姿を現す。」の「遺言執行人って誰だよ」ってことになると思います。ただ文字通り受けとるしかない。鮎川さんが遺言執行人かもしれないし、彼が遺言執行人から遺書を受けとったのかもしれない。しかし「これがすべての始まりである」は文字通りのものです。
この詩は戦死した森川義信のことを歌っているわけだけど、彼の死には「立ち会う者もなかった/情激も、悲哀も、不平の柔弱な椅子もなかった。」一人きりの死であり、怒りも悲しみも、理不尽だという不平も、声に、言葉にならない。死者は「空にむかって眼をあげ」たまま「静かに横たわっ」ている。その「胸の傷口は今でもまだ痛む」。それが森川の、戦死した者たちの遺言であり、鮎川さんはそれの遺言を執行し続けた。多くの人はそんな悲惨を忘れる、あるいは忘れようとするけどね。それ以上の解釈はできないですね。
池上 中学生のぼくが初めて鮎川信夫の詩を読んだ時には、彼が兵士だったとかいう知識は当然持っていなかったわけです。詩として伝えたいことは何となくわかった気がしたんだけど、具体的な意味を十分に理解することは、やはりできなかったですね。鮎川信夫が戦争に行ったことや、Mが森川義信であるということを知った後でも、「きみの胸の傷口は今でもまだ痛むか。」という表現に作者がどういう意味を込めているのかが、よくわからなかった。銃創だとしたら、いまでもまだ痛むわけはないし、とかね。『失われた街』を読んだいまでは、鮎川信夫と森川義信の間で生じた三角関係をめぐる出来事が、森川義信の「胸の傷口」が「今でもまだ痛む」原因になっているとか想像することもできるんだけど、今度はそういった知識が先入観になって、詩として純粋に読むことができなくなっちゃう。だから鮎川信夫の詩を、例えば彼が戦争に行ったという補助線なしに読み解けるのかという根本的な問題はあると思います。一方で田村隆一の作品は、意味を考えなくても直感的に理解できたんですけどね……。
鶴山 率直に言えば、詩としてはそれほどいい詩ではない、完成度の高い詩ではないと思います。詩の言語表現レベル、作品の完成度、完結度から言えば、田村隆一の方が上です。
池上 鮎川信夫という人の実人生、全体像をある程度把握しないと、詩もちゃんと読めませんよね。
鶴山 僕が思潮社に入社した時に、小田久郎さんから「戦後詩は鮎川信夫だ」と言われて驚いたのは、そこに理由があります。要するに戦後詩が鮎川だというのは、テキストだけからはわからない。鮎川信夫の存在感、カリスマ性は同時代の人たちにとっては決定的だったけど、それは僕らにはなかった。後から細かくテキストを読んで理解するしかなかった。
池上 戦争に行った体験を踏まえて読まなければ意味を理解することができないという点では、確かに鮎川信夫の詩は戦後詩だったんでしょうね。その意味では、ぼくは田村隆一の詩は戦後詩じゃなくて、現代詩だと思っているんですよね。
鶴山 ただ鮎川さんの、非常にまとめにくい青春性というものが、後の世代の精神を規定してしまった。それを無視すると、戦後詩の核がなくなってしまうところがあります。
僕は思考方法の基本として、二項対立的方法が意外と重要で有効だと思っています。僕らは二十一世紀初頭に生きているわけで、この時点からとっくに終わってしまった過去を振り返った時に、現代詩、戦後詩、モダニズム詩、近代詩なんかを、スパンと定義できなければならないと思います。近代詩の時代から現代詩は始まっていたんだとか、現代詩と戦後詩は一体でしょとか、現代詩とは現代書かれている詩のことで、入沢・岩成的な言葉の意味伝達性を排除した詩のことを指すわけではないんだとか言い出すと、きりがない。まず対立項を立てなければ灰色の部分はハッキリ見えて来ません。鮎川信夫が戦後詩の絶対的基盤だったと認識するのは、その意味で大事です。
ただ鮎川さんには西脇順三郎『Ambarvalia』や田村隆一『四千の日と夜』のような、詩集としての代表作はありません。吉本さんの『言語にとって美とはなにか』のような評論の代表作もない。初期に書いた数編の詩と短い散文が、その後の世代に決定的な影響を与えた。確固たる思想がなければ優れた詩は書けない、作品は強さを持たないということです。この思想のあり方は時代によって変わってゆくけど、思想という核がなければ文学表現は行き詰まるだろうと思います。
池上 はい。今回の対話の結論は、鶴山さんがいまおっしゃった、「鮎川信夫が戦後詩の絶対的基盤だった」、そして「確固たる思想がなければ優れた詩は書けない」ということでいいと思います。
あと、鮎川信夫の全体像を考える上でもう一つ言っておきたいのは、語りの人だということですね。吉本隆明もそうだと思うんだけど、この二人に共通するのは語りの人だということだと思います。二人の対談も、それぞれのインタビューや講演の文字起こしもたくさんあります。吉本隆明は書いたものはわかりにくいんだけど、講演を聴くとおもしろくてわかりやすいんです。そんなに難しいことを考えているわけじゃないんだなって、よくわかります。鮎川信夫のほうはちょっとアバウトなんじゃないかと思うところも結構あるんですけれど、語り口に魅力があるんです。特にインタビューがおもしろいですね。
ぼくがいまでも時々読み返す鮎川信夫の本は、一九八五年に刊行された『疑似現実の神話はがし』です。これは語り下ろしに手を入れたもので、文体も中途半端で語りでもなければ書いたものでもなくて、語り口や文章に魅力があるわけではないんですが、鮎川信夫という人の発想方法や考え方がよくわかります。一方で、これは手を入れて書いたなという部分は、とてもわかりにくくて、鮎川信夫独特の表現の難解さもあります。そういう意味で、とても興味深い本です。読むたびに発見があるんです。
鶴山 池上さんがお勧めする鮎川さんの散文集は『疑似現実の神話はがし』ですか。
池上 鮎川信夫全集で言うと第五巻、「時評Ⅰ」に入っている『一人のオフィス』のほか、「急いでいるのに邪魔っ気な群集め」とか「私的戦術」「遊びによる自由」など一九六八年頃から一九七四年頃にかけて書かれたエッセイですね。いちばん鮎川信夫らしい文章だと思いますね。
今回いろいろ読み直してみて、やっぱり鮎川信夫の詩は難しいと思いました。一読しただけでは、まずわかりませんね。そうとう読み込まないと、理解できたという手ごたえみたいなものは得られないんじゃないかと思います。あと、自分だったら絶対書けないなと思うような残酷な表現を用いた作品があるんですよね。連合赤軍をテーマにした「My United Red Army」とか。あるいは「橋上の人」の中の「誰も見ていない。/溺死人の行列が手足を藻でしばられて、/ぼんやり眼を水面にむけてとおるのを──」というようなイメージを読むと、やはり戦争を体験した人なのだと思います。ぼくは鮎川信夫の詩を読んでいると、時々「この詩をあなたに理解してほしいけれど、あなたには理解できないでしょう」と言われているような感じがすることがあるんですよね。でも意味や作者の意図を超えて伝わって来ちゃう激情だったり、諦め、ほのかな抒情性があったりもする。そういう意味ではピュアな詩人だとも言えるんでしょうね。
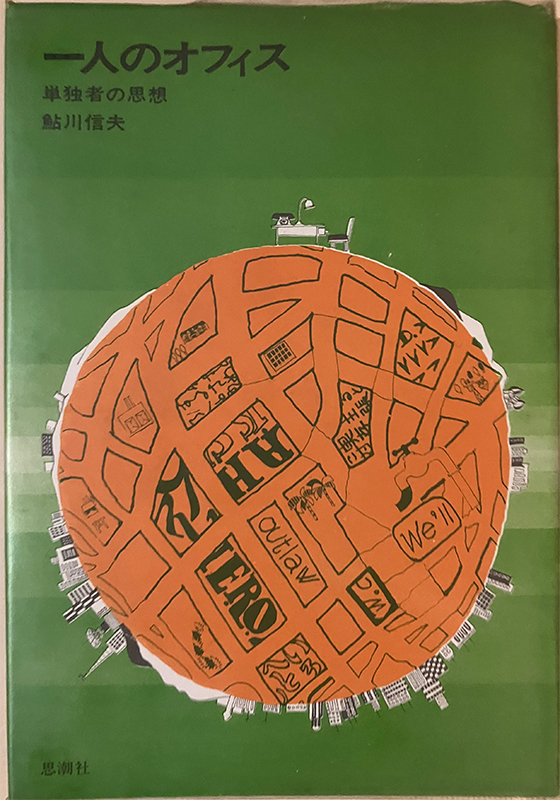
鮎川信夫『一人のオフィス 単独者の思想』
一九六八年七月十五日発行 思潮社
鶴山 鮎川さんはプロ詩人の自覚があり、テクニックもお持ちでしたが、散文もそうですが、ギュッと表現を圧縮してしまうところがあります。熱が入れば入るほど圧縮度が高くなるから飛躍が大きくなる。意味やイメージをほどよくパラフレーズすればいいんだけど、あんまり中間がなくて、緩い詩はまんま緩く書いてしまう(笑)。困った書き手でもあるんですが、詩ではなく、今池上さんがおっしゃったような、散文集を入り口にしても、鮎川さんがどういう作家だったのかは理解できると思います。
池上 現代詩文庫の『続・鮎川信夫詩集』の裏表紙に、西脇順三郎が「鮎川信夫氏の詩人としての功績は日本現代詩の発展と粛清とに最高の貢献をしたことであった」「この尊敬すべき存在は彼の全人格からにじみ出ていると思う」「鮎川の詩も評論も神秘的である」と書いています。「粛清」はただならぬ言葉だと思うんですが、どう解釈すればいいんでしょうね。
鶴山 西脇さんは、僕が知っている中で、最高に頭のいい詩人です。勘もよかった。たくさん与太話が伝わっていて、わけのわからない詩人と誤解されがちですが、すんごい切れ者です。明治元年を起点とすると、日本の自由詩の歴史はたかだか百五十年です。短歌的抒情から切れた詩を初めて書いたのが萩原朔太郎、でも思想的には弱かった。その後、欧米から最新思想と技法を輸入してモダニストたちが表現の基盤を作り、思想表現を含む詩となったのが鮎川以降の戦後詩。戦後詩がなければ入沢・岩成の現代詩はない。現代の詩は鮎川さんたちの「荒地」から始まるわけで、それは確かに過去の詩の「粛清」だったかもしれない。
池上 あっ、そうか。戦争責任論のことを言っているんですね。戦時中多くの有名詩人が詩を寄せた日本文学報国会編の『辻詩集』(一九四三年)には、北園克衛の「軍艦を思ふ」とか瀧口修造の「若鷲のみ魂にさゝぐ――春とともに」とかモダニズム詩人の作品も入っているけど、西脇順三郎は参加していないものね。『辻詩集』って軍艦を建造するための運動の一環として出版された詩集だから、瀧口修造は「若鷲」つまり特攻隊員の「み魂」に捧げた詩を書いたんです(「はげしくも炎と燃えむ/美まし國の護りとならむ」)。この時、北園克衛も瀧口修造も四十歳前後で、若書きじゃない。プロの詩人として企画に沿って書いたわけですよ。ぼくらが大学生の頃は瀧口修造といえば日本のシュルレアリストとしてすでに伝説的存在でしたから、ずいぶん後になって『辻詩集』にこういう詩を書いていたことを知って、正直ぼくは何だか騙されていた気がしました。だけど、この問題は現在でもアクチュアリティがありますよね。例えば、ウクライナを支援するための詩集を出すから詩を書いてほしいって言われたらどうするか、とかね。決して過去のこととして簡単に片づけられるような問題じゃないと思います。
しかし、「粛清」かぁ、さすがは西脇順三郎、怖い人ですね。しかも「彼の全人格からにじみ出ていると思う」とか「鮎川の詩も評論も神秘的である」とか、西脇の鮎川評自体が神秘的です(笑)。一方、鮎川信夫のほうは「師」っていうタイトルの西脇追悼の文章で「西脇順三郎先生」と呼んで、「戦争を過渡期として眺める、異邦人の眼を与えられた」と書いています。先行する世代の詩人で鮎川信夫が評価していたのは西脇順三郎ぐらいでしょうね。
今回、鮎川信夫の詩だけではなくて評論やエッセイ、時評やインタビューを読み直してみると、確かに「全人格」からにじみ出てくるものがありました。一九七二年十月九日付の「日本読書新聞」に掲載されたインタビューで、鮎川信夫は「詩の運動、文学の運動をやるなら、最低自分の人生ぐらいはとことんまで表現してみろといいたい」(「荒地とイロニイ」)と語っているんですが、その言葉を自ら実践した文学者ですね。
鶴山 鮎川さんの代表作を詩にする必要はないと思います。
池上 あと、鮎川信夫について語っている人の言葉もおもしろいんですよ。日本現代詩人会のホームページに「鮎川信夫のこと」というタイトルで、『時代を読む』が「週刊文春」に連載されていた時の担当編集者で、文藝春秋元社長の平尾隆弘さんが鮎川信夫について語った講演を、田村雅之さんがまとめたものが載っています。ちょっと引用してみますね。
「小林秀雄が「近代文学」に招かれて、戦争のことを聞かれて「僕は反省などしない。利口な奴はたんと反省してみるがいいじゃないか」と言いました。鮎川さんは「小林の啖呵は迫力がある、だけどさ『やっぱり反省しなきゃいけない。反省しない人間は人間じゃない』」ときっぱり言われました。」
これはとても鮎川信夫らしい発言ですね。「反省しない人間は人間じゃない」ということを言えるのが鮎川信夫という人だと思います。それから、ぼくがいちばんおもしろかったのは、次のエピソードです。
「吉本さんが、「毎日詩を書き続け、一〇年やれば詩人になれる」と言われました。鮎川さんは「一〇年量産したって、ダメな詩はダメ」と一蹴されました。」
このニベもない言い方がいいんですよね(笑)。もう一つ平尾さんが紹介している話で感心したのはこれ。
「赤塚不二夫さんが、「平尾さん、つげ義春の漫画は面白い?」「面白いです」「つげは書きたい時しか漫画書かない、俺は書きたくない時でも描く、だから俺はプロ、つげはアマチュアか芸術家」。鮎川さんにその話をしたら、「赤塚が、つげを認めるのは、大事なこと。いいものを認めるのは、プロの第一条件。だけどね、『これはいい詩だ、しかし俺ならこう書く』といわなければダメ」なのだと。印象に残る言葉でした。」
ここで紹介されたエピソードもそうですけれど、ぼくは鮎川信夫の発言には、いつもある種のフェアネスを感じるんですよね。
鶴山 吉本さんは、ある時期日記のように詩を書いていたからね。『初期詩篇』にまとめられているけど。『固有時との対話』はそこから生まれた。十年やれば誰でも詩人になれるっていうのは、吉本さんにとっては裏付けがあるわけだけど、まあ実際問題として、ダメな人はいくら書いてもダメだわね(笑)。ただそういうところに鮎川さんと吉本さんの考え方の違いが現れていて面白いですね。これはまた、吉本隆明編でお話ししましょう。
鮎川さんがフェアだったのはその通りだと思います。鮎川さんみたいに、最初の思想的拠点から一歩も動かなかった人は、同時代人にとっては煙たい面もあったと思います。ただ昔の「荒地」の仲間だって時の流れに応じてじょじょに変わっていったけど、それに対して鮎川さんは理解があった。吉本さんの異様な論理性はときどき社会常識からとっぱずれるけど、鮎川さんは意外に常識人ですね。
(金魚屋スタジオにて収録 鮎川信夫篇 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。
■対話への反響と要望■
「『現代詩手帖』と小田久郎氏の功罪について検討が進まれんことを望んでいます。」(T.K.)
「若山牧水がそんなにスゴイ人だとは知りませんでした。何だか詩の未来が見えたような気がして面白かったです。」(H.A.)
「最初から最後までおもしれぇし、俳句界に言及したところは痛快だった。俳人は絶対読んどけ。」髙 鸞石
「とりわけ若山牧水とジャンルの話は、「自由詩」というものを、換言すれば未来の「詩」を考える上でとても刺激的でした。課題は、では自由詩は何をもって評価の基軸とするか (すなわち、今日において美学はありうるのか) ですが、それは次回以降で語られると期待しています。」萩野篤人
「鮎川信夫の詩「橋上の人」は未完の「架橋」であることに気付かされた。「架橋」という営みは、本質的に未完だ。しかしその営為こそが未来へと開かれる。戦後詩は置き去りにされたようにみえるが、その精神性は潰えることはない。橋上の人よ、と自らに呼びかける鮎川の輻輳する声に共鳴。画期的対談。」萩野篤人
「対談2回目もたいへん面白かったです。
詩が何を表現しようとしているのか、
詩人本人もうまく詩言語に昇華できないけれども、
そこに何か意味のある芯を伝えよう、表現しようという意思が
鮎川信夫の詩にはありますよね。
池上君のいうように、戦前の橋の上で景色を見ている自分に
戦後の橋の上の同じ場所からまったく変わってしまった風景を
見ている自分が、戦前の自分に対して「橋上の人よ」と呼びかけているんじゃないかと思います。
戦前の自分は、今の風景の向こう側の空の中に透けて見えてるかもしれないですね。
同じ空間に2つの時間が流れてるんですね、きっと。
または、風景の向こう側にレイヤーのように昔の同じ空間が重なっていると
いいますか。
呼びかけだけではなくて、そこには戦前の自分に対して伝えたい何かが
あって、それは詩全体で言うしかないんだけれども、
やっぱり、今は風景だけでなく、すべてが戦前とはまったく変わってしまったんだという
決別と覚悟のようなもの、詩も今までの伝統や流れから断絶して
まったく違う立脚点に立たないといけないんだ、というようなゴツゴツした感慨の塊
が詩になってるんじゃないかと思います。」林常樹
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


