 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十一、『三四郎』第一章 リビドー全開!三四郎(上編)
とにもかくにも、まずは第一の容疑者ともいえる主人公、あるいは視点人物である三四郎に寄り添うかたちで冒頭から「読み直し=体験し直し」てみることとしよう。
「なに、気取った報告書書いてんのよ」
いずれ提出せねばならない報告書の書き出しを準備しておこうと、録音機に向かってつぶやいていた俺を、高満寺手弱女がつまみ上げた。文字通り、俺のポロシャツの襟首をつかんで持ち上げたのだ。
「おいおい、勘弁してくれよ。俺はのら猫じゃないんだ」
「さっさと読み始めなよ」
「へいへいほー」
俺たちは、VRを経由して、夏目漱石『三四郎』にダイブインしている。すでに二、三度ほど「読んだ=体験した」ことのある物語だったが、今回は探偵の目を持って、犯人の痕跡を探しながら追体験することになる。なぜ探偵かというと、ようやく、俺がこの会社に採用された本来の役割を果たす機会が訪れたというわけだ。「原典テクスト過剰親和性」というのが、本来なら不可能なVRの原典に直接接触できるという俺の得意体質につけられた診断名である。これはただ単に原典の文字をいじくれるという意味だけではなく、原典の無意識層にも自然と触れられる能力を含んでいる。いわゆる「行間を読む」能力と呼ばれているやつだ。それを俺は読書の訓練を積んで修得したというわけではなく、元々の体質として持っているということになる。今回のような事件では、作品を読み解くという解釈行為そのものが、隠された犯人像を探し当てるという探偵行為となる。
すでに説明したとおり、VRでは眼前に現れる文字を読むにつれて、それに連動した共感覚が刺激を受けて、文字が五感を刺激し、映像体験だけではなく、音響や匂い、味や触覚までも伴った体験として全身で文字が体験されることになる。
俺たちは体験もしつつ、同時に文字の意味にも十分意味を払うという二重意識状態を維持するようつとめながら、『三四郎』にチューンインした。
a:異性の味方
まずは、書き出しの一行。
『うとうととして目がさめると女はいつのまにか、隣のじいさんと話を始めている』
そう、この物語は、九州から東京へと上京する途中の汽車のなかで、うたたねをした三四郎がこんな風に目覚める場面から始まる。当然のことながら、俺たちは同時に汽車に乗り合わせてもいる。俺は三四郎の目線を通して、手弱女は客観的に全体を見る目線で。目線といっても、ただ読んでいるのではない。体験しているのだ。汽車の揺れも、車内の匂いも、乗客たちの気配も、俺たちにはびんびん伝わっている。
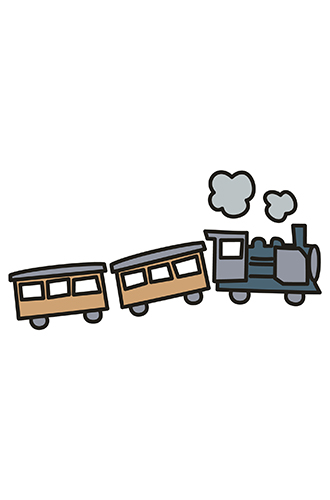
「まずこの一行は非常に意味深だよね」
さすがの書き出しだなと俺は思う。でも、脳味噌筋肉女であるところの高満寺手弱女には、その機微がいまいちわからないらしかった。
「どういうこと」
かわいらしくもなく、首を傾げて尋ねる。ああ、もっとかわいい助手が欲しかったと、俺が心の底から思うのはこんな時だ。すばらしい解説を展開する俺、尊敬の眼をうるうるさせて俺を見つめる美少女。そんな絵が欲しかったのだ。だが、いま俺をぼんやりした目で見つめているのは、筋肉の塊に埋め込まれたうろんな眼球でしかない。
「ほらこの物語の始まる前は、『うとうとして』している。つまり三四郎には意識がない、って感じが演出されてるわけだよ。起動スイッチが押されたロボットみたいに、物語の始まりとともに、三四郎の意識は目覚めるんだ。まるで、白紙状態みたいにね。三四郎という主人公が、まだ現実に触れていない、それゆえ汚れっちまっていない存在として提示されるんだよ」
そうかな、と高満寺は不満そうな顔をする。
「でも、『女はいつのまにか、隣のじいさんと話を始めている』って続くわけだから、三四郎はうとうとする前から、少なくともこの女のことは意識してわたけよね」
「うん、三四郎の目線は女を中心に見ているからね。ていうか、この小説全体を通して、基本三四郎は女のことしか考えてないんだよ」
そうなのだ。通常の「読書」のレベルでは気がつきにくいのだが、VRのかたちで三四郎の目線を追体験してみると、なんというか三四郎の目線はけっこうあからさまにいやらしい。二十三歳というリビドー全開の年齢を考えてみると、まあわからなくもないが、よく言われる青春小説とか教養小説の主人公とはちょっと思えないふしがある。読書=体感としてはむしろ、けっこう悶々小説だったりするのである。
たとえば、京都から相乗りになったこの女について、『乗った時から三四郎の目についた』とある。汽車に乗って、三四郎が物色しているのは女の姿だったということだ。もちろん、九州から山陽線に移ってだんだん京大阪へ近づいていくにつれて『女の肌が次第に白くなるのでいつのまにか故郷を遠のくような哀れを感じていた』三四郎が、九州色の肌をしたその女を『異性の味方』のように感じたせいだと一応説明はされている。
「汽車の女を、三四郎は九州に残してきた女と比較するわよね」
ひとこと付言しておこう。VRで読者=体験者が得る「体験」は各人各様である。つまり、それぞれの個人の内部で、これまで大脳辺縁系の海馬や側頭葉の周辺に蓄積した記憶や体験というフィルターを通し、五感をフル動員した体験が創出されるからだ。その意味で、同じ映像を皆が一斉にみる映画やテレビとは大きく異なっている。つまり、三四郎も、爺さんも、汽車の女も、故郷に残してきたお光さんも、それぞれにおいて言葉が喚起した容姿、声音、体臭などを持った存在としてイメージされることになる。ちなみに、俺のイメージのなかでは、汽車の女は往年の名女優若尾文子を色黒にしたような容姿で現れた。
「そう、『三輪田のお光さんと同じ色』だという。つまり、肌が黒いわけだ。実は、この小説のなかでは、肌の色の問題は意外と重要だったりするから要注意だよ。そして、この女を媒介として、九州ではうるさいと思っていたお光さんを『こうしてみると、お光さんのようなのもけっして悪くはない』などと上から目線で再評価したりしている」
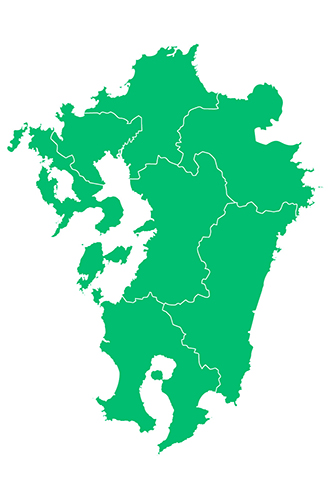
「そうよ、女を上から目線で品定めしてるのよね。なんかいやな感じ。そのあともういっかい汽車の女と比較して、お光さんをまた蔑んだりするでしょ。おいごるあぁ!」
巨漢が吼えた!
「てめぇ三四郎、いったい何様なんだよお前ぇぇぇぇぇ!!!!、・・・・って感じよね、てへっ」
いやほんま、怖いって、そんな凄んだら。
でもその後の、「てへっ」の方がもっとキモイっつうか、キツいっつうか、別の意味でコワいけど。
だけどまあそうなのだ、汽車の女に関して三四郎は『ただ顔立ちからいうと、この女の方がよほど上等である。口に締まりがある。目がはっきりしている。額がお光さんのようにだだっ広くない。なんとなくいい心持ちにできあがっている』とかいっている。当時としてはエリートであった三四郎の、強い自意識が伺われる場面でもある。なにしろ大学進学率が一%にも満たない時代に、当時日本随一の大学であった東京帝国大学の学生とならんがために上京する途上にある三四郎であるから、彼の内面にはまず、そうした期待がもたらす「根拠のない」エリート意識がすでに膨らんでいたというわけだ。
「この小説を体験して、三四郎になりきってみた読者は、女の尻ばかり追いかけることになるんだな。とにかく三四郎は女のことを見まくる。『三四郎は五分に一度ぐらいは目を上げて女の方を見ていた』『じいさんが女の隣へ腰をかけた時などは、もっとも注意して、できるだけ長いあいだ、女の様子を見ていた』ってな感じでね」
「要約しちゃうと、電車の中で三四郎はとにかく、ひらすら、そしてひたぶるに女を見ていた。そして、九州の女のことも同時に思いだしていた。冒頭はそれだけなのよね」
「ホルモン全開の青春ってわけか。ちょっと暑苦しいな」
「でもそれを、漱石はさらりと軽く書いているわよね。文体の妙というか。そこがすごいと思うわ。VRで体験しなければ、するする読めちゃうから、このもんもんとした暑苦しさはわからないようになっているもの」
「うん、そうだね」
というわけで、三四郎はまずエリート意識の塊にして、頭の中は女のことでいっぱいのもんもん野郎として登場するのである。かなり爽やかさからは遠いやつだよね。第一印象としては。
b:日露戦争
その女が、向かいの席の爺さんと話し始めたので、三四郎はその会話に耳を傾ける。
「ここってさ、二人の会話が、時代背景を導入する仕組みになってるわけよね」
ここも漱石のうまいところである。さりげない会話のようでいて、読者にはその時代がどういう時代だったかをきっちり振り返らせる仕組みになっている。
「そうそう、女は広島から四日市の方へ帰郷する途中なんだよね。京都で子供に玩具を買ったっていってるから、子供をおいて出稼ぎに行ってたことがわかる。それで、この女には夫があるわけだけど、広島の呉で働いていたのが、戦争に取られて旅順に行った。戦争が終わって一度は戻ってきたけれども、また金儲けのために大連に出稼ぎにいっている。とまあそういう境遇であるらしい。ところが、半年ほど前から、その夫から手紙も金も来なくなって安否も知れないという」
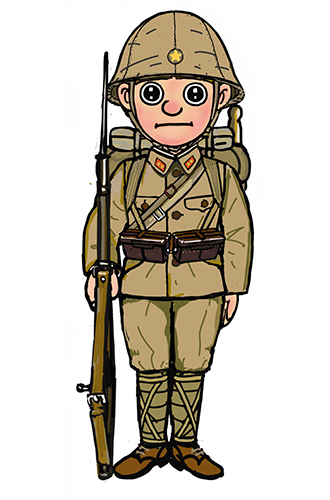
「つまり、日露戦争従軍の後、日本が租借権を獲得した大連に渡ったということよね。日本は大連を貿易都市として発展させようとしてたから、道路や鉄道などのインフラ整備を急いだ。そのための労働力として出稼ぎに行ったことがわかるわね」
正直に断っておくが、こうした知識は、実は俺たちがあらかじめ持っていたものではない。VRでは、読み方や意味のわからない単語、背景を知りたい部分は「蘊蓄」ボタンを押せば、簡単に読んでいる箇所や単語に関しての情報を表層レベルから、深層レベルまで各自で選んで探ることが出来るしくみになっている。つまり、辞書やウィキペディアレベルの情報から、事典レベル、専門家レベルまで、自由に深めることができるというわけである。これは、意味のわからない用語や単語でつまづいて、イメージ化、五感体験化が阻害されるのを防ぐためである(むろん、訳のわからない部分を、そのままに体験することで、本文とは逸脱したものを楽しむという読み方=経験の仕方を好む読者=体験者は、このボタンを押さなければよいだけの話である)。
「女の話し相手である爺さんの方は、『旅順以後急に同情を催して、それは大いに気の毒だと言い出した』とある。つまり、日露戦争に話が及ぶに至ってようやく、自分の身内の問題と話題がつながったんだよね。そして、爺さんの息子が日露戦争で戦死したってことがわかってくる」
でも、この部分に俺は少しばかりひっかかりを感じた。読んでいて=体験していてなんだか、脱臼したような落差、ついていけないと感じる唐突さがあるからだ。
「この後の爺さんのセリフ、ちょっとつながりが変じゃないか?」
「そう?」
「うん、ほらこのあたり。最初は『いったい戦争はなんのためにするものだかわからない。あとで景気でもよくなればだが、大事な子は殺される、物価は高くなる、こんなばかげたものはない』ってあるだろ? つまり、最初は戦争を批判してるわけだ。ところが、そのすぐ後で『世のいい時分に出かせぎなどというものはなかった。みんな戦争のおかげだ』と今度はいきなり戦争を肯定し始めるんだよ。そして、『なにしろ信心が大切だ。生きて働いているに違いない。もう少し待っていればきっと帰ってくる』と女を励ます言葉につなげている」
「批判が本心で、肯定は女の気持ちを思ってのことかもしれないわよ」
「そうだとしても、この批判から肯定への変化はあまりにも唐突な感じがしないかい? もしかしたら、ここにはすでに帝国主義思想による『内なる検閲』が働いているのかもしれない、なんて俺は思うんだけどね」
「どういうこと?」
高満寺は、ほんとうにわからないという顔をした。でもそれは仕方がないことだ。三段論法で説明するならばこうだ。一、筋肉は思考しない。ニ、ところが高満寺の脳みそは筋肉でできている。三、それゆえ、高満寺は思考しない。ってな感じだから。
「つまり、自由にものがいえない時代の予兆みたいなのを漱石は感じていたのかも知れないってこと。息子を戦争で殺されたことを語るうちに思わず本音が出てしまった爺さんが、ためもなく転調もなく、いきなり続くせりふでそれを撤回しちゃってるわけだから、ここには無意識の働きみたいのがあるような気がするんだよね」
「けっこう血なまぐさい時代だったのね」
「うん、そこへと向かっていこうとする時代でしょ。ロシアの南下政策と日本の満州進出の意図がぶつかったってことは、すでに植民地主義を機軸とした、帝国主義の時代だったってことだし、朝鮮総督府なんて明らかに植民地政策だからね。さっき出てきた大連だって、満州国建設の足がかりとなった地なわけだし」

「さりげなく、そんな時代背景を爺さんと女の会話で匂わせたってわけね」
「そして、そんな会話を三四郎に聞かせる奇妙な移動空間が舞台になっているというおもしろさもある」
「鉄道ね」
「そう。この冒頭で三四郎が乗っている東海道線や、九州から出るために乗ってきたであろう九州鉄道はいずれも明治二〇年代に出来たばかりのものなんだ。そして、日清、日露の戦時には物資や人員が鉄道で広島に輸送され、そこから船で戦地へと送り出された。女の夫が旅順に赴く前、『長らく呉で海軍の職工をしていた』というのは、このこととつながる。つまり、広島は当時戦争のためのターミナルだったわけだ。そして、鉄道はこのターミナルと、東京をはじめとした国土の各地をつなぐ重要な輸送機関だったことになる」
「日露戦争が終わってようやく、一般の民衆に鉄道が解放された時期が、この小説の時代ってわけね」
そうなのだ。だから、三四郎が鉄道で九州から東京まで移動するというのは、帝国の周縁から中心へと主人公が移動することを意味すると同時に、日露戦争という大きな出来事の記憶をたどるということをも意味していることになる。国民国家として世界の列強に互していこうと意気込む日本という国土の広がりを、鉄道による縦断が示しているともいえる。
(第11回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










