 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十一、『三四郎』第一章 リビドー全開!三四郎(中編)
俺は「地図」モードで、当時の日本を覆っていた列車網を確認した。三四郎が今いる位置が、青い点で示されており、九州から辿ってきた行程が黒い点線で示されている。さらに、これから辿っていく東京への経路が、赤い実線で描かれている。VRには、薀蓄以外にも、地図モード、年表モード、物品カタログモード(小説内に出てきた物品、ファッション、髪型そのもの、あるいはその類似品を見ることができるし、物によっては購入することもできる)、さらに往年の動画サイトから引き継いだ「つぶやきモード」などもある。つぶやきモードではその時々での自分の感想や意見を呟いていくことができる。
c:同衾事件
「そして、ふたたび三四郎と女の関係に話が戻っていくのよね」
「そう。爺さんが降りてから、三四郎は弁当を食うんだけど、便所に立った女の姿をここでも注視してるんだよね。『三四郎は鮎の煮びたしの頭をくわえたまま女の後姿を見送っていた』んだからね」
「そして、弁当事件が起こる」
「そう、食べ終わった弁当の折りを三四郎が窓から投げたところ、窓から顔を出して外を見ていた女に弁当の汁かなんかがかかるわけだ」
「三四郎はあやまり、女は『いいえ』と答えながら、更紗のハンケチで顔を拭く。三四郎は自分が食ったものの入れ物に残った汁をかけたわけだから、間接的に女に〈唾をつけた〉ってことになる。体液をかけたって考えると、そこには当然性的なニュアンスも含まれているんじゃないかな」
実際これをきっかけとして女が三四郎に話しかけることになる。終点の名古屋についたのは夜で、女が『一人で気味が悪いから』と宿屋への案内を三四郎に頼むという流れになる。
「たぶん、三四郎がらみで一番有名なエピソードよね」
「うん、同衾事件ってやつだ。宿屋について『上がり口で二人連れではないと断るはずのところを、いらっしゃい、――どうぞお上がり――ご案内――梅の四番などとのべつにしゃべられたので、やむをえず無言のまま二人とも梅の四番へ通されてしまった』となる。さらには『下女が茶を持って来て、お風呂をと言った時は、もうこの婦人は自分の連れではないと断るだけの勇気がでなかった』となしくずし」
「ここは三四郎の心境に寄り添って書いてるわけだけど、あきらかに意志的な無作為だよね、これ。いくら『のべつにしゃべられ』ようとも、『お風呂を』といわれようとも、はっきりとした意志があれば、別室でと頼むことはできたはずなんだから。三四郎の側にある種の下心というか期待があったのは否めない気がするな」
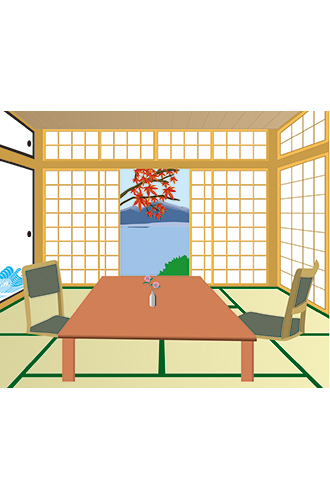
「まあ、それは女の方も同様だけどね」
「そう、女の方はむしろ積極的に期待していたとも考えられるよね。だって、三四郎が風呂に入っていると、『ぎいと風呂場の戸を半分あけ』て、『例の女が入り口から、「ちいと流しましょうか」』と聞くわけだもの。さらには、三四郎が断っているのにも関わらず、女は入ってくる。『そうして帯を解きだした。三四郎といっしょに湯を使う気とみえる。べつに恥ずかしい様子も見えない』」
「確信犯だね」
「そう、女は最初からその気だったわけだよ。いつからかはわからない。汽車の中で三四郎が自分を舐めるような視線で見ていることに気付いていたからかもしれないし、弁当の汁をかけられたことが原因かも知れない。あるいはほんとうに宿を探してもらうだけのつもりだったが、三四郎が自然な流れのように同室の部屋を取ったことで心を決めたのかも知れない。とにかく、なるほど女の側には確かに度胸があるわけだよ」
「けれども、三四郎はその逆のどっちつかずなわけね。無意識では欲望をたぎらせながら、意識のレベルではそれを受け入れられずにいる。どっちつかずっていうか、踏み出せない感じよね」
「うん、女が風呂に入ってくると『三四郎はたちまち湯漕を飛び出し』てしまうわけだからね。それでいて、宿帳には自分の妻として名をしたためてしまう。こっちでは無意識の欲望の方になびいているわけだ。意識でそれを拒む強い意志があれば、その時点からでも、自分と女は他人であるから部屋を変えてくれと頼むことはできたはずだもの」
「布団は一枚しか敷いてくれない。それを蚊帳いっぱいに敷かれてしまう。さすがにここでは布団は二枚必要だと三四郎は食い下がるものの、相手にされずに終わる。外で寝ようかとも考える三四郎だが、『けれども蚊がぶんぶんくる』というのを口実として、蚊帳のなかに入る。ここでは、無意識の欲望の側が状況を利用しているわけだ。ところが、蚊帳のなかに入ってしまうと今度は意識の方が抵抗する。蚤よけの工夫だといって、布団をぐるぐる巻いて、真ん中にしきりを作り、自分は西洋手拭いを敷いた上に寝る」
そう、無意識と意識が完全に齟齬してしまうわけだ。強く意識し欲望しながら、そちら側へと踏み出すことが出来ずに終わる。性的な他者を強く欲しながら、その他者を恐れているということもできる。女は三四郎にとって「謎」なわけだ。
「だから、翌日別れ際に一発かまされちゃうのよね」
「そう、三四郎の顔をじっとながめていた女が『やがておちついた調子で、「あなたはよっぽど度胸のないかたですね」と言って、にやりと笑』うんだ。それで三四郎は『プラットフォームの上へはじき出されたような心持ち』がしてしまう」
「ガッビーン!って感じよね。そんな二十三歳の夏なわけね」
そう、宿帳に記した年齢から、三四郎が二十三歳であることは、読者に明確にされているのである。
d:二十三
「三四郎の年齢はけっこう重要だよね。『三四郎』っていうタイトルは当時としても変わった名前だったらしいんだ。なぜ、こんな奇妙な名前を漱石は主人公に与えたのか? それは、この小説は主人公が二十三歳から二十四歳になるまでを描いたものだからだという説がある。二十三歳から二十四歳へと越境していく、つまりは、二十歳をすぎて三年目から四年目への時間のなかを成長しながら移動していく主人公のイメージがそこには込められているっていうわけだ」
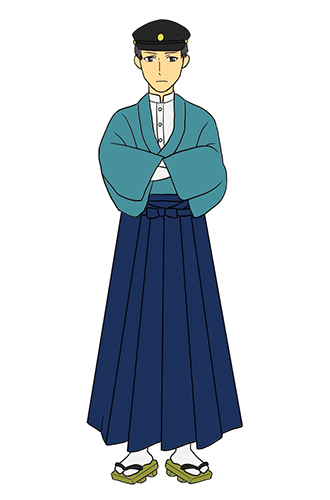
「ちょっとこじつけっぽい気もするわね」
「まあね。それから、今の感覚からすると、二十三歳で大学入学って遅いって思うけど、当時は尋常小学校四年、高等小学校二年、中学校三年、高校五年というのがふつうだったから、二十歳で入学するのが普通ってことになる。さらに、一九五〇年代くらいまでの小説に記載された年齢は数え年だから、早生まれだった場合など今日の数え方だと二歳足すことになって二二歳となる。一年浪人しての入学と考えれば、普通だったわけだし、実際漱石自身が二三歳で大学に入学したという事実が背景にはありそうだな」
「でも、ほかにも二十三って数字が出てくるわよね」
それを聞きつつ、三四郎になっている俺は、鞄のなかから適当に本を取り出す感覚を共有する。外部の視点を採用している高満寺は、そんな三四郎を作品内には描かれていない乗客の目で見ているはずだ。三四郎が適当に本のページを開く。
「それが、ベーコンの二十三ページだってわけだ」
ベーコンって言っても、当然食い物なんかではない。塩漬けした豚肉を燻製にしたものではなくって、ルネサンス期のイギリスの哲学者フランシス・ベーコンの著書のことである。
「ええ、女の一言で動転した三四郎は、女が去ったあと、電車の中で気をまぎらわそうと、適当に本を一冊取り出すのよね。それがベーコンの論文集で、読んでも理解できないその二十三ページを眺めながら、頭の中では女のことを考えているわけよね。『元来あの女はなんだろう。あんな女が世の中にいるものだろうか。女というものは、ああおちついて平気でいられるものだろうか。無教育なのだろうか、大胆なのだろうか。それとも無邪気なのだろうか。要するにいけるところまでいってみなかったから、見当がつかない。思いきってもう少しいってみるとよかった。けれども恐ろしい。別れ際にあなたは度胸のないかただと言われた時には、びっくりした。二十三年の弱点が一度に露見したような心持ちであった』と理解できないものを前にした戸惑いを露わにする。さらには、『教育を受けた自分には、あれよりほかに受けようがないとも思われる。するとむやみに女に近づいてはならないというわけになる。なんだか意気地がない。非常に窮屈だ』とかいって、このままでは女に近づけないままであろう自分に窮屈さを感じもしているわ。生身の女を前にして、どうしてよいかわからない自分にもどかしい思いを覚えているわけよね」
「でも、突き詰めない。ごまかしちゃうんだよね。自分を」
そうなのだ。この突き詰めることなく迂回して逃げるというのが、三四郎の特徴でもありダメなところでもある。
「つまるところ、ベーコンの哲学に関しては、『知は力なり』というのが、そのエッセンスとして知られている。百科全書の元にもなった知の方法論でもあるわけだよね。つまり、これまで三四郎は知識を蓄積して「力」を得たと思っていたのに、故郷を出て見知らぬ女、それも無学な女、生身の身体をさらしている現実の女を前に己の「知の力」がまったく無力であることを痛いほど悟らされたという事実が、この対比で明らかになるわけだ」
「それはそうかもしれないわね。『知は無力なり』ってわけね。でも、三四郎はそこまでの自己認識にもいたらないわけよね。そのベーコンだって実のところは、読んでもわからない本なわけだもの。なんていうか、VRで体験してみると、三四郎ってのはけっこう浅はかっていうか、思考しないのよね。たとえば、すぐに妄想に逃げる癖があるでしょ? このときもすぐに『これから東京に行く。大学にはいる。有名な学者に接触する。趣味品性の備わった学生と交際する。図書館で研究をする。著作をやる。世間で喝采する。母がうれしがる』なんて実に浅はかな未来図を描いて、『大いに元気を回復』してしまうんだもの。つまり、これから自分は知識を蓄積して、ほんとうの知の力を得る。そうなれば、さっきの女なんかもう怖くはないのだと、単純に、そして強引に自分を納得させてしまう始末なわけよ」

「そして、この場面で、そんな『知の力』を体現した自分の未来の理想像ともいえる男の視線を三四郎は再び感じるわけだね」
まあ、実際にはこの人物は世に出ることを拒んでいるので『著作をやる』以降は、あえて達成していないのだけれど、それもまた三四郎の描く未来図の容易ならざることを暗示しているともいえるわけだ。
「それが、筋向かいの席に座った、髭を濃くはやした『面長のやせぎすの、どことなく神主じみた男であった。ただ鼻筋がまっすぐに通っているところだけが西洋らしい』と描写される広田先生というわけだ」
「神道という純日本的なものにつながる神主の顔に、西洋風の鼻をつけているという描写はおもしろいわ。西洋的なものを懸命になって接ぎ木しようとしていた当時の日本のアカデミズムの比喩として絶妙だともいえるわね」
俺たちは、それぞれに広田先生の容姿を思い浮かべて失笑した。
「とはいえ、この場面ではまだこの人は広田先生ではない。三四郎は勝手にこの人物を中学教師だと決めつけてしまうからだ。ここにも、三四郎の上から目線というか、どうしようもないエリート意識がにじみ出ている。そして、自分と同じ三等客室に乗っているからたいしたものではないと決めつけ、最終的にはこれくらいの人物は東京に行けばいくらでもいると決めつけて名前すら聞かずに別れる。それどころか、自分がこれから東京帝国大学学生になるということを、尋ねてこないことにいらだちを覚えすらしている」
「熊本の高等学校の生徒だったけれど、『しかし・・・』と、三四郎はあえてためを置くのよね。そんでもって、いよいよこれから東京で大学生になるのだということを言おうとして、やめちゃう。それは、髭の男に、興味を抱かせる作戦だったわけよね。でも髭の男は突っ込んでくれない。あえて突っ込みの機会を作ってあげたというのに、髭の男と来たら『「はあ、そう」』としかいわず、それ以上詮索してくれないわけよ。代わりに三四郎の前に眠っていた男が『「うん、なるほど」』と寝言で気付いてくれるだけっていうのが笑えるわよね。これははやり三四郎の強い自意識への風刺ととるべきでしょうね。彼の浅はかなプライドなんか、寝言レベルの対応で十分なものでしかないってことよね」
そんなことを話すうちに、列車は豊橋に停車した。さっきの眠っていた男は、眠っていたはずなのに『むっくり起きて目をこすりながら降りて行った。よくあんなにつごうよく目をさますことができるものだと思った』とあるように、この男は眠っていても現実としっかりリンクしていることがほのめかされている。つまり、三四郎が口にしなかった自負は、やはり現実レベルでも大したものではないということがわかるわけだ。
(第12回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■






