 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
九、『不確定な彼女』
翌日の深夜二時に叩き起こされたとき、当然ながら俺は激しくアドレナリンを分泌し、睡眠不足もなんのそのと激烈に起っきした。
「来たか、ついに」
大事件の予感に武者震いする読解力探偵! 一人で盛り上がる俺に、寝ぼけ顔の高満寺手弱女は哀れむような眼をむけた。
「ふああ、悪いけどあんた一人で行ってくれる」
「え、なんでだよ。あらゆる事件に俺らはペアで立ち向かうことって、社の規定にも」
「書いてあるけどさ」
「それにあれだろ。今回のは相当に」
「ええ、相当にくだらない事件よ。くだらない作品内のね」
詳細を聞いて俺は激しく落胆した。現場は、いわゆる聖典文学が収納されているキャノンと呼ばれる最深部ではなく、いずれは聖典入りが有望視されているセミキャノンと呼ばれるその次の層でもなく、とりあえず今はやっている文学が貯蔵されているエンタメと呼ばれる層ですらなく、誰が読むともしれず、いつ消えるともしれない泡沫的な作品がごちゃごちゃと放り込まれているジャンク、あるいはダストボックスと呼ばれるもっとも浅い層の作品内だったからだ。
「ええっ、誰のなんて言う作品?」
「萬恭作の『不確定な彼女』」
「はあ? それ誰、そしてどんな作品?」
聞いたこともなければ、どこかでちらりと眼にした記憶すらなかった。この業界にいる以上、通常の人よりはかなり多めにいわゆる「読書」体験を積んでいるし、常に文学界の動向にも眼を光らせているつもりである。人気のある書物から、これから注目されそうな作品まで、まずねらわれる可能性のある作品は一応押さえている。
けれども、その作者と作品に関しては、完全なる初耳であった。もう一度作者名と作品名を言えといわれても、言葉に窮してしまいそうな感じだった。
「泡沫だよな、それ」
「ええ、おそらく自費出版の投稿作品だと思うわ」
「じゃあ、ほとんど情報はないんだな」
「ええ、でも一部でちょっと人気が出つつはあるみたいよ」
「へえ、それなりにおもしろいのか」
「いいえ、逆よ。まったくわけがわからないんだって。ミステリみたいな書き出しで、ミステリだと思って読み始めたらいつの間にか官能小説になってて、おおっこれは拾いものかって興奮しかけたところで、いきなりすべてがギャグになり、ええって戸惑いながら苦笑しているうちに、わおって感じの冒険小説となり、冒険がクライマックスに達しようというところで、不意に主人公の頭の中で思弁的な哲学的問答が延々と繰り広げられはじめ、気がつけば主人公はエイリアンにアブダクトされて宇宙船の中にいるというSF的展開へと移行し、っていう風に、ジャンル分け不能で、もうわけがわからないみたいよ」
「なるほど。そんなのVRで体験したら」
「そうね、ちょっとしたジェットコースター的体験になるわね」
予測不能の楽しい眩暈というわけか。それはそれで、新しいともいえるが、しかし、なんでそんなものにわざわざ侵入して手を加える必要があるのだろう。
「で、どういうイタズラだ」
「主人公の名前が坂野史泰(さかのふみやす)っていうんだけど、それが勝手に書き換えられたっていう話よ」
「じゃあ、一括変換で解決だな」
どう書き換えられたのかはまだわかっていないらしい。とはいえ、現場に行けば一目瞭然だろう。俺のような能力者になると、このもっとも浅い層への潜入はまさに朝飯前である。
「じゃあまあ、さくっと終わらせて寝させてもらうわ」
「よろしく、ふわああ」
って感じで俺たちは別れ、俺は一路きわめて残念な文学がごちゃごちゃと放置されているダストボックス、通称「ゴミ箱」へと潜り込んでいった。

「セキュリティも何もあったもんじゃないな、こりゃ」
この浅さだと、潜れる人も多いのだ。けれども、あんまりくだらない作品ばかりだから、手を加えても誰も読んでくれない。だから、誰もイタズラなんかしようっていう気にもならない。そういう言ってみれば書き捨てられた作品の墓場なのだ、ここは。
「まったく、なんなんだこの物語は」
俺はたしかに目眩を覚えかけていた。なぜなら、筋がもう破綻しまくっているからだ。冒頭で、主人公坂野史泰は、目の前で親友の真野明策が殺されるのを目撃してしまう。
「どうも元気がでない」
という真野を地元の医院に連れて行ったところ、
「じゃあ、栄養剤を注射しときましょう」
といって、医師に毒を注射されてしまったのだ。目の前で大笑いしながら「天国が見える。天国が来た。天国はこれかあ」と叫びながら倒れる真野。
「しっかりしろ!」
助け起こそうとした坂野史泰は、不意に自分が女医や看護士たちに包囲されていることに気がつく。小さな医院だというのに、看護士たちの数がやたらに多い。
「さあ、こっちにいらして」
「しかし、俺の親友の真野が・・・」
拒みながらも、坂野史泰はずるずると大勢の女性たちに引きずられてベッドに押し倒され、服をはぎ取られる。着くずした白衣のままの着エロ的艶姿の女医や看護士たちが次々と襲いかかってくる。乱交パーティー的な快楽の渦に飲まれていく坂野史泰。ところが気づけば、女医や看護婦が手にしているのはノコギリ、糸ノコ、包丁、チェーンソーなどの切断器具である。
「な、な、な、何をするんです」
恐怖に顔を歪める坂野史泰。
「決まってるじゃない。こうするのよ」
ウィーン、ギーコギーコ、キコキコキコ、バシンバシン。切断音が響き、血しぶきでベッドは真っ赤に染まる。バラバラに解体された作家之死体に加工を加える女医と看護士たち。作家之死体? あれ、主人公の名前がおかしなことになってる。
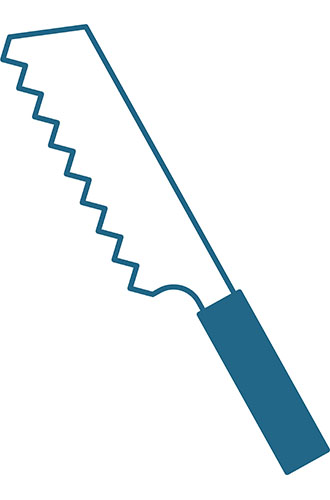
「このほうがいいんじゃない」
「そうね。でも、眼はこんな感じがいいわ」
「指はね。こう繊細で細長い感じ。そう、そんな感じよ」
「ねえ、足はほかの人のに変えましょうよ。腰高の方が見栄えするし」
「髪の毛ももう少し増やしておきましょうよ」
などなどと談笑する女医や看護士たちの手によって、元の姿とは似てもつかないものへと組み替えられていってしまう。
「できたわ。すばらしい。これでこそ、作家之死体よ」
そう、彼女らは名前まで組み替えてしまったのだ。坂野史泰(さかのふみやす)という名は、「さかのしたい」とも読める。これを少し加工すれば「さっかのしたい」となり、ここに当て字をすれば「作家之死体」が完成するというわけだ。
「すばらしい。すてきよ。これでこそ、わたしたちの作家之死体だわ」
「大好き、大好き、大好きよ」
生まれ変わった坂野史泰、いや作家之死体は女医と看護士たちにさらに愛でられる。その最中に院長からの呼び出し音が入る。
「完成したら、すぐにもってこいといっただろう」
震え上がった女医と看護士たちは、あわてて作家之死体に服を着せて、院長室へと運んでいく。院長室には、院長・犬力空也とある。
「おお、これか。なるほど、よくできている。これなら、個展に出せるな」
「ええ、多くの方の鑑賞に耐えると思いますわ」
「うん。わしのキュレーターとしての名声もますます盤石なものとなるだろう」
けれども、不意の銃撃音が響く。
「だ、誰だ」
「坂野を返せ」
現れたのは真野明策である。
「遅かったな。既に彼はわしの聖なる個展の殿堂入りだ」
「そうかな。メッキはすぐにはがれるものさ」
「もう一度死ぬがいい。さあ、お前たちやってしまえ」
「はっ」
「ただちに、犬力様」
「おおせのままに」
女医や看護士たちが白衣を脱ぎ捨てると、その下はセクシーな戦闘服である。それぞれが、機関銃や日本刀など穏やかではない武器をぎらぎらさせている。女医転じて隊長となったコマンドーの指示のもと、見事な身のさばきで散開して真野名策に迫る。
「笑止」
真野が笑う。
「焼死」
隊長が火炎放射器をぶちかますが、燃え上がったのは真野ではなく、犬力である。
「ぐひゅえええっ、あじっ、あじっ」
燃えながら死の舞踏を踊る犬力空也。
「こ、これは、なんということを」
あわてて看護士たちが、水をかけるが、すでに犬力の体は真っ黒焦げである。
「しまった」
看護師の一人が声を上げる。
「やつらの姿が見あたりません」
「くそっ。追え。逃すな」
かくして、舞台を病院から、砂漠、サバンナ、熱帯雨林、温泉保養地へと移しながら、追いつ追われつの大活劇が繰り広げられる。

そんなわけのわからない物語である。いかにも素人臭い、へたくそな展開で、もたついたり、回りくどかったり、省略しすぎていたり、説明不足だったりと、読み手を辟易させる要素が満載であった。それでいながら、そのわけのわからない展開には、ある種眼のはなせない感じが伴うのも確かだった。
当初の書き換えは、主人公とおぼしい(だが、定かではない)坂野史泰(さかのふみやす)という名前を、(さかのしたい)と読み替え、さらに(さっかのしたい)と読み変えて作家之死体という字を当てるという強引
なものだった。不可能とはいえないまでも、かなり無理のあるやり口であるのは明らかだった。
俺がそれを書き換えて、五分ほどすると、すぐにまた書き換えが行われたという通報が入った。今度は坂野の相棒役である、真野明策(まのめいさく)を(しんのめいさく)と読み替えて真ノ名作と字を当てるというちょこざいな小細工。
それを直せば、即座に犬力空也(いぬぢからくうや)を(けんりょくすきや)と読み替えて、権力好也と字を当て、さらには彼の個展を古典に置き換えるといういたずら。
まったくイタチごっこでいくらやってもきりがない。こんなクズ作品のために、俺たちパトロールが消耗させられるのでは、まったく割にあわないというものだ。
「しばらく配信停止の処置を申請しよう」
本部に連絡を入れようとしたところ、逆に本部から緊急連絡が入った。
「どうかしましたか」
「ただちにその作品から出ろ!」
本部の連絡員の声は緊迫していた。
「どうして」
「ウイルスだ」
「ウイルス?」
「ああ、間もなくその作品は崩壊する。そこにいると、巻き込まれて倒壊した活字の迷路に取りこまれて出られなくなる可能性がある」
「どういうことでしょう」
わけがわからなかった。文学作品とウイルス感染という言葉がどうにもかみ合わないような気がした。
「反聖文だよ。やつらのしわざだ」
「え、だって」
「いいから、とにかく脱出だ」
わけがわからないのはそのままだったが、反聖文という言葉が俺に緊張感を与えた。ただ事ではないのがわかった。俺は即座に『不確定な彼女』から脱出した。脱出しながら、後にしてきた作品を見下ろして、俺は驚愕した。文字が駆け回っていた。まるでブラウン運動のように、段落も、センテンスも、句読点も無視して、文字たちがてんでばらばらに駆け回っていたのだ。作品が崩壊していた。雪崩をうって崩れて行っていた。あまりのことに、俺はしばらく作品を俯瞰できる位置でその劇的な崩壊現象に目を奪われたまま動くことができなかった。やがて、作品の輪郭は失われ、ただの無意味な文字の集積となった。比喩で言えば、地震で倒壊したビルのような状態になったのである。しかも、ばらばらに崩れた単語たちは死んではいないようだった。ぶるぶると振動を始めたからだ。まだエネルギーを保っているようだった。

「もっと離れろ」
指示を受けて俺は、現実へと回帰した。その直後に、「封鎖」が行われたということだった。封鎖された壁の中で、崩壊した作品は播種爆発を起こしたということだった。他の作品へと電脳空間を経由してウイルスをまき散らすために、単語たちがばらまかれたのだ。むろん、「封鎖」によって、それは局部的な被害にとどめることができた。『不確定な彼女』が放りこまれていたゴミ箱を含むハードディスクを配信停止にし、さらには電源も切ったからだった。巻き添えを食った作品は数百に及んだが、幸いなことに泡沫的な作品ばかりであった。もしこんな爆発が、キャノンの層で起こったらと思うと、俺は身震いが停まらない感じだった。
「でも、どうして反聖文が、ゴミ箱になんか現れたんでしょう」
反聖文は、その名の通り聖典化された文学に反対していたはずである。つまり、最深部にあるキャノンにのみ関心をもっていたはずなのだ。それなのに、なぜ泡沫的作品であふれかえっているゴミ箱になんかウイルスを散布したのか、俺にはまったくわけがわからなかった。
帰還後説明を求めた俺に帰ってきたのは、こんな答えだった。
反聖文からの犯行声明には、「これは実験であり、示威行為である」と明確に示されていたという。「これより、われわれはこの原典攪乱ウイルスを用いたテロの執行へと向かう。諸君らが、解毒剤開発などの対抗手段を講じるころには、ウイルスはすでに数多の聖典文学を食い尽くしていることだろう。文学に権威は必要ない。文学に自由と平等を!」とあったらしい。
やはり、やつらは解体されてなどいなかったのである。
その夜以来、俺は仕事を終えて寝ても、緊急指令が入って起こされるという夢をみて飛び起きるということを繰り返した。夢に起こされることがあるなどとは思いもよらなかった。夢と目覚めとは反対の現象だと思っていたからだ。そんなこんなですっかり睡眠不足になり、俺は疲弊してしまった。相変わらず熟睡できているらしい高満寺がうらやましかった。あいつのきわめて収録語数の少なそうな辞書には、おそらく「心配」という単語がないのだろう。
(第09回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










