 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
八、リクルート
ようやく物語が解禁になって、さあもう一度楽しむぞと思い始めた頃がちょうど就職活動の解禁の時期と重なった。久しぶりのVRで楽しむ物語に我を忘れていたさなかに俺は指導教官に呼び出された。
実際には指導教官ではなく、もっと上の人間からの呼び出しだったようだ。なぜなら面接室に指導教官の姿はなく、代わりに茶色い背広を着た例の組織の人間とおぼしい人物と、大学の副学長が座っていたからだ。茶色い連中を見て緊張した俺に、副学長が柔和な声で呼びかけた。
「うん、君が、御来屋隆君だね。まあ、いいからかけたまえ、うん」
「あの、刑期ならもう開けたはずですが」
どうしてまたあのパトロール関係の人間がここに現れたのか、俺には皆目見当がつかなかった。
「うん、そのこととは関係ない、と言いたいところだけど、うん、そうでもないんだよね、うん」
そういってから、副学長は慌てて、
「うん、とはいっても、まあこれはいい話だと思うよ、うん」
いつものことながら、うん、うん、うるさい、この人は。
「単刀直入に言おうか」
副学長の隣に座っていた茶色い背広の男がぼくに微笑みかけた。とがっためがねの下で、狐のようなきつい眼をしていた。微笑みといっても、冷たいほほえみだった。どこか人を小馬鹿にしたような、見下したような感じさえ受けた。
「あなたは、あれですよね、VRの管理局の人ですよね」
「そう、その通りだ」
男は名刺を俺に手渡した。
「株式会社ヴァーチャル・リーディング 機構保安課虚構監督局関西支部長 鳥宮高次」
とあった。やたらに肩書が長い。
「へえ、監督局って警察じゃないんだ」
「警察ともつながってるけどね。一応企業なので、テロ対策は独自でも行っているわけだよ」
「俺を捕まえたパトロールってのは?」
「ああ、茶色い制服の人たちだろ。あれは当然社員だよ。我が社のガードマンといったところだね」
「で、ご用は」
強がってみせはしたが、内心はびくびくしていた。また古傷をつつかれるのだろうか。いやな予感がした。三年間の物語剥奪のつらさは骨身にしみていたから、もう二度とあんな眼に会うのはごめんだった。

「いろいろ調べさせてもらったんだよ。そしてどうやら、君は十万人に一人のナチュラル・ボーン・ダイバーらしいということがわかった」
「ナチュラル・ボーン?」
「そう、生得的にVRとの親和性を有するタイプのことだ」
生得的だったのか。幼少の頃、ずっとVRにつながれたまま放置されたせいだとばかり思っていたけど。
「むろん、環境も大切だがね。どうやら君のご両親は、君の能力にある程度気づいていてそれをのばそうとなさったんじゃないか?」
「いいえ、自分の自由時間を確保するために、俺をおきざりにしただけですよ。電脳空間のなかに」
「なるほど、能力を伸ばすのに最適な環境を与えられたというわけだね」
あれ、頭悪いんじゃないこの人。言ってることが伝わってないよ。
「うん、つまり、あれなんだな、うん」
副学長が割ってはいってきたんだ、うん。
「うん、VR社は、君を雇用したいとおっしゃってるんだよね。そのパトロールの一員として、うん」
「しかも特別待遇だよ、うん。通常のパトロールは、うん、特殊なダイビング装置をつけることで初めて原典内に入れるんだが、君は素のままで入れるわけだから、うん、単独行動が許される。とはいっても、最低単位のペアでということにはなるけれどね、うん。それに、うん、あれだ。君の本学での成績はトータルではあまり、うん、ぱっとしない。けれども、うん、長年原典にじかに触れてきただけあって、うん、文学作品の読解力に関してだけは、うん、指導教官も太鼓判を押してるんだ」
「へえ、ほんとですか」
「うん、『彼はまるで著者の意図に寄り添うように読むことができるようだ』って、立花教授が言ってたよ、うん。『ただ、著者が秘密にしていた水虫の悩みや、愛人との葛藤まで読みとってしまうもんだから、学者には向かないけどね』ともね、うん」
「それって、ほめてるんでしょうか。それともけなしてるんでしょうか」
「まあ、うん、どちらかといえばほめてる寄りじゃないか。うん、少なくとも君のその能力は、VR社では役に立つ。うん、それは疑いないところだ」
「で、何をすればいいんです?」
すかさず、茶色い制服の鳥宮氏が説明してくれた。
「そりゃあ、テロの防止が第一だな。その際には、君の独自の読解能力を、犯罪防止に大いに役立ててもらいたい。VRでは読解力が、そのまま探偵力となる。つまり、君は虚構世界の探偵となる、というわけだよ。とはいっても、いつも大事件が起こるわけじゃないけどね。日常的には、君が繰り返してきたような軽微な犯罪の取り締まりも担ってもらうことになる。そうそう、言い忘れてたけど、犯人逮捕の度に君には特別報奨金も支払われる」
悪い話ではなかった。専用のオフィスも用意されるということだった。かくして俺は、世界大統領になるという五歳時の夢を捨て、大リーガーになるという八歳時の夢を捨て、大富豪になるという果たせぬ夢を捨てて、虚構パトロールとなった。それも個人事務所を構える、探偵稼業のようなかたちで。なんせ特別待遇だかんね。

こうして、今日も物語の原典世界を守るため、俺は日夜活躍し続けているのだ。・・・ということであればよかったのだが、実状はさっき見てもらった通りのさえない感じである。
大した事件は起こらないからだ。読解力や著者の意図に寄り添うように読む力なんて、まったく発揮する場面がなかった。俺が逮捕された時には存在していたテロ組織反聖文は、すでにほとんど壊滅状態に追いやられたと聞いている。終身物語体感剥奪という極刑に処せられた彼等の姿を見たせいか、その後そういう大それた犯罪に手を染めようとする輩はほとんど出てこなくなってしまったのだ。
パートナーとなるのは女性だと聞かされたときには、少し期待した俺がいた。そして、まもなく期待した自分をあざ笑う羽目になった。なにしろ、現れたのは女子プロレスラーだったからだ。それも、いまはやりのベビーフェイス系レスラーではなく、ダンプ松本やブル中野の系列の方。ベビーフェイスちゃんたちを猛烈にいたぶる極悪レスラーの方だった。なにしろ、身長が百九十越えで、腕の太さは俺の倍ほどもある。聞けば、これまでに空手柔道剣道柔術古武術忍術剣術手術などを修得してきたという。プロレスラーとして活躍した過去もあるそうだ。こいつには霊長類最強を超えた、動物界最強という称号を献上しても良さそうな気がする。
「なるほど、頼りないぼんぼんだわ」
俺を一目見るなり、彼女はせせら笑った。からから笑った。
「いいだろ。俺たちの仕事は、別に体力とか戦闘力とかいらないんだから」
「そうでもないよ」
そういって、高満寺手弱女は俺を脅しつけた。
「敵は愉快犯だけじゃないのよ。テロリストだっているんわけ。そして、あたしたちは基本単独行動でしょ。あんたどうするのよ、もし小泉八雲の『耳無芳一』のなかで、テロリスト集団に遭遇したら?」
「え、なんで『耳無芳一』?」
「恐怖の換喩よ。恐ろしい状況をより浮き上がらせるために、背景をおどろおどろしくしてみたわけ。たとえば、そのテロリストたちが、芳一の顔全体からお経を消してる場面に遭遇したら、あんたどうするつもり?」
「どうするって、そりゃあ」
――ああ、えーとね、君たち、それはよくないことだよ、うん。だってほら、そんなことしたら、『耳無芳一』じゃなくなって、その『首無芳一』になっちゃうじゃないか。ね、悪いことはいわないから、やめようよ。怖いしさここ、墓地から誰か近づいてくる感じだし、ね、やめようよ。
的な感じの説得になるのではなかろうか? と頭の中で状況を思い描くだけで、俺は恐怖にがくがくふるえ出しそうな有様だった。
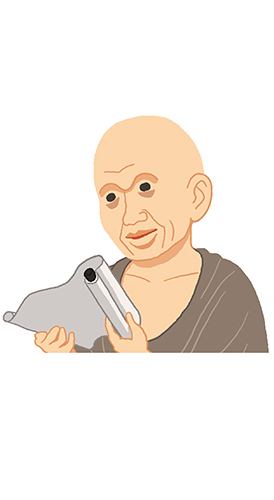
「どうしようもないわよね? まかり間違えば、あんたやつらに捕まって芳一と入れ替えられちゃうかもしれないのよ」
え、そ、それは勘弁。耳無になるのはいやだし、平家の亡霊にもお会いしたくないし。なにより、そんなことになったら、小説世界に閉じこめられてこの世界に帰れなくなるかもしれないのだ。「その瞬間に」俺は「鉄のような指で両耳を掴まれ、引きちぎられるのを感じた!」くなんかない。「『芳一!』と底力からのある声」で三度も名を呼ばれたくはないのだ。なにより、安徳天皇の記念の墓の前で、平家の亡霊どもを前にして琵琶を弾きながら、「壇ノ浦の合戦の曲を高く誦し」たりしたくはない。っていうか、できないし。
「それは、困る」
「だよね」
当然、という風に高満寺がうなずいた。手弱女が。
「そういうわけで、戦闘力のバランスをとるためにあたしが派遣されたわけ。一応、あんたのボディガードをかねてるってことよ」
ちなみにその戦闘力の算出基準を聞いてみると、二人併せて十になるのが望ましいらしい。
「で、そのうち俺の戦闘力はいくつって見積もられてるわけ?」
「ん? それはね」
ちょっともったいぶってみせてから、
「ゼロよ」
なぞと、こともなげに答える、戦闘力十点満点のわが相棒なのであった。
「でもあれだよね、テロ組織は壊滅させられたって聞いたけど」
「ああ、そうなってるわね。表面上は」
「表面上? って」
「うん、ほら、やつらあれでしょ、緩やかな組織体でしょ。つまり、中心となる反聖典文学っていうスローガンがあって、そこを中心に離散集合を繰り返してる、決まったかたちのない集団なのよ」
そうだったんだ。知らなかった。
「でも、表面上の解体は行われたわけだよね」
「うん、『おい地獄さいぐんだで』作戦でね」
「地獄さ行ぐんだで、作戦?」
なんでも、舞台は小林多喜二の名作『蟹工船』であったらしい。プロレタリア文学の象徴的な存在であるこの作品は、いずれ彼等の標的になるであろうとかねてから予想がたてられており、それに備えた罠があらかじめ張られていたのである。内通者からの連絡で、近いうちに「プロレタリア革命成就大祝賀会」を、博光丸船上にて開催する予定があることがわかっていた。
「そこには、『反聖文』幹部たちも出席する予定だっていわれてたわけ」
「なるほど、一網打尽にするチャンスってわけだな」
「そうね」
そういいつつ、高満寺はすくなからず躊躇するそぶりをみせた。巨漢の強面女の躊躇ほど、そぐわないものはない。
「なんだよ。なにくねってんだよ」
気味が悪い、とはさすがに口に出せなかった。
「結局、やつらはまんまとおびき出されたわ。そして、博光丸の船上で革命を成就した船員たちと、蟹食い放題パーティーを催したのよ。反聖文幹部たちが持参した恵比寿ビールや銀河高原ビールさらには、外国のギネスやシメイや青島ビールに小説の登場人物たちは眼を丸くしたらしいわ。でもまあ、革命の成就は物語の外で起こったことになってるから、なにやっても原典には影響ないわけ。だから、作品内で船員たちにひどい仕打ちを繰り返した現場監督の浅川は、さんざんなリンチを受けることになったみたいよ。それを笑いながらみんなで酒を飲んだってわけ」

「で、頃合いを見計らって逮捕ってわけ」
「ええ、まあそんなところね」
なぜだか、ちょっと歯に絹着せる感じ、奥歯にものを挟めた感じで、高満寺らしからぬ返事だった。もしや矯正中かと思ったが、歯に矯正具はついていなかった。
「まあいいや、とにかく『反聖文』は壊滅状態になったというわけだな」
「まあ、表向きはね」
相変わらず、据わりが悪い感じが残る。脚が一本取れた椅子に座っている感じ。
「って、どういうこと?」
「だから言ったでしょ。『反聖文』は形のない組織だって。だから、一応こっちが把握している幹部たちは一網打尽にしたけど、それでおしまいかどうかはわからないってことよ」
「鵺的な感じ?」
「そう、鵺的な、黴処理的な感じよ」
「でも、その後、活動は沈静化してるんだろ?」
「ええ、そうね。それ以後目立った動きはない。でも、組織が消え去った訳じゃないわけ。捕まえたのが本当に幹部たちだったのかどうかもわからないのよ」
「だって、尋問とかしたんだろ?」
「ええ、一応は。でも、幹部たちは、『功績に鑑み、本日付けであなたを幹部の一員に任命します』という発信元不明のメールをもらったから、『ああ、自分は幹部になったんだ』って知ったって感じなのよ。幹部会ってのがあるらしいんだけど、それもいつもクローズドなオンライン会議で、皆がアバターを立てて参加するだけらしいのよ」
「なるほど、中心に見えたのは実は末端という可能性があるわけだな」
「そうね、そしてさらにいえば、中心なんてものはない可能性だってある」
まさに、黴的である。それも、古典文学の味を好む黴だ。
「厄介だな」
「そうなの。だから、安心できないのよ」
そんな感じで、当初は俺たちもそれなりの緊張感をもって仕事に励んでいた。いついかなるときに、また『反聖文』が活動を再開するかもしれないという危機感を小脇にっ抱えていたからだ。一朝事あらば、俺の読解力、すなわち探偵力が火を吹く予定だった。
けれども、大学を出てVR社に就職して、二年ほど活動をつづけるうちに、俺たちは果てしなく続く日常という泥沼、マンネリ化という麻痺のなかへと落ち込んでいった。なにしろ、毎日毎日、起こることと言えば、ほんとうに些末な、思わず自嘲の笑いを浮かべずにはおられないようなものばかりなのだから。
たとえば、本来であれば全裸であったことをメロスが恥じることになるラストの場面で、ふいにメロスが『安心してください、履いてますよ』と白ブリーフを誇示するとかいう、年代物のギャグの挿入事件があった。
たとえば、井伏鱒二の『山椒魚』の山椒魚が、高額なダイエットに励んだ結果、無事に穴から出られるようになるという書き換えがなされた後に、「結果にコミットする」というこれまた往年の謳い文句が挿入されるという事件があった。これは、潜入を依頼した組織が明確であったために、厳重注意という措置が取られたが、こういうミーム効果をねらった犯罪も時には起こる。『我が輩は猫である』において、語り手が『にゃんともグルメ』という某社の猫缶の歯ごたえや味わいについて詳細に語る場面が挿入されたりしたこともあった。
さらによくあるのは、登場人物のファッションや髪型を自分の好みに代えてしまうというもので、『金色夜叉』の貫一お宮の熱海のシーン、「来年の今月今夜になったならば、僕の涙で必ず月は濡らしてみせるから」とあの名言が吐かれるシーンで、貫一は全身ポール・スミスでかためており、一方のお宮はなぜかハイレグ水着姿だったりするわけだ。このファッション・チェンジは結構はやったため、修正しても修正しても、貫一は宇宙服やブリーフ一丁に変えられ、お宮は時にゴスロリとなり、時に裸エプロンになりと、めまぐるしくファッションを変えられてしまうイタチごっことなった。
犯人は逮捕されることもあったし、取り逃がすこともあった。とはいえ、捕らえてみたところで、自作の潜入装置で試しに入ってみたんだぜイエイ! とガッツポーズを決める理系の学生や、もぐりの潜入斡旋業者に金銭を支払って入ってみたんですぅ、とかいうアマチュアばかり、潜入の動機も「自作の装置の性能を確かめたかったから」とか「一度原典に直接触れてみたかったから」とか「現物の味わいを知りたかったから」とか「なんかおもしろそうだったから」とか「なんとなく。うん、ほんとうにただなんとなあく」とか、本当につまらないものばかりだった。犯行の動機も、犯行行為自体もほんとうにどうでもよいようなものばかりだったため、刑罰もそれ相応で、せいぜい物語体感剥奪一年とか二年とかで、それでも「ええっ、勘弁してくださいよお」とか「そんなのつまんない。人生が灰色になっちゃう」とかいった泣き言をこぼす小者ばかりなのだった。
これで、やる気を維持せよというのが土台無理な話であって、だんだんと俺の仕事に向ける情熱も下り坂になりつつあった。そこへもってきて、今日の『檸檬』爆弾事件である。かなり緊張したし、なんとか未然に爆発を防ぐことができてほっとした。けれども、犯行声明は出ない。このレベルの、もはやイタズラとは呼べないレベルの大事件が起こった場合、これまでだとしばらくして『反聖文』からの犯行声明が出されるのが常だった。それが、今回は黙りである。これも気になる。
ということは、これは単独犯の仕業なのか、それともまったく新しい種類のテロ行為なのか? 今のところはいずれとも決めがたいというのが実状である。けれども、限りなくゼロに近づきつつあった、俺のなかのアドレナリン分泌量は急激に上昇したし、警戒信号は真っ赤っ赤に点滅している。何かとてつもないことが起こりそうな予感がしていた。
(第08回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










