 月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
by 小原眞紀子
第八幕(前編)
二日後、岐波弁護士からの電話は、悪い知らせではないらしかった。
「美希ちゃんの指紋は、男の子のいたジムの頂上付近からは出なかったようです」
ラウドスピーカーから流れる声は、ぬか喜びを警戒してか、むしろ感情が抑えられている。
が、大事務所の強みで、警察内の関係者、取材を続けている記者からも内通を得たと言う。
「その指紋の点を含めて問いただしたところ、男の子を突き落としたという彼女の証言が揺れ始めたみたいだ。もっとも、これについてはまだ、警察内部からの確認が取れてないんで」
電話が切れると、やったな、と文彦は両腕を突き上げた。
「小生意気な姪たちの見込み通りだ。嘘を吐き続ける根性なんぞ、あるわきゃないんだ」
夫の上機嫌を目の当たりに、わたしは不安に駆られていた。
玲の見込み。
楡木子叔母ちゃんは災難だった、と言った。
そして起こるべくして起こることもある、とも。
しかし深夜一時近くになって、さらにもたらされた情報は、やはり何かしらの風向きの変化を感じさせた。
虐待痕と疑われた美希の身体の打ち身は、ジャングルジムの棒の太さと完全に一致した。
美希の供述は、すでに数日前から「突き落とした」ではなく、「足を滑らせた陽平の身体を下方で引っ張った」と、妙な具合に変わっていたらしい。それがその日の午後になり、何もせず見ていただけだった、と認めた。
「この手のネタがこちらまで流れてくるのは、警察側の譲歩とみていいんだ」
張りのある岐波の声は、最初に会った晩を思い出させた。
「つまり逮捕はない、というメッセージだね」と、スピーカーからリビングに響き渡る。
結局のところ、彼らはジムで遊んでいて、陽平が天辺付近、美希が下方にいたときに陽平が足を滑らせたのだろう。慌てた美希が自分も落ちそうになり、肋骨のあたりをジムの鉄棒で強打した。
受話器を手に、文彦はそんな筋道を述べ立てていた。

「もっとも、突き落とした、なんて嘘を吐いた訳は不明だがなあ」
「神経症の子供だからねえ」
ラウドスピーカーの岐波の声が応える。
「困惑を罪悪感に置き換えたとか、混乱を周囲に投影することで、自身の気持ちの収拾を図った、ということじゃないかな」
「最初っから、そういう娘だと言っているだろが」
文彦は愉快そうに声を上げた。
受話器を置いたとたん、彼は高笑いでもしかねなかった。
「警察ってのは都合が悪くなると、こんなやり方で謝罪なしに済まそうってんだな。逮捕状はまだか、とせっついてやろうか」
息を巻く夫に、いまだ引っかかる疑念を口にできなかった。
わたしの指示でやった、と、美希が言った理由だ。
「ちゃんと逮捕してもらった上で、無罪放免してもらわねば、と迫ってやる。こっちは甚大な風評被害を被ったんだからな」
「それはマスコミのせいだもの」と、わたしは呟いた。
翌日の昼過ぎ、最初に記事が出た週刊誌の編集部に、わたしは自分で電話をかけた。
昔、教室の取材に来た記者を呼び出すと、少し出世したのか、デスクになっている。
「これはどうも。ご無沙汰しております」
あたかも知己に再会したかのような、しれっとした挨拶だ。
「先日は妹の取材をしていただき、お礼の申しようもございません」
わたしも白々しく言ってやった。
「その記事ですが、一部訂正をお願いしたい箇所がありまして」
「ええと、ああ、どちらの箇所でしょう」と、いかにも多忙そうな早口になる。「だいぶ前のものになりますねえ。今、担当者が不在で」
「では、お伝えください。最後の部分です」わたしは言った。
「明らかな事実誤認があり、ずっとその被害を受けています。ご承知と思いますが、弁護士にも相談しております。早急に、現在の見解をお聞かせください」
夾子のインタビューを担当した記者からやっと連絡があったのは、晩になってからだった。
「あのう、記事の内容についてご質問がおありとか」
「いいえ。訂正のお願いです」
この連中は、警察からのリークを受けていたのだ。
もはや逮捕はない、と承知している気配があれば、それも彼らが警察から得た確定情報と思っていいはずだった。
「演技性人格障害ってのは、いったい、何のことですか」
「ええ、まあ、わたしどもも、珍しく思いましたが」
おそらく三〇代だろう。惚けているつもりか、おっかなびっくりで妙な作り声を出す。
「現在の犯罪捜査では常識となっている概念、と妹さんにお聞きして」
「夾子はそんな話はしていないはずです」
「いえ。インタビューの際に教えてくださいました」
記者は言い張った。「警察がそういう容疑で動いている、と」
取材テープは相手側にしかない。言った、言わないの水掛け論になっては負けだった。
「でも、その後、もちろん警察にも行かれたんでしょ?」
ええまあ、と記者は言葉を濁した。「裏を取るのは責務ですから」
思わず反吐が出そうになった。
「責務を果たしたあげく、逮捕状請求を待つばかり、と、書かれたんですね」
はあ、と消え入りそうな声が聞こえる。
「あのう、雑誌の発売後に、警察の見解が変わることはあり得ます。人格障害という表現は語弊があったかもしれませんが。演技性という言葉に、着目した結果なので」
「その結果、うちの演劇教室は生徒が一人もいなくなりましたよ。貴誌も取り上げてくださった英語劇ですけどね」
「はあ、その節は」
そいつは担当外、とでも言いたげだった。
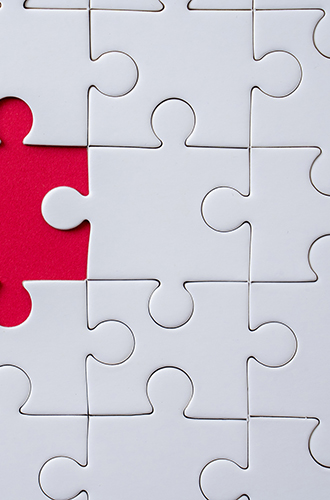
「つまりその、情報のフォローという側面もありまして。演劇人として取り上げさせていただいた経緯があるからこそ、演技性うんぬんということで警察が捜査しているのを無視できませんで」
「だったら、なぜ母のことまで触れたんです?」
「それは先生が、ご自身でもお書きになっていたことで」
あたかも新聞のコラムまで全部チェックしていると言わんばかりだった。が、大方それも、警察から得た情報に違いない。
「愚弄してるの」と、声を荒げてみせた。
「なにさ、鬼の首でも取ったように。あんたたちに先生と呼ばれる筋合いはないわ」
「お気に召さない表現はあったかもしれませんが」
用意した台詞にやっと辿り着いた、というように、取材記者はへらへらと猫なで声を出す。
「記事の主旨を、大局的にご理解いただけないでしょうか。そもそもは妹さんからの持ち込みで、ご主張を取り上げたものです。ページの大半は、現在も身柄拘束されているご義弟の弁護に当てられてますので」
文彦は、ロンドンの学会での発表の準備を再開した。
週末にホノルルへ戻れば、ぎりぎりのタイミングで間に合うという。
徹夜続きになるが、と苦笑しつつ、晴れ晴れした表情は隠せない。
「それで、いつ頃来られる?」
来月には、とわたしは答えた。
もはや日本にいる理由はなかった。周囲に無実をアピールしてから発たねば、まるで逃げるようで癪だったが、教室はすでに開店休業だ。執筆や取材の申し込みも真田の件に関わるものばかりで、無論、受けるつもりはなかった。
万一、民事裁判が起これば、日本に帰ってきてもらうことになる、と岐波弁護士は言った。
しかし、陽平を突き落としたという美希の自白が覆った以上、その可能性もまずないらしい。
横浜で文彦と食事をし、成田エクスプレスの改札で見送った。
ひとり家に戻ると、すぐに自分の荷造りと税務手続きの段取りを考えはじめる。
そう、やはり逃げ出すのだ。
近隣の誤解と悪意、血縁のしがらみから。
一人になったリビングで、久しぶりにインセンスに火を点けた。青リンゴとラベンダーが混ざった香り。
ふと、少年の肌の匂いを思い出した。わたしの胸に顔を埋めていたのは、まさにこの場所だった。髪の匂い、滑らかな皮膚の感触が蘇る。
わたしは頭を振った。
もう、関わってはいけない。妹の戸籍上の夫は、いまだ警察に捕らわれている。
文彦の姿が見えなくなって、まだ一時間しか経っていなかった。その気持ちの隙間に、最初に入り込んでくるとは。
あなたはもう、結婚しているじゃないですか。
かつて心が震えた言葉の意味を違え、彼の面影にそのまま返す。

(第15回 第八幕 前編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『幕間は波のごとく』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■








