 月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
by 小原眞紀子
第七幕(前編)
「そう出たか」
電話のラウドスピーカーから、危機感が滲んだ言葉が流れ出る。
「となると、例の准看護師へのやり方からして、別件で動く可能性もあるなあ」
あの笑みを絶やさない岐波弁護士の声とは、別人のようだった。
わたしはソファに掛け、こめかみが脈打つのを堪えていた。
「いいか、万一のときは令状を確認して、すぐ連絡をくれ。容疑はおそらく児童虐待だ。殺人教唆の罪は身柄確保の後、自白を証拠とするつもりだろう。いずれにしても無関係物の押収を受ければ即、抗議する。とにかく黙秘だ。どんな調書にも署名捺印は絶対しない」
殺人教唆。
黙秘。
わたしは逮捕されるのか。
スピーカーの声は、それを宣告しているように思われた。
「警察の身柄拘束は二日間だ。検察に送られ、勾留請求されて、さらに延長しても二三日間の我慢だからね。物証といっても、鑑定は揺れる。向うの言い分を鵜呑みにすることはない。そもそも別件逮捕は違法で、取り調べる権利なんかないんだ。とにかく頻繁に接見請求するから」
「しかし、本当にあるのか? 逮捕なんか」
うわずった口調で、文彦は食い下がっていた。
「あんな馬鹿げた、屁理屈みたいな言いがかりの挙げ句に」
いや、と岐波の声はやや緩んだ。
「まず、最悪の事態を想定しておくだけさ」
我に返ったように、ビジネスライクな雰囲気を醸し出す。
「昔を思い出してね。熱くなるなあ、大企業相手の民事と違って」
だが、その楽天的ななだめ方は、どこか医師の告知を思わせた。
きっと弁護士も医師と同様、ポーカーフェイスを訓練されるのだ。
それは最後の瞬間、ついに見放すまで保たれる。
「だけど、虐待痕の鑑定もあやふやだというなら、美希が信用ならないことに変わりないじゃないか」
少し落ち着きを取り戻し、文彦は言う。
「こっちも児童精神科の診断書で対抗できるんじゃないか? なにしろ家で性交を目撃して、男を見るのも怖くなったと言うが、どうだい、」
振り返った夫は、わたしに尋ねていた。
「真田は美希の面倒を見に来ていたんだろ?」
ええ、とわたしは頷いた。
教室が終わる時刻まで、何度か公園で遊んでもらった。
それは姉川夫妻が苦情を言いに来て、美希が「性交」を見たと主張する日よりも後のことだ。美希は特に怖がるでもなく、真田と手を繋いで戻ってきた。
「だいたい、その苦情ってのが、美希が男の子に飛びかかってズボンごとパンツを下ろした、って一件だぜ。性交を見たショックで男に恐怖心がある、が訊いて呆れるよ」
文彦は受話器に向かい、語気荒く言い続けていた。
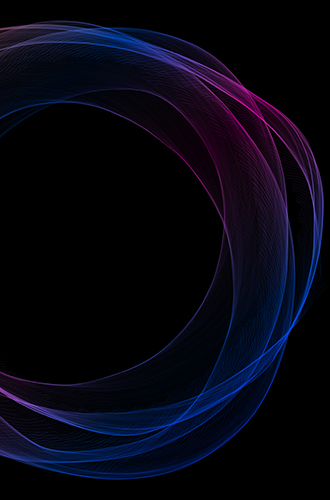
だが司直の逮捕前に、わたしを葬り去ったのは別の「逮捕状」だった。
「病院勤務は虎の穴 冤罪事件に揺れる女医の主張」
研究室へ出かけた文彦が、そんな見出しの週刊誌を持ち帰ったのは、同じ週のうちだった。
表紙に踊る活字には、怒りとともに、やや複雑な感慨がこみ上げた。
大手新聞社系のその雑誌には、以前、わたし自身が英語劇教室の取材を受けたことがある。もっとも目次での見出しの大きさは、かつての文化欄の記事とは比べものにならない。
ページを開くと、「女医の主張」という文字の下で、白黒写真の夾子が手振りを添え、真剣な表情で若い夫の無罪を訴えていた。
記事の最後には演技性人格障害について補足され、「英語劇教室を主宰する、この女医の姉」が虐待した姪が、「姉」の命令で少年に危害を与えて死亡させた件につき、逮捕状請求を待つばかり、と書かれていた。
逮捕状請求を待つばかり。
そう書かれたことはいわば、すでに「逮捕状」が出たも同然だった。
文彦の連絡を受け、岐波弁護士は出版社に抗議した。
夜遅くなり、自宅に戻った夾子を、わたしは電話で捕まえた。
「あんたの主張ばかり、よくも取り上げてくれたわね」
さすがに苛立ち、棘のある言い方になった。
「違う、姉さんのことなんか、」と、夾子も声を上げた。「記者が勝手に警察に取材したのよ。こっちから言うはずない」
むろん、そうだろう。
雑誌への岐波の抗議は、すべて夾子からの情報提供だとかわされた。が、おそらくは裏を取りに来た記者に警察がリークしたのだ。
その証拠に、母の失踪までも取り上げられている。実家の家族構成や出自を侮辱したような書き方は、夾子を情報源とするとは思えない。
「それでも警察の人権侵害に対抗するには、マスコミを利用するしかないって、玉井先生が」
弁護士と戦略を練り、片っ端から雑誌に頼み込んだのだと言う。
「そりゃ、あんたの言いたいことは、読めばわかるわよ」
医療現場の現実を無視する警察。
立場の弱い准看護師が、医療トラブルのつけ、さらに冤罪までも負わされている事実。
それらを知らせるべく、夾子が熱弁を奮ったのは確かだ。
「だけど週刊誌なんてのは、ちゃんと読まれてやしないの。広告の見出しとか写真とか、人目を引く部分だけが世間にアピールするの」
美少年看護師の殺人容疑。
結婚相手は十四浪した中年の女医。
それらがまさに、そうしたくだりなのだ。「女医」の主張は別として、その母親の失踪、演劇人の「姉」の児童虐待容疑は、「女医」の家族が、少なくともまともではない、と強調している。

「そうね。彼は当時、未成年だから写真が載せられない、って記者が残念がってたもの」
そのぶん、やたらと自分を撮っていったと、妹は言う。
「太ってみえるショットをわざわざ選ぶんだから、悪意を感じるわ。額の皺も目立つし、服とのコントラストがいかにも若作りで」
「冗談じゃない」と、わたしは怒鳴りつけていた。
「今さら写真写りがなによ。十四浪も、中年太りも事実じゃないの。あんたがどう扱われようと、知ったことじゃないわ」
「ごめんなさい」
電話越しに、妹は消え入るように呟く。
情報源の夾子が自ら身元を明かすことで、雑誌側は訴訟リスクを避けられる。病院側も噂をうち消すべく、むしろ攻勢に出られる。そう考えたのは、玉井弁護士だと言う。
「同僚の嫉妬を買っていた彼が讒言された、ということは院長先生たちも了解してくれたの。とにかく患者の訴え自体が誤解だと主張してくれ、って。あたし、それだけで頭がいっぱいで」
「ミュンヒハウゼン 欧米型の悪魔的犯罪」
「支配より相互関係型の日本社会でもあり得るか 専門家の見解」
「ほら吹き男爵は患者か看護師か 病院の苦悩を女医が語る」
例の週刊誌の発売以降、テレビと他誌が続々と事件を取り上げはじめた。
その勢いは一種、堤防の決壊を思わせた。別件逮捕と少年法の絡みで、これまで奥歯に物が挟まったような報道ばかりだったせいだろう。
「すると、すべては患者側との行き違いから起こったことだ、とおっしゃるんですね?」
朝のテレビ番組の中の夾子は、最初の写真で懲りたか、アップの髪にベージュの口紅と、年齢相応のヘアメークに落ち着いていた。
「もちろん病院側に問題がなかったとは申しません。医療過誤はないと患者さんにご納得いただけるよう、コミュニケーションを十分にはかるべきでした。けれども現場のスタッフは毎日、体力の限界まで働いています。そのわたしたちを、警察は無意味に追いつめるだけです。厚生省による医療行政も、見直していただきたいんです」
あれ以来、テレビの生出演でも、雑誌取材でも、夾子はわたしに前もって知らせてきた。許可を求めるかたちではあったが、病院や弁護士と話がついている以上、止めるわけにいかない。
「厚生省による医療行政か。偉そうに」
文彦は低く舌打ちした。
しかしながら、玉井弁護士の戦略とやらは、それなりに当たったのかもしれない。
美青年と伝えられるだけで姿の見えない真田は、視聴者のイメージを鼓舞する。そのぶん結婚相手の年増の女医に、嫌悪と同情の少なくともいずれかの関心を惹くことができる。
「こう注目されてちゃ、警察も無茶はできないでしょうし」と、わたしは言った。
「さあ、どうかな」
文彦は片頬を歪めた。「注目されてなお意固地になる、ということもある。FBIを気取るあの刑事も、そういうタイプだろ?」
そうだった。警察もマスコミを使い、意図的に都合のいい情報をリークしていた。

「東明大学病院精神科の梨山先生、いかがでしょう。こういった殺人事件は、ミュンヒハウゼン型と呼ばれるそうですが」
明らかにカツラ頭の司会者は、病院のスポークスマンの域を出ない夾子にやや不満気だった。
「はい。欧米では大量殺人の事例が知られています。そういった素質を持つ新人スタッフや、外来患者を見分けるための対処マニュアルを備えている病院もありますね」
秀でた額の梨山教授は、今の司会者の精神状態までも察知しているようだった。知的な語り口で、警察の監察医も務めているという。
次々と挙がる典型例を聞いていると、そんな動機の無差別殺人が実にありふれたことに思えてくる。
「だけどさあ、学者ってのは、自分の研究対象が一般的なものだと言いたがるもんでしょ? 医学部は特に御用学者だらけだし」
挑発的な物言いが売りのコメンテーターは、実際にはバランス感覚に長けている。こうしてテレビの液晶画面は、決定的な結論は何も示さないまま、真実の鏡然と、現代の常識を視聴者に教育するのだ。
ワイドショーがちょうど終わった頃、インターホンが鳴った。
「あのう、夾子さんの主張を、お姉さまから補足していただけないでしょうか」
妹の主張の補足。そんなのが目的のはずはない。二日一度はどこかしらやってきて、こうした猫なで声を出す。夜、通りでフラッシュを炊かれて以来、わたしは外に出ていなかった。
全大手マスコミに、岐波が送った激越な警告文が利いたのか、逮捕状請求寸前と書かれたわたしの容疑は、あれから表立っては言及されない。それでも警察が意図的に流すものか、真田との関係は尾鰭が付き、怪しげなネット上ですでに広まっている。
業を煮やした文彦は、ついにテレビとインターホンの電源を切った。
と、途端に周りが静まった感があった。近所中が凪いだようにしんとしている。
張りつめた空気の中で、わたしは息をしているだけの生き物と化した。
玄関を出入りする夫の物音ばかりが耳に届く。
思えばもはや、あの嫌がらせすらなかった。
教室の生徒には電話連絡網がまわったか、ほぼ全員が先月分と今月分を合わせた指導料を書留で送りつけてきた。受験準備があるといった言い訳のメモが入ったものもあったが、たいていは現金のみだった。中三の敏彦を含めた残り数人は、ただ欠席を続けていた。
そんなときに奇妙だったが、子供たちの夢を見た。
無邪気だの、無垢だのと思ったこともない。単に商売の方途に過ぎなかった生徒たちだが、夢の中でもリビングの階段から飛び降りたり、何が面白いのか、旧式のカセットの動きをいっしんに見つめたりしている。
ただ違っていたのは、それを喜ばしく眺めている、こちらの心持ちだった。
目が覚めると、自分がすでに、なかば監禁されていることに気づいた。
いや、まだだ。
クライマックスは、きっと逮捕なのだ。
わたしはどこか、他人の作った舞台を見ているような気がしはじめていた。

(第14回 第七幕 後編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『幕間は波のごとく』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■








