
 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
五、『山月記』:初めての改竄
その日も母は俺をVRに接続して出かけていた。すでに俺は五歳になっており、幼稚園に行っていた。けれども、その日は午前中で終わったために俺は家で昼飯を食べた。そして、昼寝に入る際にすでにVRを頭に装着されていたのだった。
その日母は慌てていた。妙に小ぎれいに着飾り入念におしゃれをしていた。すでに誰かとの待ち合わせ時間に遅刻しているらしく、そわそわしていた。
「たかしちゃん、おもしろいお話楽しんでてね」
少し息が挙がった声で母はそういい、すでに寝入っていた俺の頭にVR装置をマウントすると、日本文学を選んで適当なタイトルをクリックした。母はその本を読んだことはなかったが、気持ちがせっていて、吟味する余裕がなかったのだと思う。わたしは中島敦の『山月記』の世界とつながれてしまった。
それは最初悪夢だった。いくら文字が直接頭の中に入ってくるとはいえ、幼児にとって漢語の世界はあまりに異質だった。
「隴西の李徴は博学才頴、天宝の末年、若くして名を虎傍に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃む所頗る厚く、賎吏に甘んずるを潔しとしなかった」(『筑摩現代文学大系 34』筑摩書房、1976、p.371)などという書き出しからして、幼稚園児にかみ砕けるはずはなかった。独自に解釈しようにも、それらの漢語の連なりはあまりにも意味不明だった。幼い心が破壊されそうな苦悩にさらされて、わたしは眠りながら悲鳴をあげ、VR装置を解除してくれるように母に頼んだ。だが答えはなかった。わたしはうめき、悪夢のような消化不良の言語の群に攻撃されて泣き叫んだ。まさに児童虐待の最たるものだったといえるだろう。
幼いわたしはそれでも抗った。何とかそこから逃れようとした。だが、言語の群は容赦なく浴びせかけられ、私の意識は崩壊の危機に瀕した。すべてをあきらめてわたしがぐったりとなった瞬間だった。わたしは自分がすうっと楽になるのを感じた。不意に目の前に山が見えた。山の地面だった。わたしは虎になっていた。虎になって野山を駆け回っていた。「其の時、眼の前を一匹の兎が駆け過ぎるのを見た途端に、自分の中の人間は忽ち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口は兎の血に塗れ、あたりには兎の毛が散らばってゐた」(同書、p.372)。兎の肉の味と、血の匂いを感じ、満腹感を得ると同時に、わたしはそれらの文字を見てもいた。不思議なことに俺の周りには、虎となっている自分とは別にもう一つの世界があった。無数の文字から構成される世界が、体験世界と二重写しになっていた。そして、それらの文字をわたしは触ることができた。積み木のようにわたしはそれを積み上げたり崩したりした。「偶因狂疾成殊類」という漢字の連なりを、「狂類偶疾成因」と並べてみたり、「偶因」「狂疾」「成」「殊類」とばらばらにしてみたりした。そのうち、元の並びがわからなくなって、そのままに放置してしまった。

そのころのわたしはカブトムシに夢中だった。祭りの夜店で売っていたのを母が買ってくれて、虫かごのなかでそれを飼っていたのだ。だから、わたしは自分が虎になったことが不満だった。虎ではなくカブトムシになりたいと念じた。それはまったく意図的なものではなく、無意識のできごとだった。するとわたしはカブトムシとなって樹液をすすり、堅い羽を広げて飛ぶカブトムシとなっていた。そのため、この物語の結末はこんな風に変わってしまった。「一行が丘の上についた時、彼らは、言はれた通りに振り返つて、先程の林間の草地を眺めた。忽ち、一匹の甲虫が草の茂みから道の上に躍りでたのを彼等は見た。甲虫は、既に白く光を失った月を仰いで、二度三度羽ばたきしたかと思ふと、又、元の叢に躍り入って、再びその姿を見なかつた」(同書、p.373)。
「なんてこった」
声が聞こえた。誰かに捕まったと知れた。
「こんな小さな子が犯人だなんて」
驚きに満ちたその声の主が、わたしの体からカブトムシをはぎ取った。そして、わたしは目を覚ました。
「たかしちゃん、たかしちゃん」
母がわたしを揺さぶっていた。あわてて職場から戻ってきたらしい父親もネクタイ姿のままで俺を見下ろしていた。
「よかった。無事だったのね」
「まったく、お前はなんてことやってくれたんだ」
「だって、わたし急いでたから」
「急いでたって、なにをだ。子供ほったらかしてでかけるどんな大事な用事があったっていうんだ」
夫婦喧嘩が始まった。どうやら俺は口から泡を吹いて、意識をうしなっていたらしい。いや正確にはそうではない。意識を喪っていたのではなく、意識が別のところへと移っていたのだった。
「おそらく偶発的な現象だとは思いますが」
茶色い制服を着た男性と、女性がそこにはいた。いわゆる管理局の人間だった。むろん、当時の私にその正体がわかるはずもなかったが。
「もし、繰り返しこういうことが起こるようなら、研究対象とさせていただきますが、よろしいでしょうか」
「いえ、おそらくそういうことはもう起こらないと思いますので」
父が社会人らしく礼儀正しく答えた。
「これからは妻にもきちんと子供の面倒を見るよう言いますし、物語の選定にも気をつかわせるつもりですから」
「わかりました。そういうことでしたら、今回は偶発的事故として処理しておきます」
そういって、制服の二人は帰っていった。
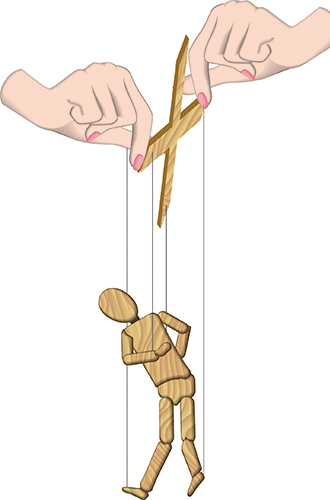
(第05回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










