 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
四、VRの起源
この例でわかるように、たいていの侵入者は素人であって、原典侵入も偶発的な一回限りのものである場合が多い。二度と同じことは起こらないというのが、通常なのだ。ちなみに、俺のように自在な原典侵入がいつでも可能な、電脳空間特殊適応性を備えているものはめったにいない。だから、だいたいの奴らは不正な装置を使って入り込む。とはいえ大多数は愉快犯であり、興味本位、面白半分といった動機しか持っていない。この分野の古典的名著といわれるヌクレオチド・デオキシリボの『聖書原典改竄者研究』やヤホー・ゴーグレの『プログラミング・フォー・フォールシフィケイション第九版』などに目を通しているわけではない。それらの著書から実践的な部分のみをハウツー本形式で抜き出した『チャート式原典侵入』『誰でも入れる古典名著』『原典改竄マニュアル』などや、インターネットのもっとお手軽なサイトを見ているだけなのだ。だから、証拠隠滅もなにもあったものではなく、いつ誰がどこでどのように侵入したのかがバレバレであり、即時逮捕ということになる。
とはいえ、何せ原典にたいする損傷が軽微である上、動機も悪質とは認め難い場合が多いため、重くても禁固数ヶ月で済んでしまうし、軽い場合は二、三年間の物語体感禁止程度の刑罰しか与えられない。
物語体感禁止というのは、当該期間の間、VRへの接続資格を失うということを意味する。でも、普通に小説や漫画を読んだり、映画やテレビドラマを見ることを禁止されるわけではない。それならなにも問題はないと思うあなたはすでに旧世代だ。いまだに紙に印刷された書物や、映画館で見る映画に固執している化石人と呼ばれる人たちだということになる。統計的には、平均年齢八十歳以上に比較的多く化石人が存在するといわれている。
つまり、いまや八十歳以下のすべての世代が、新世代に属しているということだ。小説世界を、自分の想像力のおもむくままに実体験として体験できるVRを経験してしまった世代がそれにあたる。われわれの世代からすれば、古典的メディアである書物や単なる二次元映像(あるいはそれに毛が生えた程度の3D映像)などは、実に薄っぺらいものとしか感じられない。自分の全感覚で体験できるVRと比較すると、なんとも物足りないことこの上ないのである。麻薬同様、一度このVRの読書=体験をしてしまうと、通常の物語ではまったく満たされなくなってしまうわけである。
受刑者の中には、これならまだ物語を禁止されることはない禁固刑の方がよかったと嘆くものもいる。なにしろ、全感覚で没入できる物語を欠いた人生は、散文的でつまらないものとしか感じられないからである。
かくいう俺自身が、実のところは、かつて五年間にわたる物語体感剥奪の刑に処せられた身だったりもする。
俺は生まれながらの活字(体験)中毒者だった。ちょうど数十年前の子供たちが、生まれてすぐスマホやゲームに触れたのと同じ感覚で、俺はこのVRシステムにすでに二歳にしてつながれていた。俺の母親はいわゆる手抜き系で、それなら保育園にでも預ければよいものを、ただ手元においてほったらかしておくという子育て方法を選んだ。
専業主婦であった母は、家事の合間合間にVRを装着して夢見心地の時間を過ごしていた。掃除ロボットの進化、洗濯乾燥マシンの洗練、自動調理機器の発達に伴って、家事労働はいまや完全に機械化されていた。唯一機械に委ねきれないのが子育てであった。子供がいなければ、専業主婦の「専業」という単語は「暇」と置き換えてもかまわないようなところまで来ていた。そして、「暇」を得た専業主婦は、ランチや買い物やママ友とのだべりを楽しむ以上に、VRにはまった。ハーレクインロマンスや、BLものをリアルに体感できるのだから、はまらずにいる方が無理だといえた。当時はまだヘルメット型だったVR装置をかぶって母は始終うっとり微笑んでいた。子供心にその姿がとても心地よさそうにみえたため、俺も隙をみつけては、まだ自分の頭には大きすぎるその装置をかぶっていた。

「あらあらそんなに、入りたいの」
最初はそういって俺に『ないたあかおに』やら『とししゅん』やら『ぐりとぐら』なんかを読ませていた親だったが、俺がその世界に入り込んで夢中になっているのを見て、名案を思いついたのだった。
「ねえ、たくちゃん。今日はもっとおもしろいの読ませてあげようね」
そういって、母はまだ三歳だった俺を『あんぱんまん』絵本全巻セットと接続した。そこには、果てしのない物語の世界が広がっていた。絵は単純だったけれど、俺の脳は挿し絵を書き換え、自分なりのアンパンマン世界を構築し、そこに夢中になった。俺の想像力によって受肉したアンパンマンが、同じく俺の想像力によって恐るべき姿へと造形されたバイキンマンと、果てしない死闘を繰り広げる、波乱万丈の世界がそこにはあった。あるときはジャムおじさんとなり、あるときはカバオくんとなって、俺はその熾烈な戦いを眼のあたりにした。時には、自ら食パンマンとなって、アンパンマンの手助けにかけつけたりもした。幼児が体験するには、あまりにも刺激的な世界がそこには広がっていた。おそらく友人との長い茶話を堪能してきた母が戻ってきたとき、俺は未だ物語の中に浸っていた。かくして、母は天啓を得たわけだ。母は、俺をVRの中に置き去りにするようになった。
「たくちゃん、今日は『ハリー・ポッター』シリーズを読ませてあげるね」
まだわからない言葉もたくさんあったが、すでに『西遊記』や『指輪物語』を経験済みだった俺は、憶測で意味の分からない部分を埋める能力を高めていた。つまり、幼児の世界観で物語世界を再構築するすべを身につけていたのだ。だから、俺の見た物語世界でハリー・ポッターは三歳児の姿をしていた。ヴォルデモートは、バイキンマンの姿で登場した。それが、当時の俺にとってもっとも恐ろしい悪のイメージだったからだ。とはいえ、それは三歳児が読み通す=体験し通すにはあまりに長大な物語世界だった。物語に溺れて気が付かなかったが、俺の脳はおそらく限界を超えたのだろう。全七巻を体験し終えたとき、俺は脳の困憊からくる昏睡状態に陥った。実のところ、午後三時から十一時までずっと物語世界につながれたままだったからだ。父の出張を利用して、高校時代の友人たちとの飲み会に出かけていた母が戻ったとき、俺は口から泡を吹いて意識を喪っていた。
さいわい大事には至らなかったものの、ようやく母にもこの置き去りの危険性が飲み込めたようだった。といっても、だからといって置き去りをやめたわけではなかった。それ以後は、量を加減するようになったというだけのことだった。もし俺があのとき平気で待っていたら、そのうち『失われた時を求めて』とか『チボー家の人々』とかとすら、母はつなごうとしたかもしれなかった。
それだけ、小さい頃からVRに浸りきっていたせいだろうか、俺にとってはこのもう一つの現実世界がきわめて親和性の高いリアルなものとなった。長じて、ただ受け身の物語消費者でいることに飽き足らなくなってきたのは、その意味では自然なことであった。俺は徐々にこのVRの仕組みそのものに興味を持ち始めた。まだ自我すら曖昧な時期、五感の識別すら曖昧な時期にこのVR世界に浸りきったがゆえの、特殊な親和性を俺は徐々に獲得していった。
VRの前身にあたるのは、書籍の電子配信だったといわれている。キンドルがもっとも成功した例とされている。とはいえ、これはまだ伝統的な「読む」という行為を前提とした、視覚偏重型の原始的なものにすぎなかった。つまり、「読む」意志のないところに、この電子配信はなんの意味ももたなかった。従来通り、視覚を通して得た情報をもとに空想をたくましゅうするだけの行為でしかなく、伝統的な読書とさしたる違いはなかった。数十グラムの電子デバイスに百科事典でも、「大菩薩峠」でも、水滸伝全巻でも、ヘンリー・ジェームス全集でも入れて持ち運べるというメリット、お金さえ払えばたいていの本を本屋の媒介なしに直接ダウンロードできるというメリットを除けば、それまでの書物を通した読書体験と劇的な差異があったとはいえなかった。
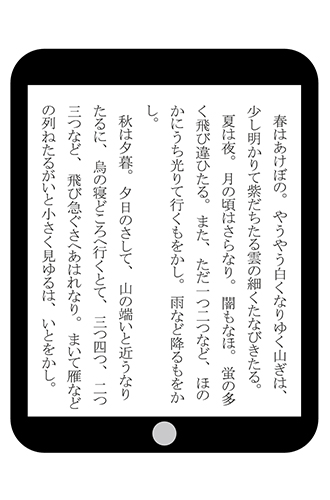
門外漢だから、詳しいことはわからないが、脳科学の分野では、かなり以前から物語体験が「全脳的」連携を生み出すことは知られていた。機能的磁気共鳴画像装置(fMRI)という装置を用いることで、脳内で活性化している部分を調べることができるようになったことによるらしい。物語を読むとき人は、そこに現れる人物像や、風景、音、動き、味覚などさまざまなものをシミュレーションしている。そのために、脳内の、通常は連携していない部分がネットワーク状につながれるということが分かっていた。また、その際、前頭葉が必要な連想を促す働きをすることもわかっていた。大脳皮質の側頭葉の連合野に連想記憶を支える器官があり、これを前頭葉がコントロールすることによって連想が可能になるというわけである。さらに、その後の脳科学の進展によって、共感覚の仕組みがより明らかになってきた。共感覚というのは、文字や数字に色を感じたり、音に肌理のような触感を感じたり、味に音楽を感じたりするような現象である。これまた、通常は連携することのない聴覚野や視覚野、あるいは色覚野などの脳内に散在した部位の間に感覚の混線(クロストーク)が起こる現象であり、脳内に平時とは異なるネットワークが形成されることを意味している。言語情報刺激を、前頭葉を介した脳内ネットワークの賦活へとつなげる方法である、人為的言語感染方式(通称、言語ウイルス、あるいはヴァーバル・ヴァイラス・メソッド)の確立にともなって、読書体験は全脳体験、つまりは全感覚体験、さらにいえば全身体験へと変貌した。文字通り、言葉がウイルスのように脳に感染して、あらゆる記憶、あらゆる体感を刺激し、きわめてヴィヴィッドな疑似体験を生み出すのである。この原理を解明したMITの脳生理科学者ジュリア・スシザ教授と、サイバネティクス学者のカマタリ・ナカトミ教授は三十年前にノーベル賞を受賞した。
この理論に基づいて、日本の弱小ベンチャー企業ドリームホークスによって、VRすなわち、ヴァーチャル・リーディングの装置が確立されたのが、それから三年後の二〇五〇年のことだった。当時、インターネット依存やスマホ依存は、電子機器の臓器化とすら呼ばれる事態をもたらしていた。誰もがSNSやネット動画に常時接続しており、ゲームやビデオもすべてこれらの機器を通して享受されるにいたっていた。これにともなって、書籍の売れ行きは急落した。ある評論家は「本は死んだ」というコメントを、これもまたSNSを通して発表した。もはや「出版」という産業は終わったとさえ言われていた。
VRは、そんな書籍の世界に革命をもたらした。それまで活字メディアを片隅においやっていた、ゲーム、ビデオ、動画の世界を完全に凌駕する体験を、この装置がもたらしたからであった。「読書」こそが、全感覚にわたる究極の充足感をもたらしてくれるものなのだということを、VRが証明してみせた。なにしろ、その時々で自分の想像力に基づいた世界が、書物から引き出され、それが視覚聴覚嗅覚味覚触覚すべてを伴った体験として享受できるのである。これまでのどんなメディアにも不可能だった、「自分中心」の快楽がついに実現したのであった。
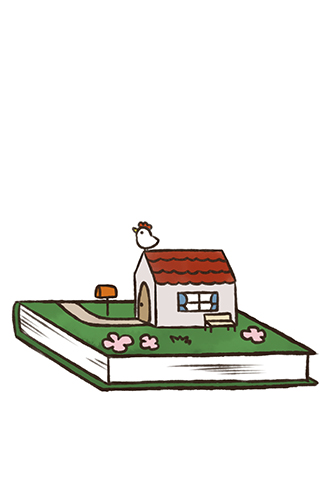
VRは、一応読書=体験とされているが、ただ単に「読む」のではない。VR以後、読書とは、全身をもって体験する疑似的現実となったからである。従来目という器官を介して、あるいはオーディオブックなら耳という器官を介して脳で処理せねばならなかったものが、ダイレクトに脳とつながるものとなった。脳は五感の元締めであるから、それは言葉を五感とつなぐ結果をもたらした。読書体験は、視覚と聴覚を介した映像鑑賞、聴覚のみの音楽鑑賞などでは得られないより強烈な身体感覚をもたらすものへと変貌した。
とはいえ、その大元は文字情報からそれぞれの読者が引き出してくる、イマジネーションである。文字を「読む」ことが、この体験のベースにはあるわけである。かくして、文字の復権が成し遂げられたのであった。再び、活字が王様の時代が訪れた。百年のブランクを経て、文学が娯楽の中心へと返り咲いた。人々は一気にこのニューメディア(いやむしろリニューアルメディアというべきだろうか? 劇的ビフォー・アフターってやつだ。)に飛びついた。
すべての文学が、オンラインで脳に直結可能な時代。文学は「読む」ものではなくなり、「体験」するものになった。考えてみれば、辞書はとっくに引くものではなくなって、打ち込むものとなっていた。文字を書く行為もまた、キーボードをたたく行為となり替わっていた。それに比して、「読む」行為だけは長らく眼球の運動と直結していたが、ついに各自の想像力に応じて「体験」するものとなった。
当初はヘッドマウント型の巨大な装置であったものが、徐々に小型化が進み、ついにスマホとワイヤレスで連動する小さなサングラスにまで縮小された。一般のレベルでの物語消費は、現在このサングラスを通して行われている。けれども、さらにいえば、実際のテクノロジーは、俺たちのようなプロ向けに小さなチップにまで縮小されている。このチップを頭に皮膚移植するだけで、あらゆる活字メディアへのアクセスが可能というのが、現状における最先端なのである。弱小ベンチャーだったドリーム・ホークスは急成長し、社名をヴァーチャル・リーディング社と変更して今日に至る。
むろん一部にアナクロニズムの輩というのは存在し、未だに書物という形態と物質性を愛し、紙のページを指でめくるという行為を重んじる一派も存在する。彼らは旧態依然たる紙の書物で書棚を満たし、その中央に座して、引き抜いた本をおもむろに開いて読むという行為を無上の愉しみとしている。これら少数派の物好きは化石人と揶揄されている。
こういう輩は、わがヴァーチャル・リーディング社の顧客ではないから、当然俺たちの仕事とは無関係である。さすがに印刷された書物は簡単には改竄されないからである。あるいは、システムの中心にあるデジタルアーカイブへの侵入が行われ書き換えがなされたとしても、紙メディアには何の影響もないからである。彼らは俺たちとは無関係に存在している、過去の遺物なのだ。

VRの本部にある巨大ハードディスクは、デジタルアーカイブと呼ばれている。デジタルアーカイブは、電子化された書物の情報を厳重に保管する書庫である。ここには、古今東西のあらゆる文書が、それこそ世界最古の印刷物とされる『百万塔陀羅尼』から野良之猫魔子のラノベ最新刊『甘党戦線異能あり』まで、『死海文書』や『ヘルメス文書』からウィキリークスの『アメリカ外交公電最新版』まで、『鳥獣戯画』から『こち亀』二百巻までおよそこれまでに印刷されたもの、文字として打ち込まれたもの、絵として描かれたもの、写真として撮影されたものはすべてここに収蔵されている。
印税についてはどうなっているかといえば、カラオケ的なシステムになっているというのがわかりやすいのではないだろうか。カラオケでは一曲歌われるたびに、その著作権者や歌い手に印税が入るシステムになっていることはご存じだろう。それと同様に、一冊読書=体験されるたびに、著者には印税が入るようになっている。なにしろ紙媒体の書籍はすでにデッド・メディアと呼んでいい状態であるから、物書きの人たちにとって今やVRこそが唯一の発表の場となっていると言ってもよい。しかも、このシステムが、読書を娯楽の頂点へと返り咲かせたおかげで、かつての作家たちが得ていたのとは比較にならない収入がもたらされるようになった。かくして「専業作家」が増加した。かつて出版不況と呼ばれた時代には、新人賞を取った若者は、まず就職するよう編集者から薦められたものであった。けれども、いまはとにかく書くことに専念するよう求められるようになった。「マスに受け入れられる作品でなくても大丈夫だから」というのが励ましの言葉である。なぜなら、VRには多種多様な読者がそれも膨大にいるため、どんな作品にでも必ず読み手が存在するからである。つまり、食いっぱぐれる可能性が大幅に低下したのである。体験の自由度が言語の方がより高いということで、絵で語るマンガよりも、小説の方がこのまれるようになったのも大きい。「作家が王様の時代」が再来したのである。
そんな作品が収録されているアーカイブに、厳重なセキュリティをかいくぐって侵入してくるハッカーが出現する可能性は当初から想定されていた。だから、原典が操作されたり破壊されたり書き換えられたことが判明した場合に備えて、代替用の原典も複数用意されている。けれども、これは操作、破壊、書き換えなどの行為が明らかになった場合にのみ実行される措置なので、気づかれないようにこっそりなされた改竄には対応できない。
それを即座に探知するシステムが、万物照応と呼ばれるものである。これは常時すべてのテキストを、複数の原典と照会し続けるという装置で、句読点一つの異常に至るまで瞬時に判別する事ができる。したがって、これまでのところ、俺たちがあわてて出動しなくても、問題解決までの間に、損傷された原典はすばやく代替用原典と入れ替えが行われ、すでに五十億を越えたといわれる読者たちには、まず間違いのない原典情報が提供されているというのが実状である。
そんななか、コレスポンデンスでは修復不能な改竄を行う輩がたまに出現する。それを可能にしているのが、ハッカー集団が開発した特殊なプログラムであり、あるいはそれを搭載したヘッドマウント型の装置である。どうしても、原典の物語を単に楽しむだけではなく、じかに原典に触れたいと思う輩はつねに存在するようであり、その多くは単なる愉快犯であるにせよ、俺たちはそれを厳重に取り締まらねばならないのである。
たいていのハッカーは装置を利用するわけだが、ごくごく希に、ハッカーの侵入経路を道具もなしに本能的に辿り、原典にまで到達できる特殊能力者が発生することがある。いわゆる、生得的ハッカーである。これは「よっしゃ、俺はハッカーになるぞ」と意志してなれるというたぐいのものではなく、きわめて偶発的、確率論的な出来事である。頭がよければいいというものでもないし、読書百遍脳己から原典に通ずというものでもない。
そして、俺の場合も、まったくの不意打ちのように、ある日突然原典に到達してしまったのであった。
(第04回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










