 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
六、『ひかりごけ』:結城雅美との出会い
それで終わったはずだった。
けれども、俺はどうやらそのときにある種の特異性を体得してしまっていたようだった。親が心配するとわかっていたので黙っていたが、接続される度に、俺はごく自然に文字列の並ぶ世界へと入っていくことができるようになった。つまり、原典へのダイブインが自然にできるようになっていたわけだ。
何となく俺にはルールがわかった。つまり、原典世界にずらりと並んでいる文字列をいじっちゃいけないということだ。いじったら、あの茶色の制服の人たちが飛んできて、俺はなんらかの処罰をうけるということ。あるいは母や父がなんらかの叱責を受けるに違いないということだった。だから、俺はそのことを誰にもつげないまま成長した。
そんな俺に変化を促したのは、結城雅美だった。というより、結城雅美との出会いだった。
どこで出会ったかって? わかった、じゃあその話をしようじゃないか。
その日俺は、武田泰淳の『ひかりごけ』の中にいた。すでに中坊になっていた俺は、中坊らしい冒険心と好奇心から、成人指定の書物の中によく潜っていた。吉行淳之介などはなかなか興味深い世界だった。こういう書物はPG十八くらいにすべきだという声もあったし、現在ではそうなっているものも実際にあるわけだが、当時はまだ野放し状態だった。過激な殺人事件や猟奇事件の頻発する江戸川乱歩や横溝正史を禁書にせよという声も当時からすでにあったが、まだそのころは野放しだった。『人間椅子』に実際に座ってみたときの、あの独特の感覚は未だに忘れられない。
巷では、AVの時代は終わったということがよくいわれていた。エロ小説が復権し、それに取って代わったからである。少し考えてみればわかることだが、なにしろVRは、各自の想像力に応じて楽しめる。隠れてこっそりアダルトビデオを借りたり買ったりダウンロードしたりする必要はもうないのだ。それらは単なる視覚像による性欲の喚起手段に過ぎないからだ。そんな単純な体験ではなく、エロ小説を直接脳に接続することで、読者=体験者は、音や匂い、色彩、さらには触覚までを伴った究極のバーチャル体験をすることが可能になったのである。そのせいで、時として、「未帰還者」が発生することが問題視されてもいた。特定の文学世界に惑溺してしまい、そこから現実に立ち戻ることを拒否する連中である。いうまでもないことだが、特に猥褻文学への没入者が多かった。従来のポルノ映画やAVにありがちだった女優への不満、男優への不満、筋立てへの不満がみごとに解消されたからである。そこでは、文字情報から、読者=体験者が、自分の想像力であらゆる官能に訴えかける強烈な体験を得ることができる。それぞれの主観によって、女優も男優も(多くの場合は、自分自身)自在に置き換え可能な文字世界の方が、より満足度が高いことはいうまでもないだろう。かくして、寝食を忘れて、各自の好みの猥褻文学に惑溺する輩が頻々と現れることになった。これを防ぐために、VR社では、丸一日戻らない場合は強制リセットがなされるという防御機構を装置に内蔵している。読者の生命を守るために必要な措置だと社では説明している。ちなみに、中坊の間では、『羊たちの沈黙』という作品に、レクター博士モードで入り込み、○○の味を体験するというのがひそかに流行したりもしていた。

さて、文学的関心というよりも、明らかに猟期的な興味から俺はその日『ひかりごけ』にダイブインしていたわけだったが、肝心の部分は本文には描かれていないことが判明して、俺はがっかりした。原文は戯曲形式になっていて、死んだ五助の死体を前にして、飢えた人たちが食うべきか食わぬべきかについて議論する部分がまずあり、結局結論が出ないでその日が終わる。船長の、
「うんだら、一日待つべ。明日の夜までだ。な、それよか、小屋を物故和して、薪にした奴を、すっかり運ばにゃあならねえ。いくらせつなくても、薪だきゃ運んどかなきゃならねえ。さ、行くべ。もうすぐみんな、一足も動けなくなるだ。さ、行くべ」という言葉の後は、
(一同、のろき仕種にて上手より退場)
(舞台、暗くなる)
(舞台、明るくなるまでに三日間を経過す)
(八蔵、すでに衰弱の極みに達して、仰臥す。西川、そのかたわらにうずくまる。船長、不在)
(『武田泰淳集 新潮日本文学42』新潮社、昭和51年第三刷,p.585)となっており、その間に人肉食が行われたことが、次のせりふによって示唆される仕掛けになっている。
「八蔵(きわめて低き声にて)なにも苦にするこたあねえだよ。な、おまえがいい人間だっつうことは、おらがよく知ってる。だからよ。
西川(すすり泣く)
八蔵 むりもねえだよ。人の肉さ喰うのは、つれえこったからな。
西川 おら、恥ずかしいだ。」
といった具合に会話が続くわけである。むろん、ダイブインすれば、ト書き部分は各自の想像力でいかようにも演出可能なのであるが、中坊であった俺は、その部分がどうしてもうまく想像できなかった。幾度もダイブインしてみたが、どうしてもリアルな映像が思い浮かばないのだった。
三回目にダイブインしたとき、俺は驚愕した。ほかにどういう反応が可能だったろう。なぜなら、洞窟はひかりごけで明るく演出され、そこに西洋風のアンティークなテーブルが設置され、白い陶器の皿に盛られた肉を、ナイフとフォークを使っておそらくは西川と船長とおぼしき二人が泣きながら食べているという場面に遭遇したからである。
そして、テーブルの脇には白い割烹着に身を包んだ若い女が立っていて、「本日のメイン、五助・ア・ラ・フランボワーズでございます。ほんのりと酸味のあるフランボワーズソースに一日漬けおきしました五助の腿肉を、赤ワイン、ローリエ、ブイヨンを加えたオリーブオイルでソテーしたものに、温野菜とマッシュポテトを添えました」
それに対して船長が、「うーん、この香り。つんと鼻をつくパスリ、セージ、ローズマリー、タイムといっった香草の匂いの奥から、サイモンとガーファンクルの『スカボローフェア』さながら、微かにさざなみたつかのごとくに呼びかけてくるのは、レモングラスとジンジャー。そして何よりも圧巻の香気を振りまくのがフランボワーズソースの薫香。ふんわりとやわらかく焼き上げられた肉は噛むほどにじわっとしたうま味を溢れさせて口内を幸せで満たしてくれる。口腔の至福、舌先の悶絶、喉元の感涙、そして胃袋の謝肉祭でありますなあ」
つづいて西川が「ああ、おれは、なんてものを口にしてしまっているのだ。それもこんなにおいしくいただいてしまっている。いいのか、こんなことでいいのだろうか。それにしても、うまい。かくして俺は生きる。生きてしまう」
と煩悶しながら肉を咀嚼し、若い女給仕が注ぐ高価なワインをがぶがぶと飲み干している。
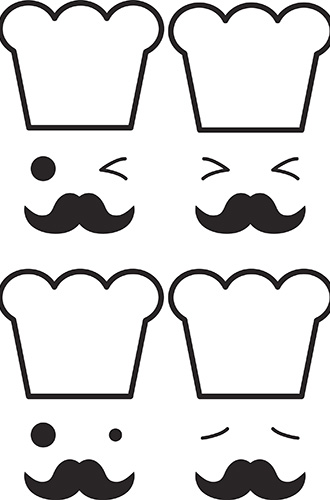
「ちょっと」
あまりのことに、俺はその若い女に声をかけてしまった。
「いいんですか、こんなことして」
「あら、あなたも食べる? 五助のお肉。まだランプ肉が残ってるわよ。お好みならサーロインやフィレだって出してあげるわ」
「ふざけんなよ。これってあれだろ。原典だろ。こんなことしたら、今この本を開いている人には、この場面がもろに伝わっちゃうじゃないか」
さすがに中学生になっていた俺には、原典に手を加えることの意味が了解されつつあった。
「あら、心配性ね、君は」
女はけらけらと笑った。
「ちょっとしたいたずらよ。すぐに撤収するから跡形も残さないし。個人的な、そしてささやかな戯れにすぎないのよ、こんなの」
そういうと、女はその場面と二重写しになっていた言葉の列から、ト書きの間に挿入した文字群をちゃっちゃっと抜き取った。一瞬後には、そこから船長と西川の姿は消え、元のト書きだけが残されていた。
「どうしたの。鳩が豆鉄砲食らったみたいな顔して」
呆気にとられている俺を、女はおもしろそうに見た。
「あ、もしかして」
女はさらに、俺の顔を注視してきた。
「な、なんだよ」
「あんた、初めてなの?」
「ち、違うよ。いろんな原典にダイブインしてきたし、『ひかりごけ』だって三回目だし」
「ちがうわ。そういうことじゃなくって、原典をいじったことがないのかってことよ」
「あ、当たり前だろ。作家の人が苦労して書いたものをいじるなんて、そんなひどいこと」
うふふ、と女は笑った。
「うぶなのね、かわいい。もしかして中学生?」
「そうだけど、それが何」
ちょっとむっとなって俺は女をにらみ返した。いつのまにか女はさっきの割烹着から、ピンクの縞模様のパジャマ姿になっていた。
「いいのよ。文学はそれぞれの人が自由に解釈していいものなのよ。遊んでも元に戻せば罪にはならないわ」
「ほんと?」
「ほんとよ。だって、わたしこれまでいろんないたずらしてきたけど、こうして、平気で暮らしてるもの」
俺が何か言おうとしたときだった。
「あ、来る」
女があたりを見回して、低い声で言った。
「虚構パトロールにかぎ当てられたわ。二人も同じ場所にダイブインしてるんですもの、目立つのも当然ね。じゃ、わたし行くわね。あんたもすぐ戻った方がいいわよ」

「あ、それでさっきの話だけど」
俺としてはもう少し、自由な改竄のことについて聞きたかったのだが、
「もうだめよ。捕まりたくないでしょ。わたしは結城雅美、あんたは?」
「御来屋隆」
「よかったら、会いにいらっしゃい。わたしは、東京の偕成会病院にいるから」
「東京?」
ちょっと無理っぽかった。だって俺は京都の中学生だったからだ。修学旅行だって、東京から京都に来ることはあるかもしれないけど、京都から東京に行くなんてことがあるはずはなかった。
結城雅美が消えたのを見て、俺も怖くなってすぐに回帰した。それ以後怖くなって、当分の間『ひかりごけ』には入れなかったし、ほかの作品に入ることも躊躇われる感じになった。ダイブインした者を監視している虚構パトロールなんてものがあるのを知ったせいだった。自分が自然にやってたことだけど、どうやらこれは禁忌に触れることのようだとなんとなく了解できたからだ。
ところが不思議な縁というものはあるもののようだ。通例うちの中学の修学旅行は九州と決まっていたのだったが、その年は火山活動が妙に活発だということで、九州は取りやめになった。代わりの行き先をアンケートで募ったところ、東京ディズニーランドが一位となった。「修学」という意味と齟齬するという声も多くあったが、班別行動でテーマを決めて東京を取材することをメインに据え、ディズニーランドは一日だけ訪れるということでなんとかまとまってしまった。
班別行動の途中で俺は友人の一人に「ちょっと野暮用で抜けるわ」と言い残して、下調べしておいた偕成会病院を訪れた。結城雅美は医師でも看護士でもなく、患者だった。
「あら来たのね」
あのときみたピンクの寝間着姿でベッドに横たわったまま、結城雅美は俺に微笑みかけてきた。
「病気なんですか?」
分かり切ったことを聞いてしまう愚かな俺だった。
「みたいね」
そう言って結城雅美は笑った。おそらく二十代のはじめくらいの年齢だろうと俺は想像した。以前、『ひかりごけ』で会ったときには、そういう観察をする余裕を欠いていたのだった。
「あら、珍しい。お客さん?」
母親らしい女性が、着替えを持ってやってきた。
「どうでもいいでしょ。ほっといてよ」
少しきつい口調で結城雅美は答え、母親は荷物を置くとそそくさと帰っていった。
「握手といきたいとこだけどね」
結城雅美は、力なく笑った。
「わたし手が思うように動かせないの。足ももう動かないわ」
「え?」
「そういう病気なの。そのうちこうやって話すこともできなくなって、最後は呼吸することもできなくなって、おしまいってわけ」
衝撃だった。若いのにそんな未来が待っているだなんて。
「あら、言葉を喪ったの。まったくうぶねあんたは。ま、中坊だからしかたないけどさ」
「治らないんですか」
「みたいね。いまの医学じゃ無理みたいよ。でも、いいの。わたし自由だもの」
「ああ」
「そうよ。さっきまでどこ行ってたと思う。メルヴィルの『白鯨』よ。白鯨を、イルカほどの大きさに縮めてやったら、エイハブ船長のやつ拍子抜けして腰抜かしてたわ。あんだけ長いお話のラストがウルトラしょぼくなって、完全なお笑いになっちゃった」
「戻してきたんですよね」
「ええ、戻したわ。でも、ちょっとだけいたずらしてきた」
「っていうと」
「エイハブに襲いかかるモビィ・ディックの尻鰭の付け根の所に、キティちゃんマークつけてきちゃった」
そういうと、ほら急いでといいながら、彼女は俺に、VRの装置をかぶるよう促した。
「最後のとこに飛ぶわよ」
俺は実はこの話をまだ未体験だったから、ラストだけ見せられてもなとは思ったが、いきなり目の前に躍り上がった白鯨の巨大さに圧倒された。思わず悲鳴を上げる俺を、結城雅美は面白そうに微笑みながら見ていた。
「ほら、海に沈んでいくわ。最後の尻尾を見逃さないで」
彼女に促されて俺は目を凝らした。そして、しっぽの付け根にキティちゃんマークが確かにあるのをおれは確認した。ただ、そう思った瞬間に、そのマークは消えてしまった。
「あ、消された」
悔しそうに結城雅美がつぶやいた。
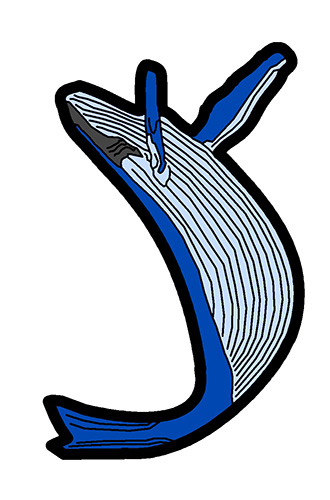
「やばいじゃないですか」
「だいじょうぶよ。痕跡は残してないから。わたしの仕業だとはばれないわ」
「どうして?」
「すばやくやったからね。パトロールがかぎつけて修復にむかったころには、誰がやったかなんてわかりっこない」
「ほんとに?」
「ええ、教えようか、コツを」
ルールは簡単だった。素早くやること。重大な変化は楽しんだらすぐに消すこと。微細な変化をギャグとして残していく場合は、絶対に足跡を残さないこと。それだけだった。
「じゃあ、そろそろ帰って」
見ると、結城雅美は眠たそうだった。
「わたし、一日十八時間くらい眠るの。ちょっと前までは十六時間だったけどね。もうすぐ二十時間になって、最後は眠ったままになると思うわ」
「すみません。疲れさせちゃいましたね」
「いいえ、楽しかったわ。弟子がとれたわけだし」
「また来ます」
「そうね、起きてたら話しましょう」
「次はどの小説に行きますか」
「うーん、わからない。そのときの気分で決めてるから」
「そうですか」
「そうです」
見ると彼女は、もう目を閉じていた。
「帰ります」
そういうと、唇を少しほほえみのかたちにゆがめてうなずいた。
(第06回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










