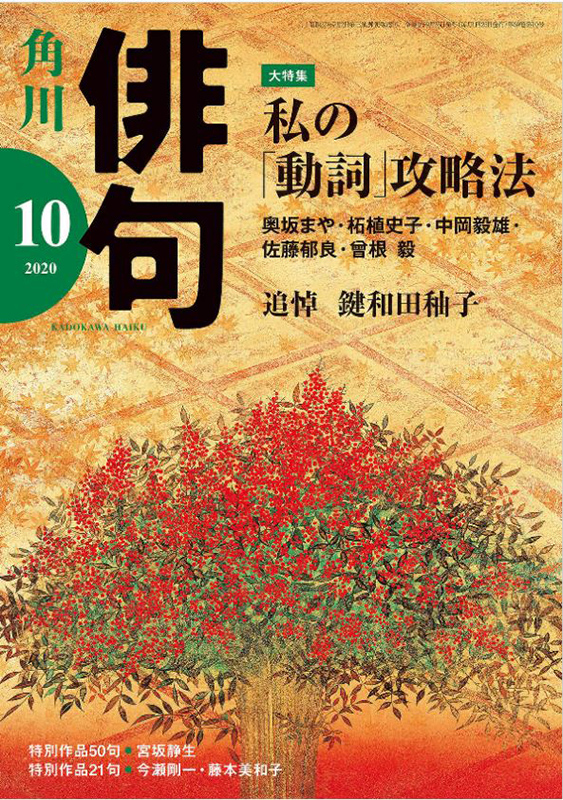
角川俳句九月号から十一月号にかけて、川名大さんの「戦後の三橋鷹女」が連載されている。川名さんは高柳重信の「俳句評論」系の批評家という印象が強いが、必ずしも前衛俳句にこだわらず俳句・俳壇全般を俯瞰できる視点をお持ちになっている。また的確な資料精査も川名評論の大きな特徴だ。俳句・短歌の世界は少部数刊行の結社誌や同人誌が基盤になっているので、時間が経つとすぐに入手困難になってしまうことが多い。川名さんはそういった膨大な資料を蒐集した上で、俳句史、俳人史の機微を明らかにしてくれる。希有の俳句評論家である。
いちばん大切なことは、その人自身が、どうしても何事かを書き、それによって何事かを訴えたいと、本当に切実に思うことであって、そうした切実な思いがなくては、うまい俳句など書けるわけのものではない。(中略)富澤赤黄男が「自己流がいちばんよろしいのです」と書いた時、それは当然のことながら、自分自身の人生観や世界観によって裏付けされた、自分の作り出した俳句詩法を指していたのである。
高柳重信「薔薇」終刊号 昭和三十二年(一九五七年)十二月
「同じことを幾度繰り返してもどうなることではない」あの日病院のベッドの上に坐って富澤さんはこう言われた。自他を鞭打ってやまぬ厳しい言葉と私はこれを解した。
三橋鷹女「最後の訪問」「俳句評論」第二十三号 昭和三十七年(一九六二年)六月
高柳君、僕は自分のもっているものを全部出しきったよ、これからいくら俳句を書こうと思っても、今まで書いてきたものよりいいものはかけないんだ。(中略)だから書かないんだと。(中略)今まで書いたのと同じレベルくらいの作品ならば、これからも書こうと思えば書けるけれども、それは無駄だ、と言うんだな。
座談会「西東三鬼富澤赤黄男の人と俳句と」「俳句研究」昭和三十七年(一九六二年)五月 高柳重信の発言
川名さんの評論からの孫引きだが、今、富澤赤黄男や高柳重信、三橋鷹女らの前衛俳人たちの作品を読む意味はこれらの言葉で言い尽くされているだろう。重信が同人誌「薔薇」を創刊した際の文章で、「薔薇」は新興俳句の芸術至上主義的側面に光を当てるのが目的の雑誌で、赤黄男と高屋窓秋を同人に招こうと画策したが、窓秋は俳句活動を中断していてかなわなかったと書いている。また重信は三顧の礼をもって鷹女を同人に招いた。彼らには決して同じことを繰り返さない純粋な俳句作家という意識と矜持があった。句集ごとに、極端な場合は一句ごとに、小説などの自我意識文学と同様の新たな試みを為そうとしたのだった。
この芸術至上主義的で独立作品(作品集)主義的な姿勢に、僕は諸手を挙げて賛成しない。俳句は非常に裾野の広い表現ジャンルだからだ。虚子のように句会で同じような俳句を読みちらし、「ホトトギス」何百号の節目に門弟から催促されて熱もなく句集をまとめるという道行きも俳句には許されている。句集をまとめなくてもいっこうにかまわないジャンルでもある。ただプロを自認するならば、芸術至上派も俳句生活派の一定の覚悟が必要だ。
他人からは余裕派と見られ、似たような、だが少しずつ変わってゆく俳句を書くのなら俳句は量産しなければならない。呆れるくらい書かなければ俳句の本質には届かないだろう。芸術至上派なら文字通り同じ試みを繰り返してはいけない。作品数は少なくなり、今のジャーナリズム制度では俳壇名誉という面でも金銭面でも苦しい立場に追い込まれる。一人の作家が俳句で同じことを繰り返さないのならば、頑張っても生涯句集は十冊を超えないだろう。どちらを選ぶかは作家次第。ただいずれも強い覚悟がなければ一流にはなれない。
敗戦
子を恋へり夏夜獣の如く醒め
ひとり子の生死も知らず凍て睡る
愛し吾子
還り来てちちははのへに夏痩せぬ
ネクタイの臙脂凍てたり結んでやる
ばら剪るつて青年ギリシャ語をつぶやく
三橋鷹女 句集『白骨』昭和二十七年(一九五二年)
鷹女第三句集『白骨』には出征した我が子を思う句が多く収録されている。社会性が希薄という意味で女性俳人ならではの作品である。こういった表現内容は身も蓋もない言い方をすれば短歌の方がふさわしいところがある。俳人も生活者の一人だから、実生活で大きな事件が起こればそれは必ず作品に投影される。しかし俳句という器を考えればそれでいいのか。もちろん鷹女は俳句に自我意識を詰め込んだ作家ではなく、俳句本質に沿って自我意識の在りかを探った作家である。
緑陰やわれや一人の友もなく
菜の花やこの身このまま老ゆるべく
昏れて無し冬木の影も吾が影も
死への近道枯猫ぢやらし摘みこぼし
白露や死んでゆく日も帯締めて
三橋鷹女 句集『白骨』
句集『白骨』に鷹女は孤独や死を詠った句を数多く収録している。桂信子はこれらに句について「この時、まだ鷹女は五十をすぎたばかり、このように老いをうたうのは、老いていない証拠ではないだろうか」と批評した。永田耕衣は「鷹女さんのばあい、晩年意識は作句上強靱に創り出された意識であり、現実上の意識きりではない。それは閑かなるべき願望の晩年意識とはウラハラに、つねに孤独の賑わいに出て、自己をあまえさせ、遊ばせ、生の執着を嵩じさせる一つの手立てにすぎないばあいが多い」と書いた。
川名さんの評論からの孫引きだが、信子も耕衣も鷹女晩年意識の文学的意図を正確に捉えている。乱暴な言い方をすれば、優れた作品、芯の通った作品を読むのは難しくないのである。またそれが次の俳句創作のヒントになる。鷹女のように優れた作品があり、信子や耕衣のように優れた批評眼を持つ俳人たちがいた時代は短かった。俳句の大海原を埋め尽くすのは俳句生活派の無数の句だが、俳句が文学であることを保証するのは前衛といった名称がふさわしいかどうかは別として、強烈な作品意識を持つ一握りの作家たちである。
羊歯地獄 掌地獄 共に飢え
三橋鷹女 句集『羊歯地獄』昭和三十六年(一九六一年)
「羊歯地獄」は一字空白のある俳句で、鷹女ではよく知られた作品である。明らかに富澤赤黄男の影響を受けている。ただこの句は鷹女を代表する作品ではない。信子や耕衣が指摘したように鷹女はぜんぜん老いてなどいない。『羊歯地獄』というタイトルがそれをあからさまに示唆しているだろう。作品至上主義的な俳句を志向する作家の自我意識は強い。それを形式的にも内容的にも表現せずにはいられない時期が必ずある。しかし本当の勝負は自我意識を抜けた境地にある。なぜか。俳句だからである。
羊歯を摑んで老年羊歯となる谿間
巻貝死すあまたの夢を巻きのこし
末は樹になりたい老人樹を抱き
をちこちに死者のこゑする蕗のたう
ふるさとは山鳩が啼く夢も老いて
青ざめて八ツ手が咲けばあの世めく
三橋鷹女 句集『橅』昭和四十五年(一九七〇年)
句集『橅』の頃に鷹女は自らの主題である死と老いと、俳句文学とに折り合いをつけたようだ。老いも死も静かである。風景のように描写される。しかしそれでいて艶やか。鷹女ならではの表現に達している。
こういった鷹女文学の全貌を、川名さんは比較的短い集中連載で明らかにしておられる。読めば必ず得るものがあるだろう。
岡野隆
■ 川名大さんの本 ■
■ 三橋鷹女の本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■














