 「世に健康法はあまたあれど、これにまさるものなし!」真田寿福は物語の効用を説く。金にも名誉にも直結しないけれど、人々を健康にし、今と未来を生きる活力を生み出す物語の効用を説く。物語は人間存在にとって一番重要な営為であり、そこからまた無限に新たな物語が生まれてゆく。物語こそ人間存在にとって最も大切な宝物・・・。
「世に健康法はあまたあれど、これにまさるものなし!」真田寿福は物語の効用を説く。金にも名誉にも直結しないけれど、人々を健康にし、今と未来を生きる活力を生み出す物語の効用を説く。物語は人間存在にとって一番重要な営為であり、そこからまた無限に新たな物語が生まれてゆく。物語こそ人間存在にとって最も大切な宝物・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、かつてない物語る物語小説!
by 遠藤徹
4.キメラ猫(前編)
「あらゆる意味で、わたしはあいつに勝利している」
海原はそう語った。
「そうかしら」
応える声があった。
「斜に構えるのはやめたまえ。その通りだろうが? 文壇での地位も名誉も権力も、巷における民心の掌握もわたしが圧倒的に優位だ。というより、あいつはほとんどなにも持っていないに等しいからな。そして、・・・極めつけは君だ」
「あら、わたし?」
「そうだとも。あいつは、ついに君を手に入れることが出来なかったんだ。なにしろ、君はわたしのものになったからね」
愛しげに、海原はそのものの体を撫でた。
「かたちとしてはね」
応えたのは、驚いたことに一匹の猫だった。けれどもそれは奇妙な猫だった。顔の右半分は三毛猫、左半分はロシアンブルーのような色の毛に覆われていた。逆に体の右半分の上体部分は黒い毛に覆われている。アルゼンチンに、キメラと呼ばれる通常の顔と黒い顔をもった変種が居ることは知られているが、この猫はもっと奇妙だった。特に青い毛に覆われた左半分の顔が異様さを強く感じさせる。
「かたちとしては?」
海原はさも可笑しそうに笑った。
「かたちにならないものがあるというのかね。精神的なものとか、そういうもののことを言っているのかな」
「そうかもしれないわね」
「それなら、わたしには関係ない。わたしはこの世にしか関心がないからね。つまり、この一回切りの生にという意味だ。死後に無間地獄に堕ちるといわれてもわたしはまったく恐れはしない。そんなものがあるとは思っていないからだ。そんなものがあると思わない人間からすれば、そんなものは存在しないのだ」
海原の膝の上で、猫は流体のように身をうねらせた。
「だから、どんな禁忌を冒そうとかまわない、というわけね」
「禁忌を恐れるよりは、それによってこの現世で得られる見返りに目を向けるんだ。この一回きりの生を太く濃く生きるためにね。わたしには、それにまさる悦びはないからだ」
猫は色の異なる二つの目で、海原の顔をじっと見た。

「そのためなら、どんな報いを受けようとも厭わないってこと?」
「そうとも。俺は過去を捨て、死後の未来を捨て、いまを選んだ。今生のこの生だけを。そのためにどんな報いを受けようと構いはしない。もっとも、俺を誅することができる能力者はすべて抹殺済みだがな」
「ただ一人を除いて」という言葉を海原は飲み込む。いやあいつはもう死に態だ。そもそも奴は言霊師の傍流、遊興と娯楽を司る外師でしかない。俺を呪殺するどころか、闘う力すら、もとより持ち合わせていないのだから。
「あら、哀れね、あなた。彼のことを懸命に見下そうとしてるのね」
どうやら、呑み込んだ言葉もこの猫には届いてしまうようだ。この世ならぬ猫なのだから、それも致し方のないところだった。
「そうとも。考えてもみたまえ。わたしは、国の政を常に背後で支えてきた言霊師の直系の子孫だよ。それに引き換え、あいつは野に下った傍流の外師の血筋だ。外れものだから外師。除外されたから外師。そもそも、わたしとでは立っている場所が違ったのだ。殺すまでもないやつ、むしろ生かしておいて弄る方が面白いやつということだ」
「とはいいながら、結局あなたは彼に囚われているのよね。ほんとは彼が必要なんでしょう? だから殺せない。だからこうやってわたしを呼び戻したりしたわけでしょ」
「なあに、これとて、あいつを悔しがらせるための方策に過ぎない。お前を俺が所有しているという事実そのものが、あいつを苦しめるはずだから」
「ほんとうは認めてほしいのよね、彼に。だから、あなたはこんなに必死なのよね。あえて、禁忌を冒してまで彼の気を引こうと懸命になってるのよね」
「そんなはずはないだろう? いまのわたしが持っている力に比べて、あいつはなんと非力で卑小なことか。わたしは小指一本であいつの首を飛ばすことだって、心臓に穴をあけることだってできるんだ」
「いえ、できないわ。できっこない」
猫はからかうような声を上げる。
「いずれにせよ、禁忌もまた力。それを使うことができるというのもまた力。そして、わたしはその力をもつことをこうして証明したのだ。あいつには絶対できないことをな」
「からっぽなのね」
猫はため息をつく。
「哀れでならないわ、あなたのことが。自分で自分を滅ぼして何が楽しいの? 禁忌を冒すようなこと、彼はできないんじゃなくてしないの。それがわからないかしら」
「強いは弱い、弱いは強い・・・そう言いたいのか? シェークスピアでも気取ってるつもりか?」
ことばとは裏腹に、海原の手はやさしく猫の背中をなぞる。猫はその意に反して、心地よさげな声をあげる。
「困ったものね。体は猫だから、猫なりの反応をしてしまうわ。残念ながら、意に反してだけど」
「十分だよ、わたしにはそれで」
ソファに腰かけた男は、薄く笑う。
「形だけでも勝ちたい、そう思ってるのね。いえ、形だけでも勝っているって」
猫の声は少し苦しげにも聞こえる。
「なるほど、あなたがたの一族は、ずっとそうやって常に勝ってきた。あらゆる歴史のなかで、常に為政者の側につくことによって。自ら言霊を操った卑弥呼の治世を例外として、あなたがた一族は常にその正体を秘匿し、陰から言霊を発して人心を操作してきた」
「そうだ。常に勝ってきたという言い方は正しくない。勝者に用いられたというのが正しい。わたしたちの一族は望むと望まざるとにかかわらず、国政に協力させられてきたのだから。為政者というのは常に残酷なものだ。協力を拒むと、その本人ではなく、本人の家族や子供など、愛する者を順番に殺していった。だから、わたしたちは悲劇の一族でもあった」
「でも、それにもかかわらず一度はそこから降りようとした。つまり、・・・消えたのよね」
「そうだ。あの勝ち目のない総力戦に国民を動員する仕事をやらされたわたしの祖父が、それを決意した。ピカドンの投下を目の当たりにして、祖父はおのが一族の呪われた運命に絶望した。だから、敗戦の日に、一族もろともに服毒して自害した」
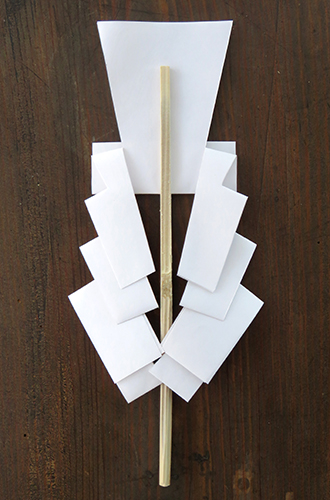
「それ以後、言霊の力に、テレビや広告という新しい力が取って代わったわけね」
「ああ、でも、メディアの操作は表面的なものだ。魂までを捉えることはできないからな。どんなすぐれたキャッチコピーでも、そこに言霊が宿っていなければ、一過性の感染力しかもたない」
「だから、為政者は、あなたたちを失ったことを激しく嘆いた」
「そうだ。わたしは祖父がひそかに囲っていた妾の子だった。おそらく祖父は、わたしが己が能力に気づかずに育つことを期待したのだろう。なにしろ、母は祖父の正体を知らなかったから、この呪われた能力のことも知らなかった。だから、一介の市民として自分の血筋がかたちだけでも存続することを祖父は願ったのだと思う」
「あなたも知らずに育った。そうよね」
「そうだ。なにひとつ知らなかった。わたしはこの呪われた能力のせいで産まれた時から吃音者だった。誇らしく思うどころか、周囲から嘲られみじめな子供時代を過ごした」
「でも、ある時開眼したのよね。あるきっかけで」
「そうだな。あるきっかけで」
海原の返事には、どこか忌々しげな感じがあった。
「くすぐられたのよね。〈外なる言葉〉によって」
「その話はやめてくれ。わかるだろう? わたしはいまたいへん不愉快だ。膝の上にいる小うるさい猫をひねり殺してやりたい気分なんだよ」
そんな海原を首をもたげて見やった猫は、さもおかしげに笑う。人間の声ではなく、あえて猫の声で笑う。
「それは本望といいたいところだけど、まあいいわ。いまはやめておいてあげる。代わりに、別の話をしましょうか」
「いやな予感しかしないが」
「そうね。そのいやな話よ。でも大丈夫、歴史の話だから。言霊の一族では無能者扱いされてきた分派の話よ」
「やはりそれか。お前は意地が悪いな」
「そうね、それが猫の性分なのかもね。でも、あなたきらいじゃないでしょ。わたしと話すのは」
「ああ、お前の声は心地よいからな。さすがは詠唱師の血筋だ。とはいえ、お前たちもまた、つねにあの外師どもとつるむ下郎どもだったがな」
「でも、あなただってわかってるでしょ。わたしたち、とりわけ外師たちがいたことで、この世界のバランスが保たれてきたんだっていうことは」

「まあ、それは認めざるを得ない。だが、いずれにせよお前たちは主流ではない。お前たちが歴史を作ってきたわけではない」
「表向きはそうね。というか、そんなことはどうでもいいのよ外師や詠唱師にとっては」
「権力には関心がない、・・・とそういいたいのか」
「極言すれば、そうなるかもね。いずれにせよ、言霊で縛られた国家は硬直化する。一つの方向へと導かれていく。それは、極めてもろい状態よ。危険な状態なの」
「それは、考え方によると思うが」
「たとえば、天照大御神が天の岩戸に籠ってしまった時、世界は完全に凍結し硬直化したわけよね」
「ああ、その話から始めるのか?」
「そうよ、だってアメノウズメこそが、わたしたちの母だもの。そして、イザナギとイザナミに捨てられた奇形児とされるヒルコがわたしたちの父だわ。もちろん、神話のうえでの話だけど」
「今様、田楽、狂言、狂歌、川柳、戯作、漫才、落語・・・」
「いわゆる芸能、それも滑稽な芸能の世界だな」
「そうね、簡単にいえば笑いの力よね。それも為政者ではなく民衆のなかから立ち現れてくる力としての笑い」
「そんな笑いの原動力だったのが、外師。そう、『はずし』って呼ばれるのは、もともとは蔑称だった。言霊の本来の力から外れた者、言霊師の世界から外された者、そういう意味だった。けれども、いつの間にかその意味は変わっていった。言霊の働きをずらし、そして外す者という意味へと」
「過大評価だとは思うがね」
不愉快そうに、海原は答える。
「口ではそう言ってるし、頭では認めようとしてないけど、あなただって魅了されているくせに。自分には到底できないあの脱臼した笑い、あの自由に憧れているくせに」
「それはない。断じてないぞ。もう終わりだ。縊り殺されたくなかったら、この話はおわりにしろ」
「あら、残念だわ」
猫は海原の膝の上で身を起こすと、液体が流れ落ちるような優雅な動きで、分厚いカーペットの上へと降りてゆく。そこで再び身を丸める。
海原は、その仕草をいとおしげに見守っている。ゆったりとした沈黙の時間が訪れる。けれども、それはどこか満たされた気配に溢れた静寂である。
(第12回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『物語健康法(入門編)』は毎月14日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







