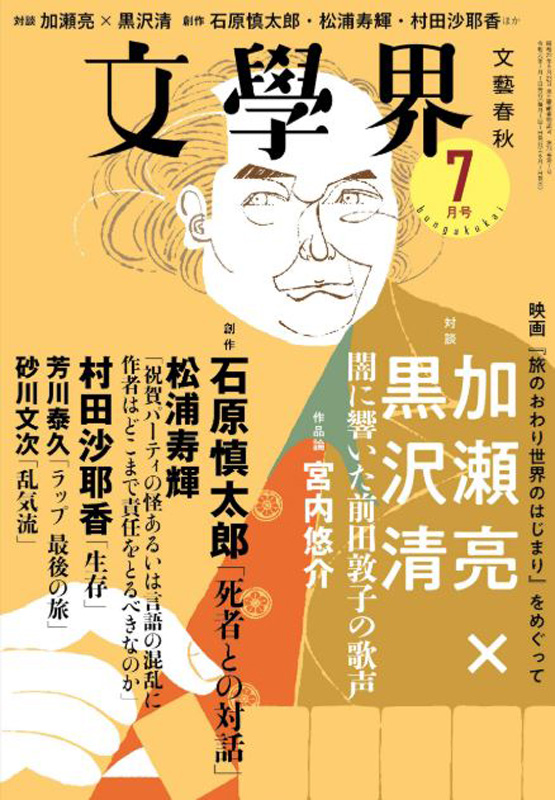
芳川泰久さんの「ラップ 最後の旅」はどこかで読んだテーマだなと思って調べたら、以前「蛇淵まで」という小説を取り上げていた。数誌の小説文芸誌を読み飛ばしているので、内容は覚えていても作者名まですぐに思い出せないことが多い。すいません。
「蛇淵まで」も今回の「ラップ 最後の旅」もいわゆる母モノだ。愛情深いと言えば聞こえはいいが、子供の精神までも束縛してしまう母親を描いた作品である。最近になって毒親という言葉が生まれたがそれとはちょっと違う。母はあくまで子供のことを思い社会的に偉大でもある。ある側面から見れば非のつけようのない母親なのだ。しかし思いもかけない形で子供を束縛する。それが大人になってもある種の恐怖として残り精神から抜けない。
この手の母モノ小説を書く作家に荻野アンナさんがいる。荻野さんの母親は江見絹子さんで画家として知られる。気難しい芸術家であり娘に厳しい母でもあった。荻野さんは父母だけでなく事実婚のパートナーをも介護して見送ったが、それを小説に書いておられる。特に母モノが秀逸だ。
小説を読む限り荻野さんが単に親孝行から母親を介護したとは言えない。怖いのだ。生きている母親が怖いというのはもちろんある。しかしそれだけではない。我が儘で高圧的で愛情深くもある母親が死んでしまうことの方が遙かに怖い。生きていれば会話してその意図や感情を確かめることができる。しかし亡くなってしまうとそれができない。献身的介護は少しでも長く母に生きていてもらいたいためでもある。
実際荻野さんの小説は母親が亡くなった後を描いた小説の方に秀作が多い。娘は常に母を思い出し恐れている。時間が経っても記憶が薄れることはない。むしろ亡くなった後の方が母の怖さが増している。この感覚は当事者にしかわからないだろう。しかし強烈な個性を持った母親が生きている間よりも、亡くなった後の方が怖いと感じる人は少なくない。
こういった母子関係は、漠然と母―娘に多いのだろうと思っていた。同性の方が密着した母子関係になりやすいからだ。しかし芳川さんの小説を読んで母―息子でも生じることを知った。論理的には決して割り切れない純文学小説にうってつけのテーマである。
このおれをいま浸食してくる強い恐怖は何なのか。お袋じたいは怖くはないはずなのに、どうしてこうもじっとして居られない感じになるのか。いくら考えても、わからない。ただ、どうしようもなく不気味で不安なのだ。何かが急に現れてきそうで。その浮上してくる何かが怖いのか、と訊かれても、何が出てくるかわからないから答えようがない。なにか姿を見せるのではないか、という予感にいたたまれないのだと気づいたとたん、おれの脳裏に、病院からお袋の状態が急変したと電話をもらう直前まで見ていた夢のなかの映像がぽつんと現れた。
それがあのときの夢で見たものだと思ったのは、その白くて丸い建造物の前におれが立っていて、その不思議な形に、これはいったい何だろう、お袋はこんなでかい墓に入りたいのだろうか、まさか、と否定してみたものの、夢が覚めてもお袋の葬式を終えても疑問が強く残ったからだった。いまなら、それは釈迦の遺骨の一部を納めたストゥーパ、つまり仏舎利塔だとわかるが、わかったとたん、おれはお袋の凄まじい意志に打ちのめされていた。というのも「また生まれてきたら、おまえを生みたい」と言って目を閉じたお袋が、そのあとおれにあの夢を見させたとしか思えなかったからだ。
(芳川泰久「ラップ 最後の旅」)
「ラップ 最後の旅」の主人公は大学教授の「おれ」で五十五歳になる。母親はもう三十年前に亡くなっているが最後まで強烈だった。母はおれが中学生の頃から自分は五十五歳で死ぬと言い続け、実際に五十六歳の誕生日直前にガンで亡くなった。見舞いに通っていたおれが最後に聞いた言葉が「また生まれてきたら、おまえを生みたい」だった。それがいわば母親の遺言になった。
おれは母親が生きている間に結婚しているので、強烈な自我意識と息子への愛情を持った母の呪縛から逃れられなかったわけではない。しかし物心ついた頃から心と身体に染みついた母の不気味でもある愛情がどうしても抜けない。一人前の男として母はおれを大学に進学させ就職させ結婚もさせたが、それでもなお母が自分の根っこのところをコントロールしていると思えてしょうがないのだ。なぜ母がそんなことをするのか、その本体(本質)はなんなのだろうと「いくら考えても、わからない」。なにがそんなに不安で怖いのかと聞かれても「答えようがない」。ここに作品のテーマが示されている。
母が亡くなった年と同じ五十五歳になったおれは、母親の最後の言葉が気になり始める。その言葉通り五十五歳で亡くなったのだから、母は必ず「また生まれてきたら、おまえを生みたい」という遺言(予言)を実行するだろう。しかし母がまたおれを生むためにはまず女の子に転生していなければならない。そしてその子がおれを生むのなら、おれはその時には死んでいるはずだ。
おれはふと、母が死んだ翌々年に生まれた娘の美紀が母の生まれ変わりではないかと思い始める。また病床で母が「自宅の仏壇に置いてある大学ノートに、家訓のような言い伝えを拒んだせめてもの罪滅ぼしに、ちょっと前からこっそり始めた俳句を書いておいたから」と言ったのを思い出した。おれの実家は春日部にあり、『おくの細道』に具体的な記述はないが、元禄時代に芭蕉が実家に泊まって子供を作ったという真偽不明の言い伝えがあった。芭蕉が先祖なのだから俳句を詠まなければならないという家訓があった。しかしそれを怠り続けた母は死の間際になって俳句を詠み始めたのだった。
母の死去直後には気にならなかった大学ノートを調べると、確かに俳句が書いてあった。またふとした偶然で娘の美紀が小学五年生の時に詠んだ俳句の中に、母が生前詠んだ句とまったく同じものがあることを知った。おれはゾッとした。娘は母の生まれ変わりじゃないのか。さらに美紀は婚約中だったが、妻が「できちゃったのよ」「ダンジらしいわ」と言った。娘が男児を産めばその時点でおれは死んでいるはずだ。おれはいてもたってもおられず、俳句好きの友人を誘って東北に吟行に行くことにした。『おくの細道』の足跡をたどり家に流れる俳句の血筋を確かめるためだ。また吟行旅行は娘の出産予定日に重なっていた。それはおれの死ぬ日でもあるはずなので、現実逃避の旅でもあった。
妻の、売店に要るものを買いに行ってくるという声に、おれは赤ん坊を焦点も定めずにずっと見ていたことに気づく。(中略)女の子か、とつぶやいていた。(中略)その声に森井の声が重なる。(中略)おれのタロット占いじゃ、おまえにうまれる孫、女の子だ。(中略)そのあとにつづく言葉を思い起こしながら、おれは震えが止まらない。言ってみれば、女帝のようなもので、豊穣の運に恵まれている、しかもな、おまえとものすごく相性がいい。そのあとだ、おまえを守護してくれる母親みたいな存在だから、と森井は言ったのだ。(中略)
おれは美紀のベッドの縁につかまっていた。お袋の意志から、おれはこうして逃れられないのか。思い返せば、お袋が、よかれと思って強い意志でおれを守護しすぎることがイヤだったのだ。でも生前、それをお袋には言えなかった。薄々、お袋の振る舞いの底には、おれへの強い思いがあると気づいていたからだろう。おれはどこかでお袋の意志を尊重するような生き方をしてきたのだ。お袋が死んでから、そのことを意識し、遅れて、いない相手に勝手に反発し、ようやく縛られない生き方に慣れてきたのに。(中略)これからずっと、この子をお袋の生まれ変わりだと思って生きるのか。お袋の仕込んだ呪縛のように思いなされた。(中略)
「お袋なの?」とおれは小さな声で訊いていた。
瞬間、赤ん坊の口元がぴくりとゆるんだように動き、おれにはそれがお袋の微笑みのようにしか見えなかった。
(同)
妻から娘が産気づいたが難産だという電話があり、おれは急いで帰京することにした。途中で無事子供が産まれたという電話がかかってきたがおれはまだ生きている。母の遺言(予言)など気の迷いだったのだと安堵して病院に行くと、赤ん坊は女の子だった。初期のエコー検査で男の子らしいと医者に言われたがその後性別を確かめていなかったのだ。
おれは同僚でちょっとオカルト趣味のある森井の言葉を思い出した。おれが母親の遺言に悩んでいることを話すと森井はタロット占いをしてくれ「おまえにうまれる孫、女の子だ」「しかもな、おまえとものすごく相性がいい。おまえを守護してくれる母親みたいな存在だから」と言ったのだった。
おれは決して「お袋の意志から逃れられない」。母親はいつまでもおれを守護し続ける。おれは孫の女の子を「お袋の生まれ変わりだと思って生きる」ことになる。それは「お袋の仕込んだ呪縛」だが、「どこかでお袋の意志を尊重するような生き方をしてきた」せいでもある。
ページをめくっていると「旅立」とくくられたところに、「弥生も末の七日」とあって、オギノが諳んじた通りだった。おれはオギノが暗記していたことに刺激され、『おくの細道』を初めから読みはじめると、地の文とはさまれる句の間合いというかリズムが心地よい。これ、何かに似ている、と思い、理由もなく、どこかラップと合いの手の感じに似ている気がして、読み進んでいたページを冒頭にもどると、「月日は百代の過客、過ぎ行く年も旅人、舟で生き、馬と生きても旅人、旅を住処なんて最高、イエー」と口が勝手に動いていた。
(同)
「ラップ 最後の旅」は二百枚の中編である。どうしてもその謎が解けず呪縛から逃れられない母子関係が主題だが、それをフィクシナルな小説に仕立てている。おれの家が芭蕉の血筋で母も娘も俳句を詠み、おれも詠み始めるというのがこの小説最大のフィクションである。
作者の芳川さんは仏文学者だが数々の漱石論もあり、特に漱石初期のユーモア小説を愛好しておられる。その影響もあるのか主人公のおれは『おくの細道』をラップ調で朗読し、実際に東北に吟行旅行に行った際も盛んにラップ調で風景を描写し俳句を詠む。タイトルにもラップが入っているので、ラップがこの小説のウリでもあるのだろう。しかし成功しているのかというと微妙だ。母子関係の切迫感とユーモア混じりのフィクションが乖離してしまっている。俳句やラップで小説を長く引き延ばした印象がある。
「ラップ 最後の旅」は明らかに私小説である。作家が実際に体験していなければ書けない。しかし実体験に基づく私小説はフィクションと相性がよくない。私小説で効果的にフィクションを活用できるのは、あまりの現実の残酷さから作家が目を背ける時だけだと言っていい。
同じ母モノ小説だが前回の「蛇淵まで」はシリアスな私小説だった。作者としては同じことを繰り返すわけにはいかず、今度の「ラップ 最後の旅」ではトラウマに近い母子関係をユーモラスに描こうとしたのかもしれない。しかしむしろ逆なのではなかろうか。芳川さんが抱えておられるテーマは極度に切り詰めたリアルな短編の方がふさわしいと思う。
私小説は過去の痛切な出来事の一断章を拡大して言語化してゆく小説形態である。作家のどうしようもない執着が自我意識の肥大化を生み、異様に緊張した言語世界に読者を導いてゆく。その中で必ずフィクショナルな虚構が生まれ、それが短編から中編へと膨らんでゆく。小説的に言えば母子関係の謎は解けなくていい。むしろ解けない方がいい。ただフィクションという混ぜ物は、かえって作家が抱えるテーマの緊張感を失わせると思う。
大篠夏彦
■ 芳川泰久さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







