 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(六)象の背中(一)
どうなっちゃってるの?
いったいこれはどういうわけ?
全身からだらっだらしたたり落ちる汗をぬぐいながらわたしは、自分に問いかけまくっている。そして終わらない。ソクラテスの問いかけのように。なによ、この暑さはなんなの、この山の傾斜はなんなの、もしかして六十度くらいとかいう? そして先をゆく二人のあの速さはなに? 問いは果てしなく溢れだすのだ。もう二百五十問目くらいだ。
ところが一方で、わたしよりずっと年上のはずの種山は、大きなリュックを背負っているくせに(そして、もじゃのくせに)、どこかしら涼しげに、そして飄々と、さらには淡々と登っていくではないか。先頭を行くガイドのバボエ君にもほとんど後れを取っていないのが凄い。っていうかあんびりばぼー。

二人の背中が遠ざかるのを、気が遠くなる思いで眺めるわたし。
なぜ? なぜ、あの二人はわたしを待っていてくれないの? なぜ、振り返りもしない?そして、なぜ、さっきから一度も休憩しないの? そしてそして、なぜ、カレン族のみなさんはこんな、こおんな高い所にお住まいになっていらっしゃるの。もしかして、タイで一番標高が高い露天風呂があるとか?
それにですね、これは道とはいえないのではないでしょうか? (そう意識モーローとなったわたしはいま、まだ見ぬカレン族のみなさんに問いかけているのだった)。これは道というよりは、獣道、あるいは雑草の合間に見出される少し草の少ない部分、とでも表現するのが適切な感じのシロモノです。少なくとも日本では、いえ少なくとも東京では、いえ最高に譲ってもこのわたしはこれを道とは呼ばない。だいたい、なんですか? さっきからブンブン見たことのないような虫は飛んでるわ、ノースリーブの袖から出た二の腕に、なにやら鋭い草の葉がシュパーンと斬りつけてくるわ、もう東京生まれのヒップホップ育ち、悪い奴らはだいたい友達、悪そうな奴らとだいたい同じな感じの青春を送ってきたわたしとしては、って、ありゃ、なんか個人情報っていうか、過去ログっていうか、秘密暴露的な感じになってきちゃってるけど、もうわけわからんし、暑いし、息切れてるし、背中なんか汗まみれだし、
「ほら、見てごらん、すごいですよ」
モーローとした意識の霧の向こうから、聞き覚えのある声が響いてきて、・・・わたしははっと我に返った。気づけば山の七合目あたりであろうか、振り返ればチェンライ、チェンマイ方面と思しきタイの街並みが遠くに垣間見える。なんて雄大な眺めなのかしら。ああ、これが登山の楽しみっていうやつね、二度と楽しむ気はないけど、って思ってると、
「違う違いますって、あやかさん、そっちじゃないよ、こっち」
種山がいうので振り返ると、わあおっ、な感じで道の(っていったって道とは呼べないシロモノであることはすでに述べたところであるが)、すぐわきに巨大な白い塔が建っていた。
「なんですか、これ? カレン族の人が作った記念碑みたいな感じのあれとか?」
「ちがいますね、これは岩じゃない。土を固めたものです。それも唾液でね」
なぞど講義調でのたまう種山。
「唾液?」
「そう。そして、これを作ったのはアリたちなんですよ。つまり、これは蟻塚ってわけだ」
嬉しそうに蟻塚にさわったり、写真を撮ったりしはじめる種山。
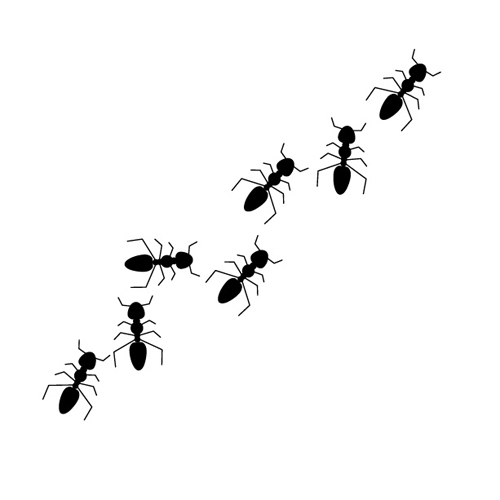
「住んでるのは白アリの仲間だろうね。こうやって塚を構築することで、高温や多湿の地域でも安全なシェルターを得ることができるってわけだ」
そうでしたか、アリさんたちの集合住宅ってやつでしたか。それにしてもでかいっすね。まるで身長百六十八センチのわたしとためですよ、これ。
「日本にないのか、これ」
チェンライで雇った、通訳兼案内人のバボエ君が、驚いたように問うてきた。
そうですよ、バボエ君。日本では黒い蟻さんは土の中に住んでるんです。そして白いのは、お家の柱の中にいるんです。
そう、昨夜はチェンライの宿に泊まったのだ。バスでの長旅のせいでわたしは宿につくやいなや瞬速でシャワーを浴び、秒速で眠ってしまったのだったが、きっと種山の方はあれこれ動き回っていたのだろう。
なにしろ、朝起きると、いつのまに雇われたのか、もうすでにガイド役のバボエ君が宿の前で待ってて、
「おやよございます」
なんて、変てこな挨拶されちゃったわけだし。
後で種山から教えてもらったことだけど、バボエ君は、カレン族ではなくカレンニー族なのだそうだ。ちょっと紛らわしいけどどっちも元々はミャンマーの部族なのだそうだ。でも、母親に連れられて子供のころにわたしたちの目的地であるカレン族の村に避難していたことがあるのだということだった。いろいろあったらしい。でも、父親がミャンマーから生還してチェンライに落ち着いたので、成人する少し前に村を出たのだということだった。
バボエ君と、ヘンテコ日本語会話していると、種山がいつものようにもじゃっと降りてきた。
「朗報だよ、あやかくん」
なんて種山が声をかけてきたので、
「さやかです、もうっ」
みたいな頓珍漢な方面に話がずれてしまったのであった。
でもまあ、その「朗報」ってのがなかなかのものだったので思わず許してしまうわたしだったりしたわけ。
やっぱり種山は昨夜、動き回っていたらしい。現地の少数民族専門の観光ツアーを紹介しているところに聞き込みに行っていたのだそうだ。結果、山深いところにあるカレン族の村に、二人の日本人が同時期に滞在していたことが判明したのだった。
「すごいじゃないですか、先生。ビンゴですね。それがその」
「おそらくね」
自分の予想が当たったというのに、種山はあまり嬉しげではなかった。チャイルディッシュな種山にしては珍しいことだった。
「それが、和也君と、そして」
「ライバル君でしょうね」
そう、そのライバル君との競争心から、和也氏は慣れない事業の運営にまで手を染めたのだ。そして殺された。わたしの推理では、おそらくはそのライバル君に。たぶん、ライバル君はその村で象の操り方を覚え、何もない場所に象を出現させる魔術を修得し、その象の首を切り落として・・・。って、そんな馬鹿なぁ。だんだん、ありえない方向へと想像が暴走してしまった。
いかんいかん、予断をもって物事をとらえてはいかんのだ。まずは虚心坦懐に事実を見据えてだな、と心のなかでサルの様に反省ポーズを決めていると、
「その村でなら、象の操り方も学べるしねえ」
とぽつりとつぶやく種山がいた。

「だめですよ、先生。予断をもって物事を考えちゃあ」
「予断?」
きょとんとした顔つきになる種山。虚心坦懐という言葉を知らんらしい。
「だって、ラーオ村は、象使いの村ともいわれてるんですよ。象はいますね、まちがいなく」
なんて、答えたのだ。
「はい、います。象、いらっしゃります」
バボエ君が、それなりにちゃんと通じる日本語で教えてくれた。なんでも、前に付き合っていた彼女が日本人だったらしい。
「でも、ユキエ帰った。おばあさん病気。そのまま。戻ってこない。電話ない。手紙ない。わたしさみしい、もののあはれ」
落ち込みかけるバボエ君。そりゃあもう脈はないはなあと思ったものの、
「だいじょうぶじゃない? きっと戻ってくるよ」
うわ、しまった。柄にもなく実のないやさしさなんか示しちゃったわ、わたしときたら。
「あなたユキエ知ってるか? 友達なったか?」
うわっ、やっぱりだ。親切が仇ってやつ? だから、友達じゃないって、日本にどれだけ女の子がいるって思ってんのよ。
「でも、ユキエなんて名前の子いっぱいいるのよ、日本には?」
「知らないのか、ユキエ。わたしのユキエ」
「うーん、名字はなに? なにユキエ?」
「確か」
少し考える風のバボエ君。ややあって、
「ナカマ、ナカマだった。ナカマじゃなかったら、ナマカ、それかナマコ」
「ナマコはないでしょうね。でもナカマだったら、ナカマユキエってこと?」
仲間由紀江?
そんなバナナですよね、やっぱり。
じゃあ、中間雪枝?
まさか、それって。わお、絶句。
だって、あいつじゃん。かつてわたしの親友の地位を許されていたものの、すでに降格されて久しい、わたしとコーヒージェリーフラペチーノをご一緒するよりもお猿のバブルス君とのアフターディナーを優先したあの?
で思い出したのだ。
「わたし帰国子女なの」
的なことをいっていたよな、そういえば中間雪枝のやつは。高校三年で日本に帰国したばかりなのよ、的なことを。その口ぶりからは、西欧諸国というニュアンスが伝わってきていたのだったが、その割には英語がペラペラというわけでもなく、怪しいとは思っていたのだ。しかし、まさか、もしや、そんな。
「どうした、あるか。どうした、あやか」
「もう、違うわよ。さやかよ、わたしは。種山のいうことを真に受けるんじゃないの」
「わかりました、さやかさん。お前はやっぱり知ってるのか、ユキエのこと」
お前って何よ、日本語ちゃんと使えよほんと。
「いや、どうかな。もしかしたらって、感じでしかないから」
「言ってたかわたしのこと、タイの、チェンライのバボエにまた会いたい、みたいなこと言ってなかったか」
言ってなかった。
「うーん、そういえば、言ってたかもね」
言ってなかった。
「そうか」
ほんとは言ってなかった。
ほんとうか、とパッと顔を輝かせるバボエ君。なんという純情な。純真な。そして愚かな。なんという日本の女知らずな、哀れな青年であろうか。
さて、そんなこんなでわたしたちは山登りを続け、ようやくカレン族の村まであと少しというところまでこぎつけた。もしいまわたしが人眼も憚らずノースリーブを脱ぎ、そしてタオルのように丸めて絞ったとしたら、保証しようではないか。大量の汗がどばあっと溢れ出るであろうことを。なぞとトチ狂ったことを口走ってしまうほど、脳のなかまで完全オーバーヒートな暑さであった。

「あれ」
と酔っぱらったような口調で言うのはわたし、
「なんだい」
ようやくわたしのペースに合わせて歩くようになった先頭の二人が振り返る。
「ほら、道の真ん中に蟻塚ですよ」
まあサイズ的にはそれほどでもないのだが、やや小ぶりの茶色い塔が、道の真ん中に突っ立っていたのだ。
「いやそれは」
苦笑する二人。
「なんです? なんだっていうんです」
詰問調のわたし。
「いやそれは、蟻塚じゃないんだよ」
こらえかねたように笑いだすバボエ君。おい、そこの君!
というわけでわたしは思い出したのだった。カレン族の村ラーオが象の村と呼ばれていることを。
「もう村が近いってことですね」
「そうだね」
ふいに種山が近くに歩み寄ってきたのでわたしはいやな予感がした。いままでほっといたくせに、ここから一緒に歩いてくれたってもう遅いのだ。そして、近くに来るということは、種山はなにかをまたレクチャーしたくなったのに違いなかった。
「もう少しですよ」
「わかりました。どうぞお先に」
「いや、後少しだし、一緒に行きましょうか」
結構です。それに、その話したそうな顔やめてください。でもやめてくれなかった。
「ところで、あなたは象洞のことを知ってますか?」
ああ、始まってしまった。
「ゾードー?」
それでも奇妙な言葉の響きに思わず反応してしまうわたしであった。
「うん、象はあの象です。さっきのフレッシュなのを出した象。そして、洞は洞窟の洞ですよ」
「いえ、知りません」
もちろん、知りませんとも。聞いたこともありません。わたしを誰だと思ってるんですか。
「じゃあ、日本に初めて象が来たのはいつだと思いますか」
楽しげに問いかける種山。なんか、問が飛躍してないか? と思いつつも、
「さあ」
首を傾げるわたし。そんなこと考えてみたこともなかった。
(第15回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







