 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(四)象の耳(下編)
「もう少し場所を選んでもよかったのでは」
「そうは思いませんね」
意外に強い口調。
「どうしてです」
「あなたはご存じなんですか、円山町のホテル街ができた経緯を?」
「いえ、でも」
そういえば確かに変だ。渋谷といえば、若者のおしゃれな街というイメージだから、その中心部にこんな日本最大級ともいわれるホテル街が存在するってのはなんだか奇妙な感じがあるっていうか、以前からないわけではなかった。
「ここは、渋谷が今の渋谷になるよりずっと古い歴史をもった場所なんですよ。かつては甲州街道から少し脇道にそれたところにある宿場町だったんです」
「へえ」
甲州街道沿いではなくて、少し脇道にそれたとこってのがなんか面白い。
「それが、明治以降に花街となって、芸者屋や料亭ができはじめ、代々木練兵場の将校さんなんかが通うようになったわけです。そこへ昭和三十年代初頭になると、岐阜県からたくさんの人が上京してきた」
「いきなり話が飛びましたね。岐阜県ですか?」
「ええ、岐阜です。御母衣ダムという大規模ダムの建設にともなって水没した村の人たちが上京してきたわけです」
「へえ」
「その人たちが、村を失う代償としてもらった補償金で、周辺の料亭や芸者屋・芸子屋、あるいは待合などを買い占めていった。そして、代わりに建てたのが今日につながる連れ込み宿、後のラブホテルだったというわけです」
「戦後の光と影ってやつですね」
苦笑する種山。しまったな、ちょっと陳腐だったか、今のセリフ。

「ええ、まあそういうやつです。ともかく、円山町のラブホテルの背後には、江戸時代の宿場町の喧騒、明治期以降の色街の嬌声、そしてダムに沈んだ遠い岐阜県の村の幻影が覆いかぶさっているのです。そう思うと、この場所そのものが、ちょっとした驚異をはらんだ展示物となる。そうは思いませんか?」
ああ、やばい。またなんかこの人の口車に乗せられている感じがしてきたぞ。
「ええ、確かにそういわれると、この場所に対しての感じ方も変わってきますね」
「でしょ? それに、俗にいう博物館ってなんかお堅い感じがするじゃないですか。
わたしが思うに、ほんとうの<知>の喜びは、そんなところにはないのです。もちろん、大学なんかにもありません。断じて象牙の塔などであってはならないのです。いわゆる大学の学問ってのは、死後硬直の状態にあるどうしょうもないものなのです」
とても、大学の教師の言葉とは思えなかった。
「じゃあ、どこにあるんです」
「日常の只中、そして欲望の裂け目にです」
「つまり?」
「たとえば、円山町です。ああいう場所で、ああいう建物であるからこそ、ラブホと間違えた客が入ってくる。しかたなくわたしの案内を受けて、部屋に入った彼らは、そこで《驚異》と遭遇する! 未知との遭遇ではありません。むしろ既知のものの変貌です。つまらないもの、何のへんてつもないものと見えたものが、突然全く違った相貌を呈する瞬間。それに遭遇して人は《驚異》するのです。結果として、彼らは思考し、想像し、もともともっていた激しい欲動を、崇高な知の喜びに変えて帰っていく」
「ほんとですか?」
「ほんとです」
一応は断言してみせる種山だったが、わたしの疑惑の眼差しに撃ち抜かれて、
「まれにはね」
としぶしぶ本音を吐いた。
「やっぱりね」
「実に遺憾なことながら、たいがいの方は怒って帰られるんですよ」
なぜでしょう、と困り顔の種山。
まあそうでしょうね、としたり顔のわたし。
「でも、いるんですよ。時には」
少しムキになる種山。ちょっとかわいいかも。
「時には、じゃなくてまれには、でしょ」
ちゃっかりからかってやるわたし。
「ええ、先日、あなたが来られる前も常連になられた方が来られてましたしね」
「ってまさか」
あの、さわやかだけど実はナンパ系だったあの若者のことだろうか、
「あの革ジャンにジーンズとかの」
「ああ、それですそれです。それが四方沢彰俊君ですよ」
「いかにも軟派な感じでしたけど」
なにしろ、さりげない感じでわたしまで誘おうとしたくらいなのだから。
「そうなんです。彼はね、驚いたことに、高校を卒業した後、一度も働いたことがないという珍しい御仁なんですよ」
「へえ、そんな生き方が可能なんですか」
「ええ、彼によれば、この世は慈母観音であふれているのだそうです」
「ジボ? カンノン?」
「ええ、黙っていても四方八方から女性の手が差し伸べられて、彼を養ってくれるっていうんですよ。ちょっと想像できませんけどね」
そりゃあ、先生じゃあちょっと無理でしょうけど。とは口に出さなかったし、出す必要もないことだった。
「でまあ、そんな彼が、ある夜美しい女性を伴ってここに入ってこられたわけです」
「ひっかけた女の子を連れてやってきたってわけ」
「ええ、そうです。彼的に言い直すならば、ひっかけたのではなく、慈愛を注ぐために顕現してくださった女性ということになるんですけどね」
うひゃあ、何よその恵まれ方。うまいこと言いすぎだし。
「間違えて入ったと気づいても、彼はちっとも落胆も激怒もしませんでした。むしろ、『じゃあ、ここではどんなものが見れるんです?』なんて聞いてきたくらいでした」
「で、さっきみたいにクラゲやら石やらネズミやら見せて回ったってわけですね」
「それだけじゃありません。二階も三階も全部見て行かれましたよ」
「四階は?」
確か、外から見た感じでは四階建ての建物だったはずなのだ。
「ああ、四階はまだ見せてませんね。あそこは特別の企画展示室なんで、企画展示がある時期に、それを見る資格があるとわたしが認めた人しかお招きしないんですよ」
「資格、ですか?」
なんなんだ、その資格って。英検三級だったらわたしだって持ってるけど、そういうんじゃないのかな。
「ともかく、彼はとても興味をもってくれました。それぞれの展示物に見入り、わたしの説明を、そうたとえるならば酒に飢えたアル中のように」
「いや、その場合、たとえるなら水を吸い込むスポンジのようにでしょ」
「いえ、やはりここは酒に飢えたアル中でなければなりません」
「どうしてですか」
「彼は完全に中毒したからです。あれから驚くべきことに女性も伴わず、週に一度はわたしのところへきてくれるんです。展示物を前にあれこれ議論を交わし、時にはわたしが驚くような卓見を披歴してくれるんです。そして驚いたことに自分で本を読んだり、インターネットで調べたりして仕入れた知識を紹介してくれるようにさえなったのですよ」
「つまり、開眼したと」
「ええ」
種山は深々とうなずいて見せた。

「彼はこう言いました。『種山さん、俺、初めて気がついたんすよ。世界ってのはこんなに面白いところなんだって』」
「へえ」
「すばらしい言葉じゃないですか。わたしは嬉しくて、即座にその日の日記にこの言葉を書き留めたくらいでした」
そんなに感動するようなセリフかいな?
では、とばかりの第四問!
「それでは、お聞きします」
ずっと聞きたかったあれを。
「これはどういうことなんですか。目下のこの状況は!」
ジェット機貸切とは(シャンパンとは、イケメン副機長とは)全体どういうことだとつっかかるわたしを、種山は微笑みとともに見やった。
「うーん、何から話しましょうか。そうですね、では弟のことからにしましょうか」
「ああ、弟さんがいるんですか」
不肖の兄というキーワードがぷわわわああんと記憶の底から浮かび上がって来た。
「ええ。実は弟は代表取締役をやっております」
「さっきの不二見コンツェルンってやつですね」
「いえ、不二見は、傘下のコンツェルンのひとつですね。全体はもう少し大きいんですよ」
「ほおっ」
大ボラの予感である。なんか、トール・テール的なスケール感が漂ってきたぞ、とわたしは警戒する。
「といいますと」
「ええ、デュボーンという財閥なんですよ、本体は」

「外国ですか」
「まあ、なんといいましょうか。その海外の財閥を統合したわけですね。父の代で。それで、弟はサッカー選手になる夢をあきらめて」
サ、サッカー?
「巨大な企業群の総帥の地位につかれたと」
「ええ、まあそうです。ブラジルのチームで活躍していたのを無理やり呼び戻す形になってしまったんですよ」
「って。プロだったですか」
「もちろんです。ロナウジージョの再来とか、ベッカムを超えたとか騒がれたもんですが、ご存じなかったですか。まあ、日本ではほとんどプレーしてませんでしたからね」
「はあ、そうなんですか」
なんという兄弟なんだ、全体君らは。
「弟にはほんとうに悪いことをしたと思っているんです」
そうだ、そうだ。わたしもそう思う。
「どうして、あなたがつかなかったんです。お兄さんのくせに」
「ありていにいえば、向いていなかった。わたしはこうしてぶらぶら生きるのが性にあっていたもので」
ああ、やっぱり不肖の兄だあ。
「でまあ、結局最終的にはジャンケンで決めることになりましてね」
ジャ、ジャンケン? そんな重大なことをジャンケンで?
「まあ確率論的にもっとも公平かつ簡便な手段であることは間違いないわけですからね。重役たちが居並ぶ中で、いわゆる三本勝負をしたわけです。緊迫した空気がみなぎる中、一対一の同点で迎えた最終決戦。そこで、わたしはグーを出し、弟はパーを出した」
「じゃあ、弟さんの勝ちじゃないですか」
「いいえ、負けた者勝ちのジャンケンだったんです」
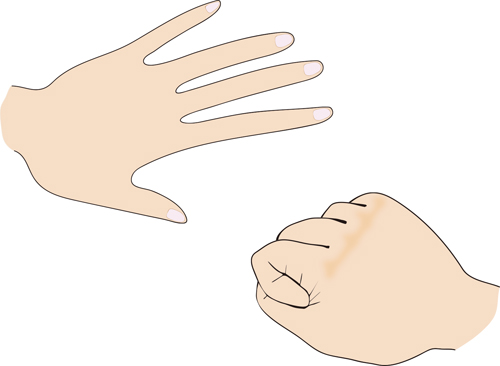
なんでまたそういうルール?
いずれにしても、この人物の醸し出す独特な余裕の理由がはっきりした。要はボンボン中のボンボンだったわけですね、先生は。
「それであなたは、会社の金でぬくぬくと学問なんかやってきたわけですね」
「いいえ、それは違います」
少しきっとなった種山であった。きっ、だなんて何をむきになっているのか。猿なのか?
「確かに、社外相談役として多少の貢献はしてきましたが、基本的にはわたしは自力で生きてきた。それだけは誤解なきようにお願いいたしたい」
ほんとですかあ、と全身疑いの海鼠、じゃなくって眼と化すわたし。
「へえ、でも、それじゃあどうやって海外の大学をいくつも渡り歩くことができたんです?」
「こんなことを言うと、なんだか自慢っぽい感じになってしまいますが」
「はあ」
「わたしはいずれの大学でも、特別招聘学生として学んできたのです」
出たよ、トクベツショーヘー。ショーヘーってどんな字書くんでしょうね。正平ですか、哨兵ですかあ。
「なんですかそれ? 奨学金とかもらえる奴ですか」
「いいえ、給料をいただくかたちで学生をやらせていただくというものでした」
嘘! そんなのあり得ない。嘘にきまってる。
「ほんとうです。日本の大学ではあまりない制度なのですが、ある種の能力をもつ学生は、将来その大学の宣伝になるということで、給料をもらいながら学生をすることができるのですよ」
「そんなに、すごいんですか、先生は」
「いえいえ、大したことはないです」
ほんと大したことない感じで微笑む種山。やっぱそうでしょうね、と思わず納得してしまうわたし。
「あなたがいまご覧になっている通りの人間でしかありませんよ、わたしは」
「でも、あのホテルはどうなんです? あんなもの、普通の大学教員の給料では買えないでしょ?」
「ああ、あれはですね、格安で譲ってもらったんですよ」
「格安で、譲ってもらった? 誰にです?」
「ええ、昔少しお世話をさせていただいた方の所有物だったのです。それでまあお礼にということで、破格の値段で譲ってもらったというわけです」
種山くうん、お世話って何かね?
「破格っていっても」
「それに、まあ多少は賞金もいただいていましたからね」
「賞金って、なんのですか」
「フィールズ賞とかバルザン賞とかそんなやつですね。ほかには、ショパン国際ピアノコンクールなんてのもありました」

「ピアノって、先生弾けるんですか」
「まあ、たしなむ程度ですが」
もうなんか、わけわかんない。
「でも、この飛行機はどうなんです。これこそ、まさにボンボン中のボンボンの待遇じゃないですか。こんな風に貸切の豪華ジェットでバンコクへ向かうなんて」
ほらどうだ、尻尾を出すがいい。狸め。
だが、ボンボン〝もじゃ〟はしれっと話を続けた。
「ええ、これはね、どうしても急ぎたかったのでやむをえずというところです。旅券を手配しようとしたんですが、通常のチケットは完売状態だったんですよ。でまあ、ちょっと弟に電話を入れまして」
「こうして、手配をさせたと」
「ええ、でもちゃんと料金は支払っていますよ」
「そうなんですか、いったいいくらなんです」
「ざっと七百万といったところでしょうか」
出たあ、尻尾でたあ。
「ほらあ、そんな大金どうやって出せるって言うんですか」
一介の大学教授に、と言いそうになってやめるわたしであった。
「これはですね、まあ弟の会社の方にプール金があるんですよ」
「プール金」
「ええ、さきほどもお聞きになったように、わたしは代表取締役就任を免れたわけですが、それでも一応兄弟のよしみで社外相談役としては会社に名前を連ねているわけです」
「そのようでしたね」
さっきの皇太子なのか執事なのかよくわからない、吉田氏の口から確かにわたしもそう聞いていた。
「でまあ、ちょっとしたアドバイス的な貢献はたまにしておりましてね、それで利潤が上がったりした場合に、その何パーセントかがわたし名義の口座に謝礼として振り込まれる。それを弟が管理してくれているとまあ、そういう形になっているわけですよ」
「なるほど」
って納得している場合ではなかった。なんとわたしはいま、世界有数の、大財閥の、傘下にあるコンツェルンの、所有する飛行機の、豪華な客室の、シャンパンが出るような席に、その大財閥の、代表取締役の、兄の、もじゃといっしょに乗っていると不意に気がついたからであったからだ。
詰問はここで打ち止めとなった。なんだか頭がくらくらしてきたせいだった。きっと調子にのって美人の客室乗務員に、何杯もシャンパンを注いでもらったせいに違いない。わたしはそう思うことにして、毛布をかぶって眠りについた。
その傍らで、種山は何語かわからない洋書を取り出して、ぱらぱらめくっていた。
バンコクに到着したのはもう夜中であった。
今度は得体の知れない私設飛行場ではなく、スワンナプーム国際空港という、れっきとしたバンコクの空港への到着であった。
「さあ、着きましたよ」
起こされて降りた。とたんに、うわ、なにこれって感じでサウナ的な蒸し暑い空気がむおおおっと押し寄せてきた。息苦しいではないか。蒸し器のなかに入れられたアンマンみたいな気分ではないか。なんだこれは。
「もう夜ですが、気温はまだ二十四、五度はあるようですね。それに湿度が高い」
種山が何でもないことのように言う。
「行ってらっしゃいませ」
美人の客室乗務員たちと、ベテランの機長、そしてテレビのスクリーンから抜け出してきたかのようなイケメンの副機長の微笑みに見送られて、七百万円の空の旅は終わった。ええっ、終わっちゃったの? しまったあ。わたし、シャンパン二三杯で良い気分になって、そのまま眠りに落ちてしまったあ。貴重なゴージャス・タイムのほとんどを眠り姫となって過ごしてしまったあ。

後の祭り・アンド・後悔先に立たず。
でも、いわゆるリムジンバスで市内に向かう途中、
「食事をしてから宿に行きましょうか」
などと種山が言いだしたので、ちょっと期待した。なんせ、飛行機が飛行機だったわけだから、夕食だってもしや満貫全席的な感じのやつかもなぞと、堪能できなかったゴージャス飛行の悔しさからもそう期待したのだけど、何か? 文句ある? でも、夢の風船はぱあんとはじけ、種山が立ち止ったのはぼろっちい屋台の前であった。
「◎▼□◇××カッ」
わたしには聴き取り不能な発音で種山が屋台のおっさんに話しかけ、
「■●○○×◎カッ」
とおっさんが返す。
「焼きそば的なものでいいですか」
振り返って不意打ち的に日本語を口にする種山。
「はあ」
焼きそばかよとがっかりしたのもつかの間、えびせんべいの間に盛られた麺を見ると胃袋が小躍りした。上に乗ってるのは赤い海老と、それから緑のはきっとパクチーであろう。
「バッタイっていって、タイではもっともポピュラーな屋台料理のひとつですよ。あまり、辛くしないように頼んでおきました」
そういう種山自身は、太い麺の入った汁ものをうまそうにすすり始めた。クィッティアウという、これまた定番の庶民食なのだと教えてくれた。
でも、告白しよう。その焼きそばは実にうまかった、と。もう一皿食えと言われれば喜んでがっついたに違いなかった。
宿も、ホテルと呼べるような代物ではなく、いかにも安そうなゲストハウスであった。
「ここなら、日本円で一泊八百円くらいで泊まれるんですよ。しかも、朝食つきです」
種山はうれしそうに勇んでそこに入っていき、また◎■▼×などを活用した言語を用いて、部屋を取った。
「明日は、早朝から動くことになりますからよく休んでくださいね」
鍵を渡すなりさっさと自分の部屋に入ってしまった。
(第13回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



