 世の中には男と女がいて、愛のあるセックスと愛のないセックスを繰り返していて、セックスは秘め事で、でも俺とあんたはそんな日常に飽き飽きしながら毎日をやり過ごしているんだから、本当にあばかれるべきなのは恥ずかしいセックスではなくて俺、それともあんたの秘密、それとも俺とあんたの何も隠すことのない関係の残酷なのか・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第四弾!。
世の中には男と女がいて、愛のあるセックスと愛のないセックスを繰り返していて、セックスは秘め事で、でも俺とあんたはそんな日常に飽き飽きしながら毎日をやり過ごしているんだから、本当にあばかれるべきなのは恥ずかしいセックスではなくて俺、それともあんたの秘密、それとも俺とあんたの何も隠すことのない関係の残酷なのか・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第四弾!。
by 寅間心閑
七、こびりつき
まだホテルに戻るのは早すぎる気がした。二人とも俺がいなくなったからすぐ、ではないだろう。もう一本缶ビールを開け、喉を潤しながら歩く。駅近くのラブホテル密集地帯には立ちんぼのオネエサンたちが何人か。結構御高齢な方々が誘うでもなく佇んでいる。パッと見東南アジア系の中年女性は、微笑みながら手招きと少々積極的だ。
「色男ネエ、今日ドウスルノ?」
途中なんだよね、とコンビニの袋を掲げると大袈裟に肩をすくめた。
今から電話をして安太に餃子耳の名前を教えてやってもいいが、台湾との時差は一時間。海外で夜中に起こされる気持ちを想像してやめることにした。そろそろホテルへ戻ろう。
鍵かけなかったけど大丈夫かな、まさか締め出されないだろうな、と思いつつフロントのおばちゃんに「戻りました」と告げる。行きがけと同じく無反応。もう寝ているのかもしれない。
案の定鍵は開けっ放しで、二人はおっ始めたばかりだった。右田氏はまだジーンズしか脱いでいない。想定内のブーメランパンツ。目が合ったので微笑んでみる。お、やってますねえ、すぐ私も行きますんで――という感じで。
彼がすぐ目を逸らした理由は分からないが、俺にとって不利な要素はないだろう。
ミンちゃんとも目が合った。やはり微笑んでみる。さっきはしなくていいって言ったけどごめんね、この人ならロングステイ何とかしてくれるからさ――という感じで。
どうにかこうにか伝わったらしく、彼女は「オッパー、こんなボディ、大好きです」と右田氏の六つに割れた腹筋に頬をすり寄せた。呆気なくオッパー交代。ちょっと寂しい気もするが、まあ仕方ない。しばらくソファで様子を見ていよう。
右田氏はハイジニーナだった。所謂パイパン。これも想定内。鍛えてるヤツって剃っていそう。実際見るのは初めてだ。刺青はトライバル。ベタベタ想定内。和彫りなら格好いいのにな、なんて思うくらい俺はリラックスしている。右田氏に缶チューハイを渡し、ミンちゃんにタオルを渡すくらいリラックス。
「?」
ポカンとした彼女に、目隠しのジェスチャー。これはすぐに伝わった。「オッパー、これをこうすると超エロいです」。ハイジニーナのトライバル・タトゥーはされるがまま。先端を軽く舐められただけで「あん」と身をよじる。チューハイがこぼれてミンちゃんに少しかかった。
段々盛り上がる二人を見ながら、スマホのムービーを起動する。右田氏の視覚を奪ったのはノリや気まぐれではない。バレずに撮影するためだ。これくらいの弱みは握っておかないと。

攻められるのが好きなのか、右田氏は四つん這いから動かない。ミンちゃんが身体に触れる度、声をあげ身体を震わせる。ベッドに近付き撮影開始、ミンちゃんの顔を外しながら撮るのは意外と難しい。
それにしても鍛え上げている。キレッキレ、とはこのことだ。一瞬ナオの顔がよぎり少し欲情しちまった。ファスナーを下ろして引っ張り出すと、ミンちゃんが「あらあら」という顔で頬張ってくれる。しばし撮影中止。不自然な姿勢で数分。でもやっぱりダメだった。三度目は無理。
ベッドから離れてムービーをチェックする。問題ナシ。さあ、長居は無用だ。ミンちゃんに二万円を手渡す。超過分はこの目隠しハイジニーナが払うだろう。よっぽど気持ちがいいのか、まだ四つん這いのままだ。
ロングステイOKになるといいな、と思いながら部屋を出る。フロントの婆さんには声をかけなかった。金はあまりない。タクシーは無理だ。始発が出るまで歩いてみよう。客が取れたのか、諦めて帰ったのか、ラブホテル密集地帯に立ちんぼは一人もいなかった。
こんな時間に大した金も持たずほっつき歩いていると、嫌でも大学生だった頃を思い出す。クラブや居酒屋、キャバクラやバーを出て電車が無くなっていたら大抵歩いていた。始発まで開けている店にも、カラオケボックスにも、誰かの家にも行かない。例外はいけそうな女がいる時で、論外は野郎しかいない時だ。
高校の頃は更に金がなかったし、朝まで遊べるのは夏休みや冬休みだけ。その分色々溜まってた。吐き出したくて、ぶち撒けたくて仕方なかった。ナオと渋谷のラブホテルに入ったり、まだ四つん這いかもしれない右田氏とパーティーで顔を合わせていた時期だ。
あれから十数年も経った。でも何も変わらない。まだ俺はこんな真夜中にほっつき歩いている。コンビニで買った水を飲みながら、たまにスマホを眺め、始発が動き出したら近くの駅から乗ればいいやと思っている。
もしカウントしていいのなら、唯一変わったのは心情だろうか。あの頃は無、何もなかった。その感覚が好きだから、歩いていたのかもしれない。でも今は違う。ミンちゃんや右田氏のこと、金のこと、帰ってからのこと、明日のこと、将来のこと……。何かしら考えてしまう。
もしかしたら忘れているだけで、あの頃も考えていたのかもしれない。だとしたら、結果はどうあれ全て溶けきっていたのだろう。今は、違う。考えたことは溶けきらずに残っている。時間では解決できないから、いつまでも残ったまんま。べっとりこびりついている。不安で心細いのはそのせいだ。
来年で三十歳。両親もそろそろ還暦だ。もし安太がマトモになったら、俺もその歳から仕切り直そうと思っている。猶予は九年。長過ぎるか。いや、ひょっとして安太はもうマトモになってるのか? 俺が気付いていないだけなのか? コースアウトしているのは自分だけなのか? こんな疑問もまた、溶けきらずにこびりつくのだろう。
人の話し声がする。すぐそこが上野の駅だが始発にはまだ早い。座り込み談笑する学生、ガラガラ音を立てるキャリーバッグの三人組、一人立ち尽くしてスマホをいじる中年のサラリーマン。終電を逃したヤツも、そうでないヤツも見た目は同じだ。俺はまだ歩く。このままアメ横を突っ切って御徒町に抜けてみよう。人影まばらな路上をカラスも跳ね歩いている。

最後は秋葉原から始発に乗り、一時間かけて家に戻った。まだ五連勤の二日目だ。寝不足状態で働くのは慣れているが、妙に身体が重い。今日めっちゃ老人みたいですよ、とロックバンドのTシャツを着た安藤さんにも笑われた。
実は昨日鶯谷でさ、と全部話したい気もする。案外、右田氏がああなったように流れが変わるんじゃないか。一緒にロックフェス行って、会場の隅っこで青姦やれたりするんじゃないか。
「もう予定決まったの? ロックフェス」
「あ、はい。店長にも言いました。一週間、丸々休ませてもらいます」
「そうなんだ。晴れるといいね」
え? と振り返った安藤さんは「ありがとうございます」と微笑んだ。やはり現時点で脈はこれっぽっちもなさそうだ。昨日の鶯谷の話は効果ナシ、いや逆効果だろう。
真っ直ぐ帰らず下北に寄ったのは、どこかで軽く呑んで帰るつもりだったからだ。もちろん寝不足だし金もない。だから軽く、一軒だけ。でも、道が悪かった。職場から下北に向かうと、まず「マスカレード」の傍を通る。迷うのも馬鹿らしい。ナオがいるかいないかも分からないが、俺はとりあえず店に入った。
「いらっしゃいませ、遅かったじゃない」
ナオの声だったが、誰かと……例えば右田氏と間違えられているような気がする。ここに寄る約束なんてしていない。客は初老の女性が一人。ナオは俺の顔を見ても慌てない。俺が忘れてるだけで実は約束してたのかな。
「あら。じゃあ、私はこれでね」
先客が席を立つ。何となく会釈。横からだと分からなかったが、メッシュの入ったオカッパ頭。ウイッグだろうか。位置的に服装は見えなかったが、カラフルにきらめく派手なネックレスは確認できた。攻めてるというか、個性的というか、主張の強さは一目瞭然だ。ナオは見送るでも「ありがとうございました」と言うでもなく、黙々とコーヒーカップを片付ける。そして二人きり。
「ああ助かった。グッドタイミング」
「え?」やっぱり約束はなかったみたいだ。「それ、どういうこと?」
「今のお母さんなのよ。色々うるさくて」
だから「遅かったじゃない」と待ち合わせを装ったのか。納得。ただメッシュのオカッパに気を取られて顔をちゃんと見なかった。似てるの? と訊くと「見なかったの?」と笑われる。
「いや、髪とネックレスで……」
「ああ、昔からあんな感じ」
よく分からないが、ナオが「グッドタイミング」と言うなら問題はないのだろう。
「で、どうしたの?」
「いや、昨日右田さんに会ったから」
「そうなんだ。ケン坊、ちゃんと調べてた?」
どうやら右田氏からは何も聞いてないようだ。だったら俺がベラベラ喋ることもない。

「うん、調べてもらった」
「そっか。何か呑む?」
この前右田氏はブラッディ・マリーだった。でもメニューを見るのは面倒くさい。
「じゃあビール」
「バドワイザーかハイネケン」
「じゃあハイネケン」
「はい、これは私からの奢りね」
「え?」
「グッドタイミング賞。本当、来てくれて助かったのよ」
そう言われると逆に色々聞きづらい。まあ、今日はこれを呑んだらすぐに帰ろう。そう決めた瞬間、二名様来店。ある意味グッドタイミング。普通の格好の老夫婦に対し、ナオも「いらっしゃいませ。空いているお席にお座り下さい」と普通の接客だ。
灰皿が必要かと尋ね、メニューとおしぼりを渡し、にこやかに注文を聞く姿をぼんやり眺めている。スマホに保存された、タオルで目隠しをして四つん這いの右田氏を思い浮かべると、十数時間ぶりにやらしい気持ちになった。やっぱり二人はそういう関係なんだろうか。ナオにあのムービーを見せればその答えが分かるかもしれないが、何か大事な物を失うような気もする。悩ましい。
ピザトーストとパスタの準備で忙しそうだったので、特に話をするでもなくハイネケンを十分かけて飲み終えた。合図をしてから席を立つ。
「ごちそうさま。また近々呑もうな」
オッケー、と口だけ動かすナオに手を振り外に出る。まだ明るい。奢ってもらったし、もう一軒寄ってから帰ろう。今度はちゃんと身銭を切って呑まなくちゃ。
悩むことなく「大金星」を選んだのは、安太の台湾逃避行を肴に呑みたかったから。発端のボッタクリ騒ぎから説明することはない。安太が女と海外にいるってだけでいいんだ。その事実だけで笑える。
店に入るとコウさんもトミちゃんもワダテツもいる。マドカちゃんに「大瓶ね」と注文するのももどかしく、みんなの間に入って「あのさ」と言いかけた時、タッチの差でコウさんに先を越された。
「さすが、いいところに来たじゃん。グッドタイミング。これこれ、ほら」
差し出された紙には、「異種交配」という仰々しい四文字。その下には「気鋭の画家と古典文学、その愛の結晶」と続く。どうやら展覧会のフライヤーらしい。となるとこの九人の顔写真の中に……いたいた。現在バーバラと台湾逃避行中の安太の顔。以前言っていた「グループ展」なのだろうか。というか、写真がずいぶん若い。これ、いつの写真だ?
「今日、店にね、髪の長い男の子がやって来て『置かせて下さい』って言うから、『まあ適当にね』なんて返事してさ、で、さっきチラッと見たら載ってるからさあ、もう驚いちゃって」早口になったワダテツは落語家みたいだ。「呑む予定じゃなかったけど、緊急事態だから来ちゃったよ」
「ていうか、この写真若すぎるでしょう」
「そうそう、アレじゃないの、ほら、奇跡の一枚」
これでかよ、とみんなで口々に突っ込んで大笑い。これでいい。この調子なら帰ってすぐ寝れる。だから台湾の話は引っ込めることにした。
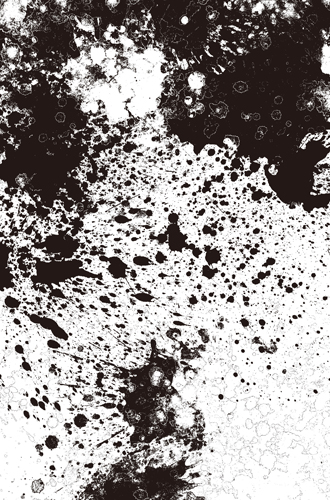
「でもあいつ、ちゃんと描いてるんだなあ」
「まあ、それはエライというかシブトイというか」
「なかなか続けられねえからな」
こんな風に雲行きが怪しくなったのは、盛り上がりが一旦落ち着いてから。気付けば安太への風当たりは柔らかくなっている。
俺の気持ちは少し違う。やっぱり描いてたのかと安堵する反面、どこかで落胆している。先日泊まった時、あのキャンバスにはちゃんと何も描いていなかったのに――。
安太はマトモになったのか、いや、今までずっとマトモだったのか。だとしたら、そもそも俺に猶予はない。単独コースアウト。もう手遅れだ。
周りの会話に曖昧な反応を繰り返しながら、そんなことばかり考えていた。この感覚だって溶けきらないだろう。きっとべっとりこびりつく。
電車で帰った方が早いのは分かっている。しかも俺は寝不足。でも歩こうと思ったのは台湾に電話する為だ。
向こうは夜八時半。バーバラとディナーの真っ最中かもしれない。餃子耳の身元判明を祝して乾杯、とはいかないだろうが、もし少しでも気を良くしたのなら「異種交配」展の話もしてみたい。いつの間に絵を描いていたのか。そんな話は電話の方が切り出しやすい。
ミンちゃんのロングステイがどうなったかも気になるが、こっちはヤブヘビ率が高そうだ。自分を君子だとは思わないが、わざわざ危険な方へ近寄ることはない。それでなくても右田氏とは近々会う。俺には安太の件がどうなったかを、彼に伝える義務がある。まあ、あのムービーがなければ、こんな風には思わなかっただろうけど。
環七を渡りながら台湾の安太を呼び出す。気の抜けた声が聞こえるのに、そう時間はかからなかった。
「もしもし」
「今、大丈夫?」
「ああ、うん、大丈夫」
声から察するに、呑み食いやぐちょぐちょの真っ最中ではなさそうだ。多分、野外ではなく屋内。
「寝てた?」
「うん、ちょっとだけ。でも大丈夫」
「そうか。あのさ、分かったよ、あいつの名前」
「あいつって……」
「餃子耳。何だっけ、ナントカちゃんの彼氏」
おお、と安太らしくない前のめりな声が聞こえた。ちょっと待ってね、と慌ただしい。メモの用意をしているのだろう。俺も右田氏から渡された餃子耳の免許証のコピーを取り出した。
「もしもし? お待たせ。どうぞ」
「ちょっと変な漢字だから、読みの方からね。苗字がカ・セ・ヤ・マ・ダ、分かる?」
「え? カセヤマダ? カゴシマのカに、セトウチのセでいい? ごめん、字は?」
「うん、カゴシマにセトウチでいいけど、まだ下の名前もあるよ」
「それってリッシンベン?」
「ん? えっと、小さいの『小』のヤツね」
「右側は漢数字の『九』と『十』?」
「そうそう。え? こんな字よく知ってるなあ」
「……」
返信がない。もしもし、と何度か呼び掛けてみる。微かに聞こえる物音から、慌ただしさは伝わってきた。
「ごめんごめん、下の名前、お願い」
どうした? と訊きたい気持ちを抑えて「ススム。字は『進行方向』のシン」と伝えると、またしばらく返信がなくなる。
「何度もごめん。でも分かった」
「ん? 分かった?」
「うん、忰山田進ね。本当にありがとう」
「待って待って。何がどう分かったかだけ教えてくれよ」
それもそうだ、と答えた後に僅かな沈黙が挟まった。呼吸を整える感じが伝わってくる。勿体ぶって咳払いの一つでもしそうな雰囲気。
「あのね、バーバラの苗字、『忰山田』っていうんだよ」
(第07回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『助平ども』は毎月07日に更新されます。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
