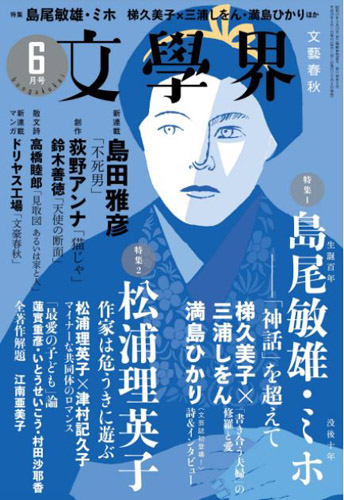
今月号から連載マンガ「文豪春秋」が始まった。第一回は「走れ芥川賞」だ。文藝春秋社が芥川賞を走らせている、または文學界は芥川賞と共に走り続けてきたということだ。世の中にはまだ、芥川賞は日本の文壇(小説家たち)が総力をあげて優れた作品を選んで授与する賞だと思っている人がかなりいる。もちろんそんなことがあろうはずもない。マンガという形であれ、文學界が芥川賞は自分たちが所有する大事なコンテンツだと宣言するのはいいことだ。他の文芸誌がこんなマンガを掲載したら怒られる。純文学の世界は芥川賞中心に回っているが、他社は自分たちが抱えるコンテンツをなんとか芥川賞に喰い込ませようと必死というのが現実だ。そうしないと純文学小説は売れないのだ。
身も蓋もない言い方だが、営利企業が自社利益優先なのは当然である。他社を利することになっても将来の自社利益を見込んでの場合が多い。それを批判するのは世間知らずだ。誰だって仕事では似たようなことをしている。出版社社員が何も布石も打たずに他社刊の本に賞を与え、百万部売れたら社長にどやしつけられる。顔から〝火花〟が出るでしょうな。
ただなぜ作家が賞を欲しがるのかは、お腹に手を当ててよく考えてみた方がいい。最初は他人から認められたい、作家として世に出たいという願望が満たされるからである。文芸誌の新人賞などがそういった賞の役割を担う。次いで文壇の有名賞が欲しくなる。なぜか。文筆で食えるようになる可能性が生じるからだ。作家なら誰だって原稿を書いてその収入で生活してゆきたい。芥川賞はそんな賞の筆頭だ。受賞すれば本は最低でも何万部か売れる。ラッキーならベストセラーになるかもしれない。
じゃあ芥川賞などの有名賞を受賞しても、その後ぜんぜん文筆でご飯が食べられないとわかるとどうなるのか。このあたりから歪みが生じてくる。最初のうちは当初の目的に沿って賞の受賞で生活できることを目指すだろう。だけどこりゃいくら書いても売れないな、と感じ始めると、文壇内で認められ業界内名士になることが代替欲望になる。ほかのいろんな賞を受賞することが目的化し始めるのだ。文壇内有名人になることが目的になってゆく。
年を取って本が売れないとだいたいそうなる。もちろんそのための努力も半端ではない。これもお腹に手をあてて考えてみればすぐわかるが、よほど飛び抜けた技術や才能を持っていなければ、誰だって見ず知らずの人に仕事を発注したりしない。文学業界も同じである。ずばぬけた才能なんてそうそう現れないから、個人的コネクションが受賞を左右することはしばしばある。もちろん作家は受賞すれば、それなりの現世利益を得られるから、賞レースに奔走するわけだ。だけどA社の取締役が誰かなんて一般の人々はほとんど関心がない。名前は聞いたことがあっても何をやっているか知らないだろう。いわゆる小説文壇システムは、そんな本は売れないが業界内で評価が高い作家集団によって形作られている。
なぜこんなことが起こるのかと言えば、特に純文学系作家のお金に対する認識が甘いからである。作家自身が賞を、素晴らしい作品に与えられる純粋無垢な栄誉だと信じ込んでいる節がある。賞は現世利益を含んでいて、作家だってそれを期待してるじゃないの、と言われても、いや賞は純・文学的栄誉だと言い張るウブな作家も多い。だけど四十、五十代になってもそんなことを言っているようでは心許ない。現世の苦悩や矛盾を書くのが小説家だ。酸いも甘いも知り尽くしていなければ優れた作品は書けない。ある年になれば、当然すべて自分で考え抜いて認識把握しているべきである。
この点は直木賞作家の方がうんと大人だ。直木賞は流行作家に与えられる賞だが、芥川賞ほど話題になりにくい反面〝実〟を取っている。じゃあ本が売れていれば賞はいらないのだろうか。お金の問題を真正面から考えればその通り。筒井康隆や夢枕獏は直木賞作家ではないし村上春樹は芥川賞作家ではない。賞と本の売れ行きを天秤にかければ、少なくとも後者の方が遙かに作家活動を続けてゆくのが楽だ。原稿を売り込んだり、本を出してくださいと版元に頼みこむ必要もない。むしろ取り合いだ。作家は言わないし、版元も余計なことは言わないので知られていないが、多くの純文学作家が本を出してくださいと版元を走り回り、一年、二年を無駄にしている。とにかく作品を書き本を出し続けたい作家は、どちらか選べと言われれば賞より本が売れる方を取る。本が売れている作家にとってこそ、賞は純・文学的な栄誉だと言える面がある。
純文学系作家がお金の問題を含む文学の現実に気づくのが遅れるとマズイことになる。純文学的な書き方、つまり「こりゃどうやっても売れませんね」という書き方に慣れきってしまうと方向転換するのが難しくなる。売れっ子作家を見れば明らかだが、作家が読者を楽しませようと意図しなければ面白い小説は絶対に書けない。
また文学者の現実認識がうんと甘くなったのは一九九〇年代くらいからである。急激に本が売れなくなった時代だが、この時代に活躍し始めた作家たちが、そこそこの作家でも文筆で食えていた時代をまだ記憶していたことが影響している。ほんの少し前まであった、賞と経済が結びついていた古き良き時代が続くだろうと期待したことが現実を見る目を曇らせた。ただ二〇〇〇年紀に現れ始めた作家たちは自らを「ゼロ年代」と呼んでいる。彼らの方が正確で冷たい現実認識を持っているかもしれない。文学を仕事とするのならそういう冷静な現実認識は不可欠である。
「さらに言えば、死者は平等に想像されるべきなのです。私に想像できるのは一人ずつでしかありません。それはこの世の法則からいって不合理だと思います。ですが、釣りをしながらぼんやりと職場の女性を想う男の人を想像しながら、夕食をオムライスにしようか肉じゃがにしようか悩む主婦を想像するのは比較的困難です。そこに繋がりがあればそれは近寄る事も出来ますが、それでも真に平等では無いのです。誰かの席は無くなってしまい、順番待ちをすることになります。それを可能にするのは神ではないでしょうか。私は無神論者ですが、もしすべての死者を同時並行的に想像し、そこに愛を生じさせることが出来るとするならば、その存在は神と呼ばれるにふさわしいではありませんか。神などどこにもいやしないと、愛する人や家族を流された人間は思うでしょう。しかし、いないと断定したところから、そこにのみ、神はいるのだと私は思いたいのです。信じないものだけがそれについて真摯に語ることのできる資格を持つこと。それがこの街にもたらされてよい一つの恩寵ではないでしょうか」
(日上秀之「あの人を見つけたならば」)
今号には二〇一七年上半期同人雑誌優秀作が掲載されている。元々は文學界が行っていたが三田文學が選考することになった。作品は文學界に転載掲載され、選評は三田文學に載る。なぜこんな面倒な形を取っているのかは知らない。日上秀之さんの「あの人を見つけたならば」が優秀作に選ばれた。一九八一年生まれで岩手県宮古市在住の作家である。
小説の舞台は東日本大震災後の東北の街である。小説のテーマも東日本大震災後の人間の精神のようだ。〝ようだ〟としたのはこの小説が激しく混乱しているからである。「神」が出て来るのは震災小説ではあり得べき姿の一つだと思うが、つきつめられていない。はっきり言えば柄谷行人以降に流行し始め、最近では批評の主流になりつつある〝創作批評〟と紙一重である。作家の曖昧な哲学的認識が小説という隠れ蓑を使って茫漠と表現されている。ベクトルは違うが構造は創作批評と同じ。
創作批評とは小説や詩のように創作化した批評のことである。小説業界で批評が小説の下位に置かれ、小林秀雄を始めとするほんの一握りの批評家にしかはっきりとした作家性を認めてこなかったのは事実である。しかし柄谷さん以降、批評家は小説をダシにして批評を書くようになった。誰を、何を題材にしても、なによりも批評家の思想や感情を表現することを優先する。漱石論なのに読み終わると柄谷さんしか印象に残らないという現象が起こる。以前と比較すれば批評のルールが壊れてしまっているが、創作批評を書き、創作批評を好む人々が一定数存在して力を持ち始めているのも事実である。
そういった創作批評家は各文芸誌でも活躍しているが、三田文學が一つのセンター雑誌になり始めている気配はある。そういう意味で三田文學が日上さんの「あの人を見つけたならば」を同人雑誌優秀作に選んだのはわからないではない。三田文學は保坂和志をやたらと持ち上げたりしているが同じ流れだろう。
それが文学の世界にどういった影響を与えるのかは現状ではまだ不透明である。ただ誰もがSNSで自己主張を繰り広げる時代に、文芸誌が強く自己主張し始めたのは現代のあり得べき〝現象〟の一つである。また多くの人がSNS上の自己主張を話半分にしか受け取らないのと同様に、各文芸誌の主張がそのまま通るわけではない。ただ従来は無色透明で、主義主張をできるだけ控えて一種の〝公器〟として振る舞ってきた文芸誌が自己主張を始めれば、情報化時代にふさわしいさらなる情報公開を促進することになる。
大篠夏彦
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
