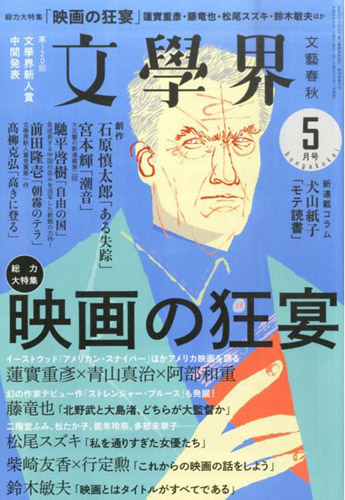
第一五三回芥川賞を同時受賞した又吉直樹氏の『火花』と羽田圭介氏の『スクラップ・アンド・ビルド』を続けて読んだのだが、つくづく純文学は難しいと思う。原則を言えば純文学と大衆文学の違いなどない。文学は文学であり小説は小説である。しかしそれは原則論であり、プロの作家ならどんな小説媒体に作品を発表するかによって、当然微妙に内容を変えなければならない。たとえば「オール讀物」では定期的に「芥川賞作家特集」を組んでいる。芥川賞作家は「文學界」系の純文学作家だが、「オール讀物」は直木賞系の大衆小説作家の作品が掲載されるメディアである。読者層が違うわけだからそれを考慮する必要がある。
ただ読者はいつだって美食家である。これも原則を言えば、読者は作家や文芸誌メディアの事情など関知しない。純文学作家が大衆小説誌に書くことで、そのメディアの風土に無理にすり寄る姿勢を見せれば、それはすぐに読者に伝わってしまう。読者は純文学作家の美質をそっくり残した、少し毛色の違う良質の大衆小説を楽しみたいのである。大衆小説――特に連載モノはたいてい紋切り型である。いつも同じような登場人物が現れて中庸な結末が待っている。そのような中庸な結末を逸脱する作品を純文学と呼んでもいいわけだが、では純文学の方が大衆文学より優れているかといえばそうも言えない。〝中庸な紋切り型を逸脱すること〟が純文学的コードになってしまっている面が確実にある。ただヒューマニズムや愛のように、純文学には大衆文学のような決まった落としどころがないから厄介である。
又吉氏の『火花』については、漫才師が小説を書いたことで従来の純文学の枠組みを破っているのではないかと期待したことから、ちょっと厳しい批評になった。ただ羽田氏の『スクラップ・アンド・ビルド』を読んで、『火花』は少なくとも渾身の力作なんだなと思った。羽田氏の作品が劣っているという意味ではない。彼は作家として生きてゆくことを決意しているのであり、恐らく今後、又吉氏よりも作品を量産して純文学界で活躍してゆかれるだろう。もちろん『火花』が渾身の力作だということも、羽田氏の作家としての決意も相対的なものである。もっと力作を書く作家が現れるかもしれないし、作家としてさらに強い決意を持った作家が出現するかもしれない。ただ『火花』という畢生の力作に対して、より読者の注目が集まったのは自然なことだと思う。読者は美食家なのである。
良い悪いの問題ではなく、作家はプロとして活動してゆこうと決意したら、現実に存在するメディアコードを意識しなければならない。テクニカルな問題としても、作家は純文学を書こうと思わなければ書けないし大衆文学も同様である。理想を言えば、作家の資質が純文学や大衆文学のコードにピッタリ重なっているのが一番いい。しかしそれは稀である。ほとんどの作家は純文学作家でも大衆文学作家でもないのである。ただ作家の中でメディアコードの方が優先されてしまうとマズイことになる。作家の固有性が徐々に失われてしまうからである。しかしそれはメディアが悪いわけではない。メディア側にも論理はある。
たいていのメディアは読者を抱えており、その最大公約数的なニーズを把握している。作家に好き勝手に書かせても本はまず売れないのであり、メディアの風土を通して作家に読者ニーズを理解させる必要がある。それにより読者にパブリシティを行うわけだ。もしくは作家が読者ニーズを十分理解した上で、さらにその上をゆく作品を書くよう促すのである。それができなければ、作家は純文学系作家、大衆文学系作家に大まかに区分されることになる。俗な言葉で言えば、文学的価値は高いのかもしれないがいつも面白くない作品を書く作家と、面白いけど読んだ端からすぐに内容を忘れてしまう作品を書く作家という読者認知である。メディアコードを正面突破できる作家だけが〝系抜き作家〟になれる。純文学に話を限れば、作家は読者に「読むのはちょっと辛かったけど、読んで良かった」と深く納得させなければならない。
衝立が見えてくる。灰色のトタン板だ。太い木枠に囲まれている。高さは三メートルぐらいか。排ガスに煤けている。道の左右にそれが現れる。車道に沿って並ぶ。隙間なく並んでいる。だんだん車道にせり出してくる。そのせいで道が狭くなる。車線をいくつか塞いでしまう。(中略)
槌音が鳴り響く。カンカンと高く響く。金属を打ちつけているらしい。衝立の向こうから聞こえる。工事をしているのだ。何を作っているのか。それを窺う事はできない。衝立が四つ角を取り囲む。重機はその向こうで働いている。
陳さんに聞いても無駄だった。(中略)訛りがとてもきついのだ。(中略)僕らは終始無言でいる。車の中でただ前を向いて座る。視界は今朝も不透明だ。深いモヤに包まれている。道沿いの建物が霞む。ブレーキランプは赤い。ウインカーは黄色い。モヤの白い膜に溶け込んでいる。窓の外一面に光が灯る。毎朝それを眺めている。
(『自由の国』馳平啓樹)
馳平啓樹氏は第百十三回文學界新人賞を受賞した新人作家である。主に「文學界」に作品を発表しておられる。『自由の国』は質の高い作品である。主人公は日本に妻を残したまま中国に単身赴任している小笠原だ。馳平氏も現在中国に住んでおられるようだが、馳平氏が日本では知り得ない現地の機微を表現できるから『自由の国』が優れているわけではない。この作品の主題は冒頭の「衝立が見えてくる」に集約されている。もちろん道路をふさぐ衝立の向こうでは何かの工事が行われている。それはいつか終わり、新しい建造物が姿を現すだろう。しかし新技術を導入したまっさらな施設ができあがっても何も変わりはしない。現実世界は細部まで明瞭に見えているのにそれは深く内面化されている。
「彼らも大変なんです。難しい事は分かっています。上の幹部からやれと言われるんです。幹部はもっと上からそう言われるんです。目標をクリアしないと大変なんです。だから一生懸命やってるんです」
「中身が伴わなかったら意味がない」(中略)
会社がここに工場を建てた。間抜けな僕らが送り込まれた。行けと言われたから来たのだ。他に何もない。単純な話だ。観光に興味はない。今の暮らしそのものが旅だから。異文化はあと一ミリも受け付けない。不安なら過去形を使えばいい。女に溺れたりできる。酒に酔い潰れるのも簡単だ。そんな店がいくらでもあるのだ。のめり込む人もまたいくらでもいる。人生をやり直す事さえ可能だろう。
それを言うなら答えは出ている。変わりたくないのだ。僕は変わりたくない。頑なにそう意識する。いつからそうなのか。よく分からない。マイノリティとしてそう思うのか。この国が肌に合わないだけか。考えすぎると本質を見失う。自分を守りたいだけだ。警戒心が強くなったらしい。それだけの話だ。
(同)
主人公の仕事は中国に建てた工場の品質管理である。しかし仕事はほとんどない。通訳が能力不足で彼の言葉を正確に翻訳してくれないからだけではない。中国では中国のやり方で物事が進んでいる。無理な生産ラインを設定しても粗悪品ができあがるだけだという主人公の危惧は的中するが、中国人たちはその手直しをいつもの人海戦術で行い、なんとかノルマを達成してしまう。通訳は「大丈夫です。小笠原さんは座っているだけでいい人ですから」と言う。主人公は仕事からも、中国という国からも閉め出されている。彼は「僕は変わりたくない」と思う。いつか弾けてしまいそうな、無茶な膨張を続けている中国がそう思わせる。しかしもちろん理由はそれだけではない。
「手っ取り早く変わろうとしたくせに。何でもいいから変わりたかったったくせに。変わりたくて仕方がなかったくせに」(中略)
「だから諦められるんだ。簡単に区切りを付けられるんだ」(中略)
僕に仕返しをしていた。弱さと曖昧さに付け込んでいた。そうしてこの広い国に追い遣ろうとしていた。僕なんて要らないのだ。そう突き付けていた。気付かなかった自分にも腹が立つ。僕らはもう破綻しているのか。やり直せないのか。彼女を甘く見ていた事を悟る。得体の知れない強さを嗅ぎ取っている。恐ろしさを感じてもいる。頼もしくさえある。得体の知れない印象が渦を巻いている。(中略)
電話を持つ手が少し震える。怒りでその酔いをごまかしている。あの真新しい空間が思い出される。侮られている。僕ひとり取り残されている。徹底的に打ち負かされている。だとしたらやり返すのだ。嫁を追い詰めてやる。どこまでもひとりにさせてやる。道がそこにあるかもしれない。思いも寄らない行き先が、離れて暮らして以来持つことのなかった希望すら。
「いっぱい稼いでね」
「こっちに来てくれよ」
「要るものがあれば送るし――」(中略)
「要るものがなくなったら呼ぶから」
(同)
主人公が中国に単身赴任した理由は、妻が日本で不妊治療を行いたいと強く望んだからだ。それはもう長い年月続いており、彼は子供を諦めかけている。しかし妻はそうではない。彼女は「手っ取り早く変わろうとしたくせに。何でもいいから変わりたかったったくせに」と主人公を責める。不妊治療を始めた当初は確かにそうだった。夫婦は子供を作ることで、今までとは違う未来が開けると夢想した。しかしその夢が潰えかかった時、主人公は中国行きを承諾した。子供なしでの夫婦の新たな未来を夢想したのである。ただそれは「弱さと曖昧さ」が入り交じった感情でもあった。妻は前へ前へと進もうとする中国と同様に、彼が日本に残してきた精子で不妊治療を続けると決意している。夫婦の道は分かれた。「要るものがなくなった」時とは、妻が子供をもうけることをあきらめた時だろうか。その時、夫婦に新しい未来は開けるのだろうか。
元旦はいつも通り騒々しい。西暦がひとつ進んだだけだ。僕は眉を窄めて歩く。幾分軽くなった気がする身体を連れて。中国でも日本でもないのだ。もう一度それを考えてみる。どちらもでない空間で生きる。帰れと言われるまでそこで暮らす。それも悪くないはずだ。国籍を捨てたと思えばいい。僕はもっと身軽になれる。何もないほど軽やかな場所にこそ自分がいる。本当かどうかは分からない。でも選ぶとはそういう事だろう。何も選ばない事と一番似ている。
駿が駆け出した。何だか機嫌がよく見える。あの店でエサでも貰ったのか。工事現場を避けて通る。広々とした道をゆく。向こうから犬がやってくる。二匹がじゃれあい始める。互いの尻尾を追って駆け回る。これだけ動いて疲れないのか。いつ見ても走り回っている。思う存分駆けている。この国に住んで犬好きになった。リードに支配されていないのが良かった。犬を食べる町もあると聞く。ここはそうでないから良かった。
(同)
主人公も妻も中国も複雑に絡み合った強靱な関係性に囚われている。そこから抜け出すことは絶対にできない。だから「国籍を捨てたと思えばいい。僕はもっと身軽になれる」という主人公の独白は反語だ。彼は「選ぶとはそういう事だろう。何も選ばない事と一番似ている」とも考える。それは一つの痛切な認識であり、自由の断念の先に現れるほんのわずかな自由の確認である。この先に思考は存在しない。物語もない。
『自由の国』は人間の自由を巡る、矛盾し混乱した現実の底にまで届いている作品である。「リードに支配されていないのが良かった。犬を食べる町もあると聞く。ここはそうでないから良かった」という作品の末尾もまた、無条件の自由など存在しないことを示唆している。思考がありきたりの結論に赴きたがるのを、最後までこらえ切った単純で美しい叙述である。『自由の国』は正統な純文学作品として秀作である。ただこのような作品を量産することは難しい。馳平氏のさらなる作家としての力量が問われるだろうが、彼が『自由の国』を書いたことをわたしたちは忘れない。
大篠夏彦
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
