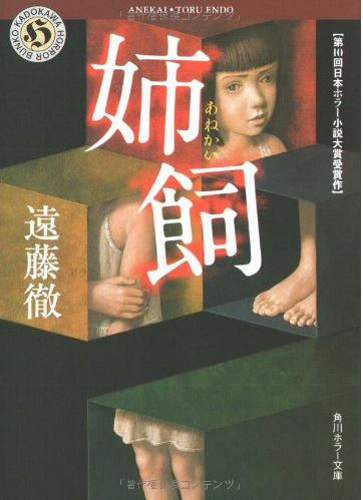
『姉飼』は遠藤徹氏のデビュー作で、平成十五年(二〇〇三年)に第十回日本ホラー小説大賞を受賞した。選考委員の荒俣宏氏は「私はこの作品が「毒」であるのか「純情」であるのか、最後まで判断できなかった」と述べている。同じく選考委員の高橋克彦氏は「いままでとは別の次元から送られて来た作品という気がする」と書いている。僕も同感だ。『姉飼』は表題作のほか『キューブ・ガールズ』、『ジャングル・ジム』、『妹の島』を収録した単行本として刊行され、現在は角川ホラー文庫の一冊として読むことができる。しかしそもそも『姉飼』は、ホラー小説なのだろうか。
通常のホラー小説は周到なエンターテイメント商品である。作家は読者を怖がらせるために主人公を決して逃げられない状況に追い込み、突飛で驚きに満ちた怪異現象を用意する。しかし遠藤氏の小説では怪異は当たり前のものとしてある。フィクショナルな因果関係の結果として怪異が起こるわけではないのだ。まずどうしようもない怪異現象が厳然としてありそこから物語が始まる。一般的なホラー小説とは逆に怪異が物語を牽引するのである。誤解を恐れずに言えば、遠藤氏の小説は怖いというよりも不気味である。そしてその不気味さは、遠藤氏が描く怪異(怪物)にリアルな手触りがあることから生じている。
ずっと姉が欲しかった。姉を飼うのが夢だった。
脂祭りの夜、出店で串刺しにされてぎゃあぎゃあ泣き喚いていた姉ら。太い串に胴体のまんなかを貫かれているせいだったのだろう。たしかに、見るからに痛々しげだった。(中略)からみつく力は相当なもので大の男でも、ずりずりと地面に靴先で溝を掘りながら引き寄せられていく。ついには肉厚の唇の内側に、みごとな乱杭歯が並ぶ口でがぶり。とやられそうになるのだが、その直前に的屋のおやじたちがスタンガンで姉の首筋をがつんッ。とやるので姉は白目を剥いてぎょええええッとこの世のものならぬ悲鳴をあげる。(中略)もしほんとうに噛まれたとしたら大変だ。まず間違いなく噛まれた部分は食いちぎられてしまう。(中略)姉は食いちぎった生肉をうまそうに噛みしめ、そして完全にかたちが失われないうちにごっくんッと丸呑みするだろう。
(遠藤徹『姉飼』)
『姉飼』は「ずっと姉が欲しかった。姉を飼うのが夢だった」という主人公の告白から始まる。主人公は小学生になったばかりの頃に、父親に連れられて地元の祭りに行った。その縁日で「姉」を見て一瞬で魅了されてしまう。姉は危険な怪物で、杭で胴体を串刺しにされた無残な姿で曝されていた。そんな姿でも怪力で、不用意に近づいた者に噛みつき肉を食いちぎってしまう。人間の生肉を「完全にかたちが失われないうちにごっくんッと丸呑みする」という記述は、彼女らが生きた人間を滅ぼし、かつ生きた人間によって生かされていることを示している。つまり姉たちは見せ物ではない。人間に飼われ飼い主を滅ぼす者たちである。言葉を喋らない異形の怪物だが、女性である以上、姉たちの飼い主の多くは男性である。
そこでぼくが見た光景。それを忘れることはきっとできないだろう。あるいはその光景がそれ以後のぼくの人生を呪縛したともいえる。そこにはたしかに姉がいた。いや姉がぶら下がって揺れていた。(中略)姉が揺れていたのは、姉が暴れるためだけではなかった。(中略)こんな田舎なのに上下の背広を着込み、ベレー帽を目深に被った男が大きな牛用の鞭で姉をぶっていたのだ。びしいっ、びしいっという音が響くたびに姉はぎぃええええい、ぎぃええええいッと、串から血をしたたらせながら声をあげる。(中略)着物はほとんどずり落ちて、腰箕のようにぶら下がっており、裸の白い体が闇の中に浮かび上がっていた。さらにその腰といわず、肩といわず、尻といわず、乳房といわずいたるところに真っ赤な大ミミズがのたくっていた。
(同)
同級生の芳美から、主人公は彼女の叔父が姉を買ったと聞く。親に内緒で芳美といっしょに姉を見にいく。「ぼくは背筋でぞくぞく蛇がのたうつのを感じた。怖かったわけじゃあない。とにかくぞくぞくしたのだ」とある。芳美の叔父・叔母の家の納屋で、二人は叔父が鞭で姉を打ち据えている光景を見る。芳美が乗っていた材木の山が崩れて大きな音を立て、覗きが露見してしまう。姿を現した叔母は平然とした様子で「いらっしゃい。芳美のお友達かしら」と言うが、芳美は「誰、あなたは誰なの?」と恐怖の声を上げる。次いで姿を見せた叔父は「ははは、いけない子供たちだ」と笑う。主人公の目を見て「君もそうなのか。どうやら、あれに魅入られてしまったようだね」と呟く。翌日納屋で、叔母が姉のように杭に串刺しになった惨殺死体で発見される。叔父が犯人であることは明らかだが、すでに姿をくらましている。芳美も消えた。村の者たちは叔父が芳美を連れ去ったのだろうと噂する。
二人が見た光景はポルノグラフィックなSMのようである。しかしもちろんそうではない。姉は醜くおぞましい怪物であり性の対象になり得ない。「君もあれに魅入られてしまったようだね」という叔父の言葉は、ほんの一握りの者しか、ただ暴れるだけの姉の存在の意味を理解できないことを示している。姉を鞭で打つのは姉がそれを望んでいるからである。姉はほかにも様々な事柄を望むだろう。飼い主は言葉を発しない姉の望みを直観で理解し叶えてやらねばならない。主人公は選ばれた者であり呪われた者でもある。
主人公は中学を出るとすぐに鮨職人になって働き始める。一生懸命修行し、わずか五年で自分の店を持つ。十分な金を貯め、小学生の時に手に入れた一枚のチラシを取り出す。姉たちを扱っていたテキ屋が配ったチラシである。十二年も前のチラシなのに、書かれている番号に電話すると通じた。主人公は「あれが欲しいんですけど。串を一本」と言う。主人公はついに自分の姉を手に入れる。すべての苦労はそのためにあったのである。
牛用の鞭はやはり必要だった。(中略)こうして、長年夢想しつづけてきたあらゆる演出を施しながら、ぼくは姉に仕え、姉を賛美し、姉に奉仕し続けた。生活のために家を空けている間、鮨を握っている間も頭のなかには姉のことしかなかった。
けれどもまもなく、ぼくは姉の虜となったものが、二度と姉なしで暮らせなくなる理由を知ることになった。それはひどく打ちのめされる体験でありながら、同時に恐ろしく甘美な陶酔感をも引き出すものだった。ある朝、姉が死んでしまったからだ。(中略)ぼくは姉の死骸を抱きしめた。いや姉の体にしがみついたのだ。意外なほどに小さく、硬直して冷たくなっていたにもかかわらず、思っていたよりずっと柔らかかった。(中略)声をあげて泣いた。号泣した。姉を失った悲しみと、姉を幸せにしてあげることができた喜びにまみれて泣いた。(中略)ぼくは姉に埋もれ、姉に満たされた。姉に包み込まれ、姉とひとつになったのだ。
(同)
姉を飼ってみて初めてわかったことだが、その寿命は長くて三ヶ月ほどだった。姉が死ぬと主人公はまた新たな姉を買い求める。そうせずにはいられないのだ。テキ屋は足元を見て法外な値段をふっかけてくる。その繰り返しの先には破滅しかない。破滅への道筋はホラー小説という物語の決まり事でもある。しかし姉という怪奇な存在と主人公の激しい執着は、楽しみとして恐怖を味わうためのホラー小説の文脈では読み解けないだろう。
端的に言えば姉は、自己が生き延びるためなら迷わず他者を犠牲にする生命存在の原理、あるいは人間存在の剥き出しのエゴそのものである。姉はペットかもしれないが決して飼い主になつかない。それどころか牙を剥いて襲いかかり、時には飼い主を食い殺してしまう恐ろしい存在だ。しかし主人公はそんな姉の飼い方を知っている。解き放たれた醜く危険なエゴは社会によって押し込められ、囲い込まれて重罪犯罪者のように細々と生かされるほかないのである。
主人公は姉に無償の愛を捧げ、「姉に仕え、姉を賛美し、姉に奉仕」し続ける。もちろん姉が主人公の献身を理解し感謝することはない。ただ主人公は姉の死を看取ることで「姉を幸せにしてあげることができた喜び」を得る。「姉に包み込まれ、姉とひとつ」になる。ではなぜ主人公は、純粋だが醜さの極点にあるエゴ存在に激しく惹かれるのだろうか。主人公の自己犠牲はなにを希求しているのだろうか。
彼が人間存在に対して、倫理やヒューマニズムといった一切の幻想を抱いていないのは確かである。むしろ剥き出しの醜いエゴに触れ、ありのままそれを見つめたいのだ。その意味で彼は真理の探究者である。また原理的だが不吉なエゴ存在を飼うことでのみ満たされるという意味で、彼は普通の常識人であり空虚な傍観者でもある。姉を飼った(買った)芳美の叔父もまたそのような人だった。彼は東京の裕福な家の子で有名大学を出たが、田舎に来て頭の弱い叔母と結婚した。希薄なエゴの女性を妻とし、次いでエゴの極地である姉を飼ったのである。
ただ主人公は、人間存在への希望をすべて失った虚無主義者ではない。彼の献身は報われないが、姉の死を看取るのは彼なのである。冷たく傍観的な彼だけが、誰もが目をそらす原初的な人間のエゴを受けとめ愛してやることができる。それによって〝姉〟は世界内で居場所を得る。誰もが目をつむり排除し続けてきた姉の存在を受け入れることで、世界全体の調和は回復されるのである。
主人公は姉を飼うためならすべてをなげうつ自己について、「ぼくのほうこそもう人間ではないのだろう。もし射殺できるものなら、そうしてほしいものだ。ただし、できれば(中略)不意打ちで(中略)殺してもらいたい。殺されるとわかって殺されるという状況に耐えられないほどにはぼくは人間的であるらしい」と独白している。もし姉が口を利けるなら〝偽善者!〟と叫ぶだろう。嘆き悲しみながら、彼だけが甘美な愉楽に包まれて生き延びるからである。しかし主人公と姉はお互いを必要としている。その愛は普通の人間同士のそれではない。それぞれのエゴがぶつかり交わり合う不吉で相互依存的な愛である。
遠藤氏の小説ではしばしば作品冒頭から、なんの説明もなく暴虐の限りを尽くす異形の者たちが現れる。それは彼の本質的興味が、異形の者たちの存在理由の探求にあることを示している。また遠藤氏の小説は通常の起承転結の手順を踏んで進まない。異形の者たちに冠せられた名前、あるいはその外形や習性や行為から言葉が紡ぎ出されてゆく。このような作品を、わたしたちは実験小説や前衛小説と呼ぶ。またいかんともしがたい表現主題を抱えた作家は純文学作家である。遠藤氏の小説はホラーに分類されるが、それは純文学ホラーとでも呼ぶべき作品群である。遠藤氏の小説は読者を怖がらせようとはしていない。自ずから溢れ出す作家の不吉な欲望が、時に読者に恐怖を感じさせるのである。
鶴山裕司
■鶴山裕司詩集『国書』■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

