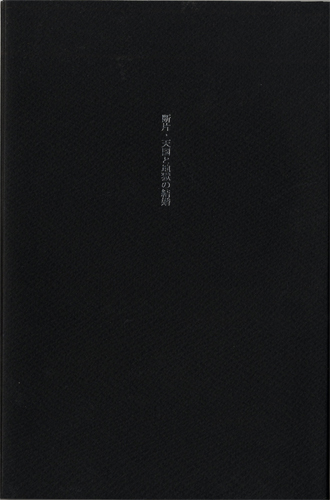
鶴山裕司氏が文学金魚で、「詩は形式的にも内容的にもなんら制約のない自由詩である」と定義してから、詩の世界では急速に〝自由詩〟という呼称を使う詩人が増えている。ご多分に漏れず詩の世界にも閉塞感が充満しているわけだから、多くの詩人たちが「詩は自由詩である」という当たり前だが新たな認識(定義)を、次代の詩を生み出すためのきっかけにしたいと考えていることの表れだろう。
しかしそれだけでは済まないのが人間の世界というものである。鶴山氏の基礎定義は「詩が本質的に自由詩である以上、「戦後詩」や「現代詩」はある時代固有の詩の潮流(エコール)として相対化される」と続くわけだが、戦後詩はともかくとして、「現代詩」を相対化することに多くの詩人たちが抵抗感を抱いているようなのだ。理由は単純で、戦後の長い間、「現代詩」が自由詩の呼び名(通称)だった。それを反映して詩の世界の数少ない商業誌に「現代詩手帖」がある。詩人たちは「現代詩」を相対化することは、「現代詩手帖」誌を相対化すること(不興を買うこと)につながるのではないかと恐れているようだ。
先日、現代詩手帖で「現代詩はまだ終わっていない」というタイトルの原稿を読んで苦笑してしまった。詩人の皆さんが大好きなジャック・デリダを持ち出すまでもなく、「現代詩はまだ終わっていない」という言表は「現代詩は終わった」という認識を含む。その言表自体が現代詩を相対化しているのである。国家から個人に至るまで、どうしても譲れない固有のアイデンティティはある。現代詩手帖が「現代詩は終わったのか?」という特集を組むのは難しいだろう。しかし頼まれてもいないのに、詩人がある雑誌の代弁者になってしまうのはいかがなものかと思う。戦後詩と同様に現代詩の相対化が始まるのは時間の問題である。
かつては時代の最先端を走っていたはずの現代詩にしがみつく以外、どうしていいかわからない詩人が多いのでそんな混乱が生じるのかもしれない。まともな物書きならやるべきことは決まっている。現在進行形で起こっている世界の大きな変動は、第二次世界大戦後の戦後レジュームの最終的な精算と崩壊を予感させる。世界の末端に文学の世界も含まれるわけで、いずれここにも大きな変化の波が押し寄せるだろう。考え抜いてそれを作品と思想にし、何事かを変えてゆくほかない。新しい思想に裏付けられた作品、新しいプラットフォームを創り出せなければ船は沈む。新しい船を造るのか、古い船を改造するのかは個々の詩人の自由である。
鶴山氏の「詩は形式的にも内容的にもなんら制約のない自由詩である」という定義は正しいと思うが、もちろん基礎中の基礎定義である。この基礎定義の先には「まったく制約がないにも関わらず、なぜ自由詩はひとまとまりの文学ジャンルを形成しているのか?」という問いが続くだろう。その解答は思想の問題に属するはずである。またそれは「なぜ短歌・俳句・自由詩・小説といった文学ジャンルは本質的に決して融合しないのか?」という問いへの答えにもなり得る。僕が興味を持っているのも、そのような原理的思想論だけである。
ゲンシュウ、ってのがありますね。幻の臭いですよ、(中略)このカセットラジオってんですか、買ったとき、機械がまだ、新しい時、機械の臭いが、するんですよ、(中略)トイレの方へ、行って、トイレの小窓が開いて、外の空気が入ってきますよ、(中略)そういう、とこでも、しばらく、機械の、臭いが、しましたね・・・(中略)六週間入院したけど、ろくな俳句は生まれませんでした、北海道に、ヌカベダという、ところがあんですよね、(中略)ヌカベダは反対に読むと、ハンカ、例のヘブライ語の、ここの、ツヤツヤガラキュウヒト、あれの、音を、ひっくり返した、ような・・・
(「戯言格子」より)
(田沼泰彦『断片・天国と地獄の結婚』より「天国 Ⅲ」末尾部分)
田沼泰彦氏の詩集『断片・天国と地獄の結婚』は、「地獄」篇十作と「天国」篇十作の二十のフラグメンツ(断片)から構成される。「地獄」篇Ⅰの後に「天国」Ⅰが置かれ、それが十回繰り返されるわけだ。「地獄」篇に収録されているのは三行表記の俳句である(Ⅴのみ一行表記)。「天国」篇に収録されているのは多少のイレギュラーはあるが散文詩である。なお引用した「天国 Ⅲ」の末尾に「「戯言格子」より」とあるが、これは田沼氏の創作(偽書)だと思う。
田沼氏は文学金魚で俳人・大岡頌司氏についての連載を掲載している。晩年の大岡氏はユダヤ神秘思想に傾倒していたので「天国 Ⅲ」は大岡氏の言葉の引用だろう。また大岡氏は第五句集『利根川志圖』まで三行表記俳句を書いていて、それが氏のトレードマークになっていた。田沼氏の「地獄」篇での三行表記俳句は大岡氏の技法の影響を受けたものだろう。つまり詩集『断片・天国と地獄の結婚』は俳句と詩(散文詩)から構成されている。
俳句を書く(書いた)自由詩の詩人は数多くいる。自由詩を創作した俳人は少ないが、加藤郁乎氏がその代表だろう。しかし郁弥氏の自由詩は俳句を行切りにして並べたような作品で、句集『球體感覚』や『えくとぷらすま』の衝撃には及ぶべくもなかった。詩人が書く俳句も同様である。安東次男氏は自由詩から出発したが、晩年は俳人だったと言ってよい。一口に詩といっても、自由詩と短歌・俳句の世界には越えがたい壁が存在するのである。
田沼氏の『断片・天国と地獄の結婚』での試みは、ひとまず俳句の自由詩化や、自由詩の俳句化を拒む形で二つの表現(ジャンル)を並列させている。自由詩が「形式的にも内容的にもなんら制約のない」表現である以上、もちろんこのような創作は可能である。しかし自由詩と俳句の間には乗り越えがたい大きな壁がある。このような表現方法を選択した以上、なんらかの形でその統合が図られなければならないだろう。
そんな昔の事はもう、すっかり忘れちまったから、今更思い出して苦しむこたあ無いさ 場末の映画館では今頃、野垂れ死んだ兵隊さん達が大勢、銀幕の中で息を吹き返してる(中略)あののざらしをうったのはだれだ、なみだかとおもったら、血じゃねえかこりゃ・・・みけんの穴から、風がへえってきて、さむくてしかたねえ、ましてここ、しべりあ・・・こおったばらが、こおったすいせんが、色あせて、こおった血が、いろあせてく・・・あののざらしをうった野はおれ、あな野あいたたくさん野、のざらしが、いろあせてく、あ野せんじょう、あ野ばすえ野ぎんまく、あ野、の野あな、あ野、のざらし野、野。
(「空葬(からとむらひ)」より)
(田沼泰彦『断片・天国と地獄の結婚』より「天国 Ⅳ」末尾部分)
詩集『断片・天国と地獄の結婚』の主題は死者の声を表現することである。引用の散文詩の語り手は戦争で死んだ兵隊である。銃で撃たれて眉間に穴があいている。「あののざらしをうった野」から末尾までは、最後の「野」だけが漢字表記されるべきもので、そのほかの「野」は助詞の「の」をあえて漢字表記にしたものである。
作者は死者の声を表現するために、日常言語では誤りと言える表記方法をあえて選んでいる。またそれは「野」への執着を表現している。生臭い現実を「野」へ、自然の方へと押し戻そうとしている。ものすごく単純化すれば、それが原理的には花鳥風月表現である俳句を作者が選んだ理由だろう。
後朝や
睡蓮閉じる
迄の伽
後朝や
畳焦がして
螢消ゆ
後朝や
縄目の筋に
沼縄生ふ
(田沼泰彦『断片・天国と地獄の結婚』より「地獄 Ⅹ」冒頭)
きた きた きた 廊下のどん突きからやってくるこの靴音で おれは毎朝 目が覚める この靴音が おれの房の前で停まるその朝こそ 壁に刻んだ辞世を遺書に書き付けるとき その朝のことを おれは 精一杯 しゃれのめして こう呼ぶだろう 「後朝(きぬぎぬ)」と
そしておれは おれに殺された彼(か)の人を呪うための遺書を こう書き始めるにちがいない 「オレハ活(い)キタ。」と 「オレハ活(い)キタ。」と 「オレハ活(い)キタ。」 きた きた きた
(田沼泰彦『断片・天国と地獄の結婚』より「天国 Ⅹ」部分)
「天国」篇Ⅹ章は死刑囚の独白である。この死刑囚は死刑に値する殺人の罪を犯したにも関わらず、なんら後悔も反省もしていない。殺した男を呪い、殺された男よりも長く「オレハ活(い)キタ。」と繰り返している。またこの死刑囚は死刑執行の朝を、「しゃれのめして」「後朝(きぬぎぬ)」と呼んでいる。詩集『断片・天国と地獄の結婚』の作品世界には、通常の意味での倫理は存在しないということである。殺人という許されざる重大犯罪も、殺した男よりも長く生きたという呪詛の言葉も、死という虚無の前では無意味だということだろう。
死刑囚の「後朝(きぬぎぬ)」という言葉と連動して、「地獄」篇Ⅹ章には「後朝」を詠み込んだ俳句が置かれている。しかし一句だけ取り出して鑑賞すれば何を表現したいのかわからない。つまり独立した俳句表現としては弱い。うっすらとした曖昧な関係性を保ったまま最後まで俳句と詩が並列して置かれており、なんらかの形で両者の統合的関係が築かれているとは言えない。俳句あるいは自由詩表現で完結できるのなら、両者の併用は原理的に必要ないはずだという絶対矛盾が詩集『断片・天国と地獄の結婚』にはある。
それは『断片・天国と地獄の結婚』で「野」への執着、つまり汚濁にまみれた現世からの超脱形式として活用できる花鳥風月的俳句作品が「地獄」と題され、生者の呪いの言葉と死者の妄執表現である散文詩が「天国」と題されていることからも読み解けるだろう。天国であるはずの俳句表現は実は地獄であり、地獄を記述する自由詩表現は本当は天国なのである。それは俳句形式でも自由詩形式でも作者の心の平安は得られず、求める表現は完結しないことを示唆している。それが詩集が「断片」と題されている理由でもあると思う。
作者があくまで『断片・天国と地獄の結婚』の主題に忠実なら、死への執着、その叙述への不吉な欲望は言語表現を貧しくするはずである。飽くことなく禍々しい呪いの言葉を繰り返すか、沈黙に耳を傾けるほかに道はない。しかしどちらの言葉も単調な繰り言になる。死は絶対不可知でありそれ自体に何事かを語らせることはできない。作者がこの煉獄から抜け出るためには、さらに新たな自由詩形式を創出する必要があるだろう。ただほとんど表現不可能な欲望を俳句形式と散文詩形式の併用によって表現しようとしたという意味で、『断片・天国と地獄の結婚』は記憶に値する書物だと思う。
小林大介
【詩集『断片・天国と地獄の結婚』書誌データ】
発行所 下井草書店
〒189-0014 東京都東村山市本町4-3-3
電話 042-397-2069
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
