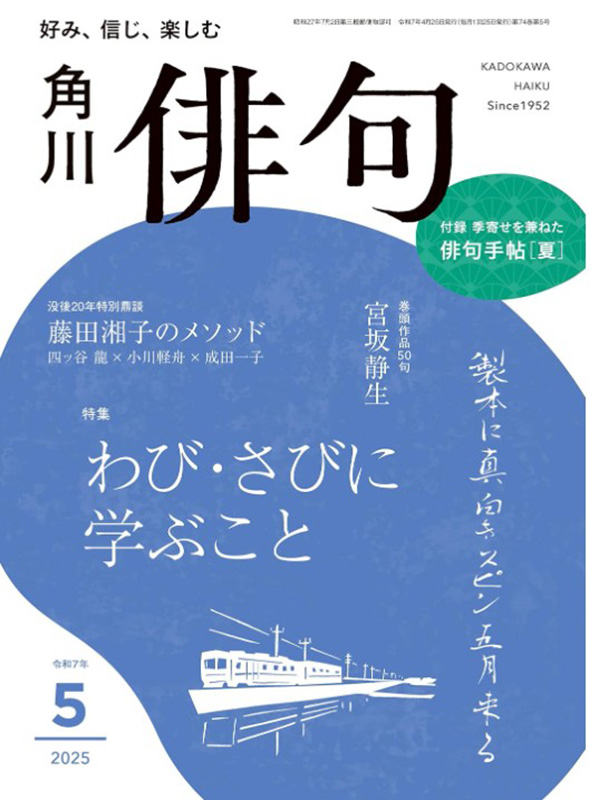
今号の特集は「わび・さびに学ぶこと」。んー、大きく出ましたな。わび・さびについてちゃんと説明できる人なんておるんかいな。キチンとやろうとすれば九鬼周造の『「いき」の構造』くらいの厚さの本にはなりそうだなぁ。
ただま、どの雑誌にも執筆の際の不文律的ルールがあって、句誌の場合は特集のお題に関する俳句を読者に紹介することである。そっちの方がメインだ。要は「明るい俳句・暗い俳句」「春の季語・冬の季語の使い方のコツ」といったお題が与えられたらそれについて簡単に説明して例句を並べ、読者がすぐに真似できるようにしてあげるのが執筆ルールである。しかし「わび・さび」という概念は手っ取り早く俳句を詠むためのアンチョコに使えそうにない。名句秀句はたいていわび・さびを感じさせますからね。俳句と相性のいい概念だがあまりにも範囲が広い。
句誌が手っ取り早いアンチョコ雑誌になっているのは悪いことではない。俳句は形式文学だが形式と表現内容は一体である。不可分なのだ。だから秀句・名句の真似をすることで俳句が上達することはじゅうぶんあり得る。お茶やお花のお稽古で理由を一切説明されず、とにかく型を習得させられるのと同じである。それを自助努力でやるわけだ。
しかしそうはいっても俳句には多少の創作というか創意工夫の余地がある。真似だけで形式と内容が充実し深化するとも思えない。「わび・さび」概念は文化論に属しており俳句固有の問題ではない。特集の要約を入り口にそれについてさらに考え理解しなければ俳句創作にフィードバックできる知識や感性を得られないだろう。
まず、「わび」について述べていく。「わび」と同系列の動詞「わぶ」は、思い通りにならず、つらい、困るという意味である。この厭うべき状態を美と感ずるようになったのは、室町時代の後期の茶の世界からである。「わび茶」の創始者である村田珠光は、当時の金をかけた茶の湯に対して、粗末な狭い座敷で、あり合わせの道具で、本当の茶の味だけを楽しもうとしたのである。「わび」は後に述べる「さび」と同じような性質だが、質素とか倹約といった傾向が強い。
依田善朗「「わび」「さび」の継承」
特集では依田善朗さんが巻頭に総論を書いておられる。村田珠光、武野紹鴎らを祖として千利休によって佗茶が成立し、一般に侘び寂びという言葉と精神が根付いたのは言うまでもない。ただあまり茶道に深い入りすると太閤秀吉と利休の対立といった小説的興味にまで行ってしまう。桃山から江戸初期にかけて侘び寂び概念が形を得たことが重要である。
利休が大徳寺で得度した禅僧だったことからわかるように佗茶の精神基盤は禅宗にある。禅は無の宗教だが一休宗純に代表される度外れた風狂も含む。この世を無常と捉える感性は言うまでもなく室町初期成立の兼好法師『徒然草』から平安末期あたりにまで溯って捉えることができる。
さて「さび」に移ろう。同系統の動詞「さぶ」の意味は、淋しくなる、古くなる、色があせる、衰えるという意味で時の経過と関連する言葉である。この厭うべき状態の中に、奥深いものや豊かな美が潜んでいるのではないかということで、「さび」という美が生まれた。もともと淋しい状況であるから「閑寂の美」と言えよう。これを初めて美と認めたのは藤原俊成である。時代的には保元の乱、平治の乱の直後の混乱した時代に、「さび」を美とする感覚が生まれたのだ。
同
平安末に詫び寂びの概念(感覚)が多くの人の心を捉えるようになったのは理由がある。慈円が「むさの世になりける也」と書いたように凄惨な殺し合いが起こる武士の世になったからである。つい昨日まで栄耀栄華を極めた人が無惨に殺されることから生じる無常観は源平合戦で頂点に達した。平家は貴族武士だったが粗暴な坂東武士たちの京都乱入でさらに都の人々の無常観は強まった。平安初・中期まで中心だった香を焚きしめ仏画を掛け、一心に祈って浄土転生を願う密教的心性は吹き飛び禅的無常観が主流になった。平安末期以降、日本人の心性はこの禅的無常観にあると言っていい。
俊成と西行は同時代人だが西行は元北面の武士であり位が低い。にも関わらず『新古今』で最も多く歌が採られたのは彼の無常観がこの時代を代表するものだったからである。説話文学を読めば平安武士と後の江戸武士ではかなりその心性が違う。平安武士はハッキリ死ぬのも仕事と思い定めた武士の原型である。ほとんど戦争機械だ。そんな武士であった西行ですら深い無常観に囚われた。西行は隠棲したのではなく死にながら生きて歌を詠んだと言っていい。
この無常観は藤原定家晩年の「見わたせば」や鎌倉初期の源実朝短歌によって美的洗練度を増す。王朝短歌の終わりは定家―実朝短歌である。以後短歌は長い長い停滞期に入り俳句が連歌を経て芭蕉発句の創出によって短歌に代わる日本短詩型文学・形式文学の主役になってゆく。
この鎌倉から室町、江戸初期に起こったのは無常観の明確な美意識化である。無常観は当たり前だが殺伐としている。決して美しいものではなく心地よくもない。しかしそれを受け入れ安定した表現に高めるためにはその〝美化〟が必要不可欠である。
室町初期に成立した観阿弥・世阿弥の能楽、室町末から桃山時代に確立された茶道はそんな社会全体の動きを示している。特に茶道は取合せの美である。最低限の要素を取り合わせ全体で調和的世界観を表現する。茶席では軸物や茶碗、花入れなどを配置するがどれか一つが目立ってはいけない。日本美術(美意識)の本質は調和的世界観にあるが茶道がそれを最初に確立した。俳句が取り合わせによる調和的世界観表現であるのは言うまでもない。文学は常に世界の大きな変容の影響を受けている。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


