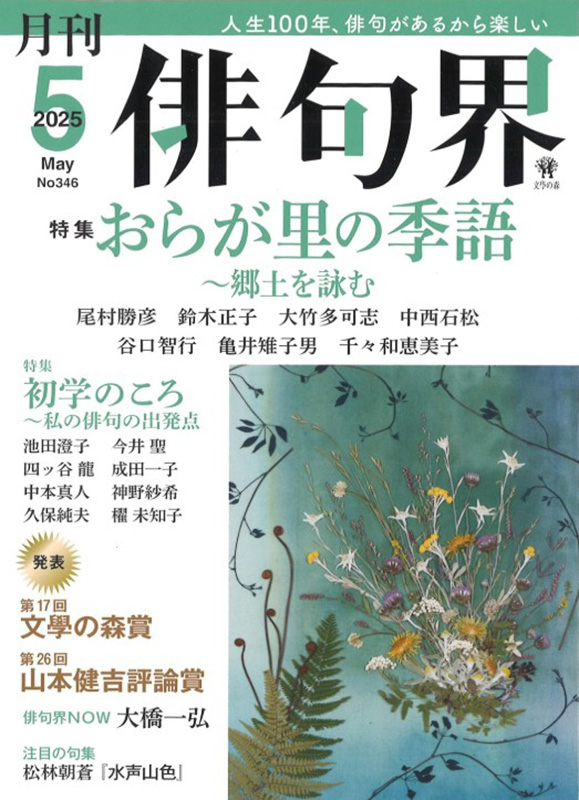
五月号では特集「おらが里の季語~鄕土を詠む」が組まれている。「月刊俳句界」ではお馴染みの特集だが、おらが里特集は好ましい。
僕は富山県出身だが、東京のコンビニで「鱒の寿司」が売られていて、それを買おうとした友人に「そんなもの買うんじゃない」と強い口調で止めたことがある。理由は笹に包まれておらず、笹の香りがしない鱒の寿司などあり得ないから。友人は呆れていたが、おらが里となると、まあたいてい理不尽なものである。そそ、友だちに高知出身のグルメがいて、誘われて高知料理の店に行ったら大皿にわけのわからないデザートが添えてあった。「刺身に羊羹はないだろ」と言ったら「高知の大皿料理はこれでいいのだ」と真顔で睨まれた。おらが里自慢はやっぱり理不尽である。
おらが里特集が好きなのは、皆さん楽しんで気軽に句を詠んでおられるからである。俳句からお遊びを排除することはできない。俳句はたまーに〝文学である(文学になる)〟のであって、あらかじめ文学であるわけではない。山本健吉が言ったように滑稽、挨拶、即詠は俳句の重要な要素である。座のお遊びの中から優れた俳句が生まれることもある。ただおふざけではなく一所懸命遊ばないと甲斐がない。
現代の句会(座)ではあらかじめ用意した句を発表して合評することが多く、即詠は抵抗があるだろう。やっても「梅」や「桜」などの正統歳時記的席題ではどうしても力が入ってしまうはずだ。その点おらが里の季語(席題)なら、たとえ故郷が違っていても肩の力が抜けるのではないか。皆で句を詠み合ってああでもない、こうでもないと秀句を練り上げてゆけば座本来の力を実感できるだろう。おらが里の季語(席題)は滑稽、挨拶、即詠にピッタリだ。それは常に俳句を俳句らしくしてしまう俳句の裏をかくのにも有効である。
歓声に風流物が空に反る
故里や風流物が空を衝く
大竹多可志
大竹多可志さんは茨木担当である。茨木のおらが里季語に「日立風流物」がある。大竹さんは「元禄八年、水戸光圀の命により、神峰神社の氏子が山車を造り、祭礼に奉納したのがはじまり。現在の山車は、高さ十五メートル、五層の巨大なものとなり、からくり人形が芝居をする華麗なものとなっている」と書いておられる。祭礼は五月か七月に行われるそうなので、春か初夏の季語である。
ただ「ひたちふうりゅうもの」では九か十音になってしまい俳句と相性が悪い。大竹さんも中句で「風流物が」と縮めて下の句に掛けて使っておられる。いっそ「常陸名物風流物数寄光圀公」と破調・のべつ調の、表記からして異様な句に仕立てても面白いかもしれない。なんの名物だろうと調べてくれる読者がいるかも。
硝子戸の己が眼や鰤起し
飛竜頭や信心篤き母の恩
中西石松
石川担当は中西石松さん。「鰤起し」は季語として定着している。北陸で最も珍重される魚は寒鰤だが、雷を伴う冬の嵐を「鰤起し」と呼ぶ。鰤を起こし漁師が網を起こすきっかけとなる嵐のことである。五文字なので座りがよく上句か下句に使うことになる。「鰤起し米塩水の朝神事」などいくらでも軽くバリエーションを詠めるだろう。
「飛竜頭」はちょっと特殊。「辞書を繰ると「飛竜頭はがんもどきの関西での異称」と書かれている。しかし我々金沢人にとってはそんな簡単な説明で片付けてもらっては困る。がんもどきと飛竜頭(金沢ではひろーずと発音する)は似て非なるものとしか思えないのである。(中略)我々が最も飛竜頭を身近に感じるのは十一月二十八日の親鸞忌すなわち報恩講である。(中略)御勤めのあと、庫裏などで出される精進料理の最も大切な一品であり、飛竜頭は報恩講と切っても切れないものである」と中西さんは書いておられる。飛竜頭は冬の季語が相応しいようだ。精進料理の定番だから「飛竜頭や寺の厨の油跳ね」でもよい。
ふるさとの黒潮晴れや懸の魚
蝸牛鳴くさういへば鳴きにけり
亀井雉子男
高知担当は亀井雉子男さん。「懸の魚」は「正月飾りの一種。高知県南西部に多く見られるが、地域によって飾り付けが少しずつ違う。私の故郷の中土佐町久礼では、腕木という横木に二尾の小鯛を結び、家の入り口や土間に掛けて豊漁と安全を願う」とあり正月の季語。
「蝸牛鳴く」は奇妙な伝承で季語である。「高知県では蝸牛が鳴くという。『土佐俳句歳時記』の解説に「山峡の田畑の岸辺などで、日和の落ち目の時などにカタカタとかカツカツというような音を発して鳴く」とある。(中略)虚実いずれにせよ、樹間のどこからともなく聞こえてくる音を「蝸牛鳴く」と、土佐の俳人が興じたのであろう」と亀井さんは書いておられる。春の季語である。「蝸牛鳴く王様の耳はロバの耳」だと飛びすぎか。おらが里の季語は思いついたらすぐに言語化してゆくのがよい。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


