 さやは女子大に通う大学生。真面目な子だがお化粧やファッションも大好き。もちろんボーイフレンドもいる。ただ彼女の心を占めるのはまわりの女の子たち。否応なく彼女の生活と心に食い込んでくる。女友達とはなにか、女の友情とは。無為で有意義な〝学生だった〟女の子の物語。
さやは女子大に通う大学生。真面目な子だがお化粧やファッションも大好き。もちろんボーイフレンドもいる。ただ彼女の心を占めるのはまわりの女の子たち。否応なく彼女の生活と心に食い込んでくる。女友達とはなにか、女の友情とは。無為で有意義な〝学生だった〟女の子の物語。
by 金魚屋編集部
4 卒業(下編)
「やっぱり赴任先にはついていけない」
彼の目をのぞきこんで言った。
「それって、つまり別れたいってこと?」
「……。進学することに決めたの。他大の大学院、受けてみる」
「そんなに簡単なことじゃないよ。進学って」
声がうわずっている。
「知ってる」
「院生なんて、陰険だし」
「私、陰険だもん」
「その先、どうするか考えてないだろ?」
「どこにもたどりつかなくても、考えてたいの」
「なにを?」
「答えがでないこと」
「なんにもならないことを考えるの?」
現実的な彼は、そう言った。
「考えていることが私だもの」
「そんなの家事をしながらだって、いつからだって考えてられるだろ」
「ちがうの」
「なにがだよ」
苛立っているのだろう。表情でわかる。
「自分でもわからない。たぶん、環境だと思う。まわりも考えているのがあたりまえなところにいたい」
「無限ループだよ」
「それでもいいの」
「なんで?」
人生は主観だから。
「一緒にいられた時間が特別だって思えたから。宮田君と会えて、結局、同じ立場じゃないとなにもわかってあげられないんだってことを感じた」
声に出しながら、私はいつか後悔するかもしれないと思った。
「そのままでいいって、何度も言ったのに」
「私が私のことを好きになれないから、他人のことも嫌いだったんだよ」
「母親が同じことを言ってたな。自分は学生の頃、可能性があったのに。あなたの世話をしているだけで終わりそうって。だから、俺のことが嫌いなんだって」
はー。と、ため息をつく。
「うん」

「わかった。がんばれよ」
「宮田君も」
「俺のほうが、好きな気持ちが強かったと思ってる」
「私のこと、わかってくれてないんだね。でも宮田君は、絶対に幸せになれるよ」
「さやちゃんこそ。絶対に幸せになってくれよな。もう泣きそうな顔、するなよ」
ありがとう。そう思った。この先、なにがあっても。
「どうしたの? 疲れてない?」
「ちゃんと食べてるの?」
「前よりも痩せたように見えるけど」
「あの人、何か悩んでるよね」廊下ですれ違ったとき、噂しているのが聞こえた。
「おかげさまで。よく寝れてるし、間食までしてます」
それだけ言って席についた。
表情で、だれも納得していないのがわかった。顔色が悪いのは、小学生のときからだったし。運動不足が原因だと医者に言われたことがある。正確には、生活習慣を指摘されただけだったのかもしれない。
低血圧の気がありますから。親御さんもそうなら、遺伝の可能性もありますね。就寝前に一杯、ワインを飲むといいですよ。医者にそう言われたのを覚えている。先生、私は未成年です。まだ子供ですよ。子供が子供だということを申告するのがおかしかったのかもしれない。先生は、苦笑いした。「とにかく、大丈夫ってことです。病気ではありませんから。次の方」私はお礼を言って、立ち去るしかなかった。寒い季節だった。バッグを肩にかけたら、ストラップが一本ずりおちた。
コートをくしゃくしゃに丸め、お腹に抱えたあと診察室を出た。受付で名前を呼ばれた。千円もかからなかった。薬は出なかった。形式的に「お大事に」と言われた。自分のことなら、お大事にしすぎているくらいお大事にしていた。私以外に、私をこれまでお大事にしてくださる方はいなかったので。私が正常なのは、わかっていた。ただ、医者のお墨付きが欲しかったのだ。分析すると、そういうことだと思う。
悩んでなんかいない。立ち止まってもいない。お腹が空かない。なんでだろう。深刻になることなんてないんだ。一人で、伸びをする。
「あの人、今三次性徴してる」
ああ。その通りだと思った。やっと、腑に落ちた。表面をなぞっているうちになにかが通りすぎていってしまったのだ。
*
場所 教務課ポスト16. 最終締め切り十五時。時間厳守。シラバスの内容を再確認する。
ファイルから卒論を取り出し、狭い口に滑りこませる。紙の束が、手から離れた。音はしなかった。はみ出した部分を押し込む。紙のかさかさした感触だけが手に残った。時計を見ると、十三時にもなっていなかった。自動ドアのマットを踏んだとき、背後から「お疲れさまでした」という声が聞こえた。教務課の事務員だ。生徒が出ていくときは、決まってそう言う。外の風は、冷たかった。意味もなく、校内を歩いた。すれ違った知り合いと友人に、卒論を提出したことを報告した。あっさりと「おめでとう」と言われた。左手にエンゲージリングを付けている子もいた。私だけが、このキャンパスで一人なのではないかと思った。

食堂に行く。いつものように、混雑している。周囲の会話に内容はなく、ただがやがやと言っているように聞こえる。食券機に小銭を投入し、四角いボタンを押す。食品と飲料とでそれぞれ色分けされていることに、いまさら気付いた。こんなに工夫されているなんて。コーヒーを選択する。FAX用紙のように薄い紙が落ちてくる。列に並び、ペラペラしたトレーを一枚取る。進みが早い。食券を、おばさんの前に置く。一分もしないうちに、コーヒーが出てくる。席を確保し、座る。
なんだか落ち着かない。私はもう、意識が部外者なのだろうか。コーヒーを飲んだら立ち去ろうと思いつつ、バッグの中から教科書を取り出し、テーブルに置いてみる。生徒であることを証明できるように。よく考えたら、だれも見てないのにおかしい。私はここにいてはいけない。立ち上がり、トレーとカップを返却口に返す。ほとんど無意識に「ありがとうございました」と発音していた。入学したときと同じような新鮮さで校内をめぐっている。お礼を言うなんて、わざとらしい。
去年の私は、軽蔑の視線と無関心で、お礼を言う先輩の姿を見ていた。やっと彼らの気持ちがわかった。拍子抜けしてしまうくらいあっさり終わるものだから、区切りをつけたくなったのだ。階段を登る。途中の窓から、テニスサークルの人たちがラリーしているのが見える。立ち止まらないように進む。まだサークルのメンバーにも会っていない。部室にむかう。古臭くて埃っぽくて、閉塞感に満ちたクラブ棟。どのサークルの扉も、やたらと重たいのだ。ノブを捻って、扉を後ろに引く。
「あーっ。さやねえ」
第一声が揃った。
「卒論、出した?」
「今提出したところ」
「私、字数ぎりぎり。しかも内容もお粗末」
「私も。とりあえず時間内に出しただけ」
「レナちゃん、間に合わなくて最初のほうだけ書いて、白紙を挟んだやつを教務課に提出したらしい。あとで教授とのやりとりで中身を差し替えるって。レナだから許されるとか言ってた」
「やり方が手馴れてるね」
「いいの? それって」
「先生も、レナちゃんのこと追い出したいでしょ? だから、大丈夫だよ。たぶん」
いつもの噂話。私がいなくても、サークルは通常運転だろう。
「じゃあね」
「え? もう帰るの?」
「元気にしてるかと思って」
「あ。打ち上げやるから。またメールするね」
「ありがとう」
「またね」
階段を上がる。ぐるぐるぐるぐる。まるで回遊魚のよう。二コマ空き時間の間、時々休みながら校内を歩き続けた。
*
教室の窓辺から、女の子たちの集団が見える。パステルカラーであふれかえるキャンパス。
「ゆかは、ドバイがいいって」
隣から、亜紀ちゃんが話しかける。彼女とは苗字が一文字同じだから、オリエンテーションの時の席順が近かった。どうして一緒にいたかと聞かれても、そのくらいのことしか思い出せない。たぶん、お互いにそうだと思う。
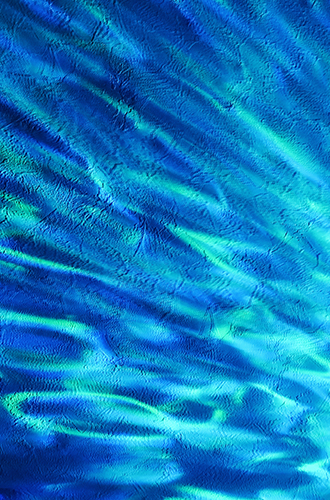
「ドバイって観光するところなにがあったっけ? ブルジュハリファだけじゃない? どうせならフランス行こうよ」
「仏文だしね。じゃあ、伝えておくね」
「まいまいとか、たらちゃんにも聞いたほうがいいよね?」
「うん。長い期間海外旅行ができるのもたぶん最後だし、イギリスにも行きたいな」
「私も。バッキンガム宮殿の兵隊見たい。でもさ、社会人になっても有給取れば行けるんじゃない?」
沈黙。
「卒業したら実家に帰らないといけないから。見合いしろって」
亜紀ちゃんは真面目な性格で、コンパにもほとんど顔を出さなかった。家と学校を往復するだけで大学生活のほとんどを費やしていた。
「三井さんっているじゃない。シャネルのバッグ持ってた子。あの子も今年中には籍入れるって」
「え~? どの彼氏と? 知らなかった」
「去年会ったばっかりの人だって。だからどの彼氏でもないみたい。ありがとうね」
「なにが?」
「一緒にいたおかげで、大学生活楽しかったし」
「遠くなっても会おうね」
「またランチしよう。まだ約束してた歌舞伎、観に行けてないし」
もうすぐ学生ではなくなる。私はどこにいても、浅く腰掛けるようにして生きてきた。立ったままでいるのもしんどいし、どこかに座りこんでしまうこともできない。
(第11回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『学生だった』は毎月05日にアップされます。
■ 金魚屋の小説―――金魚屋の小説だから面白い! ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


