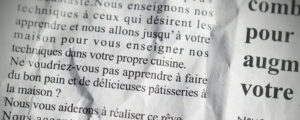 さやは女子大に通う大学生。真面目な子だがお化粧やファッションも大好き。もちろんボーイフレンドもいる。ただ彼女の心を占めるのはまわりの女の子たち。否応なく彼女の生活と心に食い込んでくる。女友達とはなにか、女の友情とは。無為で有意義な〝学生だった〟女の子の物語。
さやは女子大に通う大学生。真面目な子だがお化粧やファッションも大好き。もちろんボーイフレンドもいる。ただ彼女の心を占めるのはまわりの女の子たち。否応なく彼女の生活と心に食い込んでくる。女友達とはなにか、女の友情とは。無為で有意義な〝学生だった〟女の子の物語。
by 金魚屋編集部
4 卒業(中編)
*
共学の大学院の説明会を聞きに行く途中で、ふっかちゃんのママに会った。偶然、駅のあたりを歩いていた。
「あら。中野さんのお嬢さん」
「あ。深田さん」
レースが付いた白いエプロン。マロンブラウンの髪で、フルメイク。だれから見ても美人だ。カゴのバッグを提げている。
「お買いものですか?」
「そうよ。うちは紀伊国屋でしか買わないの」
「リッチですね」
「あら、お宅は?」
「普通のスーパーです。イトーヨーカドー。ご存知ですよね?」
好物のバナメイエビを売っているところなら、どこでもいいのだ。
「生鮮食品は紀伊国屋じゃないとダメよ」
「そうですか」
「品揃えがちがうからね」
教え諭すような様子だ。
「あ。はい」
「あらやだ。パパになにか買ってこいってたのまれたんだけど。忘れちゃったわ」
「ご主人ですか?」
「そう。パパよ。携帯買ってもらったの。メールってどのボタンかしら?」
ピンクの携帯が、エプロンのポケットの中から出てきた。スマホではない。未だにガラケーだ。メールボタンを押してあげた。
「これなのね? あなた。これでいいのね?」
絵で示してあるのに確認してくる。
「あ。はい」
「文面、打ってくれる?」
「いいですよ」
「パパへ。えーっと。なにを買ったらいいかしら?」
えーっと以外を入力し、送信する。
「ここを押すと、返信が見られます」
再びメールボタンを指さす。

「あらまあ。もう返事が来てるの?」
「あ。まだです。たぶん、画面に表示されると思います。紙ヒコーキのアイコンです」
「画面を見ればいいのね?」
口調がおっとりしている。普段から機械の説明書を自分で読まないのが習慣になっているのだろうか。なんでも任せられる男の人が身近にいること。それは、一つの幸せのかたちだ。
「そうです」
「パパがね。同僚の人から、「君の奥さんみたいな女は得難いぞ」って言われたのよ」
ふっかちゃんのママはきれい好き。家に遊びにいったとき、モデルルームのように整然とした部屋の様子に驚いた。ふっかちゃんは家事が嫌いなので、ほとんどママが掃除をしているのだという。
「たしかにそうですね」
「でも、下の娘が結婚しないのよ。それだけが悩みで」
会う度に同じことを言う。
「きっとこれからですよ」
嘘はついていない。本人もそう言っていた。
「ふみこー!」
いつのまにかふっかちゃんのパパが立っていた。カシミヤのコートを着ている。こんなに近くにいるなら、メールしなくてもよかったのではないか。
「記憶力がないなら、買い物なんかしないでもよろしい」
意外と厳しい意見だ。
「また、怒られちゃったわ」
二人は連れ立ってバス停に歩いていった。
電車に乗った。私も揺れている。赤ん坊を抱えた主婦が、端に座っている。五年前までは、大学生だったのかもしれない。突然、哺乳類のように子供を産むことに、抵抗はなかったのだろうか。いままでに得てきたものと無縁の生活を送ることにも。子供に追いかけまわされて、一日中解放されないことにも。
大学院の説明会といわれても、なにを説明されるのかが具体的に掲載されていなかった。作成した研究計画書を持って、指定の教室に座る。私服で来てよかったのだろうか。迷いが生じる。
院生の女子が、紙を配った。メガネをかけている人を想像していたが、クレリックシャツにジーンズだ。
「全員に、行きわたってますか?」
質問する姿を盗み見る。私の不勉強さが態度で伝わってしまうのではないか。
「一番端の方、空調、寒くないですか?」
声をかけられた。私のことだ。
「あっ。はい、むしろ暖かいです」
「あらそう。なにかあったらいつでも仰ってくださいね」
研究室には、受験する予定の人が詰めかけている。机の上にうずだかく積みあげられた本。パソコン。年季の入った木の机。
「外部からの人?」
となりの人から話しかけられた。スーツを着ている。
「うん」
自分で思っていたより、気弱そうな声が出た。虫の羽音みたい。
「私、ドゥルーズの研究しようと思ってるの」
内部生の女の子が言った。
「へー」
「ドゥルーズってなんや」
関西から来てる人もいるらしい。みつあみにした髪にピンクのバレッタを付けている。

「哲学者で……」
「あ。特に関心ないねん。言ってみただけやから。ありがと」
受験前から、既に火花が散っている。
「これから、説明会を行います。えー。と言っても、まだ先生がいらしてないので、受験の日程と概要について簡単に説明させていただきます」
はきはきしてるのに、女性らしい口調だった。
「紺野君、ありがとう。じゃあ、続きは僕がやるので」
先生が入室してきた。どう接していいのかわからない。
「あのねえ。緊張しても無駄だからね。試験会場じゃないから。うん。大切なのは意欲だよ。意欲。試験のことなんかは、紙に書いてあるからそれを各自で読んでください。わからないことは聞いてくれてもいいし。で、なんだっけ? あー。突然、自己紹介させるのもなんだからね。紺野君、自分の研究分野について。一言でも二言でも。述べてください」
教授はとてもリラックスしているように見える。先生だって、一人ひとり違うのだ。生徒とも親しそう。
「えーっとですね。私は、リラダンの作品における球体関節人形の表象について研究しています。院の中では、お笑い草ですけれども。自分のこだわりなので、特に気にしてはいません。去年はフランスに留学して、関連する論文を集めてきました。日本のものとは異なった切り口の論文が多く、大変勉強になりました。はい。食文化の違いも興味を引く点で、現在では味覚と幻想性の関連に関しても考察を進めています」
考察……勉強。すらすら喋る。一人で海外に出たのか。この人が。
「はい、ありがとう。じゃあ、参加者の方に、院でやりたいことをお聞きします。抽象的ですけれども、どうぞ」
私が一番先生の近くに座っている。
「あ。幻想文学の研究がしたいです」
「お名前は?」
「ネルヴァルです」
作家の名前を言ってしまった。しまった。
「君が?」
「あ。私は中野です」
「なんの分野に関心があるの?」
「幻想文学の中に登場する写実的な描写です」
「テーマが大きいね。博士課程の生徒でも、とても細かいところからスタートしているよ。まず最初は、一冊の本から語彙を拾って、作品中でどんな意味を持ちえるのかというところからスタートしたほうがいいよ」
「はい」
軌道修正させられてしまった。
「あなた、研究のことで質問があったら、いつでもいらっしゃい」
院生室の場所を案内しながら、紺野さんが言った。扉を開けてくれた。心配をかけてしまったらしい。本棚。赤地に金の文字の表紙の本。マグカップ。ポット。コーヒーの瓶と紅茶のパック。MacとWindowsが一台ずつ。小さなパソコンもある。通常の半分くらいのサイズのものだ。はじめて見た。
「あれは私の。持ち運び用なの」
奥には個人用のロッカー。葉書きやステッカーが貼り付けてある。携帯のストラップを目印にしている人もいる。

「実は、研究計画書を作成してきたんです」
「あら。じゃあ、見てあげるわ」
ファイルから取り出し、見せる。集中力があるのか、手渡した瞬間から静寂が広がった。
「これね。なんかやっぱり範囲が広すぎるのよ。普遍的なテーマにしたいのはわかるけど。あくまで作品に沿って研究を行うのが目的だから。自分の関心だけをクローズアップしてはだめ。一つの作品の中から題材を見つけたほうがいいと思う。手広く作品を読むのも大事だけど、まずは細かいところに着眼しないと。先行研究って、ご存じ? まずは今までにどんな研究がおこなわれてきたかを調べないと。テーマが重なってしまったら独自性も少なくなってしまうし。図書館に行かなくても、ネットで調べることはできるわよ。CiNiiでキーワードを入れるだけで見つかるから」
院生は多弁らしい。
「ということは、書きなおしですか?」
「言うなれば、そうね」
「つらいです」
「私はいつでもここにいるから、相談に乗ってあげる」
(第10回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『学生だった』は毎月05日にアップされます。
■ 金魚屋の小説―――金魚屋の小説だから面白い! ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


