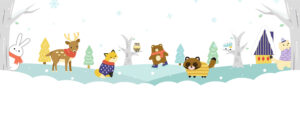 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
一、『ごんぎつね』
私はパジャマを着たまま、起きようかどうしようかと考えて、ベッドに腰をかけていた。精神爽快というわけにはいかなかったが、まず正常の状態に近かった。サラリーマンだったら、勤めにでかけるのも、さして苦痛ではない。頭ははれぼったく、熱があり、舌は乾いて、ざらざらしていたし、咽喉は突っぱり、顎はぐらぐらしている気味はあったけれど、もっと気分のよくない朝はいくらもあった(©レイモンド・チャンドラー 清水俊二訳『さらば愛しき女よ』)。
ドアに鋭いノックが聞こえた。ドアを二インチほどあけて、アッカンベーをしてから、すぐパタンと閉めてしまいたいような、横柄なノックだった(©前掲書)。
「なにやってんのよ」
ものすごい怪力でドアがめりめりと爆裂!!! する勢いで押し開けられ、俺は五フィートほどはねとばされた。怪力女であるところのわが助手、高満寺手弱女がいつものように腕を組んで俺を見下ろしていた。「太い骨の上に、太い筋肉の束がかぶさっている。もこもことした筋肉の盛り上がりはないが、ぴんっと肌が張っている。胸も腹も、おなじくらいにぶ厚いが、ゆるんでいるという印象はわずかもない。首の太さがきわだってい」(©夢枕獏「飢狼伝」)る。壁にしたたか打ちつけた背中と頭が痛かった。「背中に滲み渡るほどの痛みを感じた」(©夢野久作『ドグラマグラ』)いたわってくれる人は誰もいないので、自分で頭なでなでしてあげた。
「なるほど、こんな気持ちのいい朝に眠っているという法はないな。十時十五分だって? まだ時間は充分ある。台所へ行こう。コーヒーをいれるぜ」((©レイモンド・チャンドラー清水俊二訳『長いお別れ』)
「やめなさいよ」
べりべりと音を立てて、高満寺は、さっきから俺が多元ダイブインを行っていた『世界ミステリ全集5』『傑作小説大全』などから俺を強引に引き剥がした。
「ちょっと待ってよぉ」
せめて事務所の体裁だけでも、フィリップ・マーロウ風に維持したかったんだよぉと、俺は高満寺に情けなく懇願した。嘆願のかいもなくハードボイルドな俺は剥ぎ取られてしまった。俺は、殺風景ないつもの事務所に引き戻された。スチール製の簡易デスクとパイプ椅子。仮眠用の堅いマットのベッドと、枕代わりの座布団。机の上には書きかけの数枚の報告書。ゴミ箱には昨夜の夜食だったカップ麺の容器と、缶ビールの空き缶。
「すぐ出るわよ。事件発生なんだから」
「またかよ。どうせ、つまらない奴だろ」

まったくここのところ、どうでもいいようなイタズラでかり出されることが多くて困る。昨日も夜中の三時に叩き起こされたのだが、その事件というのが、『ごんぎつね』に忍び込んだ愉快犯が、ゴンが兵十の家においていくものを、「くり」から「春画」に置き換えたために、あの感動的なラストの部分が、
「そして足音をしのばせて近よって、今、戸口を出ようとするごんを、ドンとうちました。ごんはばたりとたおれました。兵十はかけよってきました。家の中を見ると、土間に春画が固めて置いてあるのが目につきました。「おや。」と、兵十はびっくりしてごんに目を落としました。
「ごん、お前だったのか。いつも春画をくれたのは。」
ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなづきました。
兵十は、火なわじゅうをばたりと取り落としました。青いけむりが、まだつつ口から細く出ていました。」
と、なんとも感動して良いのか笑うべきなのかわからない悲喜劇に変わってしまったというものだった。
ちなみに、VR(ヴァーチャル・リーダー)と呼ばれるわれわれの読書システムでは、読むにつれて、言語情報が身体体験に変換される。そのため、『ごんぎつね』にダイブインした俺たちは、気づけば江戸時代の農村にいるのだった。遠くに見えるみすぼらしい城が、田舎城主の『中山さま』のものなのだろう。兵十の家は、『表に赤い井戸のある』『小さな、こわれかけた家』と描かれている通り、わらぶき屋根の今にも倒壊しそうなぼろ屋だった。
そして、その家の戸口のところで、猟銃を取り落して放心している兵十の前には、こと切れた一匹の茶色い狐の姿が見えた。猟銃からは、確かに青いけむりが細く立ち上っており、ごんは胸から真っ赤な血をほとばしらせていた。そして、兵十とごんの死骸の間に散乱しているのは、古山師重の『男色秘戯画帳』や、勝川春章の筆になる『拝開よぶこどり』などといった男女の絡みを描いた一連の春画の山であった。北斎の「喜能会之故真通」、つまり蛸と女が交わっている絵のような強烈なインパクトのものもあった。
そこまで具体的なのか? との質問を受けそうな気もするが、そうなのである。ただし、それは読者それぞれの体験や記憶、さらには「薀蓄」と呼ばれるマルチレヤーなオンライン辞書の情報とリンクした結果なのであるけれども。
なんにせよ、文字だけで読むのとは格段に異なる、リアルな世界が体験できるのがこのVRシステムなのである。読書が、まさに「体験」そのものとなる。まだこの全方位体感読書を未体験の方は、ぜひわが社のVRをお試しあれ!
いかんいかん、ついつい、宣伝活動に走ってしまった。本題に戻ろう。
春画か。なるほど、独身の兵十の境遇に思いを馳せれば、ごんの親切は理解できなくもない。などと言っている場合ではないので、即座に語彙変換を行って、元通りにした。今後は、どの体験者も、兵十とごんの間に散乱しているものとしては栗しか見れなくなる。つまり、正しい読書体験が行えるようになるというわけだ。
語彙変換を行う前に、念のため犯人の痕跡を探したところ、高満寺が主人公の名前「ごん」が、一度「アメンホテプ三世」に置き換えられ、その後「暴れん坊将軍」と置き換えられ、最後に「ゆうこりん」に置き換えられた後に、元通りの「ごん」に戻されていたことを割り出した。つまり、物語のタイトルも「ごんぎつね」から「アメンホテプ三世ぎつね」「暴れん坊将軍ぎつね」「ゆうこりんぎつね」と変遷して元に戻されたことが分かった。
「また、あいつの仕業だわ」
高満寺が苦笑した。

「ああ、例の通称『しのび笑い』だな」
しのび笑いは、テキスト改変の常習犯である。とはいえ、重篤な犯罪や、悪意のある改変を行ったことは一度もなく、明らかに自分の楽しみのために微妙な改変をして一人で喜んでいるというタイプである。
「でも、らしくないわね」
「戻し忘れたのかな」
「いえ、そんなはずはないわ。明らかな挑発だと思うわ」
そうなのだ、いつもなら、「くり」を「春画」や「ティッシュ」(調査の結果、春画の前にこの変換も試していたことが判明した)などに変換して一人「しのび笑い」をした後は、丁寧に元に戻していくはずなのだ。今回のように、「くり」を「春画」に変換したまま放置していったというのは珍しいことだった。
「挑発か? あるいは模倣犯か?」
「可能性はあるわね」
読書=体験家の中には、常にテキスト変換に目を光らせていて、われわれが修復を行うまでのわずかな時間の間に、それらの微妙な変換に気づいてしまうという「千里眼」と呼ばれる連中がいる。一説には、一人の力ではすべてのテキストの変化に目を光らせることは困難なので、千里眼とは、ある種の読者=体験者ネットワークのことなのだともいわれている。あるいは、超高速のコンピューターにすべてのテクストを常時監視させ、小さな異変でもすぐに報告がなされるシステムが開発されているという説もある。いずれにせよ、彼らは基本的に鑑賞者であり、犯罪者ではない。微妙な変化や、重篤な変更を体感して愛で楽しむという悦楽主義者たちなのである。不変とされる古典テキストが、介入者の手によってほんの一時だけ変貌するその瞬間( ̄∇ ̄人)♡♡!を待望し全感覚で賞味し堪能するというやからであって、特に害はない。
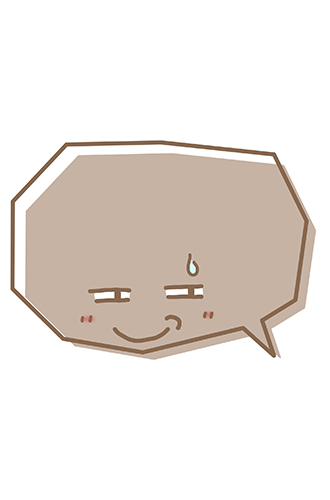
ただ、今回のケースから考えると、そうした「千里眼」のなかに、自分もやれるんだということを示したいと考える輩が混じってきたという可能性は否定できない。
いずれにせよ、この程度の変換は、笑って済ませることができる。修復だって一瞬だから、さして問題はない。
問題があるとすれば、こうした些細な改変でもわれわれが叩き起こされて修復にあたらされるという現実である。
実際、ここのところぐっすり眠れたという記憶がほとんどない。マーロウじゃないが、頭痛がするというのは本当なのだ。
(第01回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










