 ごく普通の女たちが再会したとき、何かが起きる。同窓会のノスタルジーが浮彫りにするあやふやな過去の記憶、すり替えられたイメージ。そして今、この信じがたい現実に女たちは毅然と向き合う…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ちょっぴりハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第4弾!
ごく普通の女たちが再会したとき、何かが起きる。同窓会のノスタルジーが浮彫りにするあやふやな過去の記憶、すり替えられたイメージ。そして今、この信じがたい現実に女たちは毅然と向き合う…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ちょっぴりハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第4弾!
by 小原眞紀子
13(後編)
仁は視線を上げ、大人びた笑いを浮かべた。
「人が何かするときって、たぶん、昔より今のことが原因っすよね」
瑠璃は立ち上がると、湯冷ましから急須へ湯を注いだ。
「瓜崎って人と、やくざとの関係を匂わせて、強調するため、とか考えたら、どうっすかね」
「実際以上に、ってこと?」
仁は頷いた。食事を終えた彼は、小さい子のようにデザートを待ちかまえている。

だとすれば、それはかなり計画的な陥穽ということになる。栞がそんなことを言っていたのは、瓜崎が亡くなる前だった。が、栞の口から直接、瓜崎の名を聞いたことなどない。そもそも瓜崎に対する何の恨みがあるのか。
「ま、栞さんは、鮎瀬さんのことで瑠璃さんを逆恨みしてたぐらいっすからね」
瓜崎を殺ったのは蓮谷なのか。その蓮谷に栞が働きかけたというなら、なぜわざわざ瓜崎とやくざとの関わりを匂わせたのか。
考えても堂々巡りだった。瑠璃は仁の前に、冷やした和菓子の皿を置いた。
「でね。俺、もう一回、実々さんに会おうかなって」
何ですって。と言うのに近い勢いで、瑠璃は仁の顔を見やった。
「なんか納得できないっていうか。妙な気がしたんっすよ」
また妙な気を起こした、というのではあるまいかと、瑠璃は仁を睨みつけた。
「あれは偶然だったのかな、って。白金のフェアグラウンド・ホテルで、瓜崎と蓮谷に、俺たちが出くわしたこと」
そう言いながら、仁は瑠璃の表情にたじろいでみせた。
「それだけっす。変なことしたいとかじゃ、ないっす」
「偶然じゃないって、あなたが蓮谷の顔を見覚えてたなんて、誰にも知りようがないじゃないの」
そこは偶然なんっすがね、と仁は呟いた。
「少なくとも、瓜崎と出くわすのは、予想してたんじゃないかって」
「どういうこと。実々は、ひどく慌ててたんじゃないの」
その慌てぶりに、実々を抱く気が失せた。
先日、仁はそう言っていたではないか。
「そうなんっすけど」と、仁は情けなさそうに首を傾げた。
「彼女が瓜崎のこと、あれこれしゃべるんっすよ。くどくど、しつこいぐらい。二人きりになるために、ホテルなんかに来たわけでしょ。それなのに瓜崎に割り込まれて。瓜崎本人はすぐいなくなったんっすけど、気分的になんか、ずっと居座られたみたいで」
で、その気が萎えた。つまり、それまでは十分、そのつもりだったわけだ。仁が瓜崎と呼び捨てにする理由は、そんなところか。
「実々は、気が動転してたんでしょ。それで瓜崎くんのことを、言い訳がましく説明したんじゃないの?」
いずれにせよ、また実々に会おうなどと。若い男の子など、およそ信用できない。悪さの口実を与えてやるのは御免だ。
「そのときは、そう思ったんっすけど」仁はさすがに、言葉を探すのに苦労している。「何となく変だなって。だいたい、なんであのホテルにしたんだろって」
前に使って気に入ったとか、勝手を知っているとか、初めてで行ってみたかったとか。ホテルを選ぶ理由など、いくらでもある。
「確かに多少、勝手は知ってるみたいでした。だけど、女性が気に入ったり、行ってみたくなったりするホテルじゃないっすよ。瓜崎が誰かとビジネスの相談に使うのには、ぴったりっすけど」
瑠璃は肩をすくめた。だったら実々も、社用で使っているのではないか。ラブホ代わりで何でもよかったんだろう、とまでは口には出さなかったが。自分を撮ってほしい、などというのも見え透いた口実に過ぎない。
「誰かに指図されてたんじゃないかって。あそこを使えって」
「若い男の子を連れ込むのに?」瑠璃はつい、言い放った。
取引先との関係で、社用に使えと指示されることはある。が、プライベート、それもそんな情事に、律儀に指図を守ることはない。
でも、と仁はじれったそうに首を振った。
「ほんとにいるなんて、って言ってたんっすよ」
「実々が?」
仁は頷いた。「あー、驚いた、ほんとにいるなんて、って。確かにそう言ってた。今まで、忘れてたんっすけど」
ほんとにいるなんて。
瓜崎がそこを常用していたことを、知っていたように聞こえる。だが、そういう意味ともかぎるまい。現にそのとき、仁はそう思わなかったのだ。
「ビジネスの打ち合わせが多いとこだし、よく人に遭遇するって、噂話でも聞いてたのかな、って思ってたんっす」
そうだろう。その方が自然な解釈だ。
「でも、そしたら、プライベートでは、そこ使わなきゃいいじゃないすか。あそこ、行こうと思う理由があったんじゃないすか」
「瓜崎くんが来てるから? やくざ者と?」
仁の理屈は、わけがわからない。
「上手く言えないっす。自分でもわけ、わかんない。で、実々さんに直接、確かめようって」
ね、と瑠璃は、小さい子に言い聞かせるように言った。
「いろいろ心配してもらって。でも、そんなことまでしてもらわなくて、大丈夫よ」
「そうじゃなくて。俺も、」
「報道写真に関心があるのは、わかった」と瑠璃は遮る。
「でも、それはそれ。わたしのことで、妙な女性関係のしがらみができたりしたら、あなたのお父さんになんて言い訳したらいいの」
親爺は関係ないっす、と仁は言った。こんな場面で若い子が口にする、そんな台詞にしては穏やかな口調だった。
「瑠璃さんは、もう、いいんっすか? 記憶喪失の理由もだいたいわかって、安心したんっすか? 警察が、瑠璃さんよりあの四人の方が怪しいって、射程から外してくれたから、もう知らない、ってですか?」
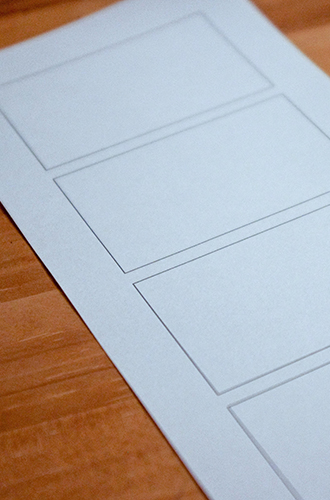
そんなつもりはない。が、言われてみれば、今の自分の落ち着きは、仁が指摘するところから来ていた。
「そういうの、逆に危険じゃないすか? 中途半端に関わるのって。状況がよくなったみたいだって、本当にそうかどうか。よくなっても悪くなっても、瑠璃さんには、それが何でか、わかんないままじゃないすか?」
「深入りが危険、ってことはないの?」
瑠璃は一言ずつ、ゆっくり言った。そんな口調でしか、年長者らしさを示せない。
「そら、ありますよ。だけど、ばれなきゃいい。深入りが他人に、わかんなきゃいいんですよ」
こっそり深入り。そんなことができるものなのか。
「もちろん好奇心、半分っす。だけど身を守るためでもあるっす。足抜けとかするには、自分も面、割れすぎっす」
面が割れすぎ、か。実々に栞。瓜崎の妻がここへ来たときにも、仁は居合わせていた。
「蓮谷だって、俺とフェアグラウンド・ホテルで会ったのを覚えてるかもしんない。松本で写真撮ったのだって、ばれてるかも。全部知らなきゃ、安心なんかできないっす」
瑠璃は微かに息を吐いた。この何も考えてないような坊やの方が、自分よりも小心なようだ。いや自分の方が怖いもの知らずで、成り行きまかせも平気でいたのかもしれない。
「で。実々に会うって? こっそり深入りするって、どうするの?」
結局は、ベッドで聞き出そうということではないのか。
「瑠璃さんに手伝ってもらうんっすよ。でなきゃ前もって、こんなこと話しませんって」
「手伝う?」
今、言ったまんまでいいっす、と仁は苦笑いした。「思ってる通りのこと、ぶつけてくれれば」
ソルティドッグを飲みながら、瑠璃は携帯が鳴るのを待っていた。
フェアグラウンド・ホテル一階隅のバーで、前払い方式の簡易なものだ。飲み物を持って、背後のラウンジに出ることもできる。
瑠璃はバーの止まり木に腰掛け、人と顔を会わせるのを避けるように、薄暗い壁を睨んでいた。

やはり、このホテルか。あまりいい気分とは言えなかった。
もう一度、あなたの写真が撮りたい。
仁のそんな甘言に、実々は易々と乗った。前回のものは納得がいかなかった。だから、ネガもデータも手元に置かなかった。いいアングルを思いついた。同じホテルの西向きの部屋、夕暮れの光で、あなたを撮りたい。
「まるきり嘘ってんじゃ、ないっす」
仁は、言い訳がましく瑠璃に言った。
「あの、真っ昼間ってのが、やっぱよくなかった、ってのはあるっす。西日で撮ったら、それなりにいいもんになるかも」
嘘でないだけに説得力があったか、実々は土曜の午後三時、西向きの部屋を特別チェックインで、ホテルと話をつけた。家族には出張と言ってある、と知らせてきたという。食事は部屋に運んでもらいましょうね、と言うからには、払いも自分で持つつもりだろう。
年増の色情狂。同い歳の瑠璃はうんざりする。しかも、今日の自分の役回りときたら。
携帯が一度鳴って、切れた。
瑠璃は止まり木から降り、バーを出てエレベーターに向かった。
十二階。一二二七号室の前に立ち、廊下を見回す。仁の姿はなかった。が、近くにいることは確かだ。
ノブを回した。打ち合わせ通り、鍵はかかってない。
「仁くん?」
一歩入ると、甘ったるい声がした。部屋には西日がいっぱいに射している。その声を無視して、瑠璃は事務的に呼びかけた。
「川村くん」
ベッドで激しく身動きする物音がした。奥に進むと、白いシーツで胸を覆った実々と目が合った。
実々の表情は驚愕、それに続いて怒りと混乱と、めまぐるしく変わった。瑠璃の方は無表情を装い、少なくとも侮蔑を表さないように意識するのがせいいっぱいだった。
二人が無言でいる中、部屋のドアが開いた。
仁は入口でいったん立ち止まり、振り向いた瑠璃と視線を交わした。瑠璃は右に避けた。
「なんで、」と、仁は一言だけ発し、ベッドの前まで来た。
あまり上手い芝居ではない。が、動転した実々が気づくはずもなかった。その声を引き金に、彼女は力まかせにシーツを引っ張り、素っ裸の上半身を起こした。スーツを着て立っている瑠璃に、なんとか対抗しようとしているのだった。裸なのを補うためか、混乱を沈めるためか、髪を肩に拡げるように頭を振っている。
「撮影なの?」
実々は大きく頷く。だから邪魔される筋合いなどない、というように。が、仁は首を傾げてみせた。こんなときに妙に正直になる、気まぐれな若者そのものだ。

「なんで、いるのよ」
やっと勇気を奮い起こしたらしい、実々の声はしゃがれていた。
「なんでって、打ち合わせしてたのよ」
瑠璃は平板な口調で答えた。「下のラウンジで。そしたら、川村くんの姿が見えた気がして。仕事のことで訊きたいことがあったから、ちょうどいいと思って上がって来たの」
瑠璃は仁に視線を向けた。「あれ、見つかった? カップのソーサー」と訊く。
ああ、と仁が応える。「ありましたよ。うちの応接間の棚に」
「だったら、それでいいかしらね」と、瑠璃は考え込んでみせる。「あとはテーブルの色目と合うかどうか、だけど」
「見てみますよ、あとで」仁は言った。「これ、終わったら」
「いつ、済む?」
瑠璃は、ベッドの上の実々を一瞥する。このモデルでの撮影がいつ済むのか、とも、この女との生理的な欲求排泄行為がいつ済むのか、とも取れる訊き方になった。
服を着た瑠璃と、同じく服を着ている仁との会話に、素っ裸の実々の顔は、屈辱に青ざめていた。
ええっと、と口ごもった仁をよそに「すぐ済むわよ」と実々は大きな声を上げた。その声はもう、しゃがれていなかった。
「今、撮影の準備にかかってたとこよ。こないだは一時間か、そこらだったわよね。早く済ませたいから出てってよ」
瑠璃が応えようとしたとき、ドアをノックする音が聞こえた。
「はい」と、瑠璃はドアに向かって返事をする。
「お食事のメニューをお持ちしました」
ドアを細く開けると、白いお仕着せ姿のボーイが立っていた。
「本日、こちらでルームサービスでのお夕飯ということでしたので。コース料理でしたら、五時までにお決めいただければ、七時にお持ちできますが」
「そうね」と瑠璃はメニューを見た。「和食とフランス料理、どっちがいいの」と、壁の影のベッドに向かって呼びかける。実々の答えはなかった。
「じゃ、フランス料理を一人前」
「一人前、でございますか?」ボーイは小首を傾げた。二つのベッドは、それぞれダブルの広さがある。
「ええ、そう。ちょっと待って」
瑠璃はドレッサーに駆け寄ると、椅子の上に置いてあった実々の服、畳まれた下着とストッキングを素早く抱えた。
「これ、クリーニングにお願い。明日の朝まででいいわ」
「ちょっと、何するのよ」という実々の怒鳴り声と、「あの、クリーニングでしたら専用の袋に」と言うボーイの声が重なった。
瑠璃は無理矢理ドアを閉め、ボーイを押し出した。
「実々はここに泊まるんでしょ。撮影はすぐ終わるかもしれないけど」と、瑠璃は実々に言った。
「わたしに会ったからって、急いで帰ったりしない方がいいと思う。かえって怪しまれるわよ。出張だって、言ってあるんでしょ?」
実々はシーツで胸を覆ったまま、ぎょっとして瑠璃を見つめた。
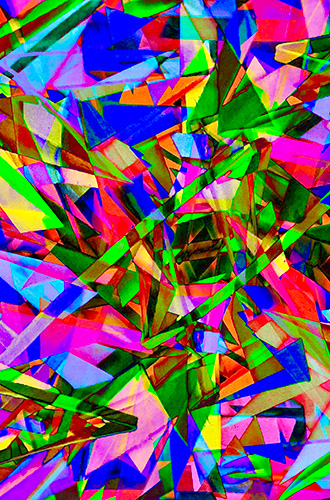
無論、嘘だった。
「川村くんの隣りにいたのが、あなたのような気がして。部屋に上がっていってるし、まさかと思ったんだけど」
冷静に考えれば、そんなことでは部屋番号を突き止めることはできないはずだ。が、今の実々に、そう言い返す余裕はなかった。
「あのね。川村くん、まだ若いでしょう」
瑠璃は諭すように言い、ドレッサーの椅子に掛けた。
「この人のお父様は、わたしの仕事上、大事な方でもあるの。その息子さんがこんな、それも結果的に、わたしが引き合わせたみたいな相手と妙なことになると、困るの」
実々は縋るように仁を見た。が、彼はすべての責任を放棄し、叱られた子供のように首を垂れている。
「未成年じゃあるまいし」と、吐き捨てるように実々が呟く。
「そうよね。だから警察にどうこうとか、父親に報告とかは思わないけど。でもまあ、ここで、ほんとに会うなんてね」
実々はぴくっと目線を上げた。瑠璃は繰り返した。
「ほんとにいるなんて。あなたが」
(第26回 第13章 後編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『本格的な女たち』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■








