 ごく普通の女たちが再会したとき、何かが起きる。同窓会のノスタルジーが浮彫りにするあやふやな過去の記憶、すり替えられたイメージ。そして今、この信じがたい現実に女たちは毅然と向き合う…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ちょっぴりハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第4弾!
ごく普通の女たちが再会したとき、何かが起きる。同窓会のノスタルジーが浮彫りにするあやふやな過去の記憶、すり替えられたイメージ。そして今、この信じがたい現実に女たちは毅然と向き合う…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ちょっぴりハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第4弾!
by 小原眞紀子
13(前編)
山本警部補と堀田はリビングのソファの、それぞれ先日と同じ場所にかけていた。
昼過ぎに伺いたいと、今日は前もって連絡があり、紅茶の準備もできていた。カップを手に取った堀田の若い横顔にはどことなく、くつろいだ様子さえ見られる。
「本日は、柿浦さんのことをお尋ねしたいと思いまして」
山本警部補は、カップをソーサーに戻した。
「柿浦、ですか? また、どうして」
「いえ。瓜崎さんと親しかったのか、と」
「特に、聞いたことはありませんが」
柿浦。ずっと独身なのにノーメークで、子持ちの実々や姫子よりも老け込み、女を捨てたような姿だ。瓜崎と親しい、と言っても女関係の一部という意味ではなかろう。
「瓜崎さんとお会いになったとき、後の予定については言っておられませんでしたか?」
「後の予定というと、その晩の、ですか」
ええ、と焦れたように山本は頷く。「友人に会う、とか、そういったことですね」
「いいえ。別れたのがもう深夜近くで」
どこへ帰るか、というなら普通は自宅だが、まさか。
「柿浦さん宅へ行く、というふうなことは?」
「いいえ。行ったんですか?」
なかば渋々、山本警部補は浅く頷いた。
「瓜崎さんの携帯の電源は切れていましたが、一瞬だけONになった形跡がありまして。もっとも遺体から携帯は見つかってないので、本人が通電させたものかどうか」
その場所が特定できて、大田区の六郷の辺りだった。そこは羽田に近く、航空会社に勤める柿浦のマンションがある。

「同じマンションの方が言うには、二、三日ほど男の方が出入りしていたと」
あたかも、たまたま得た情報であるかのように軽く言う。が、かなり網羅的に聞き込みをしたか、管理人にでも口を割らせたに違いあるまい。瑠璃は一瞬、この自分のマンションでも同じことをされたのではと考えた。
「で、それが瓜崎くんだと?」
柿浦だって女の独り者だ。どんなに身なりを構わないようでも、男を連れ込むぐらいのことはあるかもしれない。
「背格好や顔写真から、どうやら瓜崎さんのようで」
歯切れの悪い山本に、堀田が口を挟んだ。「近くのコンビニの店主も、見かけたそうです。防犯カメラの記録は残念ながら、すでに消去されてしまってましたが」
やっぱり、そんなところまで。瑠璃はうんざりして山本警部補と堀田を眺めた。
「まあ、とにかく、瓜崎さんに最後に会われたのが、香津さんではない、ということのようですので」
そうだ。瑠璃はやっと気づいた。つまりは、そういうことだ。
「そうしますと、あのメールのことが引っかかってきまして。柿浦さんのところにも届いた、とおっしゃってましたでしょう」
さらにわかってきた。捜査の内情を洗いざらい、ではないにせよ、細かく瑠璃に伝えるのは、どうやら状況が変わってきたためらしい。
「ええ。同級生の四人に発信されたようになってます」
四人。柿浦に実々、高梨と寺内。青山の教室にまで押しかけてきて、瑠璃を責めた。瓜崎を匿っておきながら、柿浦はどういうつもりなのか。柿浦だけでなく四人とも知っていて、あんな真似を?
「あのメールの通信記録も、取られてたんでしょ?」
山本は頷いた。「技術系の方たちばかりで、携帯の表示を変えるぐらいは、もしかしたら、できるかもしれないので」
とはいえ、メールの記録は瑠璃の携帯の送信ボックスにもあり、通信会社の記録でも、実際、その時刻に発信されている。
しゃべってしまおうか、と瑠璃は衝動に駆られた。
瑠璃が洗面所に立った間に送信された、というのに、やはり無理があるというなら。状況が変わった今なら、警察にも理解してもらえるだろう。
洗面所から戻ってからの記憶が消えている。理由がわからず、それが言えずにいた、と。おそらく店を出た直後、マイオトロンか、同等の代物でやられたのではないか。頭部周辺、首の辺りを狙うと、電気ショックで記憶が消える可能性があると、仁が言っていた。
そもそも人間の記憶自体、生物電気を使った磁気記録に近いものらしい。瞬間的に強い電流が流れたり、思わぬルートで磁気が作用したりすれば、記憶が消去されても不思議ではない。
そして。
瑠璃はふと、思い出した。日々に埋もれていた、微かな記憶だった。繁殖させた生物の生物電気を使い、膨大なデータを処理する。それが瓜崎自身の長期的な研究テーマだと、あの晩、聞いたのではなかったか。
「で、柿浦は何て?」
もっと事情を知らなければ、うっかりしたことは言えない。
山本と堀田は、ちらりと目を見合わせた。本来、そんなことを漏らすべきでないに違いなかった。
「最初は、会社の同僚が来ていたと」堀田が言い出した。「いろいろお話するうち、あの晩、瓜崎さんがちょっとだけ見えた、というように変わってきまして」
瑠璃は今や疑わしい人物ではなく、証言してもらわなくてはならない相手と考えているようだった。
「柿浦が、最後に会った者とも限らないわけですね?」
「そうですが、瓜崎さんは、柿浦さんのところにずっといらした、と見てます」
山本警部補は珍しく断定した。近隣住民の言い分から、そういう推測になるらしかった。
「瓜崎さんと食事されている間、お酒もだいぶ飲まれたんですよね」と、堀田が身を乗り出して訊いた。「その勢いで、何かおっしゃってませんでしたか。柿浦さんについてとか、しばらく身を隠したいといったことを」
ちょっとした些細な言葉でも、と山本も瑠璃を促す。
さあ、と瑠璃は首を傾げた。そんな状況ならば、瓜崎は、そもそも瑠璃をカモフラージュに利用しようとして会った可能性がある。酔ったところで何も漏らすはずはない。
あのときに瓜崎が残したものといえば、四人に送ったメールのほか、女持ちのスタンガンのケースということになる。
スタンガン。その類であるマイオトロンという代物について話そうという気は、すでに失せていた。
「別れ際は? 瓜崎さんは時間を気にされてましたか。何かおっしゃってませんでした? まっすぐ自宅に帰る、と?」
「わたしの方は少し、朦朧としていて」と、瑠璃は呟いた。記憶がないなどと、やはり今さら言えない。
「時計は、見たかもしれません。そろそろ帰ろうか、と」
瑠璃自身、店を出る際の記憶はないのだから、店の者の記憶を借りるしかなかった。「席を立って、レジを済ませて。そう、外の空気に早く当たりたくて」
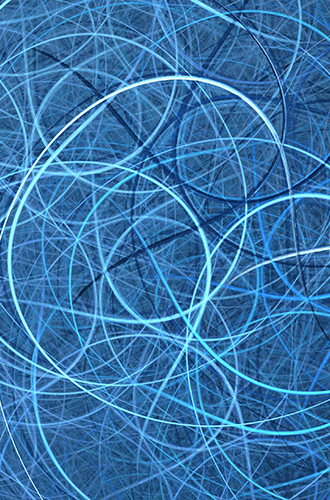
山本警部補はふーんと、考え込んだ。
「朦朧とされていたけど、携帯は忘れずに仕舞われたんですね。バッグの中か何かに」
「ああ、きっと洗面所から戻って、わたしもテーブルにあった携帯で時間を見たんです。腕時計をしないので」と、瑠璃は思いついた。
「その後、バッグに仕舞った。酔っぱらっていても、ちゃんと。携帯を置き忘れたりすると大変ですし」
「で、スタンガンのケースなど、目に入らなかった」
堀田が独り言のように、そう呟いた。
「店を出られてから、他の客のものが椅子の上に落ちたかなにか、したのかもしれない」山本も、それに応じるように言った。
そうではない。
瑠璃が席を立った隙に、きっと誰かが故意に置いたのだ。瓜崎自身が、瑠璃に何かをなすりつけようとしてなのか。あるいは、その後に瓜崎の身に起こることを予想できた誰かが、なのか。
だが、それは瑠璃の関知しないことだ。このまま逃れよう、と瑠璃は思った。本来、自分とは関わりのないトラブルの圏外へ。
「では、長々とお邪魔しました」
山本警部補と堀田は立ち上がった。「あのメールのことで、もし何かわかりましたら、お知らせいただけますか」
「はい。そちらからもお願いいたします。気になりますので」
ええ、しかし、と山本は口ごもった。「柿浦さんの件に関しては、当面の間、ご内密にお願いできますか」
「わかりました。それを聞いたら、他の三人も事情を話してくれるかもしれませんけどね」
柿浦のところに瓜崎がいたということを、あの三人が、もとより知らなければだが。
山本の視線は迷うように揺れた。「いえ、もうそれは。警察の仕事ですので」と、拒否するように掌を上げた。
「誰か、わかったっすよ。あいつ」
携帯で仁の話を聞いていた瑠璃は、「ねえ、」と遮った。
「これから来られない? 何か食べさせるから」
食べさせるって、餌じゃないんだから、とぶつぶつ言っていたが、八時過ぎには着く、と承知した。
仁の顔を見たいわけではなかった。電話、特に携帯を使って話しているのが、怖ろしいような気分に陥ったのだ。
話し言葉が宙を渡るなんて。瑠璃はキッチンに立った。何がどうなるか、わからない。話の中身が変わるかもしれないし、それが知らない間に、どこかの淀みに溜まり、誰かにすっかり聞かれてしまうかもしれない。メールも同様だ。身に覚えのないものが、出所を偽って宙を飛び交うのだ。
細々した残り物を掻き集め、ちらし寿司風のものを拵えた。炭水化物を大量摂取させておけば間違いあるまい。あとは吸い物、若い子にはもったいない本物の鰆の西京漬けを焼いて、お菓子。

「蓮谷礼治。松本で(株)ハスタニって会社をやってますけど、総会屋っすね。縄張りは中部から北陸地方」
取り皿に山盛りの炭水化物に箸を突っ込み、あらためて仁は教えてくれた。松本で撮った例の写真を、昔、バイトしていた写真雑誌の先輩カメラマンに見せたと言う。
「危険じゃないの、そんなことして」
だいじょぶっす、と仁は請け合う。「そっち関係、知らない顔はないって先輩っすから。逆に、めったなことを他人にしゃべったりしませんよ。松本で知り合いの女性を見かけたと思ったら、見覚えのある奴と会ってて、としか言ってませんし」
そんな男と、栞は何の用で会っていたのだろう。それ以前に、そいつは瓜崎とはどういう関係だったのだろう。
「東京へも、しょっちゅう来てるの?」
たぶん、と仁は頷く。「いろいろ、やってるんでしょ」
瓜崎とその男は、白金のフェアグラウンド・ホテルで何の打ち合わせだったのか。仁と一緒のところを見つけられた実々は大慌てだったが、本当は瓜崎も動揺を隠していたのではないか。
「あり得ますね。平然と振る舞ってれば、ただの男二人。蓮谷も別に異様な風体というほどじゃない」
何だと思う、と瑠璃は訊いていた。
「そんな総会屋なんかと、研究所の教授が会う理由って」
情報の横流しかな、と仁は呟く。
それはあり得た。研究所には各企業からの依頼があり、つまりはその会社の中・長期戦略に関わる社外秘を知ることになる。いわば金のなる樹々を植林しているようなものだ。が、瑠璃には瓜崎が、金のためにそんな真似をするとは思えなかった。
「へえ。そんな立派な人っすか。それとも大金持ち?」
「金持ちではあるわね、実家も。嫌な奴だけど」
何をしたいのかな、と仁は首を傾げた。「そいつが一番したかったことって何だろ。これ、うまいっすね」
鰆を箸でむしりながら、仁は言う。
こいつもボンボンの類で、美味いものを食いつけているのだったと、と瑠璃は思い出した。
「支配、かな」瑠璃は言った。
「なんすか?」仁は鰆の皿から目を上げた。
「支配。影に隠れるところのない、まったき自身の正統的権力」

ふーん、影に隠れない、と仁は呟く。
「だから一緒に出てきたのか。蓮谷とはホテルの客室で会ってたと思うっすよ。レストランとかじゃなくて」
それはそうだろう。でなければホテルで会う意味がない。
「だのに、なんで別々に下りて来なかったのかなって。よっぽど古くからの付き合いで、慣れっこになってたか、後ろめたいことなんかないと思ってたか」
瓜崎は自信過剰で、不用意なところはある。やるなら、やけに堂々とやると言うのは彼らしい。
が、瑠璃はやはり腑に落ちなかった。自信があるだけに満ち足りた男なのだ。周囲を嫉妬と不快感に陥れるほど。その瓜崎が、何の必要があって蓮谷のような男を近づけたのか。支配欲などといった理由は抽象的にすぎる。
「だけど、やくざと瓜崎が接近して、しまいには入れ替わっていたって話、前にあったっすよね」
仁はそう言い、箸を置いた。
「何のこと?」
「二十何年か前、上高地のホテルで、鮎瀬って人が会ったのが、やくざってことになってたじゃないっすか」
それは勘違いからくる、噂の一つだったに過ぎない。鮎瀬に会ったのは自分だと、瓜崎も認めている。
「栞が言っていただけよ。他からは聞いてない」
「栞さんは、なんでそんなことを?」
「さあ。ボン子から聞いた、とか」
「本当っすか? その人に、確認しました?」
どうだったか。自分のことを、やくざの女だと栞に吹き込んだだろう、などと問い質した気はする。それも含め、何もかも身に覚えはない、と言われた。いずれにしても昔の話なのだ。
「上高地の近辺で、やくざに会ってたのはむしろ、栞さんっすよね。それは最近の話っすけど」
そうだ。松本で、さほど一見、やくざらしく見えないものの、蓮谷に会っていたのは栞だ。しかもその蓮谷は、瓜崎と懇意らしい。
「栞の作り話かもしれないわね。しかも最近の」
だが、何のために。

鮎瀬の死を事故でなく、劇的な事件に作り替えるためか。二十数年前の出来事を持ち出し、騒ぎだけを起こしたいのか。
「それも鮎瀬くんを忘れさせないため? それとも自分の彼への思いを更新するためだって言うの?」
それこそ瑠璃が、仁の目を覚まさせたいと思っていた純愛路線の解釈だ。
(第25回 第13章 前編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『本格的な女たち』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■








