 学園祭のビューティーコンテストがフェミニスト女子学生たちによって占拠された。しかしアイドル女子学生3人によってビューティーコンテストがさらにジャックされてしまう。彼女たちは宣言した。「あらゆる制限を取り払って真の美を競い合う〝ビューチーコンテストオ!〟を開催します!」と。審判に指名されたのは地味で目立たない僕。真の美とは何か、それをジャッジすることなどできるのだろうか・・・。
学園祭のビューティーコンテストがフェミニスト女子学生たちによって占拠された。しかしアイドル女子学生3人によってビューティーコンテストがさらにジャックされてしまう。彼女たちは宣言した。「あらゆる制限を取り払って真の美を競い合う〝ビューチーコンテストオ!〟を開催します!」と。審判に指名されたのは地味で目立たない僕。真の美とは何か、それをジャッジすることなどできるのだろうか・・・。
恐ろしくて艶めかしく、ちょっとユーモラスな『幸福のゾンビ』(金魚屋刊)の作家による待望の新連載小説!
by 金魚屋編集部
六、三巴亡焉美吼(みつどもえおわりなきびのさけび)
これまでにないほど会場は盛り上がっていたが、当然ながらそれで終わりとはならなかった。
「えー、では続きましてぇ」
出場者を告げようとする稗田に向かって、いきなり三方向から何かが飛来した。
「うわっ、なに?」
怯えてマイクから情けない声を増幅しつつ、ステージに縮こまる稗田。稗田に突進するかに見えた三つのものらは、ぶつかる瞬間に散開した。
ひとつは白い翼を折りたたんでステージの右側に着地し、もうひとつは優雅な佇まいでステージ中央の「ビューチーコンテストオ」の看板の上に止まり、三つ目は冠をいただいた頭を掲げながらステージの左側へと納まった。
白鳥、梟、そして孔雀という三羽の鳥たち。
けれども、どういうことなのだろう。湖があるでもなく、夜中でもなく、動物園でもないこのキャンパスに、雀や鳩や烏とは珍しさのレベルが段違いなこれら三つの珍鳥が飛来するとは。
「白鳥きれい!」
声が上がった。
「いやいや、梟の佇まいも貴族的だよ」
さらに声が上がる。それを聞いて対抗心を燃やしたのか、孔雀がふぁさあああっと半円形の翼を広げた。嘆声があがった。
「すごい」
「百の目を持つアルゴスに見つめられてるみたい」
「うっとりしちゃう」
いずれ劣らぬ美しい鳥たちであった。これらの鳥たちを見ていると、こんな疑問がわき起こるのも致し方なかった。ビューチーコンテストオとはいうものの、美ってどうやって判断するんだろう?
白鳥と梟と孔雀。この三者に優劣をつけることができるだろうか?
純白のけがれなき美と、気高い森の狩人と、華麗なる目玉模様の翼。これらは三者三様の美を持っているとはいえないだろうか?
どこに判断基準を持ってくるかで優劣はすぐにひっくり返る。美の絶対基準などないということ。常に美の判断にはなんらかのバイアスが入るということだ。
「な、なるほど、順番をいちいち待ってはいられないということですね。ちょうど、次が桜木さんの出番でもありましたから、時宜を得たご登場、しかもどうやら三人こぞってということのようです」
三羽の鳥を見た稗田は、即時に事情を把握したようだった。
「白鳥は桜木泡さん、梟はもちろん香月梟さん、そして孔雀は天川石榴さん、それぞれの愛鳥として知られています。ではご登場願いましょう。皆さんどうぞステージへ!」
鮮やかなギターのカッティングとともに始まる、ロックナンバーが流れた。
「おやおや、これはあ」
稗田があおる。
「なんと、オランダのサイケデリック・ロック・バンド、ショッキング・ブルーのヒット曲『ヴィーナス』ではありませんか。そしてヴィーナスとは、古代ローマの美の女神、そしてオリジナルは古代ギリシャのアフロディーテということになります」
その音楽とともにステージに上がってきたのは、曲に合わせてということなのか、光沢のあるショッキング・ブルーのミニワンピースに身を包んだ桜木泡であった。ラテックス素材なのか、完璧なプロポーションがくっきりと描き出されている。おまけに首元から胸元にかけて三角形に広がるスリットが入っており、深い胸の谷間を垣間見させる仕掛けになっていた。
「うひゃあ」
声が上がった。
「すでにノックダウン!」
「のっけからの先制パンチ! アッパー食らってのけぞっちゃう」
観客がのけぞりつつ喝采を送った。同じくショッキングブルーのハイヒールで、カツカツとステージに上がった桜木泡は、かがんで歩み寄ってきた白鳥を抱き寄せ、そして頬ずりをした。
「恋したい人はいるかな?」
白鳥を抱き抱えながら、桜木が会場に呼びかけた。
「したい、したいよ~」
「できるものなら、君と恋したい」
「分けてちょうだい、あなたの恋愛エネルギー」
そう、桜木泡は恋多き女として知られていた。財閥の令嬢として、シリコンバレーのIT長者との結婚をアレンジされていたものの、それを拒絶して家出、最終的には長い歴史を誇る名家から破門の宣告を受けた。それでもまったく動じることなく、スカウトされたのを機に彼女はグラビアアイドルとしてデビューした。歴史ある名家の者らはこの事態に大慌てしたようだが、彼女はそれをせせら笑った。せせら笑うために、わざとその職業を選んだのだとも言われていた。
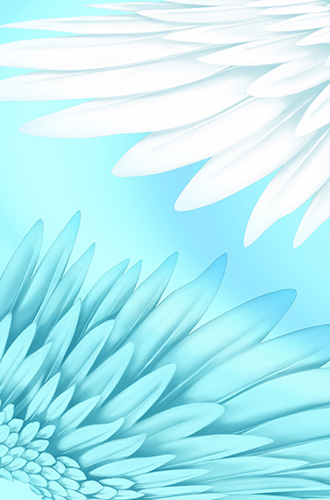
完璧としかいいようのない美貌とスタイルのゆえに、グラビアアイドルでありながら、世界各国の有名デザイナーのコレクションにもモデルとして出演している。それでも彼女はファッションモデルを気取ることはない。
「服を着ていようが、着ていまいが、どちらもわたしよ。そして、着ている服が少ない方がよりたくさんのわたしを見せているともいえる。だから、肩書きはむしろグラビア・アイドルの方がふさわしいのよ」
自信に満ちてそう言いきる彼女だからこそ、性別を超えたファンがついているのだといえた。
「どうして、あんなにおいしい結婚を断ったんです。相手は世界でも指折りの金持ちですよ」
かつてインタビュアーにそう尋ねられたことがあった。その時彼女はただ淡々とこう答えた。
「だって、好みじゃなかったんだもの、顔が」
彼女はグラビアを足がかりに、さっきのべたようにファッション界はもちろんのこととして、テレビのバラエティに、そして映画にと活躍の幅を広げてきた。しかし、同時に派手な恋愛遍歴の幅をも着実に広めてきた。芸能界、実業界、スポーツ界、そして一般人まで含めた、あらゆる世界の男性たちと浮き名を流してきた。一見つながりのないそれらの交際相手に唯一共通点があるとすれば、それは彼らがみなイケメンだったということだった。そう、彼女は典型的なイケメン食いだったのである。
あるとき、有名な家系のラーメン店の行列に並んでいるところを直撃取材されたことがあった。
「桜木さんもやっぱり、こってり系のラーメンが好きなんですか?」
そう問いかけられた彼女は、こう答えた。
「そうね。でも一番の好みはラーメンよりイケメンかな。むしろこちらが主食で、こってり系もあっさり系もなんでもオッケーよ」
そんな風に答えて世間の度肝を抜いたのであった。
自由奔放を絵に描いたような彼女だったが、どういうわけかバッシングされることはなく、むしろ女性たちの間ではある種のヒーローのように扱われていた。
「わたしも、アワちゃんみたいになりたい」
「まったく嘘がないところが好き」
「男を食い散らかす彼女こそがほんとうのフェミニズムの体現者なのよ」
アグレッシブ・フェミニストなどという造語が彼女のために作られたりもした。現在の彼女の恋人は、残虐な戦闘スタイルで知られるK―1界のスター、阿麗主(アレス)だった。「血みどろ貴公子」の異名を取る彼は、普段は快活な美男子であるものの、ひとたび闘いとなると獰猛かつ残忍な破壊神と化し、反則も厭わぬ恐ろしい怪物となる。
「見たでしょ? 彼のあの姿。あの微笑み。闘いを終えて全身に返り血をあびて。それでも凄惨な微笑みを浮かべるあの姿を。彼こそ魔神だわ。彼こそ闘魂だわ。おとなしいルールや決まりごとなんか、ぜんぶ踏みつけにしちゃう。闘神アレスの名にふさわしい男だわ。わたしは彼の荒ぶる力に惹かれるの。多くの世の男たちが失った大切な力を彼はまだ持ってるんだもの」
なんといっても有名なのは、宇宙からK―1に殴り込みにやってきたという触れ込みだったテューポーンとの一戦だろう。赤い髪に白い肌、緑の目に青い唇をもった、異形の戦士だった。阿麗主も身長二メートルと巨大だったが、テューポーンはなんと二メートル五十センチと、さらに大きかった。

宇宙人という触れ込み通り、テューポーンは奇妙な技を使った。ふとした瞬間に、蹴りを入れる足先が蛇となって相手を噛んだように見えることがあった。突如肩から数百匹の蛇が生えだして噛みついたりする瞬間もあった。再現映像でゆっくり再生してみると、ほんとうに肩から蛇が飛び出しているのがわかった。実際、噛まれた相手選手はぐったりとなって倒れ、強力な毒蛇用の解毒剤を用いなければ命の危険に陥ることもあった。あるいは、絶対決まるはずの蹴りからふわりと浮かび上がって身をかわすときがあるなど、どうも背中に見えない羽が生えているとしか思えない振る舞いを見せるのだった。
そんな計り知れない脅威のせいで、テューポーンには対戦相手がいなくなった。いらだったテューポーンは、阿麗主を挑発した。
「どうだ、阿麗主? チキンのお前にあの女はもったいないな。あのゴージャスな女には、むしろ俺の毒蛇がふさわしい。お前があの女にふさわしくなれる可能性は一つしかない。俺の挑戦を受け、そして俺を倒すことだ」
「よかろう」
阿麗主は、すでに魔物への変化の予兆を見せながら応じた。
「お前のかわいい蛇どもをすべて噛み殺し、お前のあやしい翼をもぎとってやろう」
そういって笑う阿麗主の唇から覗く歯は、いつもの白い歯ではなく、とがった肉食獣の牙と化していた。
「すてきだわ!」
桜木泡は、それを聞いてエキサイトした。恋人の身を案じたりはしなかった。
「あの怪物を倒してこそあなたはわたしにふさわしい。そういう勇者でなければ、わたしはあなたを必要としないしね。さあ、食い殺しておいで、あの羽をはやした蛇を!」
『桜木泡争奪デスマッチ』
『阿麗主よ、怪物から恋人を救え!』
『世紀の一戦! 破壊神阿麗主VSクトゥルー神話的怪物テューポーン』
スポーツ紙の見出しは、かつてなく勢いに溢れた。
そして、戦いの日は訪れた。
ゴングとともに、テューポーンは正体を現した。二本の脚は太く柔軟な動きを見せる大蛇と化した。肩からはガラガラ音を立てる猛毒の蛇がわらわら湧き出した。そして、背中には深紅の巨大な羽が伸び広がった。
「な、なんということでしょう」
解説者はのけぞった。
「神話は、伝説は、すべて事実であったのです。まさに宇宙からの侵略者。テューポーンはもはや人間ではありません。怪物、文字通りの化け物だったのです。そして、髪の毛を逆立て、いつもの白い歯を牙の連なりに変え、鋭い爪をとがらせているとはいえ、やはり阿麗主は人の姿のまま。果たして人間にこの怪物を倒すことは可能なのでしょうか?」
二匹の大蛇が阿麗主をからめとろうと襲い掛かる。それを交わしていると、肩から次々と放たれる毒蛇の波状攻撃を受ける。そいつらをつかんでは引きちぎり、その血を絞って阿麗主は飲み干し、あるいは自らの頭から注ぎかけて笑った。
「笑止。そのような小技で俺が倒せるものか!」
「来い、地上に縛られし者、狩り取られるべき獲物の仲間よ」
テューポーンは鼻でせせら笑い、翼をはばたかせて空へと舞い上がった。そして、上空からまず一匹の大蛇を繰り出し、これを食い止めている阿麗主の脇腹へと、もう一匹の大蛇を噛みつきにかからせるのだった。
「かかったな!」
不敵な笑みを見せた阿麗主は、大きな口を開いて目の前の蛇の頭を噛み切った。大量の血がどばどばとリングに降り注いだ。脇腹を狙ったもう一匹の蛇の両眼には、阿麗主の右手の人差し指と薬指の鋭い爪が突き刺さっていた。
「ぎょぐわああっ」
上空でテューポーンが悲鳴を上げた。阿麗主は目が見えなくなった蛇の体をつかんでぶんと振り回し、テューポーンをリング上にたたきつけた。すかさず馬乗りになり、その体に足先の鋭い爪を食い込ませて押さえつけつつ、背中の二枚の翼をべりべりという嫌な音を立てながら引きはがした。
数瞬の後、リング上にはぐったりとなった巨身の白人レスラーが横たわっていた。その体のどこにも、さっき皆がみたはずの蛇や翼の名残はなかった。
「こいつに取り憑いて魔物を引き剥がしてやったぜ」
全身血塗れの阿麗主は、凄惨な笑みを浮かべた。
「俺はエクソシストじゃねえからな。力づくが一番性に合ってるんだ」
拍手が鳴り響いた。
かぶりつきで終始笑顔で観戦していた桜木泡が、招かれてリングの上に上がった。
「みなさん、ご覧になって?」
桜木泡は、血みどろのリングに足の裏を染めながら、リングの上を歩き、そして同じく血まみれの阿麗主にハグをした。来ていた白いワンピースが真っ赤に染まった。
「わたしにふさわしい漢がここにいます」
血みどろで抱擁しあう二人を激しい拍手喝采の渦が包み込んだ。
とはいいつつであった。そんな阿麗主をステディとしてキープしながら、いまもあちこちで浮き名を流し続けているのが桜木泡なのだった。そう、彼女もまた荒ぶる力の持ち主だったというわけだ。恋愛相手が一人では決して満たされないというわけだ。
「だって、どんなおいしい食事でも毎日じゃあきるでしょ? エスニックなものが食べたくなったり、ジャンクなものが欲しくなったりする。それって自然じゃない?」

まったく悪びれない桜木泡であった。
彼女の薫陶を受けた阿麗主の方も、当初はおずおずと、そして今では旺盛に他の女性たちとの逢瀬を重ねるようになっていた。しかし、二人の関係は盤石なものとなったといわれていた。当初は喜び勇んで醜聞の記事を流していた雑誌各社も、そのことにほとんど意味がないことに気づいて二人の後を追うのをやめたといわれている。
「わたしたちは自分を抑えない。自分に嘘はつかないのよ。そんな正直者の二人だから互いを信用できるし、愛することができるのよ」
桜木泡は、堂々とそう言ってのけた。
いつしか、そんな桜木泡をめぐってひとつの伝説のようなものが産み出されていった。握手会に行って彼女と手を触れあえば、それだけで恋愛パワーが漲るとか、彼女がDJを勤めるラジオ番組を録音したものや、なぜか彼女が朗読しているオーディブルの『嵐が丘』や『人形の家』を聞くと恋愛運がみるみる上がるなど、いろんな風説が流れていた。桜木泡が直筆サインをした写真集などは、恋愛成就のお守りとして高値で取引されているといわれていた。
「今日はラッキーだわ」
特に喜んでいたのは女子たちだった。
「桜木泡ちゃんを生で見れるなんて。もう恋愛運ダダ上がりって感じ」
「運っていうか、挑む勇気みたいのが湧くよね」
「よーし、わたしも喰いちらかすぞぉ。待ってろよぉ、男どもぉ」
桜木泡の登場曲『ヴィーナス』がフェイドアウトするのと同時に、今度は陽気なエレクトロニックビートが波打ち始め、それに乗って歌うコケティッシュな声が会場中の萌え心をくすぐった。
「梟ちゃまだ」
「新曲『しつこいなあ。あたしメデューサの首もってんだけど、見せようか?』だ」
「サウンドも歌詞も鮮烈だけど、なによりこの歌声って、あれ」
「これ、CDじゃない。生だよ。ほらっ」
ほんとうだった。ステージの裏側から、マイクを持って歌いながら、迷彩柄のジャケットにショートパンツ、頭には白いキャップという出で立ちの香月梟が現れたのだ。
だから、いってんじゃん、いってんじゃん。
あんたうざいって、きもいって
あたしもってるからね、ほんとだからね、
メデューサの首もってるからね
えっ、なに、なに、なに、なに、なんつった
えっ、なに、なに、なに、なに、聞こえねぇ
みたいのそれ、みたいのこれ、みたらほら、石になるよ
石になるけど、みたいんだったら、ほらみりゃいいじゃん
ほらみなよ、みてみろ、みろみろ、ミロのヴィーナス、じゃねえメデューサだっつうの、 ほら、こっちみろ
独特なセンスの歌詞世界。独特なセンスのメロディ。独特なセンスの歌唱法。はまったら抜けられない中毒性の高い楽曲。新曲なのにすでに知っているファンも多く、いっしょに歌いだす者もたくさん現れた。しかも、梟は運動神経抜群で、歌いながらバク転を連続で決めたり、手にした数十本のナイフを壁際に追い詰めた司会者稗田に「動くなぁ、動くと死ぬなりぃ」と投げつけたりした。怯えて固まった稗田の周りには、ちょうどそのシルエットのかたちにナイフがみごとに突き刺さったなりぃ。
歌い終えた彼女の肩の上に、看板の上を飛び立った梟が優雅に降り立った。
「みんなみんなたぁんこんにちわぁ、香月梟でぇす。そしてぇこいつがぁわたしの相棒ヘドヴィグですぅ~、って嘘うそぉ~、だってそれってハリポタのやつじゃんかよ~、こら梟ってな感じでぇ~。えっと~、ほんとの名前はぁパラスでぇす。昔死んじゃったぁ親友のぉ名前なんだよぉ~」
「知ってるぅ~」
会場から声が上がる。
「梟ちゃんが、子供の頃仲良くしてた原須磨子ちゃんでしょ。あだ名がパラス。不慮の事故で亡くなったんだよね」
「なんだっけ、喧嘩してパラスが道に飛び出しちゃったんだっけ? なんにしても、それが香月ちゃんの一番の心の傷」
「だから、香月ちゃんはそれ以来ずっとパラスといっしょなんだよね。まずは飼ってた犬の名前があの日からパラスに変わった。犬が死んじゃった後は、ハムスターとか、猫とかいろいろあって、それでいまはフクロウのパラスちゃん」
「転生して、ずっと二人はいつまでもいっしょなんだよね」
「うるうる、さめざめ~、ありがとぉ~みんなぁ~だぁい好きだよぉ~」
ステージ上の香月梟が感激の声を伝えた。
「そぉんな風にぃ~、わたしとぉ~パラスのことわかってくれてぇ~。そうなのぉ、パラスといっしょにいるときぃわたしはぁ無敵なのぉ。二人で一人ぃ~、二人揃ってぇ、やっとぉわたしたちはぁ完璧になるのよぉ~」
「えーっと」
やっと、ナイフの檻から脱出した司会者の稗田が、しゃりしゃりとしゃしゃり出てきた。
「そういえば、あれですよね。香月梟ちゃんは、この前SASUKEの女性版であるKUNOICHIでファイナルステージ『魔女の隠れ家』をクリアしたんだよね」
「てへっ、こいつはまいったぁ~、知られちゃってたかぁ~。アイドルっぽい自作自演歌手やってるけどぉ~、一応それが本職だけどぉ~、実のところぉ~、ぶっちゃけ、ああいうの得意なんですよぉ~。なんていうのかぁ、あたし基本ん~、体育会系ぃ~なんでぇ」
「あれすごかったよねぇ」
そう、小柄な香月梟は、数週間前に開催され、テレビ放映されたKUNOICHIにいつものフリフリ衣裳のまま出場した。軽々と五本のローラーが回転するローリングヒルを飛び越え、シェイキングブリッジと呼ばれるぐらぐらの板の上をちょちょちょんと越え、そそり立つ湾曲した壁をすすすいーっと駆け上った。手脚を蜘蛛のごとく滑らかに動かして二枚の壁の間をしゅわーっと通り過ぎ、高速度で逆回転するベルトコンベア、リバースコンベアをものともせずにしゅぱっと駆け抜けた。間隔の開いたパイプの間をひゅひゅひゅひゅひゅ、猿飛猿助のように滑らかに渡りきり、そしてファイナルステージでは、スパイダーウォークの垂直版を十メートルの高さまですいすいすーだらだった、すらすいすいすいっと登り、最後の五メートルの綱登りもすいーら、すーだらだった、すらすらすいすいすいと鼻歌歌いながら登り切り、制限時間に二分の余裕を残してボタンを押した。そのあっけにとられるほどの敏捷性、口をあんぐりするほどの余裕でテレビの前の観客を驚嘆せしめたのだった。コケティッシュなアイドル歌手にすぎないと思われていた香月梟が、スポーツ界から一躍注目をあびた瞬間であった。

そして、ファイナル・ステージ・クリアの感想を聞かれた時の決め仕草、
「楽勝っ的な、テヘッ!」
はユーチューブで世界中に流され、香月梟はKAWAIIカルチャーの新たな継承者としての地位を盤石のものとした。
その映像はテレビで放送されたわけだが、それがネット上に繰り返しアップされ、拡散し、いまや「FUKURO!」といえば、外国でも「AH、KUNOICHI!」とか「Yeah、テヘ・ガール!」と即座に反応が返ってくるほどにまでなっていた。
「聞くところによりますと」
稗田が解説した。
「香月梟さんの生家は、古武道の師範の家系であったとのこと。長女であった彼女は、いずれは家を継ぐ者として、幼い頃からさまざまな武道をたたき込まれたということです。柔道、空手、剣道、合気道、柔術、さらにはテコンドーやボクシング、カポエイラに至るまで、この世のありとある武術が、この華奢な体のなかに収蔵埋蔵内蔵秘蔵されているわけです。そのなかで、彼女が合気道を教わった師範の娘が、原須磨子だったわけです。道場で出会った二人はすぐに意気投合し、武道センスに恵まれた二人は日常的にオールジャンルの格闘技で競い合う実践的練習パートナーとなりました。
そして、格闘技を始めれば虎と化すと言われた原須磨子と、鬼と化すといわれた香月梟だったわけですが、ひとたび道場を出れば、どこにでもいる仲の良い女の子たちに戻りました。最大のライバルでありつつ親友であった原須磨子は歌うことに情熱を燃やしていました。当初、歌い手である須磨子のために演奏しようと楽器を始めた香月梟でしたが、そのうち二人でオリジナルの曲を作り始め、路上ライブなどもやりました。コンビ名はパラス・アテナ。原須磨子のあだ名パラスと、梟を眷属とする女神アテナからその名前を取ったのでした。
そして、あの痛ましい事故で親友の原須磨子、ことパラスを失ったあと、しばらく失意のなかにいた香月梟は、その肩に一羽の梟を乗せて復活したわけです。今度は、一人でパラス・アテナを名乗りました」
「違うもぉん、一人じゃないもぉん」
香月梟が割って入った。
「ここにちゃぁんと、パラスはいるんだからさぁ。ねぇ、パラスぅ」
「ああ、そうでした。いまも彼女たちは二人でひとつ、永遠に離れることのないコンビとして今日もステージに立っているわけなのです」
「はぁい、じゃあもう一曲いいかなぁ」
勢いに乗った香月梟が、二曲目を歌おうとしたときだった。バチッという音とともに、電源が切れた。録音していたバッキングサウンドも、梟が弾くキーボードも、彼女の口元のマイクも、すべての音が遮断された。
どんどんどんどんどんどんどんどん。
和太鼓の音が鳴り響いた。
「天川石榴さまのおな~り~」
大音声で、口上が述べられ、舞台正面が二つに割れた。観客たちが慌てたように両脇にさあっと引いて道を作ったのだった。中央にできた即席の道には真っ赤なレッドカーペットがすさーっ!と敷き詰められた。屈強なレスラーのような覆面の男たちが、神輿を担いで現れた。
どどんどどどんどどどんどどんどん。太鼓の音がより高まった。
インドの祭礼で使われるもののような、原色の彩りが鮮やかな異教の神輿。舞台の袖にいた孔雀が飛翔し、その神輿の尖端に止まると、華やかに翼を広げた。
「皆の者、苦しゅうない。我が道を開けてくれたこと感謝しよう」
神輿の上には黒いスーツに身を包んだ女性がいた。髪の毛は金色に染めている。
「ああ、石榴さま」
「新作『つきのみちかけ』すごくよかったですぅ」
「相変わらずお美しい」
「踏んでください、あなたのヒールで」
「はい、みなさん。そうなんです」
蝶ネクタイの稗田にようやく出番が回ってきた。
「さきほどお客様のどなたかからお声上がった、最新の監督作『つきのみちかけ』、みなさんはもうご覧になりましたか? あ、映画館ではあんまり上映されないんですよね、彼女の作品は。なにしろ超ハードコアですからね。ま、全国の気骨あるミニシアター、そう東京だとポレポレ東中野とか、新宿武蔵野館、大阪だと第七藝術劇場やシネ・ヌーヴォみたいなところで特集上映はありましたけど。基本はオンライン配信なんです。あとはDVD購入とかね。そう、なんせ万人向けじゃないんで。オンデマンドでしか見れないんですよね」
「その前の作品は『ヘスペリデスの林檎』でしょ? 知ってるよ、けっこう有名だもんね」
応じる声がある。
「よくご存じで。そうなんです。彼女の作品は不定形なものとして性を描いてますから、男女の恋愛が基本で、最近ようやく同性愛ものなんかのLGBT系が認知され始めたばかりのこの国にとっては、かなり衝撃的なんですよね。
『つきのみちかけ』、ぼくも見させてもらいました。全体的にこう詩的な感じなんで、あらすじとかってむつかしいですけど、あえてぶっちゃけ単純化していうなら、性的アイデンティティが揺れ動く女性を主人公とした作品ですよね」
同意を求めるように稗田は天川を見る。でも、彼女はそんな司会者を無視して、神輿の上で石榴を自分の頭の上に載せるのに夢中になっている。
困った稗田はまた言葉を継ぎ足した。
「えっと、あー、そうですね。月が満ちてくると猛々しい異性愛者の狼女となって男を食い散らかす。でも、月が欠けていくに従ってネコ的な同性愛的傾向を募らせていくというそういう主人公でしたよね。しかも、月のみちかけの中間点では、彼女は完全な無性状態となる。ってそんな感じでしたあ」
その辺りでようやく天川は頭の上に石榴を載せることに成功する。すると、その石榴の上に孔雀が飛び乗って翼を広げる。会場から拍手喝采がわき起こった。
「えっと、天川さんはですね、AVFW(アダルト・ビデオ・フォー・ウィメン)という団体を主催者でもあるわけです。『ヘスペリデスの林檎』の作品は、コアな性交描写が多いために一般映画として公開される機会は少ないわけですけど、評価は高いんですよ。それに、最近は、ご自分の脚本を小説化したものも出版されてて、こちらもいろいろな賞を受けている。そんな創造性溢れるお方なんです」
頭の上に石榴を載せ、石榴の上に孔雀を載せた天川石榴を載せた神輿がようやく舞台にたどり着いた。バランスを取って上の石榴と孔雀が落ちないよう気を使いながら、天川は立ち上がり舞台上へと移動した。

「ありがとう、わたしのかわいいしもべたち。アルゴス、スピンクス、ヒュードラー、パイトーン、ラドーン、下がっていいわよ」
うやうやしく頭を垂れて退場する屈強な男たち。
「ご覧ください、あの勇姿を」
稗田が紹介した。
「プロレスファンの皆さんならご存じでしょう。いまの方たちは『ウォリアーズ・オブ・サモス』所属の現役レスラーなんです。まあ、覆面の悪役として活躍する軍団でして」
「そうそう、ヒールだから、最初暴れて、最後は負けるんだけどね」
プロレスファンらしき観客から声が上がった。
「そうですね。プロレスってのはショーですからね。ショーの筋書きに従って最後はヒーロー役にやられるのが常なんですよね。でも、あの覆面の下には、すごい実力者がいるってもっぱらの噂なんですよ。オリンピックのレスリングのメダリストや、元相撲取り、あるいは名を馳せた武道家もまじってるとかいいますよね」
「実際には彼らこそが最強だって説もあるよね。俺もそう思うし」
また、会場の声に助けられる稗田であった。
「そんな彼らがなぜ天川石榴のボディガードを勤めているのか? 謎ですよね? わたしにもわかりませんし、できれば知りたいところです。とにかく彼らの石榴への忠誠心は半端ないんですよね。試合がない日はいつも彼女の周りを彼らが取り囲んでいる姿を見ることができるわけですから」
「もういいんじゃないかしら?」
天川石榴が稗田をたしなめた。凜とした声。澄んだ高い声だけれど、強い意志の感じられる声音。知性と感受性、そしてなにより誰もが従いたくなるようなある種の威厳をたたえた声だった。
「あ、すみません」
思わず稗田もひれ伏すような口調になっていた。
「ようこそ、いらっしゃいました。生まれついての貴婦人、万人を統べる女主人とも呼ばれる天川石榴さんです。みなさまどうぞ、盛大な拍手をもってお迎えください!」
「なんてゴージャスなの」
「もはや目の保養なんてレベルじゃないな。まるで奇跡だ。この三人だけじゃないよ。その前に出た紀貫通にしても、吉永咲耶にしても、この世のものとは思えない美しさだった。一生分の眼福をこんな短時間で全部目にしちゃっていいんだろうか。あまりの幸福に眼球が潰れやしないかって心配だよ」
「ただのミスコン見ようと思って来たのに、この展開は何なの? 神すぎて、理解が追いつかない。わたしのなかのいろんなものが揺すぶられて、気が遠くなりそう」
そうした声は、その場に居合わせたすべてのものが共有する感慨だったろう。ぼくだってそうだ。稗田に無理矢理こんなサークルに引きずり込まれて、いやいやながら照明係として参加したわけだけど、なんだかよくわからないままに審査委員長みたいな立場に祭り上げられて、この華麗なページェントを舞台袖の一等席で見させてもらってる。観客からは、
「なんなの、あいつ」
「全然普通のやつじゃん」
「なんで、あんなやつを泡様、梟様、石榴様は審判役に選んだのかしら。いくら幼稚園時代の競争の続きだっていったってさ」
「あれじゃね、つまりはごくフツーのやつの感覚で選ばせようってことじゃね?」
「なんだよ、それなら俺にやらせて欲しかったよな」
「だって、お前三美神と同じ幼稚園じゃねえだろうが」
「ああ、その一点だけかよ。悔しいなあ。くそ、あの一般人(ル、モブ)野郎め」
みたいな、やっかみと軽蔑と羨望と憎悪がない交ぜになった、わけのわからない感情がぼくにはおし寄せていた。でもぼくにだってどうしようもないんだから、どうしようもない。ぼくが希望したわけじゃないからね。ぼくだって、自分がそんな大役にふさわしい人間だなんてこれっぽっちも思っちゃいない。だけど、あの三人に、そう幼稚園時代いっしょに遊んでいただけのあの三人に言われたんだから、従うしかない。ごくごく平凡な、「つまらない」を絵に描いたような人生を歩んできたぼくと、華々しい脚光をあびるにいたった彼女らとでは、世界が違いすぎることはよくわかっている。ほんとに、ぼくの主観なんかで、一位を選んだりしていいのだろうか? そう思うと不安でいっぱいになる。
「さあ、それでは、これで本日の出場者二十五組が全員出そろったことになります。さあ、それではいよいよ、審判の時。三美神ご指名の針素審判長は、果たしてどんな結果を出されるのでしょうか。さて、これに先立ちまして、会場からアンケートを採りたいと思います。配布いたしました紙に、皆様が一位だと思われる方をお書きいただき、皆様のお名前を添えてください。みごと一位を当てられた方には、一位の方とのツーショット写真を撮る権利が与えられますよ。さあ、皆様それではシンキング・タ~イム!」
稗田がそう告げると、会場からは悩ましい声が上がった。
「ええっ、これは難しい、難しすぎるよ」
「みんなそれぞれに美しかったもんねえ」
「違いすぎて、バリエに富みすぎてて、選べないよぉ」
「うん、でも、誰が選ばれるにせよ、一位の人とツーショット撮れるなんて、末代までの家宝になるよこれ。絶対当てなくちゃ」
「だよね、だよね、だよね」
「おい、イチロー」
稗田がぼくの前に立っていた。
「どう、選べそうか?」
「いや、無理」
ぼくは正直に答えた。
「だって、わかんないよ。みんな凄すぎるもん。みんなよって立つ美の基準が違うもん。どうしたら、いいんだろ」
「考えちゃダメだ。考えたらどつぼにはまる」
稗田は真顔だった。
「お前が言うとおり、それぞれの出場者はまったく違うバックグラウンドを持ってる。まったく違うバックグラウンドが基準になる。ってことは、考えたら決めれないってことだよ。だから、いいか直感だよ、直感に従え。それしかない。えいやっ!で決めちまえばいいんだ」
「なるほど、やってみる」
「おう、やってみろ」
ぼくは目を閉じて答えを探した。ぼくが一番インパクトを受けたのは誰だ。ぼくが一番ショックを受けたのは誰だ。ぼくが一番惹きつけられたのは誰だ。いろんな答えがフラッシュする。そして、ぼくが一番好きなのは?
答えが現れそうになった。
その時、あたりが一気に闇に落ちた。
「えっ?」
驚いて顔を上げたけど、何も見えなかった。
一面の暗闇だった。
(第06回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『ビューチーコンテストオ!』は毎月13日にアップされます。
■遠藤徹の本■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


