 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(七)象の胸(後編)
そのあと、搭乗時間までだいぶ間があった。半日以上ある待ち時間を持て余したわたしたちは土産物を買いに出かけたのであった。できるだけ珍しいものが欲しいという種山のわがままで、地元の人に教えてもらった穴場を訪問したのだ。
「いいんですか、こんなの」
っていうのが、そこに足を踏み入れた時のわたしの偽らざる感想であった。
そこには、どう考えても違法な土産物がたくさんあった。シベットキャットやテナガザルなどのタイに固有の動物が生きたまま、あるいは剥製となって売られていた。当然機内持ち込みはできないので、秘密のルートで送られるのだということだった。秘密のルートというとなんか怪しげなのに、白昼堂々、ごく普通に土産物屋として営業しているのが不思議だった。
おでこにいかにもな古傷のある小太りの親父が出てきて、何か言った。きっと、何がほしいのかと尋ねたのだろう。
「チャーン」
ぐるりと全体を見渡した種山が唐突にそう口にした。幾度も耳にしたので、さすがにチャーンが象のことだというのはわたしにもわかったのだった。
「象は売ってないんですか」
相変わらずであった。ごく自然な感じで種山ときたら、突拍子もないことを尋ねたわけだ。
さすがのあやしげな店の親父もこれには少々当惑したようだった。それでも蛇の道は蛇というだけのことはある。そんな一休さんばりの無理難題にも親父はちゃんと応えてみせたのであった。種山に近づいてきてそっとこう耳打ちしたらしい。
「なくはない。でも、送るのがちょっと難しい。なにしろ小さくないから」
なるほど、である。密輸入しようにもブツが大きすぎるわな、たしかに。
「でも、一部なら大丈夫ね」
そう答えて、親父は親指を立ててみせたのだという。
「一部って?」
意味がわからなかった。
「象牙とか、足とか、鼻とかなら」
「バラ売りしてくれるんですか?」
うなずく親父。おいおい、うなずくなよそこでって感じである。
「もちろんバラバラに輸入して後で組み立てても、動きはしないけどね」
親父はそういって下品な笑い声をあげた。
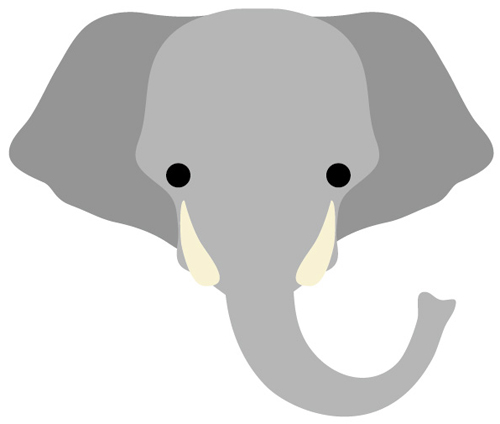
足などは、ちゃんと椅子の形にアレンジして送ってくれるのだそうだ。さきほど、わたしがコーヒーを、そうコピ・ルアクだかアルクだかをいただいた時に座っていたのが、その椅子だった。象の足を脛の下あたりで切断し、その切断面に水牛の皮で座面を取り付けたものだった。密輸入組織のひとつを探り当てた未知子お嬢様が、非合法的手段(っていったいどんなの? なんかフィルム・ノワール的な暴力のにおいがするわあ。なんせ背後にいるのが宝島財閥だしねえ。おお、怖!)で奪い取って、自宅の慰霊所で供養している品の一つだということだった。
種山の話では、というかおそらく未知子嬢から聞いたのであろう情報によれば、このように象の足を椅子に加工したものとか、壁にかけるための象の頭の剥製などもアフリカやアジアで堂々と売られていたりするのだそうだ。わたしたちがよく聞くのは象牙のことだけど、他の部分も商品にされているってわけ。アフリカのサバンナには、密猟者によってばらばらに解体された象の死骸が打ち捨てられていたりするのだという。
「まあ、確かに、これで足跡の謎は解けました。おそらく死体にくっつけてあった象の頭もああいう業者から取り寄せたんでしょうね。タイに長くいた人ならではの情報ですよね」
「うん、まあ、そういうところだろうね」
「だから、ハルさんは、こうしたシロモノを取り寄せて、和也さんに復讐したんですよ。ウライさんの恨みを晴らすために。そして恨みを晴らしたことを報告しにタイのあの村までまた出向いて行ったとまあこういうわけです」
どう、恐れ入った? わたしは少々悦に入りながら種山を見た。
「うん、おもしろいね」
さほど興味を惹かれたという風でもなく、というよりむしろ若干興味を失った感じで種山は鈍く反応しただけだった。
「ええっ、それだけですかあ」
この名探偵一条さやかの推理をそんなにテキトーな感じで聞き流していいものなのだろうか。いささかプライドを傷つけられた思いでわたしがさらに推理を補う言葉を続けようとしたとき、八王子い、八王子い、終点でええすうというアナウンスが響き、扉が開いた。
小綺麗なインテリジェントビルの三階フロアが、ハル君の作った会社「ゲヌス」のオフィスだった。種山によれば、ラテン語で「起源」という意味らしい。
小綺麗なエレベーターの小奇麗な扉が小奇麗に開くと、受付の小奇麗な受付嬢が小奇麗な笑顔で迎えてくれた。

受付の奥には、仕切りのされた部屋がいくつかあって、パソコンを前に何やら仕事に打ち込んでいる男女数名の社員の姿が見えた。みんなくだけた格好。まるでアメリカだった。
「種山様ですね、お待ちしておりました」
「ありがとう。代表はいますか? 春山俊平代表は?」
「はい、珍しく」
受付嬢は、小奇麗な笑顔で、平然と妙なことを口にした。
「珍しく? 代表が会社にいるのが珍しいことなのですか?」
とすれば、なんと珍しい会社なのだろう、とわたしは思った。
「ええ、代表は自由を愛される方なんです」
相変わらず小奇麗な白い歯をのぞかせて微笑みながら、受付嬢が教えてくれた。
「自由、ですか?」
っていうと、尾崎豊的なあれですか。ガラス割って廻ったりとかいうあれですか?
「ええ、仕事に縛られるのがお嫌いなんです。なんでも、ビートルズが作ったアップル社の社訓が『自由』だったんだそうです。それにならってネクタイ着用禁止、スーツ着用禁止っていうのが、わが社のモットーなんですよ。代表は、そんなわけでめったに社の方にお見えになることはないし、お見えになっても社長室でギターを弾いて歌ってらっしゃるばかりなんです」
おお、それは間違いなくハル君だ。陽気なギター弾きとくれば、ハル君でもう間違いなかろう。ビジネスマンに転向しても、ヒッピーな生き方を貫いているとはなかなかあっぱれじゃないか、君。
「でも、今日はお見えになっている?」
「ええ」
「どうしてですか?」
「決まってるじゃないですか。先生がお見えになるからですよ」
受付嬢の眼差しには、若干尊敬の色が覗いてすらいた。ええっ、なによそれ、どういうこと。
「遺伝子工学の世界的権威がお見えになるから、失礼のないようにとおおせつかっております。貴重な示唆がいただけるものと、代表も楽しみにしているようでした」
「それはもったいない」
ほんと、もったいないわ。でも種山もなかなややるわね。うまいこと遺伝子工学の権威なんて経歴をでっち上げたらしいわ。
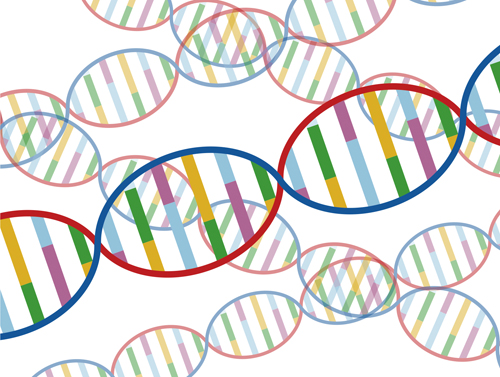
「ところで」
しゃしゃりでるわたし。いよいよ、名探偵一条さやかの出番である。
「はい、なんでしょうか、お嬢様」
「先週の日曜日なんですけど、代表は夜十時ごろから深夜の一時ごろまでどこにおられたか、おわかりですか?」
当然わからないはずだ。それだけ自由人で、かつ日曜の夜、つまり会社も休みの日である。アリバイなどあろうはずがない。さあこい、わたしの推理の裏付けよ!
「ああ、日曜でしたら」
小奇麗な受付嬢が小奇麗に微笑えんだ。
「社長室にいらっしゃいました」
「ええっ」
そんな馬鹿な、とわたしは叫びそうになった。
「どうして、いつもいない自由人が、日曜の深夜に会社なんかに?」
「あの日は、アメリカからの来客があったのです」
「アメリカ、ですか」
「ええ、わが社は、主たる業務がアメリカの製薬会社と日本の製薬会社との間での契約業務なので、英語が堪能であることが採用の重要な項目の一つにもなっているくらいなんです」
へええ、つまりわたしも英語はできますよ、と小奇麗に自慢してるわけね、お姉さんは。
「でまあ、月曜の便で帰国せねばならないとお客様がお急ぎだったので、昼過ぎから夕刻まで打ち合わせに時間がかかったのです。そこには、私と他数名の社員も同席しておりました。商談がうまくまとまってその場で打ち上げということになり、いつものところからケータリングを頼みまして、バンケットルームで」
「バンケットルームって」
「ええ、代表がビーガンですので」
「ビーガン?」
「はい、菜食主義なんです」
「ああ」
どこまでもニューエイジな人ってわけだ。なかなか本格的だ。

「そういうわけで、代表はあまり外食を好まれないのです」
なにしろ、市販の調味料には、たいてい動物性の成分が混じりこんでおりますので、と受付嬢はしたり顔で教えてくれた。ああそうですよね、うまみ成分ってやつですよね。
「そういうわけですので、わが社は、マクロビキッチンという玄米正食をベースにしたケータリングの会社と契約をしているのです。そして宴会などは基本的に社内のバンケットルームで立食形式で行うことにしているんです」
なんでもそのケータリング会社は二十四時間対応可能なのだそうだ。だから、海外とのやり取りが多く、時間が不規則になりがちなわたしどものような業種にとっては、ありがたい存在なのです、と受付嬢は若干得意げに教えてくれた。
「宴会した部屋ってどれですか」
と問うたわたしに、
「あちらになっております」
と受付嬢は小奇麗にネイルされた指先をピカらせながら奥の部屋を指さした。確かに入り口にbanquet roomと書かれているのが見えた。
「それで、代表が明日は会社を休みにするから、今日は無礼講でいこうとおっしゃいまして、お客様がお帰りになったあとも、明け方まで社員たちと盛り上がったんです」
「へえ、楽しい会社なんですね。代表の一声で休日が決まっちゃうんだ」
「ええ、こう言ってはなんですけど、経営は黒字ですし、代表はとても有能な方ですので、余裕があるのです」
自信たっぷりだった。給料もいいのよ、とその笑顔が告げていた。
「で、春山代表は、十時ごろ少し酔ったからと社長室に退かれたのです」
好物の焼米スパゲティと、ブリューノ・ビオ・ブランシュを二瓶追加注文するように告げていったということだった。
「ちょっと待ってください」
耳慣れない言葉にわたしは戸惑った。
「焼米と、ブリューノ・ビオ・ブランシュのことですか?」
なかなか察しのいい受付嬢であった。さすが小奇麗なだけのことはある。
「ええ、それそれ。それです」
「焼米と申しますのは」
長くなるので以下略。要は有機玄米をもみ殻のまま炒り、それから殻を取ったものだそうで、ひき肉の代わりにミートソースやマーボソースなんかに使ったりするらしい。そして、ブリューノなんちゃらは、ベルギー産の高級オーガニックビールなのだということだった。
「とはいっても、姿は見えなかったわけでしょ」
劣勢に追い込まれたわたしは、それでも醜くあがいていた。
「いえ、おられました」
「どうしてわかるんです」
「いつものようにギターをお弾きになっておられたからです。そして、歌っておられました。およそ数十曲を、ほとんど休みなしに」
「そんなに歌って疲れないんですかね」
「お好きですからね。歌うことが一番のストレス発散なのだとつねづねおっしゃってますから」
まあそれはタイの村でも聞いたことだった。タイの村でも高床式の小屋の中で夜更けまで歌い続けていたというから、ありえないことではなかった。

「で、また戻ってきたんですか」
「ええ、社員は一人帰り二人帰りして、残っていたのはわたしを含めて二、三人でした。もうみんなずいぶん酔っていましたが、一時過ぎに歌い終えられてさっぱりしたお顔で戻られました。それからまたちょっと飲んで、そうですねお開きになったのは、午前の四時くらいだったかと思いますね」
ぴったしである。あまりにも犯行時間ぴったしに姿を消している。とはいえ、社長室から外に出るには皆がいるバンケットルームの前を通過せねばならないし、それより前に歌うのをやめねばならない。ほかに誰か社長室に出入りした人はいなかったのかと問うたのだが、ケータリングのレストランの方が、さきほどの焼米のなんとかとかその他いくつかの追加注文を届けにきたり、皿を回収に来たりしただけだということだった。その皿は、すべて無鉛健康陶器と呼ばれる、有害物質を含まない土で焼かれた器なのだということだったが、そんなことはとうでもいい。いずれにせよ、やはりハル君は犯行に行けないということになってしまうのであったからだ。
「先生」
情けない顔になったわたしに、種山が励ましのエールを送ってくれた。
「あまり気にすることはありませんよ。まずはハル君に会ってみようじゃないですか」
(第20回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







